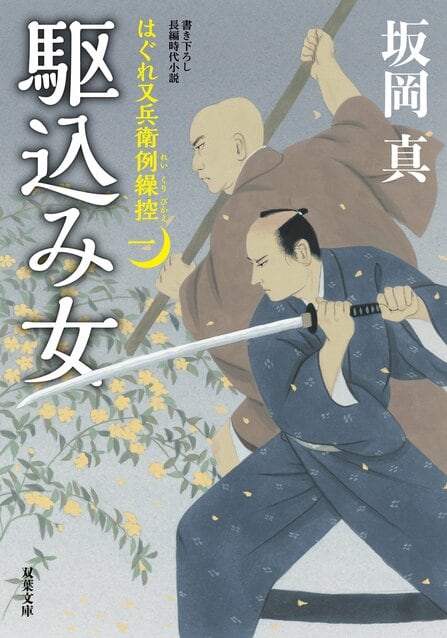二
甚太郎は給仕の娘に茶と名物の味噌蒟蒻を持ってこさせ、周囲を気にしながら喋りはじめた。
「必死の訴えを届けることもできずに、門前であえなく死んじまった。あさは哀れなおなごでござんす。鷭の旦那なら、放っておくはずはねえ。はなしを聞いてもらえるとおもっておりやしたぜ」
熱い眼差しを向けられても、又兵衛は黙然と茶を啜るだけだ。
ついでに味噌蒟蒻をひとつ頬張り、美味そうに咀嚼する。
甚太郎は小鼻をぷっと膨らませた。
「芝高輪の車町に隠売所がありやしてね、抱え主は剃刀の左銀次と申しやす。あさを囲っていたのはたぶん、そいつにちげえねえ」
髪結あがりの小悪党で、寺の住職どもに女郎を斡旋して稼いでいる。廻り同心の紐付きとなり、密訴を生業にしていた時期もあった。直には知らぬが、噂に聞いたことはあったので、甚太郎はぴんときたのだという。
「あさの握りしめていた文にゃ『さぎんじにころされる』と書いてあった。そいつを小耳に挟んじまったそばから、縄手をひとっ走りしてきたんでさあ。そうしたら、案の定、左銀次のもとから、あさっていう女郎がひとり逃げだしていた。年は二十五だそうです。場末の隠売所に置いとくにゃもったいねえほどの縹緻好しで、山吹っていう源氏名で呼ばれておりやした。車町の山吹といやあ、近所で知らねえ者もいねえほどだったとか」
「山吹か……」
又兵衛は遠い目をしながら、溜息とともに漏らす。
「ひょっとして、お知りあいで」
ふいに尋ねられても応じず、又兵衛は大儀そうに腰を持ちあげた。
床几の端に小銭を置こうとすると、甚太郎が慌てて引き留めにかかる。
「旦那、はなしはまだ終わってねえ。左銀次にゃ、おっかねえ後ろ盾がおりやす。品川宿の裏を仕切る太刀魚の茂平っていう元締めで。名前くれえは聞いたことがおありでやしょう」
「いいや、知らぬ」
「おっと、そうですかい。茂平を知らねえとは恐れいったな。さすが、世間知らずの例繰方……おっと、口が滑った。ともかく、一筋縄じゃいかねえ相手でやんす。でも、あっしはどうしても、左銀次みてえな下種野郎が許せねえ。熱いでしょう。どうしてここまで熱くなるのか、聞いていただけやせんかね」
涙目で懇願され、又兵衛は仕方なく腰を下ろす。
苦くなった茶の残りを呑み、味噌蒟蒻の味噌を指で掬って嘗めた。
ぐすっと、甚太郎は洟水を啜る。
「同じ裏長屋に住む居職の娘が借金のカタに取られ、岡場所に売られちまったんです。岡場所から隠売所へ落とされ、十年ものあいだ、好きでもねえ男どもに身を売らされたあげく、娘は抱え主のやつに折檻されて死んじまった。偶さか、ほとけを目にする機会がありやしてね、調べてみたら腹にも背中にも焼き鏝を当てられた痕がありやがった。誰がやったのかは、わからず仕舞いになりやした。どうせ、左銀次みてえな鬼畜の仕業でやしょう。あっしは娘の肌に焼き鏝を当てるようなやつが許せねえ。どうしても、許せねえんでやすよ」
又兵衛はうなずきもせず、すっと立ちあがった。
甚太郎が袖に縋りついてくる。
「旦那、左銀次なんぞは鵜にすぎねえ。鵜飼いの茂平をどうにかしなくちゃならねえんだが、茂平のやつは十手を預かっておりやす。だから、小者にゃ手が出せねえ。廻り方の旦那に訴えたら、こっちがひでえ目に遭うだけなんです。くそっ、茂平に泣かされている娘は大勢いるってのに。あっしは、十手を笠に着た壁蝨みてえな連中が許せねえ。旦那だって、そうでしょう。江戸っ子なら、茂平や左銀次みてえな悪党どもをのさばらせておくはずはねえ」
「言いたいのは、それだけか」
「えっ」
「おぬしは勘違いしておる。江戸に住んでおる者がみな、江戸っ子気質というわけではあるまい」
「はあ。でも、旦那はどうするおつもりで」
「どうするとは」
「悪党どもを懲らしめてやらねえんですかい」
「懲らしめるのは、例繰方の役目ではないからな」
「だったらどうして、ここにお越しになったので」
怒りをふくんだ目で問われ、又兵衛は平然とこたえた。
「味噌蒟蒻を食いにきただけさ」
がっくり肩を落とす甚太郎を尻目に、急ぎ足で茶屋から逃れていく。