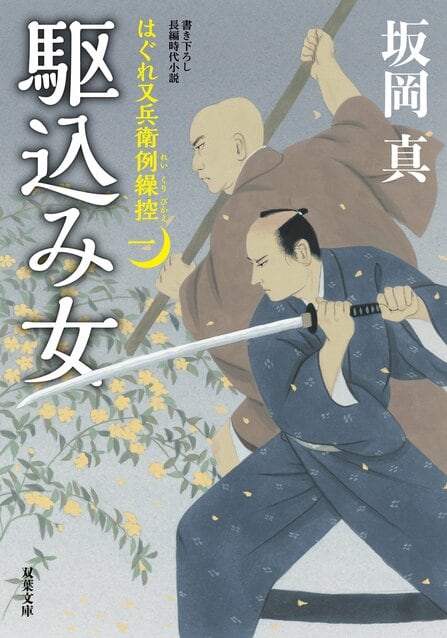三
誰もいない夕餉の膳には、牡丹餅と五目寿司が並んでいた。
「彼岸も終わったに」
賄い婆のおとよが作り置きしてくれた夕餉だ。
町奉行所の与力は南北合わせても五十人しかおらず、又兵衛の住まいは八丁堀のやや左寄りにある。二百石取りの一代抱えと定められてはいるものの、父から子へ役目を引き継ぐ者は多く、幕府も面倒臭いので黙認していた。
いずれにしろ、ほとんどの与力は所帯持ちである。冠木門のついた二百坪ほどの拝領屋敷は、独り身の又兵衛にとっては広すぎ、寒々とした印象を拭えない。
どの家でも住みこみの奉公人をあたりまえのように抱えていたが、独りを好む又兵衛はおとよ以外の奉公人を拒み、修行僧のような暮らしをしている。
十年前、吟味方の花形与力だった父は、乱心した浪人に道端で斬られた。そのときの傷が原因で半月後に逝き、母もあとを追うように還らぬ人となった。兄弟姉妹もいなかったし、早く所帯を持って両親を喜ばしてやりたかったが、ふたりが居なくなってみればそんな気力も何処かへ失せた。
ひとりでとる夕餉ほど侘しいものはない。
もちろん、だからといって、誰かを屋敷に入れる気もなかった。
嫁取りはする気にもならぬし、若党や挟み箱持ちの中間が必要なときは口入屋から通いの者を雇えばよい。
さっさと夕餉を済ませたら書見台に向かって医術や兵学の書を読み、気が向けば据え風呂を沸かして浸かる。たいていは風呂に浸からずに床へはいり、眠りが浅いときは庭に出て真剣を何百回と振りつづける。
長元坊しか知らぬことだが、又兵衛は香取神道流を極めた剣客でもあった。
座した姿勢から飛蝗のごとく跳躍し、中空で抜刀しながら相手に斬りかかる。同流の秘技とも目される「抜きつけの剣」を完璧に修得しており、当然のごとく免状も与えられていた。
よほどのことでもないかぎり、人は斬らぬ。真剣を差して町を歩くのは稀で、腰帯には常のように刃引きのなされた刀を差している。人の寝静まった真夜中にだけ、父から譲り受けた美濃伝の「和泉守兼定」を振りこむのだ。
──びゅん、びゅん。
掛け声は控えねばならぬので、ふっ、ふっと息の音しか聞こえてこない。
その代わり、風を切る刃音は凄まじい。
二尺八寸の長尺刀ゆえ、抜刀の際は鯉口を左手で握って引き絞る。この「鞘引き」に長じていなければ、宝刀を扱うことはできない。抜いては斬り、斬っては納め、退くとみせかけては前進し、左右に躱しつつ上に跳び、闇のなかで変幻自在の動きを繰りかえす。
微かな月光に照らされた互の目乱の美しい刃文だけが、又兵衛の荒ぶる気持ちを鎮める役目を担っていた。
──抜かずに勝つ。これぞ剣の奥義なり。
そう教えてくれた父は、刀を抜かなかったせいで乱心者の餌食になった。
無論、父の教えは正しいと信じつつも、又兵衛はいつも割り切れないおもいを抱えている。
へたばるまで「兼定」を振りこみ、ようやく床に就いた。
味噌汁の匂いに目を覚ますと、廊下の奥からおとよ婆の声が聞こえてくる。
「旦那さま、おはようさんで。ご飯をおつけしておきましょうかね」
「ん、頼む」
おとよの古漬けは、舌が痺れるほど美味い。
居間に仕度された箱膳には、納豆や目刺しも並んでいた。
文机の帳面や文筥と同様、茶碗や皿の置き方には又兵衛なりの決め事があり、わずかでも位置がずれていると、かならず修正してから食べはじめる。自分でも意識はしておらぬのだが、他人からみれば「鬱陶しいほど細かい」のだそうだ。
当然のごとく、四角い部屋を箒で丸く掃くような行為は我慢ならない。だからといって、きれい好きというのとも少し異なり、あるべき場所にあるべきものがないと落ちつかなくなる。生まれつきの癖ゆえ、こればかりは如何ともし難い。
ともかく、ご飯も味噌汁も温かいので、夕餉のような侘しさはなかった。
貪るように飯を平らげ、茶の出涸らしで椀を濯いでから箱膳の内にきちんと仕舞う。
「ご馳走さまにござりました」
大きな声を発しても、おとよはもう買い物に出掛けたあとだった。
又兵衛はやおら尻を持ちあげ、水玉の手拭いを肩に引っかける。
町奉行所の与力には、下々の者から羨ましがられる役得がふたつあった。ひとつ目は日髪日剃、廻り髪結が毎朝定刻にあらわれ、髪を結ったり月代を剃ってくれる。日髪日剃を断ることはあっても、ふたつ目の役得である湯屋の一番風呂だけは外すことができない。
ほかの与力や同心と鉢合わせになりたくないので、又兵衛はわざわざ亀島橋を渡って霊岸島まで足を延ばす。
馴染みにしているのは、橋木稲荷の裏にある『鶴之湯』であった。
亀島川の亀と屋号の鶴で長寿のご利益があると評判になり、いつも年寄りたちで賑わっている。一番風呂ならば、そうした年寄りたちと挨拶を交わす面倒もいらない。熱めの湯船に首まで浸かり、煩悩の数を諳んじながら一日のはじまりを迎えるのである。
何の気なく過ごしてはいるものの、よくよく考えてみれば、贅沢な暮らしなのであろう。独り寝が淋しいとこぼすのは贅沢にすぎず、その気になれば侘しい暮らしのなかにも楽しみはいくらでもみつけられた。
「芹萌えて、弾む足取り湯屋帰り」
などと、へぼ句を捻ったりもする。
あるいは、蕎麦が美味いと評判の見世には足を延ばさずにいられない。蕎麦にかぎらず、今時分の季節なら、鮟鱇でも軍鶏でも獣肉でも、美味いとなればかならず食べにいく。近頃は料理を盛りつける器なんぞにも興味を持ちだし、暇があれば骨董屋や質屋を素見してまわった。
外廻りのときは着流しでもよいが、八丁堀の役人とすぐにわかる髪形までは変えられない。又兵衛もほかの連中と同じに、額は広くして生え際をみせぬように小鬢まで剃りあげているし、短くした髷は毛先を散らさずに広げ、髱はひっつめずに出していた。
たとい、素姓がばれたとしても、素見しを止める気はない。物を買わずに素見してまわることこそが、又兵衛の秘かな楽しみなのだ。