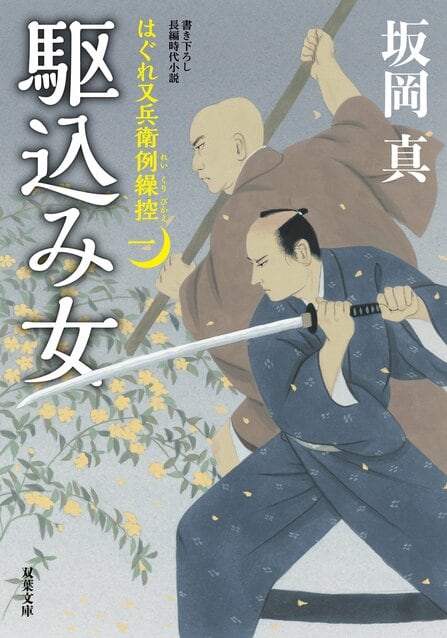いつの間にか夕陽は落ちて、往来を吹きぬける夕風に裾を攫われた。
我慢強く待っていた中間をしたがえ、数寄屋橋を渡って尾張町から銀座へ向かう。
京橋を渡ってしまえば、拝領屋敷のある八丁堀は近い。
が、又兵衛は弾正橋を目前にして足を止めた。
中間に向かってさきに帰っておくように命じ、楓川沿いを松幡橋のほうへ進む。すると、常盤町の片隅に「鍼灸揉み療治 長元坊」と、金釘流の墨文字で書かれた看板がみえてきた。
もはや、辺りは薄暗く、川沿いの道を行き交う人影もない。
引き戸を開けて踏みこみ、あまりの酒臭さに顔をしかめる。
「誰だ」
板の間の奥から、胴間声が聞こえてきた。
こたえずに雪駄を脱ぎ、勝手知ったる者のように奥へ向かう。
縦も横もある禿頭の男が、有明行燈の脇で五合徳利をかたむけていた。
七輪に網を置き、鯣烏賊を炙っている。
煤けた天井の棟陰には、家猫の目が光っていた。
「長助、あいかわらず暇そうだな」
親しげにはなしかけると、男はだらしない顔を向けてくる。
「又か。おれを長助と呼ぶな。長元坊と呼べ」
長元坊は隼の異称、鼠や小鳥を捕食するが、鷹狩りには使えない。人の意のままにならぬ猛禽の異称を、元破戒僧の薮医者は気に入っているらしい。
「長助は長助だ。ほかに呼び名はなかろう」
「この面で長助じゃ笑われる。幼馴染みでも許さねえぞ、長元坊と呼べ」
「わかったよ、長元坊」
「へへ、それでいい。さあ、ここに座れ」
言われたとおりにすると、欠け茶碗に冷や酒を注いで寄こす。
又兵衛は欠け茶碗をかたむけ、渋い顔をつくった。
「不味い酒だな」
「銭さえあれば、上等な下り酒を呑んでおるわい。知ってのとおり、揉み療治に通ってくるのは貧乏長屋の年寄りばかりだ。そいつらから銭は取れねえだろう。稼ぎのいい口があれば、乗ってやってもいいぜ」
「太刀魚の茂平という元締めを知っているか」
「太刀魚の……ああ、品川宿の裏を仕切っている爺さまだろう。ものの本に『肝に毒あり、洗い去るべし』と書いてあるのが太刀魚だ。おれの知るかぎり、茂平ってのは掛け値無しの悪党だぜ」
「なるほど」
「って、おめえ、茂平をどうする気だ」
「別に、どうもせぬさ」
「なら、何しに来た。言っておくがな、おれは銭にならねえことはしたくねえ。たとい、幼馴染みの頼みでもな、できねえものはできねえぜ」
「早合点するな。まだ、何も頼んでおらぬ」
「意地を張るな。おめえがここに来るときゃ、助っ人が欲しいときだろうが」
長元坊は「ふん」と鼻を鳴らし、欠け茶碗に酒を注ぐ。
「おめえは、むかしっからそうだ。弱音を吐いたら負けだとおもっていやがる。どうせ帰えっても、通いの飯炊き婆さんしかいねえんだろう。じっくりはなしを聞いてやっから、今日はゆっくりしていけ」
又兵衛はうなずきもせず、ぼそっとこぼす。
「昨晩、あさという娘が駆込んできた。門前で力尽き、抱え主らしき相手の名が書かれた文を遺して死んだ」
「抱え主ってのは誰なんだ」
「剃刀の左銀次、元髪結らしい」
「元髪結の筋から、太刀魚の茂平に繋がったってわけか。それにしても、腰の重い例繰方の与力さまがどうして首を突っこみたがる」
「あさには焼き鏝で折檻した痕がいくつもあった」
長元坊は禿頭を撫でまわし、ぴしゃっと小気味よく叩いた。
「女郎なら、そういうこともあるだろうよ。哀れなおなごなら、江戸にいくらでもいる」
「鬼左近も同じ台詞を吐いていたぞ」
「吟味方の糞与力といっしょにするな、けったくそわりい」
激昂する長元坊をみようともせず、又兵衛は尻を持ちあげた。
「おいおい、帰えるのか」
「ああ、馳走になったな」
「待てよ。葱鮪鍋でもつくってやっから」
「遠慮しておく」
「ったく、可愛げのねえやつだぜ。んで、もう一度聞くがな、どうして死んじまった女郎にこだわる。ひょっとして、知りあいなのか」
「知りあいではない。ただ」
「ただ、何だ」
「いや、たいしたはなしではない。ではな」
「おい、待て」
長元坊の太い腕を振りほどき、又兵衛は外へ飛びだした。
川端で夜風に吹かれていると、くうっと腹の虫が鳴きはじめる。
屋敷へ帰ったところで、冷や飯と菜が箱膳に並んでいるだけだ。長元坊の葱鮪鍋は絶品なので、ほんとうは相伴に与りたかった。が、やはり、唯一の友でもある幼馴染みを巻きこむことに躊躇いがあったのだろう。
むかしから腕っぷしだけは強かったが、闇雲に突っこんでいく危うさがある。それゆえ、よほどのことでもないかぎり、長元坊には助っ人を頼まないことに決めていた。
ただ、足が向いてしまったということは、少しばかり不安があったのかもしれない。ともあれ、明日は非番なので、高輪から品川のほうまで足を延ばしてみようと、又兵衛はおもった。