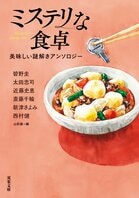ホテルの宿泊客と会えたのは、夕食の時間になってからだった。
夕食は七時からだと聞いていたので、ぎりぎりの時間になって下に降りていくと、すでに桑島さんも含めて、三人がテーブルに着いていた。
三人とも缶ビールを開けて、トルティーヤチップスをつまんでいる。
坊主頭の、精悍に日焼けした男が、ぼくに気づいて手を挙げた。
「やあ、きみも今日から?」
年齢は三十代くらいだろうか。サーフィンでもやっていそうな雰囲気だ。
もうひとりの男はもう少し上、アロハシャツなど着てはいるが、こちらはスーツ姿が容易に想像できる。平均よりは少しいい男、といった感じの、癖のない容姿をしていた。
そのふたりに挟まれて、桑島さんが機嫌良くビールを飲んでいる。
「木崎です。よろしく」
挨拶をして、向かいの席に座る。
坊主頭の男性が、佐奇森真、もうひとりが蒲生祐司と名乗った。
佐奇森たちは、すぐにぼくに興味を失ってしまったかのように、桑島さんとの話に熱中しはじめた。
「でさ、結局、ナナちゃんはどうしてこんなところにきたの? 傷心旅行?」
佐奇森がそう話しかけているのを聞いて、ぼくは心の中で苦笑いをした。
出会ってそんなに経っていないのに、ナナちゃんと呼べて、そして不躾な質問ができる。そんな男に生まれたかった。
こういうデリカシーのなさは欠点でもあるけれど、人と人との垣根を取り払うのには絶大な効果をもたらす。事実、桑島さんは、さきほどぼくと話していたときよりも、ずっと楽しそうにしている。
「違いますよう。そんなんじゃないです」
「じゃあ、なに?」
「ハワイが好きなんです。これまでも何度かきてるんですけど、できるだけ長く滞在したかったから……」
「仕事は?」
佐奇森は次々とプライベートに切り込む。蒲生はそこまでずうずうしくなれないのか、ただ横でにこにこしているだけだ。
「やめました。でないと三ヶ月なんていられませんよ」
そう言ったあと、桑島さんは少しいたずらっぽい顔になった。
「実は、来年結婚するんです」
「あいたたたた」
佐奇森は大げさに、頭を抱えた。
「なんだ、マジで? せっかく口説こうと思ったのに」
「うふふ、ごめんなさい。でもうれしいです」
ぼくは感心しながら、ふたりの会話を聞いていた。
桑島さんは相当、男あしらいがうまい。踏み込ませないのに、それでも相手に不快感は抱かせない。たぶん頭がいいのだ。
それにしても、和美さんの勘が正しかったというわけだ。
「遠距離恋愛だったんで、どうしてもわたしが仕事をやめなきゃいけなかったんです。だから、どうせやめるんだったら結婚前に好きなことをやりたいなと思って、大好きなハワイにできるだけ長く滞在することにしたんです。ここを拠点に、マウイやカウアイにも行きたいと思ってます」
そうこうしているうちに、和美さんが大皿を持ってやってきた。ズッキーニと鶏肉の炒め物のようだ。次に芹のスープ、それから茶碗に入った白いごはんが出てきて驚く。
和食ではないし、中華でもない。シンプルすぎる食卓だが、友達の家の夕食にもぐり込んだような懐かしさがあった。
もともと、腹がふくれればなんでもいいほうだ。
豪華とは言えなくても毎日食事を出してもらえるだけでありがたい。
男たちが自分の分を取り分けて、がっつきはじめる。芹のスープを一口飲むと、舌の上にうまみが広がる。
味付けは塩だけなのに、芹の鮮烈な香りのせいか、複雑な大人の味になっている。押しつけがましさもない。
疲れた身体を解きほぐすようなスープだった。
炒め物の方も、少し酸味のあるさわやかな味付けで、食が進む。
料理上手というには、あまりにも手のかからない料理だし、品数も少ない。だがそれでも和美さんの作る料理はうまかった。
これなら、食事に飽きることもないだろう。もっと豪華なものが食べたければ、外に食べに行けばいいのだ。
麦茶の入ったジャグを持ってきた和美さんに言う。
「おいしいです。和美さん、料理うまいんですね」
「適当、適当。そのうち飽きるわよ」
「いやいや、和美さんの料理はシンプルすぎて、飽きようがない」
佐奇森が茶々を入れる。そう言いながら彼も、自分の取り皿に炒め物を山盛りにしている。
「食事の提供はおまけなんだからね。うちはレストランじゃないんだから」
和美さんは冗談のように怒ったふりをしてみせる。
「本当です。おいしいです。こういうのさらっと作れる人、尊敬します。わたし、どうしても料理本通りにしか作れなくて」
そう言う桑島さんの肩を、和美さんは軽く叩いた。
「それは若いから。年を取ると、いやでも手抜きの方法は覚えていくって」
「そうなんですか?」
「ほんと、ほんと」
ぼくは、箸を止めてあたりを見回した。
やはり和美さん以外のスタッフの姿は見えない。まさか彼女がひとりで切り盛りしているということはないだろう。
それとも全部で六人の宿ならば、ひとりでも充分なのだろうか。
思い切って聞いてみた。
「ほかにスタッフの方は?」
「あとはうちの宿六。もうすぐ帰ってくるわ」
「つまり、オーナーは和美さんのご主人ですか?」
「ま、そういうこと。といっても、ヒロにもお店をはじめたからここだけじゃないけどね。宿六は建物の修繕とか、そっちが中心」
桑島さんが麦茶を、全員のグラスに注いでくれた。
「大変ですね。ほとんどひとりでやっていることになるじゃないですか」
「だから、少人数しか泊められないの。まあ普通のホテルと違って、シーツの洗濯も五日ごとだし、掃除も毎日するわけじゃないからね」
そう言えば、さきほど、掃除はしてほしいときだけドアに札をかけるようにと言われた。それ以外の場合は、部屋に入らない、と。
窓から、車のライトが差し込む。車が敷地内に入ってきたようだ。
空いた皿を片付けていた和美さんがつぶやいた。
「あ、帰ってきたみたい」
ドアが開いて、サングラスをかけた男性が入ってきた。背が高く、年齢は和美さんより少し上に見える。
挨拶すらせず、ぼくたちが座るテーブルの横を通り過ぎていく。少し怖いような気がした。
和美さんは彼を見送ってから言った。
「ごめんね、感じ悪くて」
今まで黙っていた蒲生が口を開いた。
「いや、洋介さんは別に感じ悪くないですよ。ちょっと人見知りなだけで、慣れると意外によく喋ってくれる」
「だって、技術職ならいいけど、客商売であれだもの。ちょっとひどいわよね」
隣の部屋のドアが閉まる音が聞こえた。
「その分、和美さんがカバーしてるんですよね」
桑島さんのことばに、和美さんは頷いた。
「まあね。でも気にしないでね。本当に人見知りなだけで、全然悪気はないのよ」
ぼくは蒲生の方を向いた。
「蒲生さんはここ、もう長いんですか?」
彼は顔のパーツを中心に集めるように笑った。
「長いったって、まあ二ヶ月半だからね。でもあと二週間で追い出されちゃうよ」
和美さんに向かって甘えるような声を出す。
「そろそろ働かなきゃならない頃でしょ。覚悟しておきなさい」
和美さんは笑いながらそう言った。皿を持ってキッチンに消える。
なんとなく気づいた。たぶんここでは、和美さんがみんなの母親のような役割を果たしているのだ。
年齢ではなく、彼女の性格の問題だろう。心地いいのも頷ける。
ふいに思った。
長すぎる夏休みは心を蝕む。そう言ったのは、洋介という和美の夫か、それとも和美か。
彼らは長すぎる休暇に、心が朽ち果てたことがあるのだろうか。