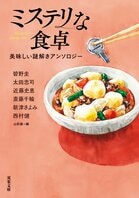ヒロの町は一瞬で通り過ぎてしまった。ハワイで二番目に大きい町といっても、こんなものなのか、と驚く。
パームツリーの並木の向こうに海が見えて、やっと南国らしい風景になる。空は相変わらず薄曇りだが。
ホテル・ピーベリーはヒロの町から車で二十分くらいの距離だと聞いた。
車に乗ってからまだ数分しか経っていないのに、桑島さんはもう和美さんと話が弾んでいる。
「ホテルにいるのは日本人ばかりなんですか?」
「今はそう。たまに中国や韓国の人もくるけど……まあ、オーナーが日本人だからね。どうしてもそうなるわ。今は日本人の男が三人。今日から女の子がくるって言ったら舞い上がってたわ。まあ、妙なことをするような人はいないと思うけど、なんかいやなことがあったら言ってね」
「いえ、大丈夫です」
ヒロを抜けてしばらくすると、急に太陽が明るくなった。思わず声が出た。
「ああ、晴れてきた」
和美さんはくすりと笑った。
「ハワイ島は天気の変化が激しいの。雨が降ってたかと思うと、急に晴れるし、かというとまた急に雨が降るし……雨が降りやすい場所といつも晴れている場所もあるから、ドライブしてて、雨に遭わないってことはないわね。必ずどこかで雨は降っている」
「そうなんですか……」
うまく話題を広げることができずに、ぼくは相づちだけ打った。
「あなたたち、車の運転はできる?」
和美さんの質問に、桑島さんが頷いた。
「はい、できます」
ぼくは少し口ごもる。免許は持っているが、ペーパードライバーだ。しばらくハンドルを握っていないから、運転できるかどうか怪しい。
そう言うと、和美さんはちらりと後ろを見た。
「見ての通りの一本道。信号だって滅多にないし、対向車もあんまりこない。日本で運転するよりずうっと簡単。ひさしぶりにハンドル握ったって大丈夫よ。さすがに無免許じゃまずいけど」
「でも、国際免許を取ってこなかったから……」
そう言うと今度は桑島さんが振り向いた。
「ハワイは日本の免許証があれば大丈夫」
どうやら、彼女はきちんと下調べをしていたらしい。旅慣れているのだろうか。
女性はこんなとき、往々にして男性よりも頼りになることが多い。
「ハワイ島は車がないと、ほとんど身動き取れないわよ。バスもないことはないけど、一日二本とかだから」
思わず少し笑ってしまった。東京で生まれ育ったぼくには考えもつかない世界だ。
「あと、ヒロに行くなら、わたしが買い物に出るときか、朝、うちの宿六がヒロに仕事に行くときに一緒に乗せていってあげることはできるわ。帰りの時間も合わせてもらうことになるけど」
つまり、和美さんは既婚者で、旦那はヒロで働いているということだ。
「やどろく?」
桑島さんが小首をかしげて、その単語を繰り返した。
「あはは、若い人はこんなことば知らないわよね。夫のことよ」
道路は次第に山に分け入っていく。といっても急な道ではなく、なだらかな傾斜が続いているだけだ。
「なんかさ、男が自分のパートナーを紹介するときって、『かみさんが』とかラフな単語があるでしょ。でも、女だと『旦那』とか『主人』とかになるじゃない。なんか、slaveっぽくっていやなのよ」
slaveと言ったときの発音が、英語を喋り慣れている人のものだ。ぼくは思わず口を挟んだ。
「かみさんだって、元々は尊称ですよ」
「え?」
「語源には諸説ありますけど、『山の神』からきているという説が強いです。もともと日本の山の神様は、女性だと言われています。『うちの山の神様』ですからね。比喩的なものだとしても、旦那や主人と同じくらい、敬ったことばだと思いますよ」
「そうなんだ……知らなかった」
桑島さんが、また後ろを向いてそう言った。ぼくは苦笑した。
昔の自分など脱ぎ捨てたつもりだったのに、ふとしたときに頭をもたげてくる。髪の色や服装で周りの人の目はごまかせても、自分自身はごまかせない。
「へえ……木崎くんって物知りなんだ」
「たまたま知ってただけです」
いやらしく謙遜してみる。まだぼくは、昔の自分をそのまま受け入れることができない。できれば切り離したいと思っている。
「着いたわよ」
少し先に、二階建てほどの一軒家があるのが見える。
青い屋根に白い壁、バルコニーや外にある階段は紫がかったピンク。可愛らしい色使いだが、雨風にさらされたせいでいい具合に色あせている。
小さなプールがあり、プールサイドにはデッキチェアが並んでいた。
フロントガラスに雨粒がぽたり、と落ちた。気づけばまた空は暗くなっている。
車は無造作に、家の前に停まった。
Hotel Peaberry と書かれた白い看板が、道路に向かって立っている。
車を降りた桑島さんが、空を見上げてつぶやいた。
「あいにくの雨ね」
「ここは雨が多いの。その代わり、作物はよく育つけどね」
和美さんは、トランクから桑島さんの大きなスーツケースを下ろしながらそう言った。
ぼくも車を降りて、外の空気を吸い込んだ。
霧のように細かい雨だった。濡れていることがそれほど不快ではない。
ホテルは高台に建っていて、眼下に海が広がっていた。
和美さんは、桑島さんのスーツケースをホテルに運んでいた。ぼくは自分のバッグを肩にかけた。
ここが気に入らないわけではない。寂しいのも不便なのも覚悟のうちでやってきた。
建物は思っていたよりも感じがいいし、景色も気持ちいい。
なのに、ぼくはひどく戸惑っていた。
自分で望んでここまできたはずなのに、目に見えないものに無理矢理引きずられてきたような気がしているのだ。
これが、旅の感傷というものなのだろうか。
ぼくにあてがわれたのは二階のいちばん奥の部屋だった。
六室というから、ペンションのような間取りを想像していたが、アパートのように外側の廊下に沿って各部屋のドアが並んでいる。ホテルの横についた階段を通って、そのまま外に出られる構造になっていて、プライバシーも守られている。
だれにも会わずに外に出るのも簡単だし、もちろん部屋にこもっていても、それを知られることはない。
一方で一階には、朝食や夕食がとれるカフェのようなスペースと、宿泊客が自由に使える共同のキッチンがあった。
和美さんの話では、ここによく宿泊客が集まって時間を潰しているということだった。
朝食は宿泊代に含まれているが、夕食は前日から予約をすることで、別料金で用意してもらえる。もちろん自炊をしてもいい。買い物は自分でしなければならないが、手に入りにくいものでなければ、頼めば和美さんの裁量で買ってきてもらえることもある。
だが、その日の午後、ホテルには人の姿はなかった。
和美さん以外のスタッフも見かけないし、宿泊客らしい人間もいない。急に不安になる。
杉下のことばを鵜呑みにしてやってきてはみたものの、ホテルのオーナーが替わって、前のように快適な場所ではなくなっている可能性もある。
だが、建物や設備は古いものの、きちんと隅々まで掃除が行き渡っているのがわかる。さっき、荷物を置きに上がった部屋も清潔だった。
人がいれば、その表情でだいたいの雰囲気はわかる。
おそるおそる尋ねてみた。
「だれもいないんですね」
「午後はね。どこかに観光に行っているか、部屋で昼寝してるんじゃない? 夜になれば会えると思うわ」
車は宿泊客が使ってもいいものが二台ある。使いたいと思った日に予約を入れて、空いていれば使える。ただし、旅行保険に加入している人のみ。
「それと、サドルロードは絶対に走らないこと。これだけが決まりね」
「サドルロード?」
「ヒロからサウスコハラに出る200号線のこと。道が悪いから、事故が多いの」
和美さんは空に指でハワイ島の形を描いた。
「ほとんどの道は海岸線沿いを通るんだけど、サドルロードはまっすぐにハワイ島を横切るの。便利と言えば便利なんだけど……住んでいる人以外には危なすぎるわ」
「わかりました」
ペーパードライバーで運転には自信がない。今日きた、空港からホテルまでの単純で、信号すらほとんどないような道ならば、運転できるかもしれないが、好きこのんで危ない道を通る趣味はない。
桑島さんが、キッチンの窓から写真を撮っているのが見えた。
さっき、ぼくもその窓から外を見た。ちょうど目の前に海が広がっていて、気持ちのいい景色だった。
ふいに、和美さんが声を潜めて言った。
「木崎くん、彼女いるの?」
「え……?」
唐突な質問に、ぼくは戸惑った。
普通、女性からそんな質問をされれば、相手がぼくに好意を持っているのかとうぬぼれてしまうだろう。
だが、和美さんはずいぶん年上で、しかも既婚者だ。単なる好奇心だろう。
「彼女がいたら、三ヶ月もこの島に滞在しませんよ」
「そうとは限らないわよ。つきあっていても、ドライなカップルはいくらでもいるでしょ」
和美さんは、まだシャッターを切っている桑島さんの方をちらりと見た。
「あの子だって、日本に彼氏がいると見たわね」
「そうですか? 彼女も三ヶ月いるんでしょう」
ぼくならば、自分の彼女が三ヶ月も自分から離れてしまうなんて考えられない。仕事や留学など、大きな目的があるのなら仕方がないが、もしそんな目的があるのならこんなへんぴなホテルに泊まることはないだろう。
和美さんは唇に指を当てて言った。
「根拠はないけど、おばさんの勘よ」
どちらかというと、傷心旅行の方が可能性は高いのではないか。そう思ったが、それ以上言うのはやめた。
女性心理を察することがうまいとは、自分でもまったく思えない。おばさんの勘にかなうはずはないのだ。