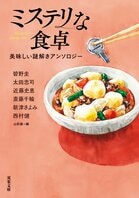食事が終わったあと、ベッドに倒れ込んでしばらく眠った。
目が覚めたときにはすでに真夜中だった。
無理もない。日付変更線を越えて、ここまでやってきた。飛行機の中で少しは眠ったが、そのあとは起きっぱなしだ。指先まで疲れ切っている。
ただ、心地よい疲れなのは事実だ。
仕事をやめてからは、立っていられないほど疲れたことなどなかった。身体が疲れなくなった代わりに、心にぬるぬるとしたものがまとわりついて蓄積していく。
不思議なことに、身体が疲れた分、その心の澱が流されたような気がするのだ。
きてよかった。少なくとも今はそう思っている。
だれもぼくの過去になど関心を持とうとしなかった。どうして教師を辞めたのかと聞かれたら、どう答えようかとばかり考えていたのに、ここにくるまでになにをしていたかも聞かれなかった。
桑島さんがいたから、ぼくに好奇心を向ける暇がなかったという可能性もあるが、それでもいい。
今はできるだけ、どうでもいい存在でありたかった。
ふと気づく。今日、夕食時に会ったのは、佐奇森と蒲生。だが、和美さんは車の中で、男性が三人泊まっていると言わなかっただろうか。
いや、夕食を食べなくてもおかしくはない。外で食べてきたかもしれないし、時間をずらして自炊しているかもしれない。
宿とはいえ、ここはユースホステルではないし、交流を望まない人間もいるだろう。もちろん、ただ出かけていただけかもしれない。
窓を開けると、心地よい風が吹き込んでくる。
部屋に冷房がないことを、最初は不安に思ったがこうやって夜になってみるとよくわかる。冷房など必要はないのだ。
夜半過ぎの風は、むしろ肌寒いほどだ。日本の夏は、夜になっても熱気が残っているが、この島の暑さは、日のあるうちだけだ。
日が沈むと同時に、地面も空気も冷える。
それにしても静かだ。信じられないほど静かだ。
椰子の木を揺らす風の音以外、なにも聞こえない。外は闇に塗り込められているが、音もまたどこかに封じ込められてしまったようだ。
ふいに、水音が響いた。
決して大きい音ではないのに、この静けさの中でははっきりと聞こえる。
水音は続いている。水を打つような音だった。まるで泳いでいるような。
そういえば、ホテルの横に小さいながらもプールがあったことを思い出す。
だれかがこんな時間にプールで泳いでいる。不思議だが、音からはそうとしか思えない。
いつの間にかすっかり目が冴えてしまっていた。ベッドから起き上がり、おそるおそるドアを開けた。
ドアの外に出て驚いた。夜なのに明るい。
いや、もちろん街灯で照らされた東京の夜よりは暗い。だが、なにひとつ灯りがないにしては明るすぎる。
空を見上げて気づく。月だ。月がすぐ近くにある。
満月だった。手を伸ばせば届きそうなほど空が近い。
ぼくは息をのんで、空を眺めていた。
ハワイ島は星が美しいとは聞いていた。各国の天文台もマウナケアという山にあり、島全体が星の観測のため、街灯を控えめにしているらしい。
だが、思ったほど星は見えない。月のせいだ。
月が大きすぎて、星がかき消されているのだ。
ぼんやりと見とれていると、下から声がした。
「新入りか?」
見下ろせば、プールで立ち泳ぎをしながら男がこちらを見ていた。
はっきりと姿は見えないが、声の響きからは若い。たぶん、ぼくと同じくらいだ。
名乗ろうかと思ったが、こんなお互い顔の見えない状況で名乗っても仕方がない気がする。
とりあえず、「そうです」と答えた。
彼はまた泳ぎはじめた。戸惑いながら、それを見下ろす。
プールの端までたどり着くと、プールサイドに上がり、身体を拭く。痩せたシルエットが月明かりのせいで、長く伸びる。
黙って見下ろしているのも妙な気がして、尋ねた。
「寒くないんですか?」
返ってきた返事はシンプルだった。
「寒い!」
身体をぬぐい終わると、パーカーのようなものを羽織って、階段を上がってくる。
やっと顔が見える。想像したとおり、ぼくと同い年くらいの男だった。長めの髪を後ろでまとめている。
ぼくは笑った。
「寒いのに泳ぐのか?」
「日焼けするのがいやなんだよ」
「美白?」
からかうように言うと、大げさに顔をしかめた。
「日に焼けると、体中が痛くなる。真っ赤になって因幡の白ウサギみたいになる」
そう言われてはじめて気づいた。近くで見た彼の皮膚は、病的なくらい真っ白だった。身体には適度な筋肉がついているが、ここまで色が白いと確かに日焼けはきついだろう。
彼は、廊下の手すりに身体を預けてこちらを見た。
「これから三ヶ月いるのか?」
「ああ、そのつもりにしている。きみは?」
彼は顎のあたりに手を当てて、息を吐くように笑った。
「俺は……あと一ヶ月ってとこだな……」
なぜか彼の口調に、嘲笑のようなものが潜んでいる気がした。
彼はパーカーの前を合わせて身震いをした。唇が白い。
「やっべえ、こんなところにいたら風邪引く」
彼は自分の部屋のドアに手をかけて、鍵を開けた。ぼくの隣の隣の部屋だった。
部屋に入る前に、彼はこちらを見て笑った。
「楽しみにしてろよ。きっとおもしろいものが見られる」
「え?」
聞き返す間もなく、ドアは閉まった。名前を聞き忘れたことに気づいたのは、そのあとだった。
この続きは、書籍にてお楽しみください