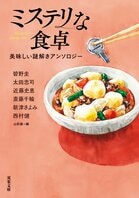杉下は、ハイボールをちびちび飲みながら言った。
「もったいないじゃないか。四ヶ月もなにもしてないんだろ」
「本は読んでるよ。映画もDVDで観てる。別に暇をもてあましているわけじゃない」
これは少し強がりだ。
家にこもって本ばかり読んでいるのは、本当に本が読みたいからではなかった。ほかになにもすることがないからだ。
毎日が無駄に終わったと思うのが怖くて、たまっていた本を片付けているだけだ。
「まあ、無理にとは言わないけれどさ……」
杉下はあきらめたようにそう言った。
海外旅行なんか興味がないと決めつけていたのに、そうなるとなぜか急に気にかかる。
「小心者だから、危ないところとか行きたくないんだよな。不潔なところも駄目だし」
「安全で清潔なところに行けばいい。ヨーロッパとかならそれほど危険じゃない。アジアに比べれば金はかかるが」
「ふうん……」
そう言われてもヨーロッパに見たいものなどない。町並みが美しくて、美術館には教科書で見たことのある名画が並んでいるのだろうということは想像できても、魂が揺さぶられるようなものはなにもなかった。
ふいに杉下が目を輝かせた。
「ハワイはどうだ?」
「ハワイぃ?」
不満そうな声を出してしまったのにも理由がある。
その当時、ぼくがハワイに抱いていたイメージはたったひとつ││正月になると芸能人やミーハーな人々が大挙して訪れる島││だった。
海で泳いで、ブランドものを安く買う。日本人があふれて、どこでも日本語が通じるリゾート。そこになにか新しいものがあるとは思えない。
新婚旅行かなにかで行くのならまだしも、たったひとりで行ってなにをするというのだろう。
杉下はそんなぼくの反応も予想していたようだった。
「あ、馬鹿にしたな。でも、意外にいいんだよな。あそこ」
「家族連れやカップルばかりだろう。よけいにいやな気分になる」
「ホノルルはな。でもホノルルはハワイのほんの一部だ。オアフ島でもホノルルから離れれば、日本人の家族連れの数はぐんと減るし、マウイ島やハワイ島やカウアイ島まで行けばそれぞれ風景も空気も違う」
ぼくは杉下も、ハワイなど馬鹿にしているとばかり思っていた。
最近、彼が行ったのもラオスやブータン、スリランカなど、メジャーな観光地とは言えない国ばかりだった。
そう言うと彼はにやりと笑った。
「実は俺も行くまではそう思ってた。でもあそこは不思議な島だよ。行った人間を魅了するんだ。小さな島々なのに、信じられないくらいいろんな顔を持っている」
「へえ……」
「なんたって、気候がいい。暑いには暑いが、風がさわやかだ。人も親切だし、それこそ日本語が通じる場所も多い。旅行のストレスはほとんど感じなかった」
「なるほど」
ヨーロッパと聞いたときにはまったくそそられなかった気持ちが、少し浮き立つのを感じた。
ヨーロッパの人々はよそよそしいイメージだが、南の島の人はあたたかそうだ。大柄でよく太っていて、いつも明るい。
そのときはちょうど十月で、急に寒くなったことも関係していたのだろう。ぼくは南に行きたかった。まぶしいほどの太陽が見たかった。
「ハワイ島に行ったとき、おもしろいホテルがあったんだ」
そのときは知らなかったのだが、ハワイ島はハワイ諸島の中でもっとも大きい島だ。ハワイ諸島の中で区別をつけるために、地元の人々はビッグアイランドと呼ぶ。
「日本人が経営してるんだけどさ、長期滞在者割引があって、ほかのホテルに泊まるよりも長期ならぐんと安い。町からは少し離れていて不便だが、ホテルの中にプールもあるし、なにもせずにだらだらするのにはもってこいだ。部屋は全部で六室だったかな」
「六室? 小さすぎるだろう」
「まあな。ホテルというより、B&Bと言った方がよさそうだ。でも部屋もきれいで飯もうまかった」
ぼくは首をかしげた。隣の合コン集団は、盛り上がらないままに席の並び順を変えている。
「でも、そんないいホテルで、しかも部屋数が少ないのなら予約が取りにくいんじゃないのか?」
「それがそうでもないんだ。なぜなら、このホテルには妙なルールがある」
「ルール?」
「そう、そのホテルに客が泊まれるのはたった一回だけ。リピーターはなしだ」
それを聞いて驚く。普通、そんな小さいホテルはリピーターを当て込んで営業するものではないのだろうか。
「どうしてだ?」
「オーナーが言うのには、常連客ばかりで馴れ合っている宿の空気が嫌いなんだと。まあ、俺もバックパッカーだからわからなくもない。長期滞在の多い安宿は、その宿の主みたいなのがいたりするからな。しがらみから自由になりたくて、日本を飛び出しているのに、その先でまたしがらみ作ってどうするんだとぼくも思うよ」
それは日本を出たことのないぼくにはよくわからない。
「もともとオーナーもバックパッカーだったらしい。世界を放浪して『長すぎる夏休みは人の心を蝕む』という結論に達したと言っていた」
胸にかすかな痛みが走った。それはぼくも気づきかけていた。長すぎる休暇はたしかにぼくの心を侵食していた。澱のようなものが次第に心に溜まってきているのに、それでも身体は自堕落さに慣れて、なにもしたくないと思い始めていた。
「だから、その宿ははじめての客しか泊めない。いちばん長くて三ヶ月。アメリカにビザなしで滞在できるのは三ヶ月が最長だからな」
杉下は静かに首を横に振った。
「俺はあんまりよく考えずに一週間しか滞在しなかった。普段もひとつの都市には一週間しかいないことにしているから。でも、今になって思えば三ヶ月あそこにいればよかったよ。一度泊まったからには、もうあそこへは戻れない」
彼があまり懐かしげに言うから、ぼくもこう尋ねてしまった。
「そのホテルのことを、教えてくれないか?」