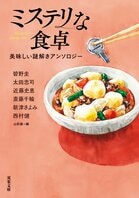きょろきょろとしていると、そばに白いバンがすうっとやってきて停車した。窓が下がって四十歳くらいの日本人女性が顔を出した。
「木崎くん?」
「あ、はい、そうです」
ぼくの名前を知っているからには、この女性がこれから滞在するホテルの人なのだろう。
後ろのドアを開けてくれたので、後部座席に乗り込む。
無造作にパーマをかけた髪と大きなサングラス。友達との会話などではおばさんと呼んでしまいそうな年格好だが、本人はおばさんと呼ばれたら怒るだろう。
日本人なのはひとめでわかるが、一方で日本にいる同じ年代の女性とはどこかが違った。美白など気にすることはないかのように、肌は日に焼けてうっすらしみが浮いているし、なにより、日本でこの年代の女性は、こんな服装をあまりしない。
上半身は背中がクロスになったキャミソール一枚で、ブラジャーさえしていないことがはっきりわかる。あとはハーフパンツにビーチサンダルだけだ。
痩せていて、胸もほとんどないからいやらしさはほとんど感じないが、やはり少し戸惑う。
五ヶ月前までは小学校の教師として働いていた。同僚にもこの年代の女性はいたし、生徒の母親にも多い年代だった。家庭訪問やPTAの総会などで会う人たちは、たいてい化粧をして、夏でもストッキングをはいている。たまに、ラフな服装をしている人がいても、せいぜいTシャツとジーパンだ。
こんな格好をしている人がいれば、白い目で見られるだろう。
ぼくが乗り込んでも、彼女はなかなか車を動かそうとしなかった。ハンドルに腕を乗せて、空港の出口を見ている。
「どうしたんですか?」
「もうひとり同じ便でくるはずなんだけど」
数部屋しかない小さなホテルで、しかも長期滞在者がほとんどだというから、てっきりぼくひとりなのだと思っていた。
すぐに、先ほど、荷物レーンで見かけたOLのような女性が自分の身体ほどもあるスーツケースをごろごろと押して歩いてきた。だれかを探すようにあたりを見回している。
もしや、と思っていると、運転席の女性が窓を開けた。
「桑島さん?」
彼女がぱっと笑顔になる。
「ホテル・ピーベリーの方ですか? よかった」
運転席の女性は、ドアを開けて車から飛び降りた。
スーツケースを受け取って、後部のトランクに載せる。細い腕に筋肉が浮き上がった。
車に乗り込もうとした桑島という女性は、ぼくに気づいてはっとした顔になる。
ほかに客がいるとは思っていなかったのだろう。
ひとりだと思っていたのに、同乗者がいたという鬱陶しさは、さきほどぼくも感じた。なのに、若い女性にあからさまにそういう顔をされると、自分勝手にも少し傷つく。
こんなことなら、さっき荷物を下ろすのを手伝ってあげればよかった。少しは印象もよくなっただろう。
ただでさえ、ぼくは髪を金髪に染めている。お世辞にも好青年とは言えないだろう。
彼女はぼくの座っている列ではなく、ひとつ前の列の座席に腰を下ろした。
「木崎淳平くんと、桑島七生さんね。わたしは瀬尾和美。よろしくね」
運転席の彼女はそう言った。
桑島さんの髪からはふわりといい匂いがした。きちんとブローされ、下品でない程度に染めた髪。
「和美さんはホテルの……?」
桑島さんは答えを和美さんにゆだねるように、曖昧に尋ねた。
「スタッフよ。ふたりとも何でも聞いてね」
「よろしくお願いします」
桑島さんが晴れやかな声でそう言った。ぼくも挨拶をしていないことに気づいて、あわててぺこりと頭を下げる。
和美さんは、髪をかき上げて笑った。
「こちらこそよろしくね。ま、なんにもないけど、そこがいいところよ」
ハンドルを切って車をUターンさせる。
彼女は笑いを含んだ口調で言った。
「日本じゃ、なにもしないでいることも難しいでしょ」
ぼくにこのホテルのことを教えたのは、杉下という友人だった。
高校の同級生だったが、大学時代に海外旅行にはまり、定職に就かないまま旅に出てばかりいる。引っ越し業務や宅配便の配送など、実入りのいい仕事で二、三ヶ月働いて金を貯めると、それを持って数ヶ月や半年海外に出る。その繰り返しだった。
性格はまったく似ていなかったのに、なぜかウマが合い、杉下が日本に帰ってきている間は、しょっちゅう一緒に飲み歩いていた。
それは、ぼくが仕事をやめて、四ヶ月ほど経ったときのことだった。
チェーン店の安い焼き鳥屋で、隣の席にはまったく盛り上がらない合コン集団がいた。その重苦しい空気がこちらにも伝わってくるようで、ぼくたちの話もいつものようには盛り上がらなかった。
鶏皮を歯で引き抜いた後、杉下が唐突に言った。
「おまえさ、海外にでも行ってきたら?」
そのときは、彼が自分の趣味をぼくに押しつけようとしているとしか思えなかった。
「え? やだよ。英語できないし」
「できないって、おまえ高校の時、成績よかったじゃないか。中学から大学まで十年も勉強して、できないはずないだろ」
「できないよ。練習問題は解けても、喋れない」
「練習問題が解けるってことは、語彙も豊富だし文法もわかってるってことだろ。あとは慣れだけだよ」
普段は自分の嗜好をこちらに押しつけることなどない男なのに、なぜかこの日は執拗に食い下がった。
たぶん、彼はぼくのことを心配していたのだろう。
不思議だった。これまではずっと、ぼくが杉下のことを心配していた。今はそれでよくても、彼女と結婚するときはどうするんだとか、力仕事はいつまででもできるわけじゃないとか、小言めいたことを言ったこともある。
その構図が逆転して、彼がぼくを心配するようになるとは考えもしなかった。
ぼくが学校を辞めたいきさつは話していないが、普通なら教師は年度の途中で退職したりしない。自己都合の退職だったが、なにかがあったことは察していたはずだ。
しかもいつまで経っても新しい就職先を探そうともしないし、しかも髪まで金髪にした。金髪のまま、教師として雇ってもらえるはずはない。髪を染めたことで、ぼくは教師として再就職するつもりがないことを意思表示したも同然だった。
本当のところは、ただやってみたかった、というだけにすぎなかった。
美容室で、冗談のように「金髪にしてみたい」と言うと、担当の美容師がその気になってしまって、やっぱりやめると言い出せなかった。
それでも金髪にした時点で、妙な解放感があったのは事実だ。
持っていた服はスーツも含めてなにもかも似合わなくなり、新しい服を買わなければならなくなった。
周囲の人々の反応が変わったのもおもしろかった。電車の席も、いつまでもぼくの隣だけが空いていたし、警察の職務質問もよく受けるようになった。
たかが髪の色ひとつで、ここまで扱いが変わるということが、羊のような人生を送ってきたぼくには、珍しく、しかも楽しかった。