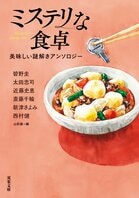目が覚めると、毎日のように雨が降っていた。
この土地の雨は、いつも同じ表情をしている。夕立のように、一瞬の激しさであたりをずぶ濡れにしてしまうことはないし、ざあざあと音を立てて降り注ぐこともない。
この土地の雨は、霧に混じるようにひそやかに、そして静かに地面や木々を湿らせる。少し歩くくらいならば、傘を差す必要はない。
不快ではないとはいえ、ここにくる前に抱いていたイメージとは百八十度違う。もっと、常夏のまぶしいほど暑い太陽を想像していた。
だが、少なくともぼくが滞在しているこの町は、泳ぐのには少し肌寒い。海に入っている地元の人々もいるが、ぼくはそんな気にはなれなかった。
四国の半分以上あるという、この大きな島でも、雨が降る場所は限られているらしい。西の方の海岸線沿いでは、ほとんど雨は降らない。
ひとつの島が、雨の降る地域と降らない地域に、くっきりと分けられることは、それまで日本から出たことがなかったぼくには、かなりの驚きだった。
よく考えれば、それは少しも不思議なことではない。
人間だって、土砂降りばかりの人生もあれば、曇り空さえないように見える人もいるではないか。
第一章
飛行機は旋回して、だだっ広い大地に降りた。
お世辞にも上手とは言えない着地のあと、機体はゆっくり滑走路を滑っていく。
ぼくは、肘掛けから手を離して、深く深呼吸をした。飛行機は苦手だ。
今まで飛行機に乗ったのはたった一度だけ、大学の卒業旅行で沖縄に行ったときだ。たった二時間半だったのに、背中は鉄板のように強ばり、手のひらが汗でぬるぬるになった。一緒にいた仲間たちから、ずいぶんからかわれた。
大学生のときのぼくは、仲間たちから頼りにされ、仲間たちを引っ張っていくタイプだった。そんなぼくが、飛行機が怖いと言うのがおかしいと彼らは笑った。
たった四年ほど前のことなのに、ずいぶん昔のように思えた。
たぶん、時間ではない。ぼくが遠い場所まできてしまったということなのだ。
成田からオアフ島までは七時間。そこで乗り継いで、ハワイ島まで一時間。計八時間乗っても、飛行機には少しも慣れることができなかった。
これが、一週間くらいで帰る旅行でないことが、今は心底ありがたいと思う。
帰国便は三ヶ月後。長い長い休暇だった。
日本であくせく働いている友人や知人が聞いたら、うらやましがるのか、それともあきれるのか。
飛行機が停止し、乗客たちが席を立つ。ぼくも機内持ち込み用のリュックを手に立ち上がった。
飛行機を出て、タラップに立って一瞬戸惑う。
なにもない。そう思ったのだ。
だだっ広い滑走路と、それを区切るフェンスは見えた。だが、フェンスの外にも建物などなかった。
分厚く重そうな雲が、遠くの方、地面ぎりぎりまで広がっていた。
後ろの大柄なアメリカ人が咳払いをした。立ち止まっていたことに気づいたぼくは、あわててタラップを降りた。
乗客たちがぞろぞろと向かっている方向にはゲートがある。あそこで乗る際の手続きをするのだろう。だが、その先にはビルや建物はない。ゲートをくぐった先も屋外だ。
屋根もない売店やレストランらしきものがあるだけで、空港と呼ぶのにはあまりにも貧相だ。日本では、地方の駅ですら、もう少しいろいろあるだろう。
戸惑いを隠せないまま、後ろの乗客に押されるようにゲートをくぐり抜けた。
さすがに荷物をピックアップするところに屋根はあるが、そこに寄らなければ飛行機を降りてそのまま外に出てしまえる。
入国手続きは、ホノルルの空港で済ませているから、このヒロ空港でしなければならない手続きはなにもない。そうわかってはいても、なにか忘れ物をしたようで落ち着かない。
だが、はじめて知った。
大きな建物や山がなければ、地面ぎりぎりまで空が続くのだと。
日本では、地面ぎりぎりまで続いている空などほとんど見られない。見られるとしたら、海の向こうに広がる空だけで、そうでなければ空は途中で途切れている。
空は高いところにあるものだと思っていた。そうではなく、地面から数センチ上でもその間に遮るものがなければ、そこには空がある。
そんなことを考えながら、預けた荷物が出てくるのを待つ。
そんなに大きな荷物ではない。パラシュート素材の旅行鞄の中には、Tシャツと替えのジーパン、あと下着が少し入っているだけだ。貴重品やノートパソコンはリュックに入れてるし、カメラは悩んだ末、家に置いてきた。
ほかに必要なものは、こちらで入手すればいい。
ベルトコンベアーの上を、スーツケースに交じって流れてきた自分のバッグを見つけて、持ち上げる。
日本人の若い女性が、巨大なスーツケースと格闘している。ほかの旅行者と比べても、ひときわ大きいスーツケースで、百リットルは入るだろう。
ちらりとこちらを見た目が助けてほしそうだと思ったが、関わり合いになるのは面倒だ。
顎のとがった、顔の小さいかわいらしい女性だったから、数ヶ月前のぼくならば喜んで手伝っただろう。
売店の横を通ると、冷蔵ケースの中にプルメリアのレイが食品のように収められているのが見えた。売っているのだろう。
昔、どこかで見た映像では、ハワイに到着する旅行客の首に、現地の女性がこのレイをかけていた。歓迎の意を示すのだと聞いたことがある。
なんとなく、自分の首にも、現地の豊満な美女がレイをかけてくれるような気がしていた。ツアーでハワイを訪れたなら、そんなサービスだってあったかもしれない。もちろんツアー代に込みで。
だが、そうでなければ、歓迎のしるしすらショーケースに収められて金を出して買うほかはないのだ。
ともかく、この地に降りて、まだ十分も経たないのに、ぼくはなにもかもが思っていた情景と違うことに困惑していた。
ハワイは日本人だらけで、どこに行っても日本語が通じると聞いていたけど、日本人は少ししかいない。
ホノルルまでの飛行機は日系航空会社を利用したから、日本人はたくさん乗っていたが、みんなホノルルで降りてしまったようだ。
ヒロというのは、ハワイで二番目に大きな町だと聞いたのに、空港のまわりはなにもない。
そして、なによりハワイと言えば、はじけるようなまぶしい太陽を想像していた。すべての色が輝いて、澄んでいるのだと勝手に思い込んでいた。
だが、太陽は灰色の雲にすっかり覆い隠されて、今にも雨が降りそうだ。
こんなものだ。ぼくは失望をそんな一言で片付けた。
失望はいつにも増して、自然にぼくの気分になじむ。むしろ愛おしく感じるほどだ。
旅のわくわくする気持ちよりも、よっぽどぼくに似合っている。
空港を出て、あたりを見回す。
滞在するはずのホテルから、迎えがきているはずだった。飛行機の時間はちゃんと伝えている。
だが、ここは南国だ。日本とは違う時間が流れているかもしれない。
空港の前だというのに、客待ちしているタクシーすらごくわずかだった。想像よりも遙かに田舎だ。こんなところに、三ヶ月も滞在していられるのだろうか。
予約の変更ができる高いチケットを買おうかとぎりぎりまで悩んだが、結局は格安チケットを買ってしまった。
あまりに値段が違うことが理由のひとつ、もうひとつはその不自由さがかえって心地よく感じられたことだ。
望んで島流しに遭うのだ。時間が長ければ長いほど、見えるものもあるだろう。