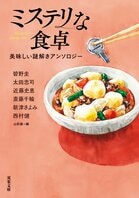次にカフェ・ルーズを訪ねたのは、金曜日のことだった。早すぎるかと思ったが、円が言った「気になること」とはなにか知りたかったのだ。
店内には、三組ほどの客がいた。円はカウンターの中で、なにか作業をしていた。
「あ、奈良さん!」
カウンターの椅子に腰掛ける。甘酸っぱい匂いがぷんと漂った。
「苺?」
苺を煮ている匂いだ。昔、母がよく苺ジャムを作ってくれた。
「ジャム作ってるの?」
「ジャムじゃないんです」
だとすれば、苺ソースか。ヨーグルトなどにかけて食べたらおいしそうだ。
「苺のスープです」
「苺のスープ?」
思わず聞き返してしまう。そんな料理ははじめて聞く。
「北欧の方で食べるんです。昨日作った分もあるので味見なさいますか?」
頷く。苺のスープだなんて想像もできない。
円がキッチンから運んできたのは、ガラスのボウルだった。透き通った赤い液体が中に入っている。
ボウルまで冷やしてある。冷たいスープだ。
スプーンでそっと口に運ぶ。甘くて、いい香りがする。違和感はまったくない。ジュースではなく、スープとしか言いようがないのは、少しだけとろみがついているせいだ。
ジュースよりも苺を食べているという感覚が強い。
春の香りと甘酸っぱさがとろみによって凝縮されている。
「おいしい……」
「バニラアイスやマスカルポーネをのせてもおいしいんですよ」
それは想像しただけでおいしい。おいしくないはずがない。
円はじっと瑛子の顔を見つめていた。
「苺を煮てても、なにができるかはわからないですよね。ジャムかもしれないし、スープかもしれない。スープの存在なんて頭にない人かもしれない」
彼女はなにを言おうとしているのだろう。スプーンを止めて円を見返すと、彼女は声をひそめた。
「紀谷ビル、一年後に老朽化で建て替えが決まっているそうです。多くの店舗は、すでに退去することになってる」
「えっ?」
正彦がカレー専門店をやると言っているビルだ。
「どういうこと?」
「建て替えが決まっているビルで、新規開業をはじめても一年後に立ち退かなくてはならない。それを契約者が知らないはずはない」
「つまり、彼が嘘をついている……」
「もしくは、蘇我さんが騙されているかどちらかです」
どちらもあずさにとってはよくないが、どちらかというと正彦が騙されている方がましだ。
「もし、彼が嘘をついているなら……」
彼女は結婚して、彼の店を手伝うと言っていた。そこには金銭的援助も含まれている可能性がある。
「結婚詐欺の可能性もあるってこと?」
瑛子がつぶやくと、円は目を見開いた。
「結婚するという話なんですか? 新しい店をはじめるばかりのときに?」
たしかに言われてみれば、同じタイミングではじめる必要はない。
円は眉間に皺を寄せた。
「彼が嘘をついている可能性はあります。うちの前で植えているハーブ。大葉月橘はカレーリーフという別名もあります。珍しいものだけど、スリランカのカレーを作るときに使うんです。エスニックカレーの店をやると言っておいて、それを知らないのは、嘘をついているか、単に不勉強なのか……」
瑛子は息を呑んだ。あずさに知らせなくてはならない。
彼が嘘をついているかもしれない、と言うのは難しいが、建て替えのことだけでも教えられるし、その先は彼女が気づくか気づかないかだ。
結局のところ、結婚詐欺かどうかまではわからなかった。
店の契約は一年になっていて、正彦は一年経ったら別の場所に移るつもりだったと言い張ったから。
だが、あずさは正彦と別れた。貯金をしているから、開業資金はあると言い張った正彦だが、調べると貯金はほぼないことがわかった。
貯金がない状態で店を始めるのはどう考えてもおかしい。
あずさにはこれまで働いて貯めた定期預金がある。そこで彼女はようやく気づいたらしい。
結婚詐欺かどうかはともかく、当てにされているのは自分の預金なのだと。
そこで正彦を家から叩き出し、きれいさっぱり別れたという。
あずさは、すっきりしたように振る舞っているが、彼女が傷ついていないはずはない。そのことに胸は痛むが、少しでも早く気づけたことはよかったと思うしかない。
瑛子の日常は変わらないが、変わらないこともひとつの幸福なのだと最近思うようになった。
ただひとつの変化は、自宅のソファと同じくらい好きな場所ができたことだ。
カフェ・ルーズの窓際の席は、日当たりがよくてとても気持ちがいい。
この続きは、書籍にてお楽しみください