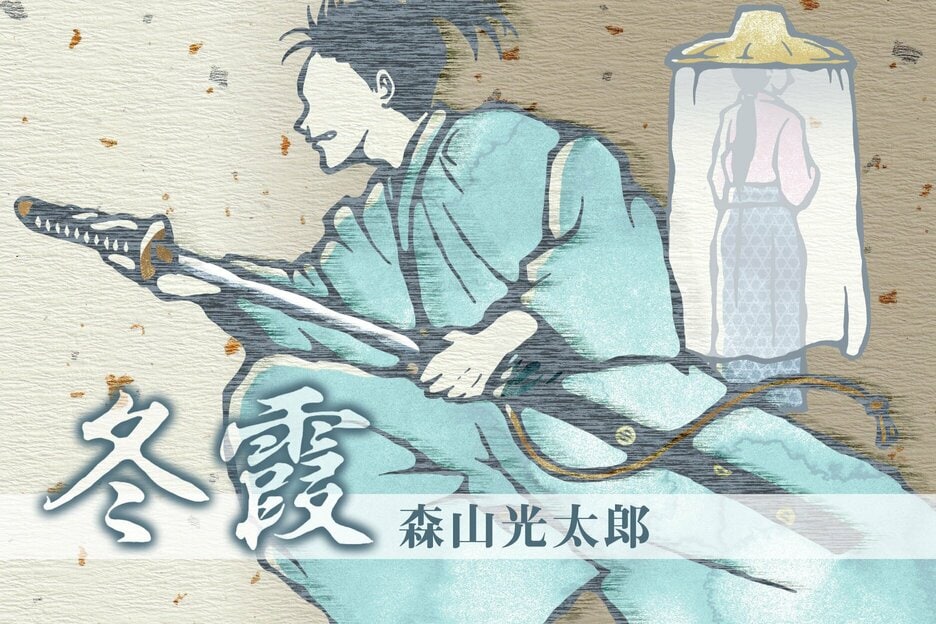三 高師直
貞和三年(西暦一三四七)六月──
十二畳ほどの部屋の中には、じっとりとした暑さがある。
綿を抜いた夜着が脱ぎ捨てられたまま隅に追いやられているのを見て、高師直は二日酔いの頭に手をあてた。すぐ目の前には、裸の女が静かな寝息を立てている。昨夜は、見目麗しいと思ったものだが、日が昇ってみれば、なぜ一夜を共にしたのか疑念が込み上げてくる。起き上がり、さらにもう一人の女が夜着に埋もれて寝ているのを見つけて、師直は強張った肩を回した。己の悪癖に苦笑し、師直は近くの女の身体を抱き寄せた。
女が、面倒そうに瞼を開いた。塞ぐように口づけし、女のふとももをまさぐった。柔らかな肌は汗でしっとりと濡れている。手に吸い付いてくるような滑らかさが、師直は好きだった。戦ばかりしてきた人生で、唯一心を休めることができる。
四十歳を超えてはじめて、女は安らぎを与えてくれるのだと知った。
かつては、戦だけが自分の全てだった。血の臭いを嗅ぎ、敵の断末魔の叫びを聞けば、心は鎮まり、言い知れぬ快さに酔いしれることができた。戦が性に合っていたのだろう。戦い続けた果て、幕府の武の化身とまで謳われるようになり、師直もまた自負していた。
だが、そんな自分が、戦場に寂しさを感じるようになったのは、主である足利尊氏の天下が見えてきた時だった。多くの友が戦場で死んでいったことに、不満はない。彼らも、思うさま生きたのだ。ただ、残された者を苛む寂しさは、厄介だった。酒で誤魔化すことはできない。主に弱音を見せるわけにもいかぬ。貴船社の巫女を見初めたのは、そんな時だった。
妖しげな笑みの巫女を抱いた翌朝、巫女の姿は忽然と消えていた。女に執着するようになったのは、いまだその夜の心地よさを探し求めているからなのだろうとも思う。
隣で声を洩らした女の頬が、ほんのりと赤く染まった。
「まだ、起きるには早かろう」
笑い、師直は女に覆いかぶさった。
朝日が障子を白く光らせ、屋敷の外の堀川通りから人の声が聞こえ始めた頃だった。
廊下を走る音が響き、従者が障子の外に何かを置いた。火急とのこと。それだけを呟き、また駆け去っていく。師直は目をこすりながら、落ちている小袖を拾い上げて身につけた。
障子を開けると、朝日のまぶしさに、思わず呻いた。廊下に置かれた文箱には、赤い紐がつけられた書簡があった。師直の判断を要するものは赤い紐と決められている。拾い上げ、書簡を開く。
南朝の後村上帝が、全土に軍の催促状を発した。それを受け、南朝の楠木正行も、千早城に兵を集めたという報せだった。
南朝の命運は、後醍醐帝が崩御した八年前に一度尽きたはずだった。
主柱と呼ぶべき武士が皆討ち死にし、後醍醐帝が崩御したことで倒れかけた南朝を蘇らせたのが、若き後村上帝だ。当時は、わずか十二歳になったばかり。南朝の英雄北畠顕家を傍で見てきた幼帝は、雌伏の時だと宣言し、この七年間、小競り合いは続けながらも大きな戦は命じてこなかった。
だが、その若さと理想の高さは、いつまでも続く雌伏に耐えらないことは分かっていた。なにより、後村上帝自身が、北畠顕家の軍とともに戦場で生きてきた人だった。
南朝方が動き出したことに、驚きはない。
「茶を持て。まずは、茶だ」
障子を左右に開け放ち、師直は足下を履くこともなく、庭に下りた。
「南朝の洟垂れどもも、ようやく死にたくなったか」
一人、高笑いした師直は、大きく伸びをした。
深緑に苔むした庭には、かつての運河を模すように、細いせせらぎがある。
唐花紋のあしらわれた桃色の小袖の裾をまくり上げ、高師直は足を水に浸した。ぬるい水だった。
余裕の欠伸をみせる師直の姿は、北朝きっての名将であり、足利尊氏への忠誠心の高さから、今関羽とも呼ばれている高師直の自信を表してあまりあった。
師直の戦の強さは、敵だけではなく、味方すら恐れさせてきた。なんとか引きずり落とそうと、人の妻に懸想して夫を殺したなどという根も葉もない醜聞を広められたこともあるが、師直自身はどこ吹く風で気にも留めていなかった。主君である足利尊氏さえ分かってくれていれば、それでいい。
たった一騎で万余の敵に囲まれても動じることがない猛将師直の懸念は、書状の中にある後村上帝や楠木正行のことなどではなかった。
塀の向こうからは民の賑わいが聞こえてくる。
壮年の男の笑い声や、童を叱る母の声、翁媼たちの話し声。目を閉じると、彼らの顔に浮かぶ安堵が浮かんでくるようだった。
「ここまで、十年」
そう呟き、師直は瞼を開いた。足元の澄んだ水の中で、光沢のある沢蟹が師直の足の上に上っていた。腰をかがめて摘まみ上げると、そのまま口の中に放り込む。強い苦みが舌に広がる。頭蓋の中に響くばりばりという音が、師直は好きだった。
京に平穏をもたらしたのは、自分たちだという自負が、師直にはあった。
これまで、幾度となく死を覚悟した。鎌倉の幕府を滅ぼし、武士や民を軽んじた後醍醐帝を京から駆逐した。日本全土を戦場とした南北朝の戦では、南朝方の北畠顕家に惨敗し、尊氏とともに西海道まで落ち延びもした。わずか二千騎で辿り着いた筑前国(現在の福岡県)多々良浜で、師直たちを待ち構えていたのは、二万を超える南朝方の大軍だった。
目の前に延々と続く旗指物に、尊氏はこれが天命と死を受け入れていた。
その時、蒼白な顔の尊氏とおそらく似たような顔をしていたであろう自分を叱咤したのが、若き日の足利直義だった。
「激昂した姿など、あれが最初で最後だったな」
三条殿と呼ばれる尊氏の弟直義は、常に冷静沈着をもって功をなす気質の将だ。
千里を見通し、時を超えた先さえ見ているのではないかと思ったこともある。戦働きを得意とする師直と、神がかった洞察で謀略を得意とする直義。性格もまるで似ていないが、だからこそ互いの穴を埋めることができたのだと思う。
死ぬならば、せめて敵の中で。多々良浜でそう叫んだ直義の背を追って走り出し、師直たちは勝利したのだ。尊氏と直義、そこに自分を加えた三人のうち、一人が欠けていても今の京の平穏はなかったはずだ。
「まだ、道はなかばであろうが」
京の平穏を、あまねくこの国に広げるために、この十年間、後醍醐帝の開いた南朝方と戦い続けてきた。力の尽きかけている南朝など、もうじき滅ぼせる。そこからが、本当の戦いの始まりだと師直は思っていた。
武士が、あまりに力を持ち過ぎている。それは、幼少の頃から師直が感じていたことだった。父祖伝来の領地を持ち、戦が起きれば武力をもって天下を乱す。彼らは、天下の平穏のためではなく、自らの領地のために誰につくかを決める。幾度となく裏切りを繰り返す彼らを、師直は憎んでいた。
武士の力を削ぎ、受け入れぬ者は根絶やしにする。
滅ぼさねばならぬのは、武士だけではない。兵を揃え、武士の真似事をする寺社などは、さらにたちが悪い。弱い民の心につけ入り戦に追い立て、自らの利にならぬ者を仏敵と名指しする。かつて、師直の弟は、身動きが取れぬように荒縄で縛られ、東坂本の山中を引きずり回されたうえ、比叡山の延暦寺で斬首された。
届けられた首級は傷だらけで、砂にまみれていた。それがまことに弟の首なのかも分からなかった。弟らしきものを見て、鈍い悲しみが身を包んだだけだ。心の底から悲しんでやれなかったことが、今も棘のように心に突き刺さっている。
弟を延暦寺に引き渡した武士の中で、尊氏率いる北朝の幕府に頭を垂れている者も多いが、棘の痛みを忘れたことはなかった。思い出すだけで、手足が熱くなり、顔を見れば刀を抜きそうになる。
力を持つ者は、皆殺しにしなければならない。
表では安穏と笑い、腹の底では裏切る時を見極めている者が死に絶えれば、戦などなくなる。弟のような惨い死に方をする者もいなくなるだろう。
青年の頃、三人で誓った道は、まだ半ばだ。肌でそう感じているからこそ、自分は新熊野をめぐる直義の動きに大いなる怒りを抱いたのだ。
腕の鳥肌を抑えるように、もう片方の手で掴んだ。
三年前、京に現れた新熊野を一目見て、師直は尊氏の子だと確信した。
もとより、尊氏には会うつもりなど欠片もなかったようだが、尊氏に謁見を拒否するように進言したのは、直義だった。武士の王となった尊氏に、新たな子が現れれば、家督争いの種にもなりかねない。そう告げた直義の判断には、師直も同意していた。そして、追放するならば、人知れず死なせるべきだとも思った。
大樹(征夷大将軍)の血を名乗る不埒者を許せば、足利の名に傷がつくことになる。
師直に先んじて刺客を送ったのは、尊氏の後継者である義詮の母だった。北条家に連なる名門赤橋家の烈女だが、命のやり取りを甘く見るきらいがあった。送り込まれた二人の刺客は、新熊野によって返り討ちにされた。
尊氏の血を引くならば当然の結末だろう。獅子の子は、獅子なのだ。新熊野の警戒心をいたずらに煽るような真似には苛立ったが、尊氏の子が強い武士であるということは、妙な誇らしささえあった。自分は、同じ轍は踏まない。獅子を狩るには、それなりの礼節がいる。
腕に覚えのある武士を集めたのは、二年前の春のことだった。十四人の刺客と、新熊野を逃がさぬために高一族が率いる忍び三十人を京に集結させた。鼠一匹逃げる隙間はない。
暗殺決行の夜、師直の屋敷に届いたのは失敗の報せだった。
新熊野の周囲を、得体のしれない武士たちが十重二十重に守っている。それが直義麾下の今川直貞であることが、次の日には判明した。その報せに、師直は驚いた。なぜ、尊氏の道を壊しかねない男を、拒絶するように進言した直義が守っているのか。
そして、あろうことか、昨夏、直義は自らの養子として新熊野を迎えた。
尊氏による全土の平穏を誓い合ったはずの直義が、戦乱の芽となる存在を受け入れたことは、師直にとっては許しがたい裏切りに近かった。受け入れただけではなく、直義は新熊野を足利一門として、直冬と名乗らせてもいる。
「何を見ている」
友が、尊氏の治世を乱すことはない。
そう思う一方で、乱に備えることが、尊氏の矛としての己の使命でもある。もしも直義が裏切るのであれば、自分がその首を取らねばならない。
「先触れを出せ。殿の下へ向かう」
邸内に向かってそう叫ぶと、師直は小袖を脱いで庭に放り捨てた。慌ただしい足音を響かせた下女が、藍色の直垂を広庇まで持ってきた。
二条通りまでのぼってくると、屋敷の雰囲気が一変する。
職人が多く、鉄の臭いの強い八条や七条あたりと違い、薫物や香木の匂いがあちらこちらから漂っているのだ。近頃では、香木を焚き、その香りの格式をあてる遊びが流行っているという。金や所領を賭け、身を持ち崩す愚か者もいるようで、幕府でも取り締まるか否かの議論が起きていた。
「これは、麝香と白檀かな」
呑気に鼻をひくつかせた師直は、束の間、香りの元を探そうとしたが、首を左右に振った。
尊氏が居を構える二条大路の屋敷に入ったのは、日が中天に昇った頃だった。
待っていたのは、鴬張りの古い廊下をせわしなく往復する尊氏だった。師直を見て、もろ手を挙げた尊氏が庭に降り立った。
「師直、待っておった。喉が渇いたろう。茶を用意しておるぞ」
額に汗を浮かべ、尊氏が嬉しそうに微笑んでいた。
目は切れ長だが、垂れた眉はどこか愛嬌を感じさせる。師直を迎え入れる無邪気な姿だけを見れば、この男が武士の棟梁などとは誰も思わないだろう。千軍万馬を圧倒する戦場の姿は、絵巻物のいかなる英傑もかすむが、平服を着た尊氏は、人を魅了する愛嬌がある。
「肌に空気がまとわりつくような京の暑さは、何度経験しても慣れませんな」
「儂もじゃ、師直。鎌倉のからりとした夏が懐かしいのう」
「また、鎌倉に帰るなどと申されますまいな」
慌ててそう釘を刺した師直に、尊氏が鼻を鳴らして笑った。
「儂も聞き分けのない童ではないのだ。かような時に我儘は言わぬ」
「そのお言葉が真であれば良いのですが」
尊氏の気まぐれには、師直も直義も昔から手を焼いてきた。思い立ったら、明らかに誤った道であろうと、聞く耳を持たず自分の道を進もうとする。それが致命的な状況になるまで、決して動かない。
かつて尊氏が、建武の新政に叛旗を翻した時もそうだ。後醍醐帝が尊氏の討伐を命じたという報せに、引き留める師直たちを振り払って泣きながら一人出家し、後醍醐帝に赦しを乞うた。つい昨日まで建武の新政を糾弾していた尊氏の変貌に、諸将は戸惑っていた。長くともにいた直義や師直ですら困惑していたのだ。当然だろうと思う。
多々良浜の戦の時もそうだったが、尊氏の不可思議なところは、誰もが死地に追い込まれたと思う場所から、無人の野を行くがごとく、挽回するところにある。
主君不在のまま、後醍醐帝側の新田義貞率いる南朝軍十万に惨敗し、自害を覚悟した師直たちの前に、尊氏は目を赤くはらして現れた。
お前たちが死ぬならば、生きていても仕方がない。
そう呟いて騎乗した尊氏は、破竹の勢いで進んできた新田軍を、鎧袖一触で四散させてみせた。死屍累々たる戦場に立ち、腕を突き上げた尊氏を見て、誰もが足利尊氏という男こそ、武士の棟梁だと確信した。
自分で窮地を作り、自ら挽回し、声望を得る。それを狡いと思わせない才能こそが、尊氏の天下人たる所以なのだろう。
畳が二枚置かれた釣殿まで歩き、尊氏が大きく背伸びをした。
「先ほどの戯言だが、京にはお主がおる。儂一人が鎌倉へ行こうと構わぬとは思っておる」
「過分なお言葉でございますが、殿が後ろに立っていると思えばこそ、我らは力を出せるのです」
「ほう。四十歳を超えて、お主もついに追従を言うようになったか」
「追従などではございませぬ。されど、またぞろ南朝の者どもが動き出しております。殿が不在になることを、三条殿も懸念されておりました」
直義の通称を出したことで、尊氏は訪問の理由を察したのだろう。
尊氏はにやりとして、顎の鬚に手をあてた。尊氏の温和な表情に隠されていた戦の気配が、いきなりむき出しになったような気がした。
「師直、お主にしては珍しく後手を踏み続けておるな」
「申し訳ございませぬ」
「よい。直義が守ると決めたならば、容易には手が出せぬであろう」
「御意。新熊野は、三条殿のもとで元服し、京の町では評判となっております」
「悪評か?」
「いえ。仁科の御老公と刀を交えて降したことなど、聞こえのよいものばかりでございます。近江の山で鬼を退治したなど荒唐無稽のものまでありますが、民と一緒になって宴を楽しむ姿も聞こえてきます。身の上もあいまって、かつての九郎判官(源義経)の再来と申している者もおります」
「戦で功を成したわけではなかろうに」
尊氏の言葉にひそむ愉悦は、尊氏の本心なのだろう。
新熊野が初めて京に現れた時、尊氏が笑いながら発したのは、斬れという言葉だった。