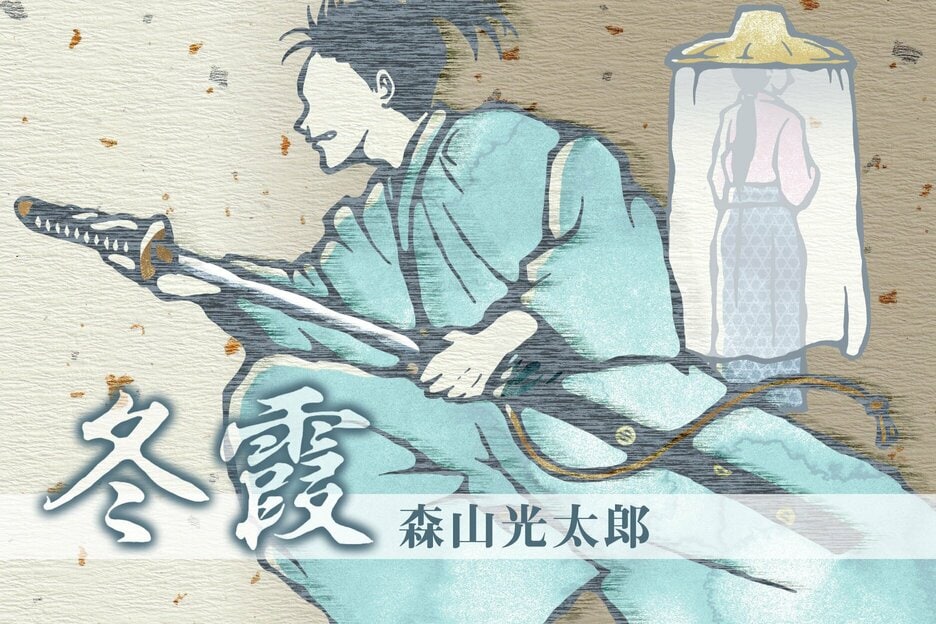七 霞
二人の将が、交錯した。
時がゆっくりと流れたようにも感じたその瞬間、暗闇に赤い火花が閃いた。遅れて、耳をつんざくような金属音が響き渡る。二人の刀と槍が大きく撥ね、すれ違う。
高師直は、すでに今川範国の陣の中にいる。
好機を逸した。胸の中に広がる悔しさの中で、霞は声を張り上げた。
「幸俊、今川勢を食い止めなさい」
深野池を渡ってきた五百の兵のうち、三百の兵を川尻幸俊に任せ、霞自身は二百を率いてその場に踏みとどまった。
師直を討つことが叶わないならば、少しでも時を稼ぎ、正行を逃す。
正行の突撃によって、戦場は大混乱に陥っている。五段に構えた師直の軍は、四段目までが崩壊し、潰走し始めた部隊もある。槍兵による正面からの突破と、左右からの奇襲は正行の想定通りだった。あと一息の時があれば、正行の槍は師直を貫いていた。
歯を食いしばり、霞は正面に目を凝らす。
星明かりの中、二つの騎馬隊が対峙していた。
楠木正行と、足利直冬。
正行は朱色の鎧に身を包み、短槍を脇に挟んでいる。率いる三百騎は、その父以来、楠木家に従ってきた古参の兵だ。身につける鎧はまちまちで雑然さすら感じるが、いずれも熟練の武人たちである。
片や、黒衣に統一された騎馬隊は、戦場でも異質だった。何か触れてはならぬ化生のようにも見える。先頭で刀を構える足利直冬は、どこか絵巻物から飛び出てきたような印象すらある。戦場に似つかわしくない言葉だが、華やかささえ感じさせる直冬の姿が、鴉軍に妖しさを纏わせているのだと思った。
対峙する二人の間に、何かが満ちていくのを感じた。戦場の兵たちもそれを感じているのだろう。戦場が静まり返り、固唾を呑む音が、そこかしこから聞こえてくるようだった。
「……怯えている?」
不意に口からこぼれた言葉に、霞は自分で驚いた。直冬も正行も、怯えとは無縁の二人だ。
北朝方の細川や山名を打ち破り、初陣以来いまだ無敗の正行が、向かい合うわずか二百騎の鴉軍に怯え、戸惑っている。正行のことは、霞が童だった頃から知っている。なによりも人の死を嫌い、敵を殺すことも、己が死ぬことも嫌がっていた育ての親だ。
直冬に、死の気配を感じ取っているのだろうか。
だが、正行以上に怯えているのは、直冬の方だった。涼しげな表情は汗にまみれ、漆黒の鎧をまとった身体は強張っている。初陣の恐怖なのだろうか。そう思った時、不意に直冬の目が、こちらに向いた。闇の中、分かるはずもない。そう思ったが、確かに直冬の目には驚きが滲んだ。
先に怯えを置き去りにしたのは、正行だった。
馬腹を蹴った正行が、一騎で突出した。味方の意表さえ突く唐突さで、麾下の三百騎が遅れて駆けだしていく。風が唸りを上げた。正行のすぐ後ろの兵が、弾けるように宙に飛んだ。仁科盛宗の矢だ。それを合図に、鴉軍も動き出した。
先頭を駆けるのは、黒衣の鴉軍の中でただ一騎、白い狩衣姿の今川直貞だった。糸のように細い刀を後ろ手に構え、姿勢を低くしている。少し遅れて、直冬が駆ける。
「直貞、邪魔だ!」
「大将が先陣をきる莫迦な軍がどこにありますか」
二人の声が響いた直後、二つの騎馬隊がぶつかった。
「楠木殿を援護します」
そう命じ、霞は二百を小さくまとめた。今川勢が前に押し出そうとしてきているが、三百を率いる幸俊が、何とか食い止めていた。ただ、範国勢は数千以上。半刻(約一時間)も持たないだろう。
駆け出した時、全身に鳥肌が立った。
正面に、黒衣の鴉軍がいた。いつの間にか、直冬が先頭になり、霞の方へまっすぐと駆けてくる。
背中から冷たい汗が噴き出す。
正行は――。
いきなり、左手から地鳴りのような喊声が轟いた。
無数の旗が左右に広がっていた。
平四つ目紋。白の旗に染められた四つの四角が、星明かりによってじわりと浮かびだしている。左手の飯盛山に布陣しているはずの佐々木道誉の軍勢だ。潰走したはずの一段目から四段目までの幕府兵を吸収し、四条畷を埋め尽くすような大軍となって進軍している。
逃げ場がない。刀を握りしめた時、すぐ目の前に直冬がいた。
馬上の直冬が、霞を見下ろしている。刀を、突き出していた。直後、刀がはじけ飛び、わけも分からぬまま身体が宙に浮いた。抱きかかえられているのか。兵たちが置き去りになり、戦場が凄まじい速さで遠ざかっていく。
直冬の息遣いが聞こえた。
「許せ。これしか手がない」
強張った声が聞こえた次の瞬間、宙に放り出された。視界の中に水飛沫が飛び交い、すぐに全身を刺すような冷たさが身体を包み込む。息ができない。苦しさの中で、無意識のうちに鎧を脱いでいた。
深野池に投げ込まれたのだろう。必死で足をばたつかせ、水辺の葦をかき分けるようにして泳いだ。葦の陰に、田舟を隠してある。田舟が、次々に動き出していくのが分かった。麾下の兵たちが、逃げ出しているのだろう。安堵した時、霞に気づいていない舟が正面から迫ってきた。声を出すことができなかった。水の冷たさで、息が苦しい。
「止まれ!」
薄れていく視界の中で聞こえたのは、幸俊の声だった。
閉じた瞼に、陽の光を感じた。赤く、波打っている。そう思った瞬間、飛び起きた霞は、全身の痛みを感じた。口から呻きが漏れる。
「おお、目覚められましたか」
聞こえたのは、野太い幸俊の声だった。瞼をそっと開けて正面を見ると、小屋の入り口にもたれかかるようにして立つ幸俊がいた。日中なのだろう。小屋の中は明るかった。見回すと、小さな小屋の天井には獣の皮や骨がぶら下げられている。猟師の小屋だ。強すぎる獣の臭いに気づき、思わず鼻をつまんだ。
「ここは」
全身にある鈍い痛みを庇うように膝を抱えた霞に、幸俊が膝をついた。
「紀伊国にございます。綴連王(霞)は、三日、寝ておられました」
「三日でございますか」
繰り返すように呟き、霞は顔を上げた。幸俊の顔は、いつになく神妙だ。
戦場で直冬に刀を奪われ、深野池に投げ込まれたところまでは覚えている。その直前、南朝方は北と南から挟撃を受けていた。
嫌な予感がした。
「楠木殿はどこにいるのでしょうか」
幸俊が押し黙った。小屋の外から、時を刻むような雁の鳴き声が聞こえた。
「京に」
それだけ言葉にして、幸俊が板の床に白い絹布を置いた。見覚えのある文字だった。細く几帳面さを感じさせるそれは、正行のものに間違いなかった。かつて千早城で渡された書簡に記されていた辞世の句に、下の句が加えられている。
正行が、この世からいなくなった。それだけが伝わってきた。
「……首は」
「師直の命によって、市中を引き回されたうえ、六条河原に晒されました」
頭を垂れた幸俊の言葉が、空気を震わせた。
「戦場に突如現れた黒衣の騎馬隊が綴連王を攫った時、楠木殿と綴連王は三方から包囲されていました。北からは高師直、南からは佐々木道誉、黒衣の騎馬隊の背後には、さらに南宗継率いる黒草衆の忍びがおりました」
「私は、直冬に救われたということですか」
許せ、という声が耳に残っていた。だが、その声が悲しみを消すことはなかった。
「楠木殿は、誰の手によって討たれたのでしょうか」
「最後まで奮戦され、楠木殿は飯盛山の麓にて自害なされました。無数の黒草衆を斬り倒し、力尽きたところで弟君と刺し違えられたようです。戦場には、黒草衆の骸がいくつも置き去りにされていました」
殺されることを怖がっていた育ての親が、誰かに殺されたのではないことを知り、霞は小さく拳を握った。早鐘のような鼓動を落ち着かせるように、息を吐きだした。肌が露わになっている腕を見れば、いくつもの痣がある。
「幸俊、棒を取ってもらえますか?」
壁に立てかけてある四尺(百二十センチメートル)ほどの乳白色の樫の棒を指さした。幸俊が頷き、すぐに霞の前に置く。
棒を支えにして立ち上がる。漏れそうになった呻きを堪え、霞はゆっくりと一歩一歩進んだ。草鞋を履かせようとした幸俊に首を横に振り、裸足のまま小屋の外に出た。
冷たい風が、正面から吹き付けてきた。舞う黒髪をかきあげる。
「随分と山奥に来たものでございますね」
視界一面に広がるのは、荒涼とした冬の山々だった。葉を落とした樹海のところどころに、白い雪が覆いかぶさっている。山の中腹にあるのであろう小屋の周囲には、目立たないように人が配置されているのが分かった。
風の冷たさに身体を震わせたとき、幸俊が綿入りの藍色の袷を差し出してきた。
「西国から連れてきた者たちです」
幸俊の言葉に頷いた。四條畷の戦、深野池を渡った五百の兵は、西国からかき集めて連れてきた兵だった。いずれも北朝方に親兄弟を殺されており、霞の呼びかけに集まってきた。
「どれほど、生き残りましたか?」
「逃げ出した者の数は分かりませぬが、ここまで付いてきたのは四十七名でございます」
集まった大部分が死ぬか、逃げたかということだ。だが、包囲されたことを考えれば、死んだ者の方が圧倒的に多いのだろう。霞自身、直冬によって池に投げ込まれていなければ、生き延びることができていたか怪しい。
命を借りた。よりによって、淡い思いを断ち切ろうと決めた相手によって、助けられた。その事実が悔しく、だが心の痛みを鈍くさせているような気もした。
「楠木殿の死を嘆くことは、まかりなりませぬ」
自分に言い聞かせるように、霞は呟いた。嘆く暇があるならば、次の備えをせよと、正行は言うだろう。
勝機は、ただ一度きり。出陣前の正行はそう言って笑っていた。
四段目に構える師直を後退させ、飯盛山の佐々木道誉が大軍をまとめて挟撃を完成させるまでの瞬きの間に、師直を討てるか否か。正行はそう予見し、事実戦場は神懸かりのように正行の言葉通りになった。
後醍醐帝が死んで七年、あらゆる戦を想定してきたからこそ、正行は細川、山名という雷名高き幕府の大名を破り、武の象徴である高師直にもあと一歩まで迫ることができたのだ。
「ただ、備えが足りなかった。楠木殿が生きていれば、そう言うのでしょうね」
失敗は、次への布石でしかない。
「四条畷の敗戦が全土に伝われば、どうなりますか」
考えることを委ねるように、幸俊に身体を向けた。くしゃくしゃの髪を掻き、幸俊がそうですなと呟く。
「楠木殿の死は、各地の南朝方の心を折りましょうな。楠木の名は、南朝方にとって特別な意味のあるものにございます。高師直もそれが分かっていたがゆえに、自らを死地に置くような戦で、楠木殿を誘きだしたのでしょう」
四条畷は、明らかに大軍を率いる高師直にとって不利な地形だった。正行もまた、誘いだということを認めていた。
「今、幕府の軍勢は高師直と、その弟高師泰の二軍に分かれ、河内国の平定に乗り出しております。ただ、この二軍の動きは、河内国制圧だけに留まるものではないかもしれませぬ」
「吉野行宮(仮に設けられた御所)を狙うと?」
「師直は、帝の権威をものともせぬ荒武者とも言います。この戦で、南北朝の戦に終止符を打つつもりかもしれませぬ」
帝を討つなど、史に残る咎だ。師直がそれほどの覚悟を持って出陣してきたというならば、正行を殺すためだけに、四條畷という死地に身を置いたことも納得できる。吉野行宮にいる後村上帝が討たれれば、東国の南朝方と、西国の南朝方の連携は失われ、各個撃破されて終わってゆくだろう。
「吉野の動きは?」
「正行殿の弟君を元服させて、南朝方の大将に任じたようでございます」
「虎夜刃丸を?」
思わず、頓狂な声が出た。ちらりとこちらを見た幸俊が頷いた。
「名を楠木正儀とされたようです」
正行の弟は、まだ十六歳になったばかりのはずだ。吉野の朝廷が楠木の名に縋ろうとする気持ちは分かるが、元服したばかりの正儀に、歴戦の高兄弟の相手は、いくら何でも荷が重すぎる。
麾下の者を楯くらいにしか思っていないのだろう。霞の父である大塔宮もまた、そうやって殺されていったのだと思うと、正儀が哀れだった。吉野の山奥で、霞の後を弟のように付いて回っていた虎夜叉丸のあどけない笑顔を思い出し、拳を握った。
「綴連王として、いかが動かれますか?」
幸俊の問いかけに、霞は短く息を吸った。この男は、南朝方でもなければ北朝に忠誠を誓っているわけでもない。霞の示した西国の水運を束ねることが、自らの利に繋がるがゆえに手助けしているだけだ。返答次第では、いつでも離れていくと思っていい。
首を左右に振り、息を吐いた。
「吉野の逃げ道を作っておきましょう」
幸俊が、嬉しそうな顔をした。
霞が吉野の朝廷に恨みがあることを、幸俊は知っている。吉野が滅びれば、北朝方の勢いは止めようがなくなり、西国の水運も、やがて幕府が支配することになるだろう。霞が吉野を見殺しにして私怨を晴らそうと動くならば、今ここで見限るつもりだったのかもしれない。
父を見殺しにした南朝に、恨みはある。だが、霞が独力で北朝方と戦える力を手に入れるまでは、南朝を楯として上手く使うべきだ。
「さすがの深慮にございます」
「正行が死んだとはいえ、全てが終わったわけではありません。紀伊に隠し湊となる地をいくつか備えましょう」
「すでにそれがしの手下が見つけてきております」
「私がそう命じるであろうことを、予期していたのですか?」
幸俊が笑った。
「まさか。それがしにさようなことを考える頭はございませぬよ。実は、石見国の益田兼見が、人目を避けるように紀伊に来ておりましてな。戦況を読み、いずれ必要になると」
四條畷の戦を見極めに来たのだろう。鵺のような男のやりそうなことだと思った。
「綴連王。楠木殿が敗れ、南北朝の秤は大きく北朝方に傾いたと言ってよろしいでしょう。されど、いまだ征西将軍宮もおりますれば、信濃宮もおわします。霞殿の道が終わったわけではござらぬ」
「それは、益田殿の考えでしょうか?」
幸俊がにやりとして首を振った。
「綴連王に賭けている者の総意でございます。帝が生き延びたとしても、吉野の勢いは数年で取り戻すことはできますまい。敗れたるは吉野、勝ちたるは高師直。この戦で、高師直の名声は、さらに高まるでしょう。それこそ、足利直義の権勢に届きうるほどに」
「幕府内の不和が起きると?」
「兆しはございました。不和というものは戦時ではなく、平時にこそ大きくなるものでございます」
確かに、そうなのだろう。今回の戦では、南朝という敵を前に、尊氏と直義の兄弟の不和は露呈することなく、むしろ尊氏方の高師直の戦を、直義は支え続けている。だがこの先、南朝が衰えていけば、直義と尊氏は外敵を気にする必要がなくなる。
自分の勝機は、そこにあるはずだった。
北朝方の不和の芽となる男を思い浮かべた。敵なのだ。使えるものは全てを使わなければ、勝つことなどできはしない。
「高兄弟の軍勢を撹乱します。吉野の野伏(在野の武士)には、亡き大塔宮を慕い、今なお吉野に参じていない者が多くおります。綴連の名を用いて、彼らをまとめ上げ、正儀の指揮下に入らせてください」
「御意。帝はいかがいたします?」
少し思案し、霞は顎に手を当てた。
「吉野の帝には、紀伊国の阿瀬川城に遷幸していただきましょう」
「阿瀬川城でございますか。確かに周辺に大小十余の城郭があり、守ることには適しておりましょうが。朝廷がそれを認めますかのう?」
朝廷を仕切っている北畠親房は、伊勢国(現在の和歌山県)に勢力を保っている。もしも吉野が攻められれば、伊勢国に逃げようとすると幸俊は言っていた。
「私が自ら吉野へ赴き、北畠殿を説きます」
「紀伊国にこだわるわけを教えていただいても?」
「京から伊勢までの道は遠く、なにより伊勢は守りが堅すぎます」
それでいいのではというように怪訝な表情をした幸俊に、霞は微笑んだ。
「楠木殿が死んだ以上、師直を止められる武将はおりませぬ。十中八九、吉野は陥落します。そうなれば、北朝内部での師直の権勢は高まりすぎます」
幸俊は、直義の権勢に届くと言ったが、霞の見立ては違った。この戦のはじめ、二度の戦で細川顕氏、山名時氏という北朝方の大名が敗れており、いずれも直義の腹心と呼ぶべき者たちだった。直義が手をこまぬけば、この戦が終わった時、直義の味方をする者は少なくなるだろう。直義は、なんとかこの戦で挽回しなければならない。
だからこそ、南朝の追討には、直義派の武将が大将として送られるはずだ。そもそも直冬が木津で調練を繰り返していたのも、そのためだった。
守の堅い伊勢国では、北朝方が侵攻を躊躇するかもしれなかった。
「紀伊国に直義方の将を送り込ませ勝たせることが、肝要です」
ここから、戦は新たな局面に変わる。南朝と北朝の戦ではなく、北朝の内部の争いになってゆくだろう。しばらくは、霞たちが表立って戦うことはできない。
北朝内部で争っている間に、力をつける。
西の海を制し、いずれ万余の船を並べ、瀬戸内を攻め上がる己の姿を、晴れ渡る空に思い浮かべた。
冷たい風の中、いつの間にか身体の痛みが消えていることに気づいた。
貞和四年(西暦一三四八)一月──
その戦は、前代未聞のもので、その後数百年を下っても同じことは起きていない。
春寒残る吉野行宮に攻め寄せたのは、高師直率いる四千の大軍だった。長きにわたる南北朝の戦に終止符を打つため、帝を殺すことを決意した師直だったが、すでに吉野行宮に後村上帝の姿はなく、山間に溢れた北朝方の兵は、師直の怒りが乗り移ったかのように行宮となっていた蔵王堂を始めとして、坊舎をことごとく焼き尽くした。
帝の住処を燃やした師直の暴挙は、北朝方の公卿すら、悪行によってすぐに師直は滅びることになると嫌悪したという。だが、吉野という天然の要害を見れば、武士として師直が徹底的に焼き尽くしたことも頷けることであり、事実この後、南朝の帝が吉野に戻ってくるまでは二十年余の時がかかっている。
公卿の評判を落としたが、武士からの評判はかつてないほどに高まった師直と競うようにして、出陣を命じられたのは直義麾下の直冬であった。