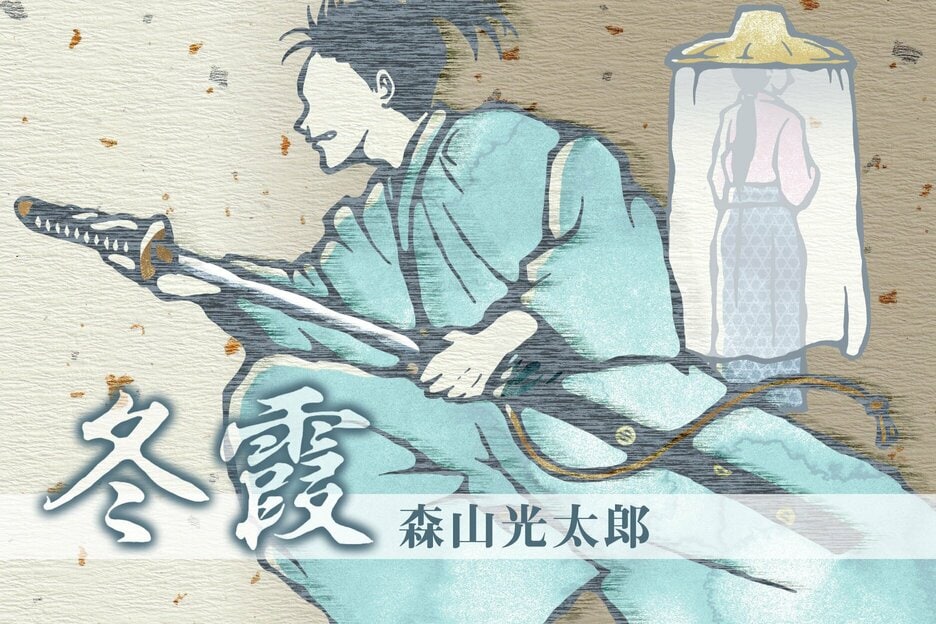五 直冬
伏見で調練を繰り返していた直冬のもとに、足利直義からの使者が現れたのは、九月の終わりのことだった。急ぎ参上することを命じられた直冬は、仁科盛宗に調練を任せ、今川直貞をともなって馬を北へ駆った。
直義の養子となって一年、届けられた書簡の文字の乱れは、これまで見たこともないようなものだった。常に冷静な男が焦っている。
そろそろ、京を出陣した北朝方の細川顕氏と、南朝方の楠木正行との戦が始まる頃だ。うちうちに直冬に命じられていたのは、顕氏が勝利した後、南朝の残党を討つことだったはずだが、直義の乱れた文字に嫌な予感がした。
三条坊門殿の櫓門に辿り着いたのは、夜も更けた頃。朱塗りの櫓が、篝火の炎に照らされて闇夜に浮き上がっているように見える。殺気立った空気に気後れせぬよう、直冬は息を吸い込んだ。
「なんと言うか。御伽草子に出てくる鬼の城のようにみえるな」
「三条殿を退治してはなりませぬぞ」
白粉姿の直貞の言葉に、直冬はその背を一度叩いた。
門の横には四つの篝火が立ち、警固の兵は二十人ほどもいそうだ。
門衛に案内された屋敷の中も、いたるところに兵がいた。彼らは、屋敷の中から従者が持ってきた文箱を受け取ると、三人一組になって駆けだしていく。直冬たちが廊下を通って奥の書院まで向かう途中も、八組の兵が必死の形相で門を飛び出していった。
「約定の刻限よりも、遅れておる」
書院の襖を開けると同時、厳しさの混じった言葉が中から飛んできた。部屋の中には、四隅に灯が置かれている。直冬と直貞は、門衛に促されるまま、襖のすぐ前に座った。
付け書院の前に文机を置き、直義は胡坐をかいて筆を走らせている。こちらを振り向くこともなく押し黙った直義が、信じられないような速さで書状の束を次々に生み出し、筆を擱いたのは、ゆうに半刻(約一時間)も経ってからだった。
振り返った直義が、いきなり畳の上に仰向けに倒れた。直冬が立ちあがるよりも早く、直貞が慌てて傍に寄ろうとした。直貞を制するように、直義が右手だけを上げ、何度か振った。
「よい。いつものことであろうが。屋敷に寄りつかぬ直冬が目にするのは、初めてであろうが」
暗い天井を見つめたまま、荒く呼吸する直義が、唸り声を上げた。
「しばし待て」
深い息を十ほど繰り返し、直義がおもむろに上半身を起こした。直義の目元には、こちらが息を呑むほどの濃いくまが張り付き、着ている紺色の直垂も何日替えていないのか、嫌な臭いを発している。香木などは焚かないのかとあたりを見渡したところで、直義が華美を徹底的に嫌うことを思い出した。公家や武士からの進物すら、一切受け取らないという。
寝る間もなく、執務を続けているのだろう。鴉軍の過酷な調練で、十日間ほとんど飲まず食わずで戦い続けても、ここまでやつれはしない。己の一手に、国の命運がかかっている。それは、ここまで人を苛むものなのか。
言葉を失っていると、直義が疲れて濁った瞳だけを向けてきた。
「直冬、息災か」
どこかぎこちなさを感じさせる養父の言葉に、直冬はようやく我を取り戻した。
慌てて片膝を付き、頭を垂れた。伏見の調練以来、二月ぶりだった。
実の父である尊氏との不和が噂される直義の養子となって一年の間、直義が尊氏に反するつもりならば討つことを覚悟してきたが、今のところその気配はない。
むしろ、民を慈しみ、寝食を惜しんで政に取り組む直義の姿は、他の誰よりも幕府に忠実なように見える。征夷大将軍として天下を支配する尊氏にとって、直義は無くてはならないものだと感じ始めていた。
もし、いずれ決裂する時が来るとすれば、直義と尊氏の仲を取り持つことができるのは、その子である自分だけだろう。直義を討つのは、それが叶わなかった後でも遅くはない。今は、直義の下で、武将としての力を身につけるべきだった。
「直貞の力添えもありますれば」
そう言うと、直義が薄く笑った。
「阿呆だが、私の見る限り、直貞はなかなかの玉だ。お主の磨き方次第で、輝きも、割れもする。まあ、今はまだ欠けている部分も多く、磨くのにもひどく苦労するであろうが」
直義の言葉に、右隣に控える直貞が嬉しそうな顔をしたのが見えた。肩を回した直義から、骨のきしむ音が聞こえてきた。
「幾晩、寝ておられないのでしょう?」
「どれほどになるかな。三日を過ぎたあたりから数えてはおらぬが、全土に書き送った書の数は、二百四十三をちょうど超えたところだ」
「枚数を覚えておられるのでございますか」
「自慢にもならぬ特技だ。頭の中に成すべきことが浮かんでくる。終わったものには、横線を引いてゆけば、いまどの程度終わったかを把握することなど造作もないであろう」
こともなげに言った直義だが、それをできる人間など、直義以外にはいないだろう。
「お身体にさわります。せめて、数刻でも休まれてください」
「とは言うがな、直冬。今、私が数刻休めば、この国の動きが数日遅れる。政を司る者が、火急の時に己の身を気にしだせば、国は倒れる」
もう一度肩を回した直義が、短く息を吐きだした。
「まあ、案ずるな。他の者に任せられるものは任せておる。やっているのは、私にしかできぬことだけだ」
とはいえ、直義の仕事ぶりが速すぎて、その下につく吏僚たちもまた夜を徹することになっている。一人の天賦の才が、政を司ることの危うさを見た気がした。
「お言葉を返すようですが、父上が倒れられれば幕府は立ちゆきませぬ。くれぐれも休息を」
重ねて言った言葉に、直義が狐につままれたような表情をして、微かに笑った。
「息子の言葉だ。よかろう。以後、気をつけよう」
そう言った次の瞬間、その顔に冷徹さを張り付けていた。
「呼び出したのは、他でもない。南朝との戦況は把握しておるな?」
「はい。戦況は、直貞に調べさせておりますゆえ」
頷き、直冬はこの一月余りの戦を思い浮かべた。
楠木正行との最初の戦は、八月十日のことだった。
京に向かって進軍してくるという幕府の予想に反して、紀伊国の隅田城を攻めた正行は、わずか一夜の戦いで落城させている。大勝を喧伝しながら軍を返した正行は、そのまま河内国内の北朝方の拠点を攻め、この一月の間に池尻、八尾を制圧した。
その進軍の速さは尋常のものではなく、かつて幕府を幾度も窮地に陥れた正行の父、楠木正成の再来だと京の民は噂していた。北朝方の武士の中にも、怯えながらそう語る者が出始めている。
初陣ながら、それほどの戦ぶりを見せる正行に、直冬は妬心のようなものを抱いていた。
直義の眉間にしわが寄った。
「昨夜、顕氏が敗れた」
まさか、と言いかけて、直冬は言葉を呑み込んだ。直義は戯言を言うような人ではない。だが、直義の言葉が真であれば、七千の兵を率いた細川顕氏は、わずか千の楠木勢に敗れたことになる。なにより、顕氏は楠木正行とは比べ物にならないほどの歴戦だ。北朝で顕氏よりも戦功を挙げている者といえば、北朝の武の象徴である高師直くらいのものだ。
妬心が大きくなったような気がした。
「細川殿はご無事なのでしょうか?」
「命からがら、逃げ延びはしたらしい。楠木正行という武将は戦を良く知っておるな」
感情を滲ませることもなく、淡々と直義は述べた。
「河内国に入った顕氏の軍には、立て続けに各地の南朝方蜂起の報せが入ってきた。熊野、和泉、天王寺。いずれも、無視できぬ地だ。顕氏も迷ったのであろうな。天王寺に向かおうとしたその夜、正行が顕氏の軍に襲い掛かった」
「各地の蜂起は真だったのですか?」
「いや、おそらく、正行の流した偽の報せだったのであろうな」
直義にしては、歯切れの悪い言い方だった。
「河内国に放っていた忍びの多くが殺され、正確な報せが届いておらぬ。おそらく、楠木の手の者の仕業なのだろうが、戦が起きた藤井寺近くに潜んでいた一人も、胸に傷を受け、私のもとに辿り着いた直後に死んだ」
楠木一族は、多くの忍びを手下に持ち、全土に散らばらせているという。
正行の、敵に動向を悟られまいとする動きが、判断する力に長けた者を封じるためには有効なのだろう。直義ですら、報せが無ければ正しい判断を下すことはできない。正行は、相手の優れている部分で勝るのではなく、優れた部分を封じようとしている。
直義が文机の上から書をつかみとった。
「二日もすれば、詳しい知らせが届く。朝廷の混乱を避けるためにも、先んじて動いておきたい。直冬よ。鴉軍を率い、木津(現在の木津川市)まで押し出せ」
「大和国(現在の奈良県)からの南朝の進軍を止めれば?」
「吉野の者たちが北上を考えるかもしれぬし、相手は神出鬼没の楠木正行だ。こちらの意表を突いて、河内国ではなく大和国からの上洛を目指すかもしれぬ」
鍛え抜いた鴉軍であれば、吉野から北上してくる千から二千程度の兵を止めることはできるだろう。だが、細川軍を破ったという楠木正行の精強な本隊が現れれば、どうなるか分からなかった。
「鴉軍のみで止められそうにない敵が現れた時はいかにすれば?」
「無理はするな。顕氏の後詰として、山名軍一万がじきに河内国に入る。山名の軍勢が整い次第、兵を集めてお主のもとにも送る」
直冬を山城国と大和国の境目を守る盾となし、戦況次第ではそのまま南朝を攻撃する役を担わされるのだろう。だがそれを、軍を司る高師直が許すのだろうかと思った。そもそも鴉軍は私兵のようなもので、幕府の兵を率いているわけではないのだ。なにより、無位無官の直冬では、幕府の兵を動かすことはできない。
直冬の懸念を察したかのように直義が、書を渡してきた。
「お主の叙任が決まった。私の推薦だが」
どこか謝るような感情を、直義は口調に滲ませた。
「従四位下、左兵衛佐。かつて源平の頃、相国平清盛が初めてついた職だ。案ずるな。私が奏上したものだが、高師直もあっさりと認めた。伏見の調練で、お主の力を認めたのであろう」
言葉が出ないまま、受け取った書をよく見ると、間違いなく自分の名が記されていた。朱印が押され、その下には尊氏の花押が記されている。
従四位という位階は、武家の中でも相当に格式のある家でなければ、与えられないものだ。かつて鎌倉幕府を取り仕切っていた北条家の者たちにさえ、従四位に辿り着くことが、武士としての極みとされていた。
不思議な血の高揚があった。足利直冬の名を与えられた時に感じたのは、己の存在が間違っていなかったのだという安堵だった。だが、今のこの血の滾りは、己の力が期待されていることへの喜びなのだろう。直義が奏上し、そして尊氏が認めてくれた。
「これで、困らぬな?」
ため息を吐いた直義が、じっと直冬の表情を見つめてきた。その直後、用件は終わりだとでも言うように手を振り、再び文机に身体を向けた。
山城国と大和国の境に位置する木津は、かつて恭仁という都が置かれていたという。
宮城があったとされる灰色の巨石の前で、直冬は大きく背伸びをした。北の後山には、辰砂をまぶしたような真っ赤な紅葉が山裾に広がっている。
三方を山に囲まれ、南には木津川が流れる木津の地は、都としては理想的な場所に思えた。
攻め込み難く、守りは容易い。なにより淀川の河口で海船から積み替えられた荷が川船で木津川に運び込まれ、伊賀国や大和国、紀伊国への街道が交わるため、人や物が集まりやすい。ここを南朝方に抑えられれば、北朝方は畿内の南一円を失うことになる。
冷たい風の中、木津に辿り着いたのは十月一日のことだった。
木津に置いた本陣の幔幕の内側には、いつも通りの白装束と赤鞘の刀を佩いた今川直貞と、床几の上で腕を組み瞑目する仁科盛宗がいる。幔幕の外からは、鴉軍二百騎が兵舎を設営する音が聞こえていた。初陣だが、まだそこまで焦りがないのは、彼らが平然としているからだろうと思った。
戦が長引くことに備え、木津に到着した直冬は盛宗と話し合い、越冬の備えを決めた。この地が材木の集積地であることもあり、小高い丘に三重の柵を持った砦の造営を命じている。十日もあれば、砦としての形はできそうだった。
木槌の音を楽しげに聞きながら、白粉姿の直貞が口を開いた。
「東国では、小田某という武士が北朝に叛旗を翻したそうです。鎌倉殿は、その対応に追われ、上洛は叶いますまいな」
「将軍家の世継ぎも、苦労が絶えぬなあ」
しみじみと聞こえるように、ことさら肩から力を抜いた。
鎌倉には、尊氏の嫡子である義詮がおり、鎌倉殿として関東支配を任されている。直冬よりも三歳年少であり、尊氏の期待を一身に背負っている。考えてしまえば妬心に捕らわれそうで、あえて目を背けてきたものだ。
直貞は、こちらの心の隙間をすっと衝いてくるきらいがある。直冬の強がりも、見て取っているかもしれない。直義の麾下として、忍びを束ねていたことで、人の機微を見抜くことが癖になっているのだろう。
ため息を堪え、直冬は幔幕の内側に移動し、盛宗の向かいに置かれた床几に座った。
「鎌倉殿の許には、歴戦の武士も多く与力としている。案ずる必要はないさ」
「まあ、東国は高一族の死闘もあって、北朝方の武士が多くおります。殿が気になさるべきは、西国の動きでございますな」
「西国と言ってもなあ。征西将軍宮(懐良親王)は俺が対峙するには大きすぎる敵だぞ。龍と猫のようなものだ」
「御意」
即答してきた直貞に、少しは悩めと言うか迷い、続けるようにと頬杖を突いた。直貞が苦笑した。
「亡き後醍醐帝の皇子は、戦に長けた者が多い印象ですが、その中でも征西将軍宮は政の才も飛び抜けております。事実、西海道(九州)の肥後国に寄って立ち、四面楚歌の中で徐々に勢力を伸ばしているようです」
「たしか、大陸の明との交易も成しているようだな」
「そのようですね。征西将軍宮の小細工でしょうが、西国では、すでに京が楠木正行によって落とされ、北朝方は駆逐されたなどという風聞も飛び交っております」
「なぜ、それを京にいるお前が知っている」
「殿を助けるのが私の役でございますからな。鎌倉殿が東国であれば、我が殿の戦場は西国になるのは自然。その地の仔細を調べるのが、私の務めにございます」
何を当たり前のことを聞いているのだというように、直貞がため息を吐きだす。苛立ちを感じながらも、直冬は舌打ちを噛み殺した。
「おい、白粉。それで、征西将軍宮の動きはどうなっている」
幕府が最も懸念しているのは、楠木正行の戦に乗じて、西海道の南朝方が上洛を目指すことだ。もしも、征西将軍宮が西海道の北朝方を破って上洛を目指せば、数万規模の大軍になるだろう。それを止める役を担わされるかもしれないと思うと、手の震えはごまかせなかった。じっとこちらの手を見つめる直貞の口元が、にやりと吊り上がった。
「西海道でも征西将軍宮率いる南朝方の動きは活発になっているようですが、まだ海を越えて上洛を狙えるほどの力には育っておりませぬな。大軍を運ぶことのできる海の道があれば、また別なのでございましょうが」
直貞の顔が西に向いた。空は青く晴れ渡っている。互いに思い浮かべたのは、同じ女の姿だろう。霞の話を口にしようとしたとき、のそりと盛宗が立ち上がった。
白い長髪を濃紺の直垂の後ろで束ねており、どこか人間離れした厳格さを感じさせる。それが厳格さではなく、戦に出られぬことでふて腐れているだけということに、最近ようやく気付いてきた。齢五十を超えてなお、磨き上げた武を戦場で披露することだけを生き甲斐としている。
人を食ったような格好の直貞と、戦が無ければ駄々をこねる赤子のような盛宗。自分にとっての右腕と左腕を見て、直冬は頭を掻いた。癖がありすぎはしまいか。
「御老公、どこに?」
「何もせずにおるのは、弓の腕を腐らせることになりますからな。ちとばかり、兵を連れて山に入る」
「いつ出陣の教書(命令書)が届くか分からぬ。なるべく声の届くところにいてくれ。勝手に出陣したら、あんた、怒るだろう?」
「そりゃ、そうじゃ」
盛宗が呵々と笑った。
木津の本陣に、直義から待ち望んでいた兵が送られてきたのは、十一月二十日のことだった。隣国の河内国では、二月前に細川顕氏が大敗して以来、大きな戦は起きていない。
楠木正行は、幕府軍の合流を待っているのだろう。寡兵にもかかわらず、正行には相当な勝算があるらしかった。兵力を分散させることが、戦い方の常道であることを思えば、正行の振る舞いは傲慢と思えるほどの自信を感じさせた。
「それが、狙いかもしれぬが」
源平の血を引かない正行が兵を集めるには、己の力を見せつけるしかない。それも、圧倒的な力の差としてだ。事実、顕氏が敗れてから、南朝方の兵は増えているとも聞き、北朝方の兵の徴募は滞り始めていた。
本陣前に集められた千五百の兵を見て、直冬は絶句した。
千五百の兵は、歳こそ二十歳から三十歳くらいの者が多い。だが、鎧を身に着けている者はほとんどいない。
「直貞よ、どうにも目の調子が悪い」
前列で欠伸をした者など、襤褸のような布を身体に巻きつけ、拳大の石を握っているだけだ。
「刀を持ってきている者が百人程度。あとは鍬か棒を持った者たちのように見えるが、直貞。これは、俺の目が悪くなったせいではあろうな」
直冬の軍の副将として、兵の前に立つ直貞の顔からも、いつもの愉快さは消えていた。
「殿、それならば、私も目が悪くなったやもしれませぬ」
呟いた直貞の横で、いきなり盛宗が高らかに笑った。
「このまま戦場に連れていけば右も左も分からぬまま敗けそうですのう」
「敗けるだけならばまだ良い。百も生き残るものか」
死ぬと分かりきっている者を戦場に送り込むつもりは無かった。
直冬の横で、盛宗が濃紺の直垂の袖をまくり上げた。
「細川殿が楠殿の倅に敗れたことで、幕府方もなかなか兵が集まらぬと言っておったからのう。細川殿の後詰の山名殿も、兵を集められず、一万が六千しか集まってないと聞く。千五百だけでも、送り込まれたことを良しとすべきでしょうな」
それに、と続けて盛宗が笑った。
「新たな兵ほど、鍛える楽しみも大きいでな」
白髭を揺らす盛宗の笑みに、直冬は鴉軍の調練を思い出して背筋が寒くなった。
戦場では、いかに技に長けていようとも、死に怯えた者から真っ先に死んでいく。そう言った盛宗は、鴉軍の兵を、いっそ死なせてくれと泣き叫ぶまで追い込んだ。十日間にわたって山中を這うように行軍し、夜は眠ることを許されず、時に二軍に分かれて夜戦を模したぶつかり合いを繰り返した。直冬が泣かなかったのは、白粉を涙と汗でぐちゃぐちゃにした直貞を見て、自分はこうなるまいという意地だった。
死を恐れぬようになることで、兵の顔つきは明らかに変わった。戦場で生き延びさせるためにも、調練は敵よりも恐ろしくあらねばならないことを、その時に知った。そして、伏見の調練で細川顕氏に圧勝したことが、鴉軍の自信となった。
口元を右手で隠し、直冬は目を細めた。
考え込む時の癖だが、そうすることで自然と何をすべきか見えてくる。
「御老公、長柄の得物を使って、敵を足止めすることに絞って調練をしてほしい」
盛宗が目を細めた。
「ふむ、それならば、ひよっこどももいくらかは役に立つやもしれぬのう。じゃが、それにしても二月、三月はかかろうて」
「もう少し時をかけてほしい。できれば、半年ほど。それまでは、こいつらが戦の役に立たぬと敵には思わせておきたい」
にやりとして、直冬はみすぼらしい兵たちを眺めた。
「ほう。その悪だくみは、もちろん儂も連れて行ってもらえるのじゃろうな」
「御老公の弓は、必要になる」
「よかろう」
相好を崩した盛宗が、兵の方へ歩き出した。
「直貞、鴉軍はいつでも出陣できるようにしておけ」
「我らの出陣は、京からの教書によって決まりますが」
「いや」
そう呟き、直冬は胸の中にある嫌な予感を口にするかどうかを迷った。正行の戦は、初陣とは思えぬほどに狡猾で果敢なものだった。山名軍六千が加われば、北朝方は一万二千の大軍になる。南朝方の正行勢は、二千から三千ほど。だが、それでも正行には勝てないのではないかと思っている自分がいた。
もしも、北朝方が負ければ、京からの教書など待っている暇はないかもしれない。ただ、その時、自分は正行という武士に勝てるのだろうかという恐怖があった。木津の丘を、必要以上の砦となしたことも、戦場に対する己の恐怖の裏返しかもしれない。
「直貞」
「なんでございます?」
「楠木一族の忍びを遠ざけることはできるか?」
直貞が、そこに潜む者を見つけようとでもするように、紅葉に染まる山を見上げた。
「わずかな時、一日程度であれば」
「十分だ」
頷きを返し、直冬はこめかみに拳をあてた。
今、楠木正行の目に映っているのは、細川顕氏と山名時氏の大軍だろう。優秀な忍びを抱える正行であれば、直冬が木津にいることも分かっているだろうが、戦力と呼べるものでないことも知られているはずだ。千五百の兵の調練が遅れていることも、すぐに伝わる。そもそも、初陣すらまだの自分を、正行は気にも留めていないかもしれない。
足利直冬という武士の姿を、正行の視界から消す。
正行が幕府の大軍に意識を集中させた時、奇襲は上手くいく。
「直貞。正行の首を狙うぞ」
すこしばかり声が上ずっているのは分かった。初陣ながら細川軍を破った正行への怯えだということは、認めた。怯えているからこそ、正行に打ち勝ちたかった。
「御意。全ては、殿の思うままに」
目を細めた直貞が、ゆっくりと頭を下げた。