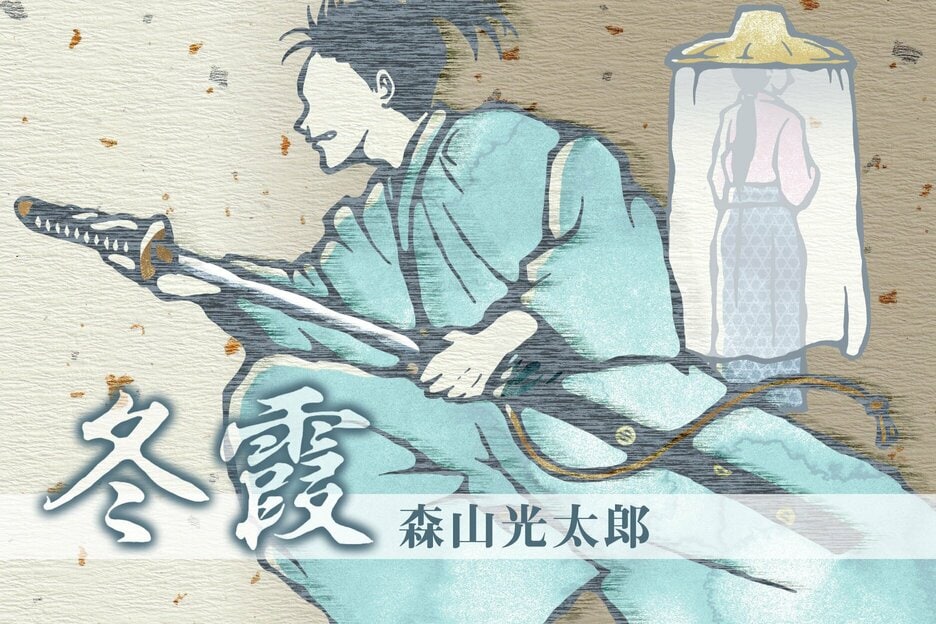この男を、見極めるために、京まで来たのだ。
そう思った刹那、新熊野の姿が消えた。いや、消えたように見えただけだ。三間ほどの間合いを一瞬で詰め、盛宗の足元に蹲った。光が閃いた。遅れて、宙に血が舞う。血霧の中、二人が弾けるように飛び退り、刀を構える。
新熊野は地を這うような下段。盛宗は威圧するように、天に向かって刀を突き上げた。その威圧は、盛宗の焦りのようにも見えた。新熊野の顔は、涼しい。
盛宗の二の腕から血がしたたり落ち、その顔から笑みが消えた。
鬼の形相だった。
昔、絵巻物で見た弁慶と、牛若丸の立ち合いを思い出した。盛宗麾下の武士は、二人の気迫に呑まれ、一歩も動けていない。二人の間に、何かが満ちた。そう感じた瞬間、二人が交錯した。再び血が舞った。盛宗のものだ。一息も待たず、振り向きざまに盛宗が新熊野に斬りかかる。新熊野の刀が、流れるように盛宗の刀を受け流す。
盛宗の咆哮をかき消すように、耳をつんざく金属音が響いた。
信じられない光景だった。向かい合った盛宗の刀が、中ほどから断ち切られていた。周囲の武士たちも、目を見開いている。
「鋼を斬るとはのう」
盛宗の頬に、愉悦混じりの笑みが広がった。闘志は衰えていない。むしろ、こちらの息がつまるほどの殺気を放ち始めた。
間合いを取った二人が、構えた。
次、交錯すれば、どちらかの首が飛ぶ。
そう思った時、不意に、石畳を叩く足下(下駄)の音が響いた。静寂をいきなり破ったかのような音だった。心の臓が凍りついた。すぐ後ろにいる。だが、気配は一切感じなかった。もし追っ手ならば、振り向く間もなく殺されるだろう。
気取られぬよう、霞が右手を柄に伸ばした時、背後から舌打ちが聞こえた。
「戯れもほどほどになされ」
もう一度、足下の音が鳴った。
「戯れ、じゃと」
唸るような声を上げたのは、息を荒らげる盛宗だった。
その視線が、闖入者に向けられたことで、霞もまた振り返る余裕ができた。
すぐ目の前に、異装の男がいた。緋色の直垂を身につけ、腰には白鞘の刀が吊るされている。首元に獣の毛皮を巻く姿は、乱心していなければ到底できない格好だった。白粉で顔を塗っているようだが、殿上眉は描いていない。
奇異な姿の闖入者は、霞を見ることもなく新熊野の傍まで近寄ると、深々と盛宗に向かって頭を下げた。
「今川直貞と申します」
「言わずともわかる。さような珍妙な格好、今川の不出来者しかおるまい」
直貞と名乗った男が、気にする風でもなく微笑んだ。
「仁科様、どうか刀をお納めください」
「武士の立ち合いを止めることの咎を知っておろうな」
「仁科様の立ち合いは戦場にこそございましょう。ここは戦場ではございませぬ。さすれば、これもまた命をかけた立ち合いにはござらぬ」
背後の陽は、すでに高く昇っている。時が止まったかのように誰もが動けぬ中、呆れたように笑ったのは新熊野だった。
「御老公。弓であれば、俺の敗けだったかもしれぬ」
「莫迦なことを。刀でもまだ敗けてはおらぬ」
盛宗の言葉には応えず、刀を納めた新熊野が、霞の方に近づいてきた。
「間に合ってよかった」
その額に滲む汗が、輝いて見えた。見上げる格好になった。
「なぜ、追ってきたのです」
「あんたと俺は似ている。自分を殺すような真似はしたくないと思っただけだ」
胸の内に落胆のようなものが広がったことに、霞は袖の内で拳を握った。
「直貞。この姫君をお送りしろ」
名指しされた直貞が、あからさまに面倒そうな顔をした。白粉の塗りたくられた顔が、いっそう滑稽に見えた。獣皮の毛並みを整えるように撫で、直貞が盛宗へと身体を向けた。
「この場は、私が預かります。袖にされた女が逃げ、新熊野様がそれを追ったまで。侍所の御役目を妨げようとしたわけではございませぬ」
「骸二つ、どう説明する」
盛宗の低い声に反応した霞を、新熊野が目で抑えた。
「いかようにも。我らは、あずかり知りませぬ。侍所も、今はまだ三条殿(足利直義)と事を構えるおつもりはないでしょう」
涼しげに言い捨てた直貞が、もう一度頭を下げると、おもむろに背を向けた。
「霞殿、こちらへ」
その囁きに、背筋が凍った。京に辿り着いてから、一度も名を名乗ってはいない。強張った背に、新熊野の手が添えられた。
「今は、敵ではないさ」
新熊野の呟きとともに、歩き出した。追ってくる気配はない。大徳寺の境内が見えてきた頃、新熊野が立ち止まり、霞の方を振り返った。微かに笑ったような気がした。それが自分の願望なのか分からぬまま、直後、新熊野が背を向け、境内に消えた。
「新熊野様は、戦の世の仇花とでも言うべきお方です。御身にも、重なる」
口を開いたのは、今川直貞だった。重なるとはいかなる意味なのか。人を食ったような顔をするこの男には聞きたいことが多くあったが、それを拒絶するように直貞が顔を背けた。
「願わくは、人知れず老いていってほしいものですが、この世がそれを許しますまいな。新熊野様も、貴殿も」
歩き出した直貞を追うべきだと思った時には、すでにその姿は杳として消えていた。
二 新熊野
夏の朝陽が、深緑の竹林に燦々と降り注いでいる。
大徳寺の境内にある古びた東屋に腰をかけ、新熊野は強張った肩を伸ばした。
夜通し、仁科盛宗と飲み明かしていた。いくら飲んでも酒に酔うことはないと思っていたが、身体には少しばかりの気だるさがある。若僧の心胆を試してやろうという思惑が見えて、負けるものかと飲み過ぎたかもしれない。巨大な蜘蛛の巣のある天井に向けて、息を吐きだした。
霞という女を追いかけて、立ち合ったのが出会いだった。
立ち合いから十日ばかり経った頃、仁科盛宗は唐突に酒を持って現れた。白い長髪を後ろでまとめ、紺色の直垂の背には、麻縄で繋がれた酒壺が四つ。刀を斬られたことへの腹いせか、それから二か月、十日に一度は同じような格好でやってきては飲み比べをしようとする。昨晩は、従者もつれてきており、抱えてきた酒壺は十を超えていた。
酔うと、かつての戦を語るのが癖だった。そして、決まって戦で死にたいと言って眠るのだ。偏屈な爺様ではあるが、政のしがらみを感じさせない盛宗のことは、嫌いではなかった。
そろそろ、今川直貞が来る頃だった。
いつも、気が付くと傍にいる。気配の殺し方が、異様に上手いのだ。気になって、どのような育ちをしたのか何度か探りをいれたが、決まってはぐらかされた。
今も、そうだ。
「どうぞ」
新熊野の頬のすぐ横に、水の入った竹筒が差し出されていた。
二歩ほど後ろに近づくまで、やはり気づかなかった。二歩あれば、殺されることはない。
「弓だと分からんな」
「何がでしょう?」
惚けるような直貞の言葉に鼻を鳴らし、新熊野は竹筒を受け取った。直貞が、東屋の向かいに座った。
「仁科殿が出入りするようになって、寺の者たちからの折檻はないようですね」
流行りの婆娑羅気取りなのか、いつも通り朱色の小袖と白鞘の刀を身につけている。公家でもないくせに、白粉化粧をしているのだが、それは素顔を知られないための用心なのだという。
「あれはあれで良い受け身の鍛錬になっていたのだがな」
「鎌倉では、もっと酷い扱いを受けていたのでしたね」
「生かさず殺さず。酷い扱いを、俺の修行だと決めた僧がいた」
黄金色の法衣を好んだその僧とは、二度と会うことはないだろうが、会えば刀を抜くことを堪えられないだろう。母を失ってからの十年余。鎌倉の東勝寺で過ごした時は、思い出すことすら苦痛に思えるほどだ。ただ、生きることに必死だった。
「東勝寺は、北条家の菩提寺ゆえ、滅びた北条氏に連なる者が多かった」
「そこに、足利の血縁を名乗る新熊野様がやってきたというわけですか。寺の者からすれば、恨みを晴らすには格好の童だったのでしょうね」
「十人に囲まれての殴る蹴るは日常。杉にぶら下げられ、拳ほどもある石を投げられ続けたこともある」
生き延びるために、あらゆることを身につけた。武術はもとより、独りゆえ、時間はたっぷりあったから与えられた書は人の三倍読み込んだ。旅人が来れば、山野で一人生きるための知恵も学んだ。野に生える草にも、食べられるものと食べられないものがある。夜空に動かぬ星があることも知った。
「ある日、折檻を受けて気を失ったことがあった」
直貞が、続きを促すように頷く。
「起きてみれば、深い山の奥。里の光などは見えず、獣の声が夜の中に響いていた。着の身着のままで、刀も取り上げられていた。あの時は、まいったな」
「いくつの時です?」
「十やそこらだ」
「よくぞ獣の餌にならなかったものです」
大げさに驚く直貞に、新熊野は片方の口の端を上げた。
「痩せこけた童など、食いでが無いと思ったのだろうさ。だが、夏の野山で良かった。知識があれば、食うものには困らぬ。寺よりも良いものが食えたぐらいだ」
直貞が笑った。歳は二十。新熊野と同年だった。京に来て二年、時折現れては他愛のない話をしては帰っていく。父、足利尊氏への謁見を拒絶され、途方に暮れていた新熊野のもとに、尊氏の弟である直義が遣わしたのが出会いだった。
新熊野を拒絶することを尊氏に進言したのは、直義だという。そうしておきながら、麾下の直貞を、従者として遣わしてきた直義を、新熊野は警戒していた。父子の仲を裂き、何を企んでいるのか。自分を何に使おうとしているのか。
尊氏によって、この国は平穏を取り戻しつつある。父を妨げるというならば、自分の手で直貞たちを殺す。いつの日か、そう決意していた。だが、ゆったりとした日々が続き、今のところその気配はなかった。会えば酒を飲み、時に街に繰り出す。直貞には友に近い感情も出てきてしまったように思う。初めての友が、これほど珍奇な男というのは想像していなかったが、いずれ敵になったとしても、後を引かない気もした。
沈黙を怪訝に思ったのか、直貞が首をかしげた。
「味方はいなかったのですか」
「一人、円林という僧がいた」
十七歳になる前、新熊野を鎌倉から京まで連れ出したのも、円林だった。六歳で出会った頃、老境に差しかかっていた。
「円林殿が寺の者たちを止めることは?」
「なかったよ。それどころか、あの坊主は陰で俺への折檻を扇動していた気配すらある」
「それは、味方ですか?」
「どうだろうな」
苦笑し、肩を竦めた。
「敗れた者の憎しみ、執拗さ。勝者を狙う者の性を、俺に伝えようとしていた。俺を武士として育て上げ、足利との繋がりを作ろうとしたのかもしれん。なにしろ、大樹の後ろ盾があれば、東勝寺の住持になることも容易いと思っていたであろうしな」
「思惑が外れたということですか」
直貞が得心したように頷いた。円林に伴われて上洛した新熊野が、尊氏への謁見を求めて拒絶されたことを言っているのだろう。苦虫を噛み潰したような円林の表情を思い出して、思わず笑った。直貞が顎に手を当てた。
「されど、なにゆえ東勝寺に行かれたのです。そのような扱いになることは予想できたでしょうに」
「亡き母が、生きているころに、円林に俺のことを頼んでいたのだ。俺のために、何かをしてくれたことのない母だったからな。むしろ喜び勇んで入寺した」
母が死んだのは、鎌倉幕府が滅びた日だった。
黒煙を上げる東勝寺を見下ろしながら誓ったものは、未だ胸の中にある。
母を殺す戦を起こした者を滅ぼさねばならない。鎌倉を滅ぼすため、武士を扇動したのが、この国の王であることを知ったのは、歳を重ねてからだった。
王が敵であるならば、逃げるのか。自らへの問いの答えは、決まりきっていた。
たとえ、天に等しいものが敵であろうとも、歩みを止めるつもりは無い。
そう願った童の心中を、円林は気づいていたふしがある。だからこそ、東勝寺では恨みの矛先を変えようとしていた。過酷な仕打ちを受ける新熊野を見て見ぬふりをし、憎しみを思い出させないようにしていた。
過酷な日々は、新たな恨みを生み、母の仇の姿を塗りつぶした。だが、消え去るわけがない。十年の歳月を経て、胸の奥底で鋼のように陶冶されたようにも思う。傷つくことで、誰かが自分を見つけてくれるとも、幼心に思っていた。
ただ、平穏を迎えつつあるこの国を乱すことが赦されるのかと考えるようにもなった。
鎌倉幕府が滅びて、この国は全土が飢えた。
南朝と北朝の戦乱は、全土の民から兵粮を奪うことで続いたと言っていい。南朝の英雄北畠顕家が、陸奥から京まで進軍してきた時など、わずかな蓄えを奪われた沿道の民の多くが、その年を越せなかったと言われている。なにも南朝に限った話ではない。北朝方の尊氏が再起をかけて九州から上洛した時も、同様の悲劇が各地で起きている。
民は片手に載る程度の雑穀を、家族で分けて食べるしかなく、それを水に薄め、二日に分けた。戦が起きれば、わずかな雑穀すら、兵に奪われる。民を待っているものは、死だけだった。東勝寺で出ていた朝夕の膳が、日々少なくなる様を見て、世の飢えを知った。
尊氏が征夷大将軍に任じられて八年。南朝の主柱をことごとく討ち果たし、政敵であった後醍醐帝が薨去した今、大きな戦は鳴りを潜めている。父は、母を殺した戦の元凶を、自ら斃したのだ。
民の顔つきは、目に見えて変わった。こけた頬をしている者が、いなくなった。戦乱に苦しんだ民が、先を見据えて笑おうとしている。後醍醐帝が薨去したいま、敵を求めて生きることは、民を苦しめることではないのかと迷っていた。
首を左右に振り、新熊野は歩き出した。
直貞を振り返った。名門今川家から追放された、はぐれ者。自分とも境遇は重なる。大徳寺で出会った霞という女もまた、南朝の血を引きながら、厄介払いされた者だということは、直貞が調べ上げていた。
憂いを帯びた綺麗な目を、思い出した。薬の入った貝殻を渡してきた。新熊野を助けることに、もどかしさも混じっていたように思う。その葛藤に、どこか惹かれた。
今のところ、直貞の主である足利直義に、霞をどうにかするつもりは無いようだった。南朝に離間をかけるために泳がせているのかもしれない。
だが、神がかった謀を成す直義のことだ。その目が誰を見ているのかは分からない。もしも父に仇なすつもりであるならば、刺し違えてでも止める。
「それを今日、教えてくれるのだろうな」
新熊野の問いかけに、直貞が小さく頷き、ついてくるようにと歩き出した。