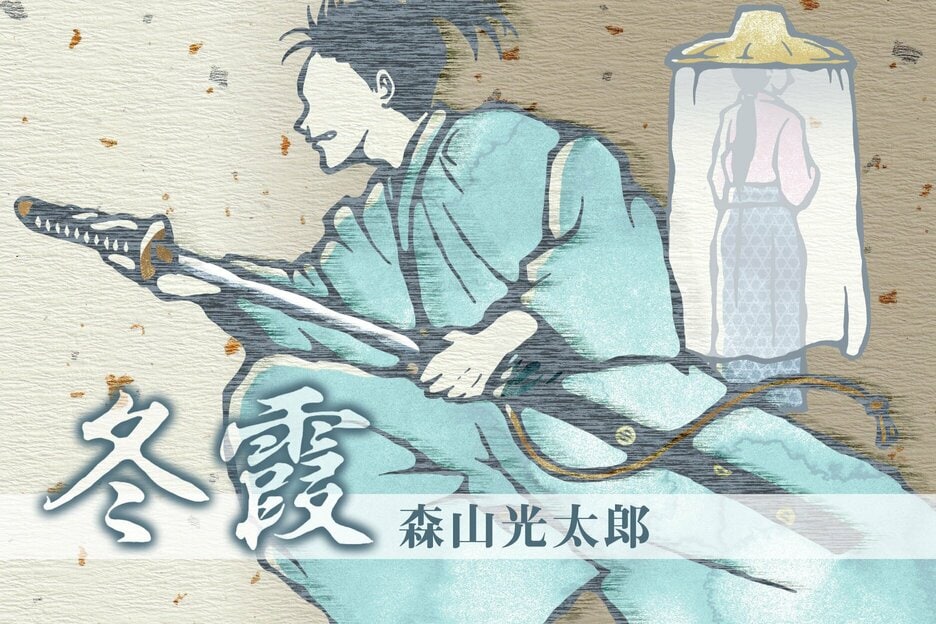実子であることを、尊氏が疑ったわけではない。新熊野が携えていた二つ引き紋の入った刀は、かつて尊氏が越前という白拍子に授けたものに間違いなく、顔立ちも尊氏の若い頃によく似ていた。似ていたからこそ、尊氏は直冬に新たなる敵の姿を見たのだと、師直は思っていた。
尊氏は、鎌倉幕府という巨象のごとき大敵を滅ぼし、この国の王たる後醍醐帝に打ち勝って、武士の王となった。
赤橋家や師直の仕掛けた暗殺が失敗に終わった時、尊氏は新たな遊び相手が現れたとでも言うように、片頬を吊り上げ、無邪気に笑ったのだ。
己の道を妨げる者を斃すことこそが、尊氏の生き甲斐だった。鎌倉幕府が滅び、後醍醐帝という強敵がいなくなって以来、自らの強敵となる存在を、尊氏は探し求めていた。
それが実の子であることなど、尊氏は気にも留めていない。むしろ、血の繋がった子を討つことで、さらなる強さを手に入れることができるとでも思っているかもしれない。
直冬を殺せと命じるのは、死地を乗り越えることで、己の敵に相応しい器になるという歪んだ望みゆえのことだと、師直は気づいていた。
「南朝で派手に動いているのは、楠木正成の倅だったな」
尊氏の呟きに、師直は頷いた。
「河内(現在の大阪府)守護の楠木正行でございます。死んだ父と同じく、兵粮を運び込み、戦備えをしております。殿と三条殿の不和を、南朝の者どもは、好機と見て取ったのでしょうな」
数年来、尊氏と直義の間に溝があることは、全土に知れ渡っていた。
とはいえ、もともとは二人が互いに嫌い合っているというわけではない。
幕府が始まった時、一刻も早く全土を鎮めるため、直義が古い権門の力を最大限に利用したことがきっかけなのだろう。全土への安国寺の設置など、幕府の威光を広げることは上手くいったが、幕府草創で新たに名を上げた武士たちは直義の政からはじき出され、彼らの多くが直義への不満を抱いたのだ。そして、彼らが頼ったのは、直義と同等以上の力を持つ尊氏や師直だった。
二人の兄弟を取り巻く者たちの不和が、兄弟の不和として囁かれ始め、直冬が養子となったことで、不和は対立として世に広まった。その風聞は、京洛どころか、遠く鎌倉までも届いているという。事実、尊氏も直義も、同じ北朝方でありながら、自らの屋敷を戦時のように固めているのだ。
直冬の姿は忌々しい。だが、数年来、難攻不落の吉野に閉じこもっていた南朝が、重い腰を上げて戦備えを始めたのだから、彼らを引きずり出したとも言える。
直義は、それを狙っていたのだろうか。あの男であればと思えてしまうのが、直義の怖さでもある。尊氏もまた、弟の目論見を分かったうえで、あえてそう振る舞っているのかもしれない。
もしくは、弟すら、新たな遊び相手になりうると見ているのか。言い知れぬ怖気が込み上げてきた時、尊氏が口を開いた。
「ずっと思案しておるが、お主の考えを聞かせてもらおうか?」
「はっ。いずれについてでございましょうか?」
「討伐軍の将は、誰にすべきか」
それを問われることは分かっていた。頷き、丹田に力を込めた。
「先手は細川顕氏殿。後詰は山名時氏殿がよろしいかと」
ともに、直義派の大名だ。尊氏が、ちらりとこちらを見た。尊氏は、強い大名の力を削ぐべきだという師直の考えを知っている。仄暗い恨みも、分かってくれている。
名を挙げた二人は、これまでの戦で幾度となく功績を上げ、幕府の中でも大きな影響力を持っている。削ぐべき、武士だった。
こめかみに拳をあてた尊氏が息を吐いた。
「お主と直義は、やはり相容れぬか」
全土の武士の力を削ぎ、幕府のみが軍を持つという師直の考えに、直義は真っ向から反対している。直義はそれこそ百年という時をかけて成すべきことであり、師直の目指す戦は、世を滅ぼすと言い放った。直義の言葉も理解はできるが、あまりに甘い。
その百年の間に、どれだけの死者を出すというのか。
尊氏にしてみれば、師直を取るか、弟を取るか迫っているようにも聞こえているかもしれない。師直を選べば、実の弟が尊氏の前に立ちはだかることになる。
尊氏が拳を下ろし、苦笑した。
「吉野との戦、直冬を出陣させる」
尊氏が、師直を見ることなく言った。細川と山名の力を削ぎ、直冬も殺す。吉野の南朝を滅ぼせば、ついに師直の望む最後の戦が始まる。
「そこで、殺してみよ」
茶器を投げ捨てた尊氏の言葉に、昔見た下野国の青空を思い出した。
焚火を囲み、野で獲れた兎の肉を串に刺し、炙っていた。
傍の岩の上には、大陸から入ってきた岩のような赤みがかった塩が一つ。まだ若かった尊氏と直義、そして自分が笑っている。懐かしい。その光景が、ただ懐かしかった。
会談からは、十日が経っていた。
尊氏と会談したその日のうちに、師直は備中国(現在の岡山県)の守護となっていた一族の南宗継へ、上洛を求める催促状を送った。これまでも、師直を裏から支えてきた男だ。直冬を戦場で殺すためにも、人知れず動くことに長けた者が欲しかった。
暁もまだ遠いのだろう。昨夜、大路を歩いているところを連れ込んだ女が、隣で寝息を立てている。暗がりではよく分からないが、師直好みの肌の白い女だったはずだ。女の身体を押しのけて寝床から起きた師直は、障子を静かに開け、紫色の空を見上げた。
庭の松の枝に、黒い紙が巻き付けられている。
宗継が率いる黒草衆の使うもので、到着の報せだった。直義に気取られぬよう、宗継には屋敷に来るなと命じていた。
「まあ、すでに気取られておるかもしれぬが」
苦笑して、黒い紙を手に取った。無骨な筆で、八幡とだけ記されている。
「随分と早かったな」
呟くと、師直は傍に控えていた従者に馬を命じた。
空腹を感じたが、朝餉にはまだ早い。我慢して直垂の袖に腕を通した師直は、門の前に用意された葦毛の馬に飛び乗った。ついて来ようとした従者に、要らぬと首を振り、馬腹を蹴った。姿は見えないが、すでに黒草衆の忍びは、師直を遠巻きに護るような配置になっているはずだ。
京の夏は、明け方でもまとわりつくような暑さがある。嫌な汗が滲んでいたが、馬上の風で、徐々に身体が冷えてきた。
八幡に辿り着いたのは、笠置山の峰に朝日が顔を出した頃だった。
宇治川の土手で下馬し、師直は汗を拭った。
朝焼けの中、片肌脱ぎになった武士が、宇治川の流れを前に、弓を構えていた。師直の足音は聞こえているだろうが、石のように微動だにせず水面を見つめている。
十歩の位置まで近づいた時、弦の震えが響いた。水面が弾け、矢が水の中に突き立つ。
「良いところをお見せしたかったのですがな」
苦笑と共に振り返った武士の顔には、目立つ頬傷がある。南宗継。短く刈り揃えられた顎鬚は昔から変わらない。仁王像のように引き締まった身体からは、見る者を畏縮させる武の匂いが漂っていた。
「お主はいつも矢で魚を狙っておるのか?」
「まさか。若様がいらっしゃったので、我が研鑽を見ていただこうかと」
「若様などという歳でないのは、お主も知っておろうが」
南家は、師直の祖父の代に枝分かれした一族だった。宗継は、師直にとって又従弟にあたる。武略に長けた高一族の中でも、宗継の武勇は頭抜けている。師直を惣領とした高一族が、戦に勝ち続けてきたのも、宗継のような戦人が多いからだった。
からかうような表情の宗継が、河原の砂利に弓を置いた。
「すぐに、朝餉を用意させます」
宗継が手を叩くと、それまで土手の陰に控えていた従者たちが、一斉に飛び出してきた。
いずれも、鍛え上げられている。黒草衆は、個よりも集団で動くことに長けている。足利の治世を裏から支えるため、宗継が鍛え上げた忍びだった。手際よく竈をつくり、火を熾す。岩に座って待っていると、鮎の香りが河原に立ち込めはじめた。
「美食を好む若様の口にあえばいいのですが」
従者が運んできた机に、膳が用意されていた。握り飯には水菜の浸物が添えられ、程よく焦げ目のついた鮎には、塩が浮かんでいる。口の中に、涎が溢れるのを感じた。
「戦場では草の茎でも美味いものだが」
宗継が五人の従者を下がらせ、師直たちは握り飯を口に運んだ。鮎に箸をつけた時、宗継が笑った。
「鮎の肝を真っ先に食べるのは、昔から変わりませぬなあ」
「脂の甘みと肝の苦みが、一番美味い」
口に入れた鮎の肝は苦く、あまり脂の甘さは広がってこない。落胆が表情に出ていたのだろう。宗継が苦笑した。
「あと、一、二か月ばかりすれば成魚となり、若様の好きな味になりましょうが」
「すまぬ、いらぬ気を遣わせたな」
「いえいえ、昔からのことでございますれば。とはいえ、今の時期、若鮎は仕留めやすうございます」
意味ありげな視線を膳の上に向けた宗継が、箸で鮎の頭を切り取った。
「若い鮎は、少しばかり挑発してやれば、すぐに針に食いつきますからな。水から上げてしまえば、そこで終いでございます」
「鮎のこと、ではないな」
師直の言葉に、宗継が頷いた。
「戦が始まりますな」
食べ終わった鮎の細い骨を川の中に投げ込み、師直は頷いた。
「聞いておるであろうが、南朝の楠木正行が動き始めておる」
「やはり、南朝の柱は、楠木一族ですな」
思い入れのあるもののように、宗継がしみじみと呟いた。
「此度が初陣と聞きますが、幕府の武士の中にも、しり込みする者は多いでしょう。父親の正成殿はまさに機略縦横、神出鬼没でした」
「まことよ。儂も正成の戦には手を焼いた」
「若様だけではありますまい。北朝のほとんどの将が、幾度となく煮え湯を飲まされてきました。それこそ、たとえではなく」
宗継が顔をしかめたのは、正成が煮た糞尿を城から落として、北朝方の兵を撃退した話を思い出したからだろう。
人の意表を衝く戦い方が得意な男だったが、真正面から向かい合っての戦も、見事なものだった。楠木正成を討った湊川の戦いでは、わずか七百騎を率いるだけの正成に、五千の兵でぶつかった直義は、あわや首を取られる寸前まで追い詰められていた。もしも、正成が源平どちらかの血を引き、武士の棟梁と認められていたならば、南北朝の勝敗も変わっていたはずだと、尊氏がしみじみと呟いたのは、今でも覚えている。
正行は、それほどの男の血を継いでいる。血が騒ぐのは、どうしようもなかった。
「されど、こたびは細川と山名が指揮を執る。万が一にも後れを取ることはあるまい」
「であればよいのでござりますが」
含みのある物言いをした宗継が、すっと目を光らせた。
「しかし若様。苦戦は必要だとお考えなのでは?」
細川顕氏と山名時氏を指名したのは師直だったが、尊氏も否定はしなかった。
直義麾下の力を削ぎたいという思惑が透けて見えるのだろう。ただ、それだけでないことを、宗継も分かっている。若鮎を朝餉に用意していたことにも、周到さを感じた。
宗継の瞳が、東の空へと向けられた。
「それがしを備中から呼び寄せたのは、新熊野のことでございますな」
宗継が顎鬚を撫でた。
「新熊野。今は直冬ですか。鎌倉でその母を討ったのは、それがしでござりました」
「まことに大樹の血かもしれぬと、報せてきたのを覚えておる」
「童の戯言に過ぎぬと思いましたが、あまりにその瞳の光は強く」
「気圧されたか」
やや沈黙の後、宗継が頷いた。
「逃げることを許せぬという瞳をしておりました。わずか六歳の童が、それがしと向かい合ってなお、前に出ようとしておりました」
「分からぬな」
歴戦の宗継を圧倒するほどの気迫を持った童など、俄かに信じがたい。
鎌倉時代の新熊野について調べさせたが、東勝寺の喝食として虐げられている姿しか分からなかった。真っ赤に焼けた鏝をあてられるなど、目を背けたくなるような仕打ちもあったが、新熊野は逃げ出すこともなく、ひたすら耐えていたという。東勝寺の僧の中には、滅びた北条家の縁者が多いこともあり、足利の名を名乗る童は、打擲の的だったという。
「東勝寺では、己を偽っていたのだろうか」
「どうでしょうなあ。それは分かりませぬが。されど、今の直冬を殺すことは、いささか骨が折れましょう」
「お主ほどの武士がそう言うか」
「刀の腕は、あの仁科の御老公が認めるところと聞きます。傍には、狡猾で抜け目のない今川の子倅もいる」
「今川の不出来者ごとき」
「とは言いますが、若様。今でこそ縁を切られておりますが、あの珍妙な姿を除けば、今川殿の当主も認めていたほどの器です」
白粉を塗りたくり、こちらを莫迦にしたような風貌を思い浮かべて、師直は舌打ちした。宗継が、たしなめるように竹筒の水をすすめてきた。
「なにより、直冬の兵を率いる力は侮れませぬ」
「伏見での調練のことか」
「御意。直冬が新たに編成した百の騎馬武者。あれは、尋常のものではございませぬ」
宗継の言葉に、師直は鼻を鳴らした。
小童と吐き捨てたい気持ちはある。
だが、戦にかけては随一という自負のある師直の目から見ても、直冬の作り上げた騎兵は見事な強さを持っていた。鴉軍と称する黒衣の百騎は、伏見の原野に現れ、一刻も経たぬうちに細川顕氏率いる千の兵を散々に打ち破ってみせた。
直義麾下の力を見ようと、遠くから調練を見ていた師直ですら、殺すべき相手であることを忘れ、戦人として感嘆の声を上げたほどだったのだ。血反吐を吐くほど鍛え上げたのだろう。だが、兵の強さだけではない。細川兵を引き裂いた直冬の動きは、師直であってもそう動くであろうものだった。間違いなく、直冬は将としての力を持っている。
もしも、直冬が尊氏との血の繋がらぬ若い武士であったならば、師直が鍛え上げたいとも思っただろう。鍛え上げれば、自分を超える戦人になるかもしれない。
惜しい、という気持ちは強くある。だが、この国の平穏に、直冬という男が邪魔であることも確かだった。
「尋常でない男だからこそ、死なせてやらねばならぬ」
尊氏の後継者である義詮は、人好きもよく、荒くれ者の多い東国の武士にも好かれている。
人を従える器は間違いなくある。だが、父である尊氏も認めるところで、義詮の戦の才はからきしだった。
もしも直冬が、義詮を認めぬと天下に名乗りを上げれば、天下は再び長い混乱に陥るだろう。武士は、血に惹かれる。強い棟梁を、本能が望むのだ。師直が義詮を後見しているとはいえ、直冬に同調する者は各国の守護の中にも出てくるだろう。
そうなれば、全土の武士の力を削ぐという師直の使命も、はるか遠のく。
だが、それ以上に師直が恐れていることは、尊氏が新たな敵を見つけてしまうことだった。戦場の尊氏は、見る者全てが打ち震えるほどの威容がある。武士であれば、武士の王の姿を一目見れば惹かれる。そして、武士の心の奥底にある戦への渇望を、激しく呼び覚ます。
乱世には代えがたい英雄。
しかし、世が治世を望むいま、武士の王を戦場に立たせてはならない。戦場に立つのは、自分や宗継のような武士でいいのだ。
宗継の頬傷が歪んだ。苦笑したようだ。
「ご心配召されるな。直冬は、それがしが」
「頼めるか」
「鎌倉を出れば、斬る。直冬が覚えておるかは分かりませぬが、そう言ったのはそれがしです。なにより、直冬の母の仇でもある。万が一、それがしが返り討ちにあったとしても、直冬の胸中にある恨みは消えましょう」
「本来であれば、儂が片付けておくべきことだったのだ」
「なんのなんの。些事は、それがしに任せてくだされ。若様は、南を滅ぼすことだけに集中なされ」
「お主も南だろう」
「若様と戦うのは勘弁ねがいたいですな。若様と戦うのは、命がいくらあっても足りなさそうだ」
はっきりと笑った宗継が、右手を挙げた。
いつの間に近づいていたのか。師直たちから百歩ほど離れたところに、五十を超える者たちが片膝で跪いている。黒草衆。彼らが身につける潤朱色の肩布は、死してなお幕府に仕えることを誓う者の証だった。