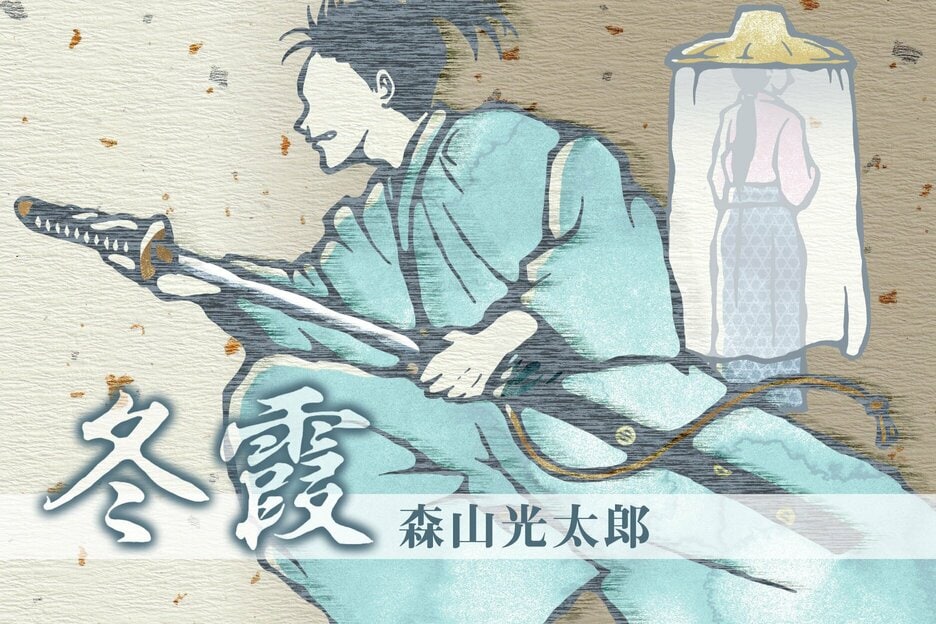見事な漆喰の白壁が、四方を囲んでいる。
元は公家の邸宅だったものを改修したのだろう。導かれた三条坊門第は、見事な寝殿造の屋敷を持ちながらも、堅牢な櫓門を備え、短い幅ではあるが堀を備えている。華美を嫌い、ひたすら理を追い求めると言われる主の性を表して余りあった。
警衛する十人ばかりの武士の一団が三つ。いずれも若い武士だが、恐ろしく腕が立つことは伝わってきた。南朝を圧倒し、足利の天下となった京で、いったい何をそれほどに警戒しているのか。
「新熊野様」
先導する直貞が、緊張した面持ちで主殿へと手を突き出した。
「三条殿がお待ちです」
高欄のある切目縁がゆったりと突き出し、開け放たれた几帳の内側には、畳が敷き詰められている。取り換えられたばかりなのだろう。藺草の匂いが、京のしっとりとした夏の風に混じっていた。
二十枚以上の畳が敷かれた会所の中央。深緑の大紋を身につけた面長の武士が一人、座禅を組んでいた。折烏帽子は、微かの揺らぎもない。歳のころは四十前後と聞いていたが、瞑目する目尻の深い皺は、男をより老年に見せる。
切目縁に昇った新熊野の足音に、男が目を開いた。
男の双眸に、釘付けになった。思わず身構えるほどの光があった。
「信濃の御老公と、刀を交えたらしいな」
苦笑とともに呟いた男が、足利直義だと確信した。向かい合うだけで、伝わるものがある。男の纏う空気は、黒く重い。男が立ち上がった。
「足利左兵衛督直義である」
告げた直義の視線が、新熊野の腰の刀に向けられた。
「新熊野。お主の、叔父ということになるのかな」
どの口が、それを言うのだと思った。
尊氏に、新熊野を子と認めるべきではないと進言したのは、お前であろう。落ち着け。心の中でそう呟いた。もしも、この男が父を害するような企みをしているのであれば、それを言葉にさせるまでは耐えるべきだった。
「血を、認められてはおりませんが」
「一目見ればわかる。目は大樹と似ている。口元と耳は、越前殿だな」
さりげなく直義が発した名は、死んだ母の名だった。心臓の音が跳ねるのを感じた。直義の視線が、新熊野の手元に向けられた。いつの間にか、拳を握っていた。
「誰もが見惚れるほどの人であった。器量もよく、機知に富んでおった。そう言えば、新田の小太郎も見初めていたな」
握った拳が、音を立てた。知っていたのか。
「鎌倉陥落の折、母は殺されました」
直義の目には、何の感情も映らず、じっとこちらを見ている。何を見定めようとしているのか。己の優位を信じて疑わない視線に苛立った時、直義が首を左右に振った。
「大樹が鎌倉の幕府を裏切ったゆえ、越前殿は死んだ。それは動かしようのないことだ。新熊野よ。お主はそれを非難するか」
「母が殺された。その仇を憎まぬ子がおりましょうや」
「ふむ。されど、お主の瞳の中に、大樹への憎しみはないように見える」
「戦場の死は理不尽。多くが理不尽に殺される様をこの目で見てきました。鎌倉の小路を逃げるさなか、宙に舞った童の首は、いまだ瞼の裏に焼き付いております。その後も長く、南朝と北朝の戦乱に焼かれ死んだ民を、数えきれないほど見ました」
直義が小さく頷いたのを見て、新熊野は続けた。
「大樹によって勝利した北朝の治天は、泰平の兆しを見せています。なればこそ、民は笑みを取り戻し、鎌倉から京への途次も、賊に遭うことはありませんでした。戦場の理不尽を、理に変えた。それを知っているがゆえ、戦を恨めど、大樹への憎しみはありませぬ」
畳の上に静寂が広がり、風の音だけが聞こえた。
直義が目を閉じ、暫くして開いた。
「新熊野。お主が京へ辿り着いた二年前、大樹はお主を拒絶した」
煽るような言葉に、苛立ちがはっきりと怒りへ変わった。父を唆したのは、お前だろう。
まだ、若かった。父に会える。母を失ってから十年、孤児として寺の者たちから蔑まれてきた新熊野にとって、血を分けた父が生きているということは、いつの頃からか心の支えになっていた。傷つけられた自分を、ようやく見つけてくれるのだと心は躍っていた。
歓迎されないことなど分かりきったことだった。尊氏には、名門赤橋氏の娘である正室との間に生まれた義詮がいた。新熊野にとっては異母弟にあたる。常勝の名将高師直が後見し、次代の将軍と目されていた。比べて、新熊野の母は、出自すら定かではない。尊氏にしてみれば、自身の子と確かめる術もないのだ。もしかすると、尊氏は自分を見て笑ってくれないかもしれない。何度となく考え、不安に苛まれてきたことだ。
それでも、一目会えば、気づいてもらえると信じていた。傷ついた自分の姿を見てくれれば、己が子だと、抱きしめてもらえると。
激しい夕立の中だった。遠く、二条万里小路の屋敷を眺め、鎌倉を出立する時に抱いた淡い期待は、音を立てて砕けた。会うことすら、許されなかった。征夷大将軍である父の身分を思えば、当たり前のことだと、何度も言い聞かせた。
まだ、傷が足りないのだ。耐えてきた十余年の想いが溢れ、鴨川のほとりで、人目をはばからずに泣いた。
心を落ち着かせるように、息を吐きだした。
敵かもしれぬこの男の屋敷までついてきたのは、直義の心のうちにある企みを見定めるためだ。それが、父の助けになるのだと自分に言い聞かせてきた。
「三条殿が、私を拒絶するように進言されたわけも、理解しています」
「ほう」
面白がるように、直義が口元を歪めた。
「武士としての位を極め、治世に臨まねばならぬ時に現れた自らの子と名乗る男。邪な心を持つ者がいれば、治世を乱すために用いようとしましょう」
義詮が次代の将軍となれば、高師直の権勢は高まる。だが、気性の荒い高師直を好まぬ者は多く、彼らが新熊野を擁立しようと考えれば、幕府は二分されるだろう。直義がそう考えたとしても、不可思議ではなかった。
だが、だからこそ高師直や義詮の母赤橋登子が新熊野の処断を求める中、それに反対した目の前の男の思惑が気になった。なぜ、この男は新熊野を拒絶しながら、殺そうとしなかったのか。あまつさえ、今川直貞などを送り、高一族の刺客から、新熊野を護るような真似をしてきた。
数年来、直義と尊氏の仲は、全土の風聞になるほど悪い。武を司る兄と、政を司る弟。後醍醐帝亡き後、南朝の采配を一手に握っている北畠親房の耳にも届いており、新たな戦を始めることを命じたともいう。
顔を伏せ、畳の目を見つめた。
「拒絶され、呆然自失となっていた私のもとに、直貞が現れました。しばらくの間、大徳寺で雌伏せよと」
「大徳寺での扱いは聞いておる。足利の血を騙る愚か者として、折檻を受けていたようだな。私を恨んだか?」
「いえ」
首を左右に振り、あからさまに笑った。
「幕府と折り合いの悪い大徳寺でなければ、私は何某かの放った刺客によって命を失っていたでしょう。ゆえに、三条殿を恨むなど」
「それが本心かどうかは分からぬが」
直義が目を細め、分かるか分からないほどに笑った。
「ようやく、師直もそれどころではなくなったからのう。私は根っからの臆病者。備えすぎるほどに備えると、昔から兄にもよく言われたものだ」
直義の笑みに、新熊野は背中が寒くなった。この優しげな笑みのまま、直義は親王殺害という前代未聞の決断をしたのだろう。誰にもできぬことを、容易くやってのける。兄弟二人ともにだ。それが、足利の強さでもあるのだろう。
「二手先、三手先では足りぬ。十手、二十手先まで読み、それら全てに備えることで、私は兄を支えてくることができたと思っておる。遠祖よりの悲願である征夷大将軍の位に、兄を押し上げることができた」
「私を生かしたのも、使いどころがあったからだと?」
「それもある。が」
直義が、はっきりと分かる笑みを浮かべた。それまで塑像のようだった直義に、いきなり血が通ったように感じた。
「甥は殺せぬ。それに、兄に子殺しをさせたくもなかった」
目の前の笑みには屈託がない。だが、どこまでが本意なのか見えなかった。笑みの中にある瞳は、沼のように感情の揺らぎがない。次の瞬間、この男の号令で衛士が雪崩れ込んできたとしても、不思議とは思わなかった。
戸惑っていると、直義がゆっくりと立ち上がった。
「ついてまいれ」
背を向けて歩き出す直義を前に立ち上がれずにいると、直貞が促すように傍で頷いた。連れだって通されたのは、三十畳ほどもある会所。薄茶けた文机が所狭しと並べられ、どの机にもうずたかく書が積まれている。新熊野の目を引いたのは、机の前に座る二十人ほどの武士たちの静けさだった。筆を持ち、一心不乱に書きつけている。現れた直義に気づくそぶりも見せず、直義もそれを気にしていない。
部屋の中に、見えない重さが垂れこめているようにも感じた。
「国を動かす重さだ」
緋扇で顔をあおぎ、直義が笑う。その笑みは、寂しげなものがあった。
「一人消え、二人消え、そしてまた一人増え、二人増えた。人が変わろうとも、国を治める者が為すべきことは変わらぬ。この重さを維持できる者だけが、天下人であることを許される。その証に、我らの成す政の多くにも、先帝の遺勲がある」
後醍醐帝のことだろう。鎌倉幕府を滅ぼした後、後醍醐帝のもとであらゆる者たちが天下泰平に尽力した。決裂し、北朝と南朝に分かれ、血で血を洗う戦を繰り広げた者たちも、もとは肩を並べて同じ方向を見ていたのだ。
「先帝の志した建武の御新政は、あまりに性急。そして誠実さを欠いておった。ゆえに、乱れが大きくなった」
さらに歩き出した直義が沓を履き、石庭に降りた。見事とは到底言えない。手入れもされておらず、無造作に砂利が敷き詰められただけの庭だ。
「人が歩けば、乱れる。それが当然のことだ。新熊野。乱れたものを綺麗に整えようとしても、いずれ乱れる。ゆえに、政とは乱れを大きくさせず、乱れの中に秩序をもたらすことに過ぎぬ」
「乱れぬことは、無理なことだと?」
砂利を踏みしめた直義が、しゃがみ、小石を握った。
「全ての民が、己の想いを殺すような世であれば、それもまた成せようがな」
肩を竦め、そんな世は地獄だなと直義は嗤った。直義が手を叩くと、従者が一枚の紙片を持ってきた。全土の地図だ。初めて見るほど、精緻なものだった。
「乱れの中に秩序を作ろうと、私は全土に寺塔安国寺と利生塔を置くことを決めた」
「鎌倉滅亡より続いた戦乱の鎮魂と聞きました」
「表向きは、そうだ。新熊野。その裏側には何がある」
問いかけてきた直義の目は、強く鋭い。測るような視線は、やはり不快だった。
「幕府の力を示すこと。安国寺の創建は、六十六に分かれた諸国に、足利の意思が通じる地ができたも同然です。ただ、同時に、官吏を育てようともしたのでしょう」
直義の目が細くなった。
「先ほど、三条殿が申された。人が変わっても為すべきことは変わらぬと。先帝の失敗は、その政ではなく、それを捌ける官吏が不足していたことです」
その不足が、後醍醐帝の裁きを停滞させ、全土の武士が帝を見捨て、足利尊氏を推戴することに繋がった。後醍醐帝の政の遅さに、苛立つ武士を、鎌倉でも多く見た。
「ゆえに、寺塔創建を利用し、実務に長けた者を育てようとされた。だが、それが三条殿を苦しめてもいる」
「詳しく」
「大樹が鎌倉を滅ぼし、南北朝の動乱を制しつつあるのは、名もなき新たな武士の台頭ゆえです。それまでの国を治めていた権門ではなく、乱世で成り上がろうと命を掛けた枝葉の武士が味方をすればこそ、大樹は勝ち続けてきた。されど、世は治世に向かいつつあります。今、世に役立つのは、武に強い者ではなく、文を治めた者です。ゆえに、政を束ねる三条殿は、戦に功のあった者を重用できない」
言葉を区切った。戦で功を成せば、立身できると夢見た者たちは、事実、直義の政から遠ざけられている。それに不満を持った者たちが、尊氏やその腹心である高師直のもとに集まり、直義との対立を深くしている。
それ以上言葉を続けるか迷った時、直義が頷いた。
「言ってみよ」
なぜか、その言葉に温かさを感じた。それが呼び水となったのか、言葉が流れ出した。
「第二の先帝となることを、三条殿は恐れているのでは?」
直貞の慌てたような表情を、直義が緋扇で抑えた。
直後、直義が愉快そうに声をあげて笑った。
「兄が、私を討つと?」
「人の世は輪廻。幾たびも繰り返されてきたことです。私を庇護下に置こうとしたのも、大樹の血を継ぐ私が三条殿の麾下にあれば、その時役立つと思われたからではありませぬか?」
万が一、直義と尊氏の戦となれば、勝敗は火を見るよりも明らかだった。
「大樹の麾下には、高師直がいます。常勝の名将。幕府に仕える数多の武士の中でも、その采配は頭抜けている。彼が味方に付いたとなれば、全土の武士は大樹に頭を垂れましょう」
尊氏を頂点として天下を治める幕府としては、きわめて歪な力関係。だが、高一族は戦上手が揃っており、彼らを面白く思わぬ者たちも、認めることだった。師直と対立した時、新熊野が直義の麾下にあれば、師直に同調する武士の動きを鈍らせられるかもしれない。
「頭は良く回るようだな」
にやりとした直義が、認めるように頷いた。
「疑い深いところは、大樹とは似ておらぬ。むしろ、私と似ている」
似ていると言われても、嬉しくはないと思った。
「そうでしょうか」
「若き日の私を見ているようだ。いつも、兄には疑いすぎだと叱られたものだ。だが、悪くないぞ、新熊野。人の悪意は、時に想像を絶するほどの昏さを持つ。時に、善意も」
ただ、と区切り直義が息を吐いた。
「いくつか間違っておる。兄者は私を信じておられる。私もまた兄を信じている。それにな、第二の先帝となり死ぬことが、兄者の助けとなるならば、私は進んでその道を行くであろう。なにより、師直はかけがえのない友だ」
鳶色の強い瞳は、嘘を言っているようには見えない。だが、本心とも思えなかった。どこか、浮世離れしている。己の命すら、駒の一つと思っているような気配があった。
「新熊野。私がお主を庇護したのは、大樹の治世を真のものにするためだ」
「畏れながら、真のものとは?」
「衰えたとはいえ、いまだ吉野の南朝の力は侮りがたい。先帝の遺児たちが全土に散らばり、各地で力を蓄えている。揃いも揃って傑物。見事なものよ」
「東山道の信濃宮、西海道の征西将軍宮ですね」
後醍醐帝の皇子である宗良親王と懐良親王。信濃と肥後(現在の熊本県)を本貫として、勢力を伸ばしつつある。直義が頷いた。
「大樹が天下人となったとはいえ、王家の血は、揺るがしがたいものがある。皇子という旗があるだけで、その力は強大なものになっていく」
直義の政に不満を持つ者が、尊氏のもとに集まるならばいい。だが、彼らが直義憎さのあまり南朝に帰参すれば、天下は戦乱へと揺り戻される。
「武士は、血を貴ぶ。血には、血なのだ」
まっすぐに見つめる直義の瞳に、新熊野はこの男が自分を庇護した理由の一つが分かった。後醍醐帝の血に、真っ向から対峙できるものは、足利の血しかない。だが、尊氏の子は義詮の他はまだ幼く、その義詮も鎌倉の支配で手一杯だ。直義に子はいない。
新熊野が察したことに満足したのか、直義が直貞に合図した。
直貞が開いた書には、四文字の名が黒々と記されていた。
足利直冬――
「お主の名乗りだ。私が、親となる」
「それは」
慌てる新熊野を、直義がじっと見ていた。
「否、とは言うな。直冬」
喉元に刀を突き付けられている。そう感じた。
「大樹のためにも、お主の名がいる」
父は、それを許したのか。問おうとした新熊野は、だが父という言葉を口に出せず、息を呑み込んだ。自分でも驚くほど、鼓動が速くなった。地面を見つめ、新熊野は呼吸を整えた。
直義の養子となれば、二人の対立に巻き込まれる。父と離れることになる。心に痛みを感じた時、同時に黒い獣がじわりと浮き出してきた。父と対立する直義の懐にあって、父のために働く。周りは敵しかいない。
傷だらけになるであろう己の姿に、黒い獣が笑った。
「吉野が近く大兵を興す。東西に向かう将が、足利には足りぬのだ」
言葉を出せないでいると、直義がふっと肩の力を抜いた。
「今のお主らは、どこへ行こうか分からぬ根無し草にすぎぬ」
お主らとは誰を差しているのか。口を開こうとした新熊野を、直義が首を左右に振って抑えた。
「母を殺した世を恨むなとは言わぬ。だが、父の創り上げた世を愛してほしい」
それにな、と直義が微笑んだ。その横顔には、寂しげなものがある。
「兄と弟は、助けあうべきであろう」
そう告げた直義は、話は終わったとばかりに歩き出し、屋敷の中に消えた。
「俺に、兵を率いさせるつもりか」
「三条殿はそうお考えでしょう」
こともなげに言う直貞が、目の前に跪いた。
「ただ、それだけでもありませぬ。三条殿の頭の中は余人では覗けぬほど複雑。されど、誰よりも人らしい方です」
「人を駒のように見る瞳からは、そうは思えんが」
「それが、三条殿の生まれ持った御役目ゆえ」
立ち上がった直貞が、膝の砂を払った。
「殿も、いずれ、分かりましょう」
「殿だと?」
「今より、私は殿の麾下です。仁科の爺様も、殿といれば退屈せずに済みそうだと申しておりました」
直義は、自分を使って何かを企んでいることは間違いない。幕府内部の対立、そして南朝との戦。今川直貞の役目は、監視か、用済みになった時の刺客か。
「殿というならば、その白粉は落とせ」
吐き捨てた直冬に、直貞が舌打ちした。
直義が自分を利用しようというならば、自分もまた彼らを利用するまでだと思った。父の助けとなるためには、力がいる。武士としての力ではない。将としての力だ。直義が手を出せないほどの軍を創り出す。
空を見上げる新熊野の傍に、直義の従者と思しき男が傅いた。手には、黒の直垂が捧げられている。上衣には、染め抜かれた二つ引きの大紋。足利家の家紋だ。
大徳寺で出会った女が、脳裏に浮かんだ。南朝の血を引く者ということは、直貞から聞いていた。南朝の血を引きながらも、南朝の朝廷から疎まれ、孤独に世を旅している。何を成そうとしているのか。なぜ、出会ったのか。民の祈りとは、かけ離れた存在のように思えた。
西の空、そびえたつ純白の入道雲は、今にも崩れ落ちそうに見えた。