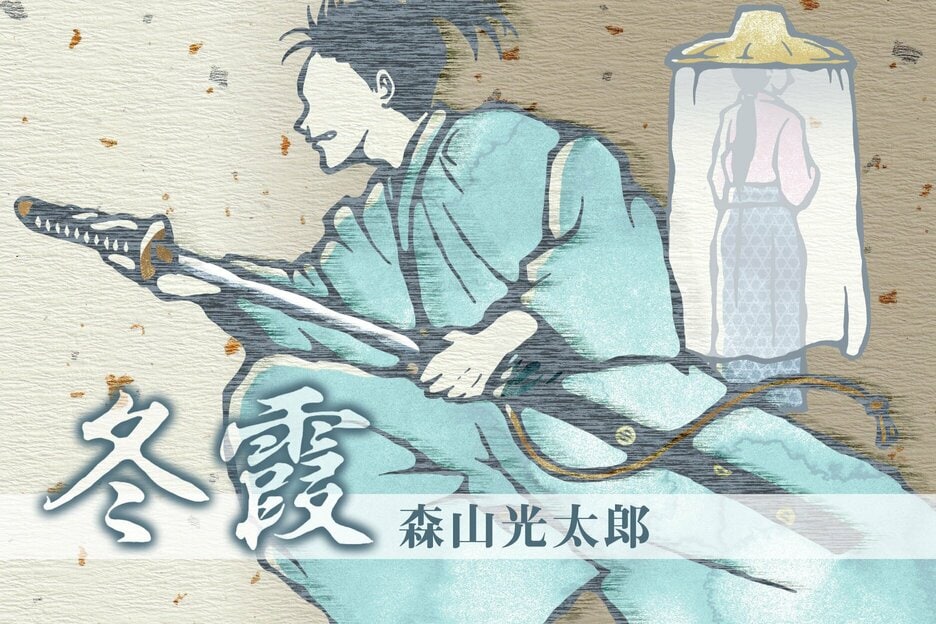六 師直
貞和三年(西暦一三四七)十二月──
「あ痛たた」
右ひざの擦り傷の痛みに顔をしかめ、高師直は石清水八幡宮の石段を一段飛ばしで駆け上っていった。馬に引きずられたことによる擦り傷は、全身に広がっている。全身が痛いのだが、込み上げてくる安心感のせいで身体は軽かった。
戦に出ようとする尊氏を止めることに、五日間の時を要してしまった。それでも、時を無駄にしたという思いよりも、武士の王を戦場に立たせなくて済むという安堵の方が高師直の中では強かった。
「殿は、楠木正行に大敵の姿を見てしまったのであろうな」
細川顕氏に続いて、山名時氏までもが大敗を喫した。
その報せを屋敷で受けたのは、十日前の日の出の頃だった。身支度を整えて屋敷を出ようとした師直は、門の方から聞こえてきた喧騒に、嫌な予感がした。慌てて裸足のまま門へ向かうと、やはりそこには鎧を着た尊氏が、颯爽と騎乗していた。
師直を見つけた尊氏は、満面の笑みを浮かべ、行くぞと呟き駆け出そうとした。止めることに必死だった。尊氏の鞍にしがみつき、十間(約十八メートル)ほど引きずられもした。
全身の擦り傷は、その時にできたものだ。
もしも、自分が負ければ、殿の出府を。そう叫んだ師直に、尊氏はようやく馬を止めた。
『いかに、戦う』
馬上から降ってきた尊氏の言葉に、師直は正行との戦で想定しうる限りのことを話した。正行との戦だけではなく、西国と東国の話まで及び、三日三晩経った頃、ようやく尊氏は残念そうな顔をして、師直に任せると呟いた。
「人生、思い通りにはいかぬものよなあ」
まだまだ若いものには負けぬと思いながらも、歳とともに傷の治りが遅くなってきている。こみ上げる嘆息を無理やり呑み込み、師直は見え始めた真っ赤な楼門に手をかざし、足に力を込めた。
戦が始まる前は、細川、山名軍も苦戦はすれど、敗れるなどとは微塵も思っていなかった。だからこそ、黒草衆を率いる一族の南宗継を呼び寄せ、南朝方の残党による奇襲を装って直冬を殺すつもりだったのだ。だが、直冬を戦場に出すような余裕は、もはや無くなっていた。
もし戦場に送り出した直冬が負ければ、全土に広がるのは足利一族の敗北となる。直冬を排除する前に、幕府そのものが滅びかねなかった。事実、すでに日本全土で、南朝方に寝返る大名が出始めている。北朝が滅びるのではないかと公卿たちは怯えきっており、京の民の中にも逃げ出す者がいた。
民は、北朝方が敗れることを恐れている。その気持ちもよく分かる。十二年前、南北朝の戦で京は焼け野原になった。洛中から焼け出された民は、食うものも着るものもなく、日に日に痩せ細り、多くの死人が出たのだ。放置された亡骸で、街には腐臭が漂っていた。
だが、師直が恐れることは、それ以上に、正行の躍進の報せを聞いて笑った尊氏を戦場に立たせてしまうことだった。戦場に立った尊氏の声は、武士の心に大きな火をつける魔性のものに近い。味方だけではなく、敵の心すら揺さぶり、気づけば心の底から戦を望むようになるのだ。
自分よりも強大な敵に勝ち続け、幕府を作り上げた尊氏が、今なお強大な敵を求めていることには師直も気づいている。だが、平時に戻ろうとしている今、武士に火をつける者は、戦場に立つべきではなかった。
男山の頂上にある石清水八幡宮に参詣した師直は、黄色や黒、白といった色とりどりの旗指物が風にたなびく八幡の平野を、石段に腰かけて見下ろした。燦燦と降る陽光が、全軍を包み込んでいる。
「壮観だな……」
総勢で二万の軍勢だ。
軍勢の催促状は、直義によって山陽道、山陰道、東山道、東海道に広く出されている。直義は、細川軍が敗れた時点で山名軍の敗北も見越して動いていたらしい。
僅か一月で、これほどの大軍を上洛させるため、直義はかなり無理をしたようだった。各地の守護に、公家や寺社の荘園から兵粮を徴収することを許し、朝廷との折衝も一手に取り仕切っていた。
「あくどいと言うのか、強かと言うのか」
南朝方の勢いを逆手にとって、公家や寺社を弱体化させる一手は、まさに鬼謀だった。
師直の一族はもとより、安芸国(現在の広島県)守護の武田信武、近江国守護の佐々木道誉、駿河国(現在の静岡県)守護の今川範国、下総国(現在の千葉県)守護の千葉貞胤らまで参陣している。尊氏を支えてきた大名たちが、これほど一堂に会したのは、南朝の英雄北畠顕家と存亡をかけた十年前の決戦以来だろう。
本陣まで戻った時、南宗継が幔幕を潜って入ってきた。鬚は短く刈り揃えられ、茶色の直垂は皺ひとつない。黒草衆の忍びを統率する者の几帳面さが滲んでいた。
「若様がお戻りになられたのが見えましたので」
宗継の目立つ頬傷は、戦の空気を強く感じさせ、戦場では気持ちを落ち着かせてくれる。
「楠木の動きは分かったか?」
「先ほど、河内国に放っていた黒草衆の二名が戻りました。どうやら、楠木は和泉に軍勢を向けたようでございますな」
「和泉には、淡輪一族がいたな」
「御意。若様との決戦の前に、背後を衝く恐れのある淡輪殿を討とうというのでしょうな」
「七日ほど踏ん張れと伝えよ。その後は、城を捨てて逃げよと」
鎌倉以来の名族であり、南北朝の戦でも一貫して北朝方として戦ってきた一族だった。野戦は並だが、守りの戦には長けている。
「宗継、直冬に張り付かせている黒草衆は、全て呼び戻せ」
「直冬の監視はよいので?」
「今はいらぬ。それよりも、木津へは常に戦況を報せるようにしておくがよい。大樹に認めてもらおうと、戦いたくてうずうずしているであろうからな」
木津にいる直冬の軍の動きは掴んでいた。わざと、新兵の調練を遅れさせているのは、直冬なりに楠木正行を謀ろうとしているからだろう。小賢しいと思いながらも、無策のまま正行と戦い敗れていった細川や山名よりは好ましかった。
僅か二百騎でしかないが、直冬は鴉軍という精強な騎馬隊を持っている。直冬の若さが、初陣で戦果を挙げ続ける正行を無視できるとは思わなかった。使えるものは、いずれ敵になる者であろうとも全てを使うべきだ。
そう都合よくいくとは思っていないが、乱戦の中で直冬が死ぬことも十分にある。
にたりと笑い、師直は頭の中に河内国の地勢を思い浮かべた。
「河内の飯盛山に五十名で拠点を作ってもらいたい」
「飯盛山でございますか」
考え込むようにした宗継が、迷いを振り切ったように頷いた。息を吐きだし、師直はずっと考えてきたことを口にした。
「戦場は、四條畷だ。この戦で、楠木一族を根絶やしにするぞ」
「血を、絶やしますか」
「うむ。細川顕氏、山名時氏の敗戦で、ようやく分かった。あの一族の血は、太平の世にはいらぬ」
楠木正行が、良い戦いをするであろうことは、その血筋を考えてみても分かっていた。だが、六倍の兵力を持っていた顕氏、時氏を完膚なきまでに叩きのめしたことは、正行がいかに戦巧者だとしても説明できないものだった。
「確かに楠木一族は戦巧者の集まりだ。その点だけ見れば、我ら高一族にも通ずるところがある。だがな、宗継。正行のあの強さは、楠木の背負った史があるからこそだ」
「正行の父楠木正成から始まった、御伽草子のような勝利の数々ですな」
「そうだな。源平の血も引かず、河内の悪党として突如、後醍醐帝に与した楠木正成は、時に二十倍、三十倍の敵と対峙して勝利し続けてきた。その結末が、鎌倉幕府の滅びだ。倅である正行もまた、寡兵でもって幕府軍に圧勝してみせた」
「楠木という名が、勝利を表す旗になりつつあると?」
勝利を表す旗、という言葉に、師直は背筋が寒くなるような気がした。
「正行には、正時、虎夜刃丸という弟が二人いるという。その二人も、必ず討ち取る」
「黒草衆の報せでは、末の弟は吉野で後村上帝を守っているようですが」
覚悟は、決めていた。後の世、帝を討った咎人と罵られることもあるだろうが、この戦で、楠木一族もろとも、南朝の帝を弑す。武士の王に再び刀を取らせぬためには、それがこの戦で果たすべきことだった。
「この戦は、吉野の宮城を落とすまで帰ってこられぬと思っておいてくれ」
師直の覚悟を受け取ったのだろう。宗継が目を細め、頷いた。
八幡を出陣し、河内国に踏み入ったのは、年が明けた二日だった。
明け方から駆けに駆け、四里(約十六キロメートル)を二刻あまりで進むと、師直は深野池と飯盛山に挟まれた隘路に陣を敷いた。四条畷のすぐ南、野崎と呼ばれている地だった。
息を切らして膝に手をつく兵たちの足元を見ると、一様に泥にまみれていた。
黄金色の葦が一面に広がっており、歩くだけでも難渋する。地面から這い上がる風は、水の冷たさを帯びているのか、芯から身体を凍えさせるようだった。昼間、太陽の光は燦燦と降り注いでいるが、明け方になれば靄に包まれるかもしれない。この地で奇襲を受ければ、引くことも進むこともできずに大混乱に陥るだろう。
大軍を率いる将が、戦場に選ぶべき地では、決してなかった。
左手には、その昔、神武帝と長髄彦が天下を賭けて争ったとされる生駒山に続く飯盛山がそびえている。深い木々に覆われているはずだが、この二日ほどで降った雪で、白く染まっていた。右手に広がる波ひとつない深野池は、黒く静かだ。
「どうにもこうにも、大軍を動かしようがないな」
想像した通りの地形に、師直はにやりとした。
正面から、葦を踏みしだくようにして、鎧姿の宗継が現れた。
「若様、この地を避けるようにと、諸将から悲鳴のような伝令が届いておりますが」
傍にいることを命じた宗継の手には、味噌で漬けたのであろうしなびた大根が二本、握られている。一本を受け取ると、答える前に大きく噛みちぎった。やはり、味噌だったのだろう。甘みのある辛さが口の中に広がった。
「甘えは許さんと伝えておけ。これしきの死地に踏み込めぬがゆえ、負けるのだ」
戦にかけて、誰の言葉も聞くつもりは無かった。
自分ほど戦い抜き、自分ほど勝ってきた者はいない。
ふふんと笑うと、高師直は全身の血が騒いでいるのに気づいた。北畠顕家と雌雄を決した戦以来、久々の戦場だった。この十年ほどは、京で北朝方の全体の戦略を練り、戦そのものは幕府麾下の武士に任せてきた。
殺し合いを前に緊張した兵たちの気配と、地上の勝者を見極めようとする傲慢な天の気配が入り混じり、独特の匂いが戦場を包み込む。鼻をひくつかせると、ここが戦場なのだと思えた。その予感が外れたことは、かつて無い。
「ふむ。やはり、儂は戦場こそが住処なのだろうな。仁科の御老公を莫迦にできぬ」
「仁科殿は血が好きなだけでございましょう。戦場さえあれば、あのご老人は満足しますからな。若様のそれは、なにか大きなもの。例えば天下がかかったような戦場でこそ、満足される類のものでございます」
やれやれというように首を振り、宗継が苦笑した。
「面倒そうな顔をするな、宗継」
「してはおりませぬよ。若様の方こそ、相手が強敵であればあるほど、今みたいな顔をされます」
「いかなる顔をしているというのだ」
「気づいておられませんのか。八幡を出陣した時より、ずっと笑っておられますぞ」
ゆっくりと、頬に手を当てた。
「笑っておるか」
「ええ、しかと」
尊氏を戦場に出さぬよう気を砕いてきた自分が笑うべきではないとも思うが、立場が違うと思いなおした。自分は、尊氏の下で戦に生きて、戦に死ぬだけの刀であればいいのだ。旗になることは決してない。
そう自分に言いきかせ、落ち始めた太陽に目を細めた。
「さて、正行は、このあからさまな誘いに踏み入ってくる度胸はあるかのう」
四条畷は、小勢で大軍を迎え撃つにはこれ以上ない地だった。
自分が南朝軍を率いる将であれば、北朝方の大軍をなんとかこの地に誘い込むことに腐心する。幕府の驍将を破り続けている正行であれば、この地が己に利することを分かっているはずだ。
だからこそ、いま、正行はまさに迷っているだろう。
なぜ師直が自ら死地に乗り込んできたのかと。自分をおびき寄せるための罠ではないかと疑っているはずだ。
「若様は、来ると思っておられるのでしょう」
宗継が竹筒の水を渡してきた。ぐびりと、喉が鳴った。
「まあな。正行に、まことに旗としての資質があるのであれば、来るであろうな」
もしも敵が足利尊氏であれば、罠と分かっている地にも飛び込んでくる。そして、圧倒的な不利を覆して大勝するはずだ。己の敵になりうる。尊氏がそう判断した男であれば、必ず踏み込んでくると思った。
強敵との戦いは、武士として師直の望むことでもあった。愉しいと、心が思ってしまう。
ただ、それでも、正行は尊氏ではない。
「宗継。佐々木道誉の陣に行け。今宵、黒草衆を先導として、飯盛山へ埋伏せよと伝えよ」
「ここを戦場とするならば、飯盛山を取った者が勝ちますな。黒草衆に、飯盛山の拠点を作るように命じられた時から、この地を戦場にすることを決められていたのですか?」
「我らは大軍だ。大きな隙を見せてやらねば、正行は釣れぬ」
「正行を戦場におびき寄せるため、若様自身が囮となりますか。さすれば、それがしも備中の兵を率いて飯盛山に?」
「いや」
言葉を区切り、師直は顎の無精鬚を撫でた。
「道誉を飯盛山に埋伏させたのち、お主は黒草衆を率いて、正行の首を狙え」
戦場の誰の目にも見えるところで討ち取ることができればなおいいが、こだわりは捨てようと思っていた。闇討ちのような形だとしても、殺すことができればそれでいい。
軽く頭を下げた宗継が、背を向けて歩き出した。
白い稲妻が曇天を裂くように閃き、直後、天地を揺るがすような轟音が響いた。
「やってくれる」
口の中に唾が溢れるのを感じた。
戦の始まりは、幕府軍の意表を突いていた。
布陣してから三日、兵の緊張が緩んだ。師直がそう感じた時だった。四条畷を照らす夕陽が飯盛山に隠れ、西の曇天があっという間に空を覆うと同時に、南の地平がせり上がったように動いた。現れたのは、五百ほどの小勢だ。
こちらは、一万五千の兵を三千ずつ五段に構えている。
見たこともない長さの棒を構えた五百ほどの兵が、横一文字となって突進してきていた。二間(約三・六メートル)ほどの長さの棒の先には、遠目にも分かる鋭い刃物のようなものがついている。
「……あれは、槍というやつか」
南朝方で新たに整えられた武具の一つとして聞いていたものだ。どれほどのものか。目を凝らした師直は、思わず息を洩らした。ぶつかった瞬間、師直軍の前衛が抵抗することもできずに崩れた。断末魔の叫びが、風に紛れて戦場にこだまする。
「あれでは、こちらの刀は届かぬな」
呟き、師直は左手の山裾に展開している三千の兵を前に出すよう指示した。その間にも、楠木軍五百の槍兵が前に前にと突き進んでくる。
「だが、前に進めば進むほど、お前たちにとっては袋小路となるぞ」
そう呟いた時、楠木兵が一斉に槍を前に向かって投げつけた。
師直兵との間に空隙ができ、その瞬きの間に、楠木兵が抜刀した。敵ながら目を奪われるほど、見事な動きだ。五百の楠木兵が左右に分かれた。その直後、分かれた真ん中から、新手の五百が槍を携えて突進してきた。一段目が破られ、二段目も楠木兵に押し込まれている。
「息をつく間もくれぬのう」
楠木正行という武士が、これまで数倍以上の敵に勝ち続けてきたわけが、ようやく分かった。兵の強さと、将の采配が、高いところで噛み合っている。この七年、正行は吉野の山奥で、ひたすら一人一人の兵の力を練り上げてきたのだろう。その兵の力を、最大限発揮するための戦を、正行は練り上げてきている。
近頃、似た思いを抱いたのを思い出した。足利直冬。鴉軍を率いた若き将を見た時のことだと気づき、師直は苦笑した。若い武士が出てきている。時の流れを感じたような気がした。
「まだ、まだよ」
肩を回し、師直は従者の曳いてきた葦毛の馬に騎乗した。
潰走しかけている一段目の武田信武に、そのまま南に駆け、兵をまとめ直すよう伝令を出した。千葉貞胤率いる二段目の三千に、三段目の三千を後詰に入らせたことで、敵の勢いが鈍った。師直のいる四段目に届くほどの勢いは消えた。
「さて、どうする、正行よ」
儂を、愉しませてみよ。
友に話しかけるような親しみが、言葉に滲んでいると思った。正行の兵は、千から三千ほど。残った兵が、どこかに埋伏しているはずだ。左手の飯盛山に視線を向けた時、すぐ横に黒草衆の忍びがうずくまっていることに気づいた。
「飯盛山に、南朝方の四条隆資が攻め寄せました。数は、およそ千。佐々木殿は、これをいなして敵の後背に進軍。四条勢は、県下野守が引き受けております」
「戦況は?」
「五分にござります」
さすがに歴戦の佐々木道誉は、戦の勘所を心得ている。飯盛山を死守するのではなく、敵を挟撃するための埋伏であることを分かっている動きだ。頷くと、黒草衆の忍びが、葦の茂みの中に消えた。
「さて、正行よ。お主はどこにいる」
呟きは、もはや殺すべき相手への愛しさのようなものだった。
師直軍の前衛を突き崩す千の楠木軍の中に、正行がいないことは確信していた。槍を取り入れた操兵は侮りがたいが、それだけで細川や山名を破れるとは思わない。正面の兵を率いているのは、正行の弟の正時あたりだろう。
戦場を見渡す師直の視界から、空に残っていた残光がゆっくりと消えた。紫の空がじわりと黒く染まり、星が滲み出す。
刹那、左右から喊声が轟き、戦場に衝撃が走った。
師直は、思わず拳を握りしめた。左手の飯盛山から、数百の騎馬武者が、雪崩のような勢いで師直の本陣めがけて突進していた。右手から迫る敵も数百はいる。この暗闇の中、深野池を渡ってきたのだろう。夜戦が得意とは聞いていたが、連携の見事さに鳥肌が立った。
正行もまた、この地が戦場になることを見越して、相当な備えをしてきている。
首の根本が、ひりひりとしてきた。
「良き敵だ!」
叫び、師直は四段目の三千を左右に広げた。そのまま師直は百の騎兵を連れて、五段目の今川範国の陣へ駆けた。儂を、見失うなよ。師直の心の中の呟きが聞こえたかのように、左右の敵は、ぴったりとついてくる。
葦原のせいで、馬の脚が遅い。
すぐ後ろを駆けていた南次郎と土岐周済房の声が聞こえた。御免。ちらりと振り返った師直の目に、左右に分かれて駆けてゆく二人の姿が見えた。敵との距離は、一町(約百八メートル)もない。敵の中に駆け込んだ南次郎が、槍に撥ね上げられるようにして、宙を舞った。
次郎を殺した騎馬武者が、まっすぐと師直を見つめている。
一騎だけ、朱色の鎧に身を包み、その気配は宵闇を晴らすような荒々しさに満ちている。薄い星明りにもかかわらず、朱色の騎馬武者の姿が、やけにはっきりと見えた。
「やはり、儂を狙って来たのう。見事じゃ」
肩越しに師直が呟いた瞬間、騎馬武者が槍の穂先を天に向かって突き上げた。
「楠木河内守正行、参る」
天を震わすほどの大音声に、兵たちが気圧されるのが分かった。
不利な地に踏み込み、圧倒的な勝利を得る武士。尊氏の姿が正行に重なり、師直は身体中の血がかっと熱くなるのを感じた。
すでに第一陣は、態勢を整え反転してきているはずだ。飯盛山を降った佐々木道誉もまた、正行の背後にいる。何より、正行は師直だけを見ていた。討つべき敵の姿だけを見て、その他を見ていない。
左手の飯盛山の木立から、烏が飛び立った。やはり、こちらもまだ若い。すこし道筋を引いてやれば、容易に動く。
「ここは戦場。正行よ。よもや、狡いとは言うまいな」
正行の若い猛々しさが、眩しくも感じた。
「六郎、しばし足止めをしてまいれ」
長く、傍に付き従って来た上山六郎左衛門が笑っていた。
「面白き敵ですのう」
そう答え、反転していく十騎の先頭で、六郎が刀を天に突き上げた。正行の名を呼ぶ大音声が響き、敵が殺到する。六郎が馬上から消えた。その先で、阿修羅のような正行の目が、炯々と光っていた。
今川範国の陣までは、残り三町(約三百二十七メートル)ほど。師直は、逃げる馬脚をわずかに落とした。追いつかれるか否か、ぎりぎりのところだろう。馬蹄の響きが近づいてくる。範国の陣までは、残り一町をきった。ちらりと振り返り、師直は目を細めた。
「残念だ。戦も、もう終わりだ」
黒衣の騎兵が、戦場の端に滲み出していた。
先頭を駆けるのは、足利直冬だ。異様な速さで、まっすぐに正行めがけて駆けている。正行が顔を歪ませるのが分かった。範国の陣に飛び込み、反転した。範国率いる三千の兵が、すばやく師直を包み込む。
咆哮した正行が、馬首を直冬の方へ変えた。
「若僧同士、じゃれ合うのがちょうどよかろう」
笑いながらそう言った時、直冬が、正行と斬り結んだ。