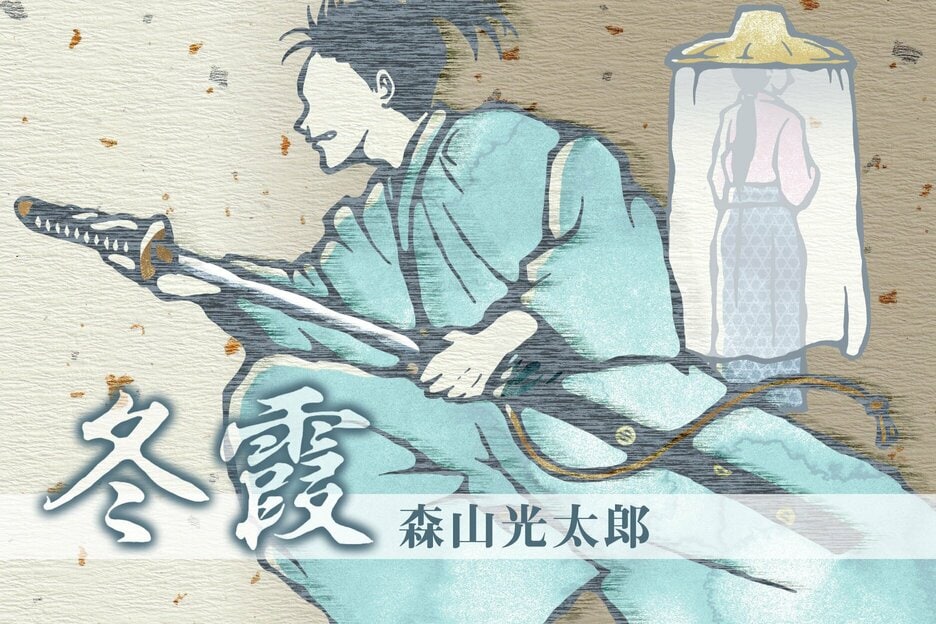山崎から山伝いに摂津国に入った時、嫌な気配を夜の中に感じた。
夜の山では、驚くほど遠くの音が聞こえる。聞こえてきたのは、鳥の声だった。
山道に慣れない者なのだろう。警戒する山鳥の鳴き声が、五町(約五五〇メートル)ほど後ろから、聞こえてきていた。つかず離れずのつもりなのだろう。素早い動きに目ざとい鵯の声は聞こえない。
獲物を狙う猟師であれば、鳥に気取られるような歩き方はしない。十中八九、霞を追ってきた者だろう。
今川直貞が口にした物の怪という言葉が、脳裏によぎった。
あの言葉が直貞の忠告なのだとすれば、追っ手は直冬を敵視する者だろう。浮かぶのは高師直の名だが、そう思わせておいて直貞の手の者かもしれない。直冬の言葉を思い返せば、直貞の仕えていた足利直義もまた、怪しげな動きをしている。
「あの腐れ白粉め」
これまで口にしたことのないような罵倒が、自然と口からこぼれた。
孤児として過ごしてきた直冬は、普通であれば粗野を感じさせそうなものだが、貴公子としてのたたずまいを生まれ持っているのか、不思議と見る者を惹きつける。鴉軍の兵も、信濃の鬼と称された仁科盛宗でさえ、自然と直冬を主として受け入れているのだ。生まれ持っての武士の大将というものなのだろう。
それだけに、直冬の傍に付き従う直貞の毛色は、ことさら異様に見える。
名門である今川家の出自であることは間違いないらしいが、今は一族を追放されている身だった。追放された経緯を調べさせたが、一年近く探ってもこれはと思うものは見つからなかった。出てくるものは、狐に憑かれたのだとか、鴉天狗を見初めて山にこもったなどと言う、人を馬鹿にしたようなものばかりで、噂を流した者の薄ら笑いが透けて見えるようなものだった。おそらくは、直貞自身が流したものなのだろうと思うと、それもまた腹立たしかった。
足利直義が重用していたという一事をとってみても、直貞が見た目とは裏腹に優れた武士ではあるのだろう。認めたくはないがと心の中で呟き、霞は短く息を吐いた。
三日月の明かりが雲に隠れるのを待って、一度、葦屋(現在の芦屋市)の浜辺に出た。
ひと気のない砂浜には、波の音だけが響いている。
もう少し西に行けば、源平合戦における一ノ谷の戦いで平家が源氏に敗れた須磨となる。平家が没落する決め手となった戦場であり、かつて後醍醐帝を支えた楠木正成が討たれたのも、すぐ近くだった。そこから、南朝の衰退も始まったことを思えば、縁起のいい土地とは思えない。
海沿いを行くべきか、山道に戻るべきか。
海沿いを行った方が速いが、六甲山には追っ手を撒く備えがある。
湊川の隠し湊に、肥前国に配置していた戦船を待たせていた。
瀬戸内の沿岸部の刀禰(役人)には吉野の名を使って、銭を撒いている。戦船の航行が止められることはなかった。湊川から河内の楠木正行のもとへ向かうつもりだったが、海沿いを行けば、隠し湊につくまでに追い付かれそうだった。なにより、誰とも分からぬ追っ手に、戦船を見せるわけにはいかなかった。
「一日、遅れることになりますが──」
六甲山で、追っ手を振り切る。
童の頃から、修験者の真似事をして山を歩いてきたのだ。山の中で後れを取るとは思わなかった。運が良ければ、敵の力を見極めることもできるかもしれない。決心してすぐに、六甲山へと駆けた。道なき道を、わざと音を立てるように進んでいく。
中腹まで登った時には、全身が汗だくになっていた。
滝の音が聞こえた。藪をかき分けると、すぐに小さな滝つぼが現れた。月明かりに照らされ、宙に舞う水飛沫が煌めいている。身に着けていた小袖を地面に置き、草鞋をその傍に揃えて脱ぐと、水辺に転がっている一抱えもある岩を、滝つぼの中に放り込んだ。
岩が水に落ちる前に、咄嗟に藪の中に身を滑り込ませた。直後、水柱とともに鈍い破裂音がこだました。
息を殺して待った。
手のひらほどもある蜘蛛が顔を這ったが、身じろぎ一つしなかった。数えた呼吸が百を超えた。不意に、右手から葉の擦れる小さな音が聞こえた。十歩も離れていない。
刹那、霞は前に転がるように藪の中を飛び出した。
飛び上がりざま、懐剣を引き抜き、背後に思いきり振り上げた。暗闇に、火花が飛び散る。その向こうには、覆面の小柄な男の瞳が、炯々と光っていた。聞こえた葉の音は、陽動だったのだろう。男の胴を蹴り上げたが、避けられた。男と距離ができた。互いに、得物の間合いの外だ。
男が身につける潤朱色の肩布は、まるで血を流しているようにも見える。
「高一族の手の者でございますね」
呟きに、男は身じろぎ一つしなかった。楠木正行から、聞いたことがあった。幕府を開いた足利尊氏を、高師直は表と裏の両面で支えてきた。選りすぐられた者は、潤朱色の肩布を許されるという。
「水浴の邪魔をするとは、無粋な方ですね」
刀を向け合う場で、軽口を叩く自分にすこしだけ驚いた。
話に応じるつもりは無いようだった。小刀を後ろ手に構えなおした男が、息をつく間もなく近づいてきた。疾風のような斬撃をさがりながら躱す。もう二歩、さがった時、水辺に脱いでいた草鞋を、蹴り飛ばした。目を見開き、草鞋を斬り上げた男の胸に、霞は懐剣を押し込んだ。骨と骨の隙間。人の身体で、貫ける場所は限られている。
男の目から光が失われた時、いつの間にか止めていた息を吐きだした。懐剣を抜くと、水が溢れ出すような音が響き、男の身体が崩れ落ちた。
川で懐剣を洗うと、霞はすぐに男の亡骸を川から百歩ほどの場所まで引きずり、藪の中に押し込んだ。これで、屍毒が川に流れこむことはないだろう。
男から剥ぎ取った衣服を検めてみたが、何者かを示すものは無い。目立つものといえば、潤朱の肩布くらいのものだった。
二刻(約四時間)、六甲山の中をあてなく進んだが、追っ手の気配は感じなかった。先ほどの男以上の手練れが潜んでいるかもしれないが、東の空がうっすらと明るくなった頃、霞は湊川の上流に隠してあった高瀬舟に乗り込んだ。馬でもなければ、追い付けない。
高瀬舟の中に用意していた舟渡しの装束に着替えると、そのまま流れの中に舟を押し出した。河口までは、およそ二刻。中流まで辿り着いた頃には、土手の上に人影が出ていたが、霞の姿を怪しんでいる者はいなそうだった。
海が見えてきた。
広く青い空の下に、深い蒼の海が広がっている。
河口の船溜まりには、船渡しや漁師たちでにぎわっていた。その端に高瀬舟をつけ、霞は人の中に紛れるように、身をかがめて歩いた。西へさらに一刻進むと、人目を避けるような岩場の陰に、小舟が一艘待っていた。傍には、黒く日焼けし、潮風によってくしゃくしゃとなった黒髪を頭にのせた川尻幸俊が手を振っていた。武士というよりも、海寇(海賊)のようないで立ちだ。肥後国川尻荘の国人であり、西国を回っていた時、楠木の一族が是非にと会うことを勧めてきた武士だった。
独立独歩の気風が強い肥後国人らしく、天下の主が誰であろうと気にしないようで、大陸との交易の話を持ち掛けると、面白いと諸手を挙げて賛同してきた。
近づくと、幸俊が太鼓のように突き出した腹をゆすって笑った。
「京の高倉高辻に購った土地を見た帰りでしたが、まさか戦場に連れていかれるとは思ってもおらなんだ。綴連王の勝気にはまいったものでざいます」
西国を回る時、霞は護良親王の落とし子として綴連を名乗っていた。霞という名も伝えてはいるが、その名を呼ぶ者は少ない。
「京に土地を?」
「天下の主が誰であろうとも、購ってしまえば、土地は残りますからな」
にやりとして、幸俊が小舟を指さした。
「沖に、戦船を連れてきています。行き先は、河内でよろしいですな?」
「ええ。助かります。幕府の兄弟喧嘩は、南朝を平地に誘いだすための罠だと判断しました。楠木殿を止めなければなりませぬ」
「いやはや。綴連王のお考えも分かりますがなあ。罠であろうと、楠木殿が容易く敗けるとも思いませぬ」
「今、楠木殿の集められる兵は多くとも二千程度。吉野の守りを考えれば、動かせるのは千ほどでしょう。幕府は、細川や山名など歴戦の勇将を招集し、一万以上の大兵を集めているのです。敗れずとも、大きな傷をうけます」
幕府との戦を決めた後村上帝もまた歴戦の帝ではあるが、気が急いているように思えた。北朝との戦を始めるならば、西海道の征西将軍宮や、東山道の信濃宮と示し合わせるべきであり、それを結ぶのが、自分が作り上げようとしている西国の水運だと思っていた。散発的な蜂起では、各個撃破され、南朝の衰退を世に知らしめるだけになる。そうなれば、利を得るのは北朝だけだ。
「今、吉野の朝廷を倒れさせるわけにはいきませぬ」
「それは、綴連王の望みのためでございますか?」
幸俊の声には、霞の意志を確かめるような気配がある。今でも、途方もない意志は、変わらないのかと、幸俊の浅黒い顔が問いかけてきている。
己の利に繋がるならば、南朝も北朝も関係ないと思っている男だ。それを示し続けることができるならば、使いやすい。霞は頷いた。
「父を見殺しにした吉野の朝廷も、父を殺した北朝も、私にとっては仇」
だが、今の霞の力だけで、その二つを相手取ることはできない。だからこそ、南朝を強くして、北朝とぶつけるつもりだった。
「まことに、それだけにござりますかな?」
問いかけるような眼差しの幸俊に、霞は肩をすくめた。出会った時からそうだったが、この男は獣の直感のようなものを持っている。観念して、霞は口を開いた。
「正行だけは、死なせたくない」
言葉にして、ゆっくりと息を吐いた。
「唯一、私を守ってくれた親代わりなのです」
幸俊が微笑んだ。
「承知。では、すぐにでも行きましょうぞ。沖までは、それがしの巧みな操船をお目にかけます。小舟ですが、帆を立てられるように作り直しましてな、これが心地よいのでございます」
「追っ手がいるかもしれません」
「ほう、綴連王を追うなど、不遜極まりないものですな。まあ、安心めされい。儂が来たからには、御身に指一本触れさせませぬぞ」
豪快に笑う幸俊が、小舟に乗り込み、櫂を握った。
万事、緻密に物事を進める楠木一族と違い、西国の武士たちはどこか大雑把な気風がある。楽天的とでも言うべきなのか。為せば成る、と本気で信じている者が多い。
苦笑して、霞もまた小舟に乗り込んだ。
和泉国(現在の大阪府)や河内国は、他の国と比べて南朝の勢力が強い土地でもあり、船をつける場所に困ることはない。和泉国の岸和田荘に上陸したのは、八月九日の朝だった。
霞は、幸俊が調達してきた馬に乗り、千早城を目指した。馬であれば、半日の距離。日が沈む頃には、金剛山の麓まで辿り着いていた。
「これは、一足遅かったやもしれませぬな」
月明かりの差す千早城の影を見上げ、幸俊が呟いた。篝火の数は少なく、城内に人がいるようには見えない。山間の猟師を捕まえて聞いてみたが、つい昨日までは、にぎにぎしく兵で溢れていたという。
「神速の名を、父親より受け継いだというわけですか」
正行の父である楠木正成は、かつて神速の用兵で鎌倉幕府の大軍を翻弄し続け、ついには後醍醐帝を勝利に導いた。北朝に高一族ありと言うならば、南朝には楠木一族がいる。南北朝の戦乱は、戦巧者の多い二つの一族の戦であったと言っても過言ではなかった。
千早城の城郭まで登ると、やはり門を守る兵も少なく、城内は空だった。正行麾下で、顔見知りでもある兵が、霞の顔を見つけて近づいてきた。
「殿より、霞様にお渡しせよと」
篝火の近くで、受け取った書状を開いた。
「楠木殿はなんと?」
覗き込むように顔を突き出してきた幸俊の前で、霞は書状を握りしめた。細く、丁寧な文字は、正行の生真面目な性格が滲んでいる。
かえらじと、かねて思へば、梓弓――
そこには、辞世の句にも見える言葉が、記されていた。かねてより、武士として帰らぬ覚悟はしていた。武士としての、正行の矜持のようにも読めるが、無謀な戦を命じた南朝は、もはや帰る場所ではないと言っているようにも見えた。
それでも、正行が最期まで南朝と共にあることを、霞は知っている。
心の底から戦を嫌っていたが、南北の動乱は、いずれかが戦場で滅びねば終わらないというのが、口癖だった。正行の父正成は、南朝に忠誠を尽くし、その死に様は、敵味方に名高く語り継がれている。
その子である正行が選ぶことのできる道は、一つしかなかった。
書状は二枚、続いていた。
「紀伊国(現在の和歌山県)の隅田城を落とし、河内国の幕府方を攻めるようですね」
「隅田城ですか。たしか、岩倉一族や葛原一族が拠る城でしたな」
「吉野と河内を結ぶ道の真ん中にあります」
「退路の確保、でしょうかな」
幸俊に言われずとも分かっているが、頷き、霞は顎に手をあてた。
一度、動き始めれば、正行は決して止まらない。霞のとっての育て親代わりでもあった武士のことは、よく分かっていた。
「川尻殿、西国から動かすことのできる船は、何艘ありますか?」
「戦船となると、兵の調練の終わったものが二艘。兵を運ぶだけであれば、百石(約十五トン)積みの刳船が十艘程度でございましょうかな」
「四百人程度は、運べますね」
「かなり無理をすれば」
万が一、正行が敗れた時、西国まで逃す道がいる。
「肥前、肥後の船を集めてもらえますか?」
「それは構いませぬが、綴連王は?」
「私は石見の益田殿のもとへ向かいます」
「化かされぬよう、お気を付けください」
幸俊の心配そうな顔に、思わず微笑んだ。石見国の益田一族は、古来より己が一族の興隆を見据え、天下が二分した時には双方と手を結んできた強かな一族だ。
霞に接触してきた益田兼見という武士は、次の当主にも目されている男であり、南北朝を天秤にかけている。ただ、日本海のただなかに浮かぶ見島を拠点として、大陸との交易で財を築いているとも言われ、交易の独占を目論む足利家とは折り合いが悪いと噂されている。
「備後国(現在の広島県)の鞆の浦で、落ち合いましょう」
「日取りは?」
「十月の終わりには」
「ふむ。かなりの急行軍ですな」
突き出た腹を一度叩き、幸俊が頷いた。
「お任せを。出立は明日に?」
「いえ、今すぐに行きましょう。海の男が、疲れたなどとは申しますまい」
引きつった笑いを浮かべ、幸俊が首肯した。
「一日の遅れが、取り返しのつかないことになるかもしれません。楠木殿には、書簡を残します」
顔見知りの兵が筆を用意する間に、霞は用意しておいた握り飯を懐から取り出し、幸俊にも渡した。ほおばった幸俊が、顔をしかめた。
「ちと、辛うございますな」
また、加減を間違えたのか。一向に上達せぬ腕に舌打ちして、霞は辛い握り飯を呑み込んだ。