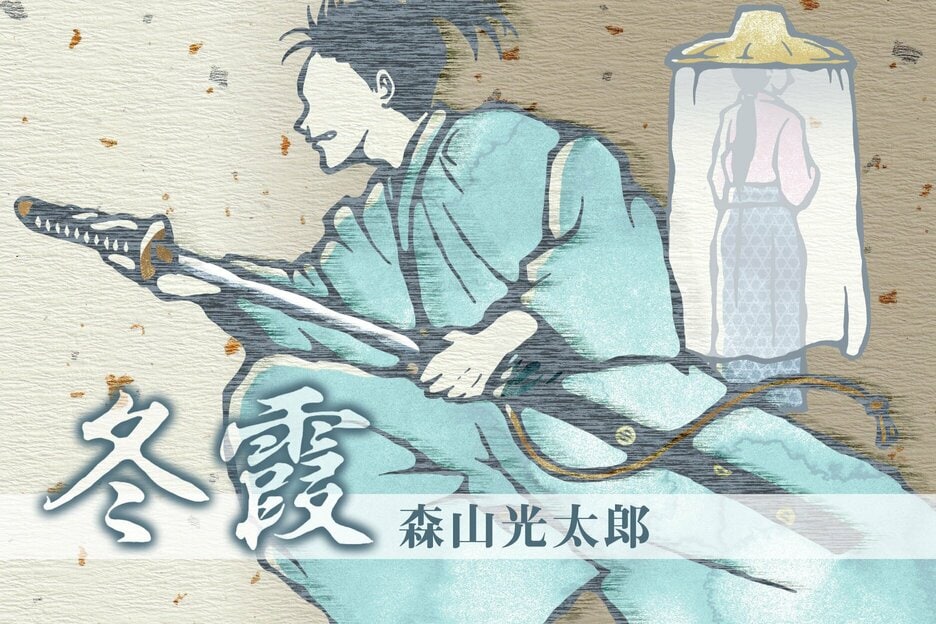四 霞
貞和三年(西暦一三四七)八月──
鴨川の土手を歩く霞は、日差しを避けるように土手に植えられた柿の木陰に入った。季節は秋だが、この数日は暑い日が続いている。柿の枝を見上げると、緑がかった黒色の寒蝉が一匹、じっと張り付いていた。
「京に来て、一年……」
呟いた時、寒蝉がにわかに飛び立った。
北朝の動きを見極めるまでは京を離れないつもりだったが、南朝の動きが慌ただしくなったことを受けて、霞も京を出ることを決めた。
足利兄弟の対立を好機と見た南朝が、ついに戦を始めることを宣言していた。
思慮深く慎重な楠木正行の決断とは到底思えない。
この数年、大きな戦が無かったことで、北朝の軍勢は十分な力を蓄えている。戦ともなれば、南朝の十倍以上の兵を集めるはずだ。吉野の朝廷は、山にこもり過ぎて世情が見えなくなっているとしか思えなかった。都合のいい報せに飛びつき、正行に戦を命じたのだろう。正行の苦渋の表情が目に見えるようだった。
戦を止めることができれば最善。止められなくとも、正行だけは逃す。この先、北朝と戦うためにも、正行を死なせるわけにはいかなかったし、逃がすだけならば、今の自分にもできるはずだった。
京にいた間も、西国の隠し湊を動かし続けてきたことで、動かせる船の数も増えている。
肥前国と石見国で調練していた戦船もようやく形になり、済州島の島民を雇った交易も、高麗との航路をなんとか確保できそうだった。幕府と高麗王朝の目を盗む必要があるため、多くの取引ができるわけではないが、高麗では刀が高値で売れた。引き換えに手に入れた青磁は日本全土で珍重されており、肥前の金蔵には、宋銭が積み上げられ始めている。
透明な青みがかった器というだけで、霞はその価値が分からなかったが、銭になるのであればそれで良かった。
あと二年、時が欲しかった。
それだけの時があれば、今は二艘の戦船も、三十艘ちかくまで増やすことができる。三千の兵を輸送し、正行の戦を助けることもできるはずだ。
袖をまくり上げているが、嫌な汗は流れ続けている。
戦が始まれば、その日のうちに、畿内のあちこちが戦火に包まれるだろう。足利兄弟の不和を狙った蜂起。吉野の朝廷を率いる北畠親房は、回天の好機と思っているようだ。だが、一年間、足利兄弟の動向を見続けてきた霞は、それが北朝の仕掛けた罠でないとは、どうしても言い切れなかった。
ため息を吐き、霞は遠く、南の方角に見え始めた土煙に目を細めた。足利直冬が今日、この場所を通ることは、手下から報せを受けていた。
「鴉の軍、ですか」
遠くの土煙は、直冬が新たに編成した騎兵のものだ。
幕府内の調練では、無類の精強さを見せ、その編成には、義父である足利直義も莫大な私財を投じたと言われている。
直冬こそ、足利兄弟の動きの不可解さの、中心にいる男だった。
後醍醐帝が薨去してから八年、軍を握る尊氏と、政を握る直義の不和が徐々に大きくなっていったことは、誰もが知っている。だが、それが深刻な対立にならなかったのは、尊氏の弟に対する溺愛があったからだ。
幼い頃から、手を取り合ってきた二歳差の兄弟の絆は分かちがたく、かつて尊氏は、直義に降りかかる不幸の全てを自分が引き受けると、神に祈ったこともあるという。
対立しながらも崩れることのなかった兄弟の絆に、誰の目にも見える亀裂が走ったのは、新熊野が現れてからだった。
征夷大将軍となった足利尊氏のもとに、不意に現れた新熊野は、はじめは尊氏に拒絶された。後継者争いを避けるための判断としては妥当であったし、何より新熊野がまことに尊氏の子であるという証もなかった。
尊氏の腹心である高師直が、直冬暗殺に動いたことは、楠木一族の忍びが掴んでいた。それを見れば、足利一族の血を引いていることには間違いないのだろう。だが、師直の暗殺は、直義の配置した護りによって失敗している。
兄が拒絶した直冬を受け入れ、足利一族の対立の芽を作った直義の思惑が、測り切れなかった。南朝を平地に引きずり出そうというだけなのか。直義は、自ら天下人になる思惑を持っているのではないか。もしも、直義が幕府に叛旗を翻すつもりならば、この一年、霞が野放しにされてきたことにも納得できる。
直義勢力の伸長を警戒してか、備中を守っていた高一族の兵が八幡まで進出してきており、調練を繰り返している。黒草衆と呼ばれる忍びも、かなりの数が上洛しているようだった。
童にも分かるような、戦の匂いが京には流れている。
あまりにも、できすぎている。そう思わずにはいられなかった。
薄茶色の土煙が近づいてきていた。
先頭で騎乗するのは、直冬だ。黒の水干を風にたなびかせ、黒く染められた綾藺笠を頭に載せている。見ているこちらまで暑くなりそうないで立ちだった。他の兵も全て同じ格好だが、一騎だけ白い狩衣の男がいる。白粉をつけた男に舌打ちし、ふたたび直冬に目を戻した。
この一年で、いくらか険が取れたからだろうか。京の町娘の間でも、直冬の話がよくのぼる。どこか面白くなく、調子に乗っている顔を見てやろうという意地の悪い思いがあったが、近づいてくるにつれ、じれったさが身を包んだ。
こちらに気づいたのだろう。直冬が手をあげ、にこりと笑った。直冬の合図によって、黒衣の騎馬が右に逸れ、一糸乱れぬ動きで河原へと駆け下っていく。
今川直貞のみを連れて、直冬がゆっくりと近づいてきた。
「久方ぶりだな」
下馬した直冬に、霞も一度会釈した。
この男たちは、霞が南朝に連なる者であることを知っている。だが、やはり敵意を見せはしなかった。取るに足りない存在と思われているのか、それとも何かに使おうと思っているのか。
その両方ではあるのだろうが、その油断が命とりになると、霞は自分に言い聞かせた。
「随分と身なりが小ぎれいになりましたね」
「勘弁してくれ。大徳寺で出会った時は、折檻された直後だったのだ」
「殿よ。折檻されずとも、あの頃の殿の御姿は、見すぼらしきものでございました」
呆れたような言葉を発した直貞の背を、直冬が軽くたたいた。
「やかましい」
微笑む直冬の直垂には、二つ引きの紋がある。足利の家紋。父を、殺した家紋だ。心の臓が締め付けられるように感じたが、表情には出さなかった。
「こんなところで出会ったのは、偶然ではあるまいな」
直冬の言葉に、霞は軽く頷いた。
「京を出る前に、あなたに一言お礼をと思いまして」
「礼?」
「鷹峯では救われました」
河原に下り、各々が馬体を洗う鴉軍に目を向けると、その中に白髪の老人がいた。
直垂の紺色は以前よりも濃く、黒に近い。尋常ではない弓を向けられた記憶がよみがえった。若い兵の中で、その白髪は良く目立つ。仁科盛宗。霞の手下を殺した武士だ。あの時、直冬が現れなければ、霞は盛宗に射殺されていたはずだ。
直冬が肩をすくめた。
「救ったわけではない。ただ、南朝のつまはじき者である亡き英雄、大塔宮の忘れ形見に興味があった」
「ならば、私があなたの前に姿を現したわけも、察しているのでしょうね」
「さあな。今の俺には、分からぬことが多すぎる」
「そうは思えませんが」
「そんなことはない。北朝と南朝の戦が起きそうだ。それは分かる。だが、誰が誰と対立しているのかは、田舎者には難しすぎるな」
直冬が惚けているようには見えない。傍に立つ今川直貞などは、何かを知っていそうだが、口を開くつもりは無さそうだった。短く息を吐いた。
「貴方の養父は、何を狙っているのかを教えてください」
下手に言葉を繕う必要はないように思えた。
この男の養父である足利直義の命で、父は殺された。
どちらかが絶えるまで、殺し合う。
覚悟した己の定めからすれば、いずれこの男とも殺し合うのだろう。だが、今ではない。直冬たちを使って成すべきは、北朝の分断だった。おそらく、この男たちもまた、同じように自分を見ているはずだった。南朝を分断させるための奇貨として、直冬やその養父直義は自分を使うつもりなのだろう。
それまで、互いに手は出さない。おかれた境遇が、どこか敵意を削ぐようだった。
鴉軍に目を細め、霞は額の汗を拭った。
「随分と鍛え上げたようですね」
「かつて読んだ書に出てきた騎馬の軍勢がいる」
「何の話です?」
「六、七十年前、この国を滅ぼさんと攻め寄せた蒙古の話だ。まあ、この国に来たのは高麗の兵であったというが、本来の蒙古騎兵の強さは、何者にも止められぬものだったという」
「蒙古の兵を目指したとでも?」
「ああ。血の滲むような調練を課した。直貞など、涙で白粉が崩れ、見るに堪えなかった」
「もとより見るに堪えない風体でしょう」
「それは、あなた方に風流を解する心が足りぬゆえでございましょうなあ」
直貞の非難の言葉に苦笑し、鴉軍の方へ目を向けた直冬の気配が、柔らかなものになった。
「伝え聞いた話では、大樹も我らを認めてくださったという」
実の父に認められたことを、喜んでいるようだった。その呑気さが哀れにも思えたが、それもまた、霞の気持ちを惹きつけるわけなのだろう。
「京の民の間でも、鴉軍という呼び名とともに話題になっておりました」
「あまり良い名とは思わぬが、名付けは三条殿だ」
尊氏を父と呼ぶことができず、養父である直義のことは三条殿と呼ぶ。そこに直冬なりの了見があるのだろうが、それが直冬の青臭さを際立たせているようにも感じた。
「三条殿が首を縦に振るまで、長かったよ」
直冬が鍛えた兵を、直義は五度にわたって検分し、兵の練度が足りぬと罵倒したという。その度、直冬は兵と共に京から姿を消し、一月ほど経ってから、襤褸をまとったような状態で戻ってきていた。
六度目の検分で、直義は鴉軍という名を授け、そして伏見での調練でのお披露目を許した。
南朝との戦を想定した調練であることは明らかだった。河内国守護の細川顕氏をはじめとして、南朝との戦で活躍した武士が招集されていた。
高師直や佐々木道誉など、尊氏派の有力な大名はおらず、足利兄弟の対立をことさら強調しているようにも見えたが、京の民に紛れて観戦していた霞の受けた衝撃は、足利直冬という武士の強さゆえだった。
千の細川軍が伏見の野に布陣し、向かい合うように、鎧まで黒く染められた鴉軍百騎が並んだ。悠然と構える鴉軍に対して、細川軍の勢いは最初から激しかった。戦巧者の自負がある顕氏にしてみれば、自分の子のような年齢の直冬が、自らの十分の一しか率いていないことに怒りすらあったかもしれない。
鴉軍の退路を断つように顕氏が動いた時、直冬はいきなり疾駆した。
それはまるで、原野に吹き抜けた黒い嵐だった。
細川軍を縦に立ち割り、反転した鴉軍は、何が起きたかも把握できていない敵に無造作に突っ込んだ。三度、鴉軍が細川軍を駆け抜けるまで、一息もなかった。潰走する細川軍の中で、わずかな兵に守られた顕氏を鴉軍が包囲したところで、調練の終了が告げられた。
調練の様子は、次の日には京の話題の中心になっていた。直冬の名を上げさせるため、直義が策を授けたのだと言いまわる者もいたという。
「細川殿を容易く破ったと聞きました」
直冬が拳ほどの石を拾った。角の取れた滑らかな丸い石の中心には、左右に白い筋が入っている。石を見つめる直冬が、不意に力を込めた。
「細川殿の戦を知っていたがゆえに、容易く見えたのだろう。どのように力を籠めれば、罅を入れることができるのか。割れやすい石を、俺は知っている」
差し出した直冬の手には、二つに割れた石が載っている。いらないと首を振ると、微かに落ち込んだような表情を見せ、直冬が土手に投げ捨てた。
「もうじき、吉野との戦になる。細川殿は、手の内を隠していたのかもしれん」
「謙遜なさるお方だとは知りませんでした」
「万人に称賛されたいわけではないさ」
立ち上がった直冬が、お前もそうだろうと言わんばかりに笑った。
「南朝との戦には、俺も出陣することが決まった。大樹の命だ」
直冬が笑みを浮かべ、束の間で申し訳なさそうに引っ込めた。この男は、感情を隠すのが下手だと思った。直冬は、認めてもらいたい人が生きている。そう思うと、どこか身体の芯から、力が抜けるようだった。
「ご無事をお祈りしております」
「あんたの口から、武運と言うわけにはいかないよなあ」
楠木正行を除けば、今の南朝を率いる後村上帝や北畠親房がどうなろうと、知ったことではないとも思う。ただ、北朝を敵とするためには、吉野の朝廷が滅びることは避けたかった。
霞の微妙な思いを察したのか、直冬が小さく頷き、話を変えた。
「鎌倉では、一人も味方はいなかった。その頃と比べれば、仁科の爺様も、鴉軍の兵もいる」
「殿、私の名が、抜けておりますぞ」
直貞の言葉に舌打ちした直冬に、霞は笑いかけた頬を引き締めた。
「仁科殿が弓の名手といえど、背後から飛んでくる矢を防ぐことはできないでしょう」
戦の最中、高師直が直冬暗殺を仕掛けるのではないか。霞の疑念は、直冬にも伝わったのだろう。だが、それにこたえることはなく、直冬は口を結んだ。
「此度の南朝軍を率いる楠木正行は、その父に劣らぬ驍将です」
「ほう、かの御仁は、初陣もまだのはずだが」
「それは貴方もでしょう」
父の代で始まった戦が、その子の代でなお続いている。どちらかが滅び絶えるまで、戦は決して終わらない。かつて寂しげに呟いた楠木正行の言葉が、脳裏に甦った。
「河内に行くのか?」
言葉にした直冬に、霞は頷いた。
「楠木殿は、私の育ての親でありましたから」
「霞殿」
名を呼んだ直冬が、迷うように川面へ目を向けた。
「細川殿は、強いぞ」
直冬の言葉を遮るように、今川直貞がゆっくりと頭を下げた。
「逢引きは、そろそろ終わりです」
霞が睨みつけると、直貞は怯える猿のような真似をして苦笑した。そういえば、伏見の調練でも白い狩衣姿で先陣を切っており、目立つ莫迦がいると嘲笑の的になっていた。
「さような怖いお顔は似合いませぬよ。それよりも、河内への旅は、お気を付け下され。道中、物の怪が出るとも噂されております」
何のことかと聞き返そうとした時には、すでに直貞は背を向け、河原へと歩き出していた。残された直冬と向かい合う格好になった。
なぜ、京を出る前に、敵の前に姿を現そうと思ったのだろうか。涼しげな直冬の顔を見て、霞は自問した。京を出れば、直冬とははっきりと敵になる。その前に、決別しておきたかったのだと自答して、霞は鼓動が速くなるのを感じた。決別するほどの間柄でもないはずだ。
短く息を吐きだした。
「戦場で出会えば、敵でございます」
「そうだな」
目を逸らし、直冬が呟いた。その言葉に寂しさを感じたのは、助けられた恩を返していないからだと思った。借りを作ったままでは、敵として向かい合った時に甘えが出るかもしれない。そう言い聞かせた。
少しだけ迷い、首元に下げた絹の懸守を外した。長寿の祈りを込められた小さな薬師如来像が包まれている。一度、救われた。だから、一度だけ、直冬の命がつながることを祈るために購ったものだ。
「これを」
手渡した懸守を握った直冬が、しばらくそれを握り、ゆっくりと首を左右に振った。
「神仏には頼らないと決めている。いつの世も、神仏は人を助けてくれはしないからな」
直貞だけではなく、この直冬もまた妙なこだわりを持っている。かつて鎌倉や京の寺で虐めぬかれたことを思えば当然かもしれないが、寂しさが表情に出てしまったのだろう。直冬がくすりと笑った。
「気持ちは受け取った。だが、先に薬を貰ったのは俺の方だ」
「あれしきのこと」
「人にやさしくされたのは、久しぶりのことだった。だから、嬉しかった」
直冬が懸守を、霞の方に返した。受け取る時、直冬の手に触れた。そう思った時、不意に直冬に抱きしめられた。遠くから、鴉軍の兵の囃し立てるような叫び声が聞こえた。
声を上げそうになった霞の耳元で、直冬が声を落とした。
「足利直義は、俺を使って幕府を乱そうとしているかもしれぬ」
背筋が、張り詰めた。直冬の腕の力は振りほどけそうにもない。足利直義と呼び捨てにしたのは、この男が直義を敵と思っているのからなのか。
「新たな動乱となれば、悲しむのは民だ。大樹への裏切りを、俺は止めなければならん。その時、手を結べるかもしれない。そう思っている」
囁いた直冬が、すっと離れた。その顔には、強張った微笑みが張り付いている。
悲しげな微笑みだと思った。それを、直冬自身は気づいているのだろうか。
見て見ぬふりをしているのかもしれないが、直冬は薄氷の上に立っている。実の父である足利尊氏からは拒絶され、幕臣の多くは直冬を疎ましく思っている。にもかかわらず、尊氏に認めてもらおうと、庇護者である直義の策謀を暴くことが己の使命だと信じているのだろうか。
想像して、霞は自分の胸に手をあてた。周りは、全て敵。そんな緊張の中で、直冬は生きている。自分と同じだ。だが、生き方が交わることは、決してない。
直冬は、父を殺した者たちの血を引いているのだ。
双子のような生き方を宿命づけられているにもかかわらず、支え合うことは許されない。
心に痛みが走った時、直冬が目を伏せ、身をひるがえした。