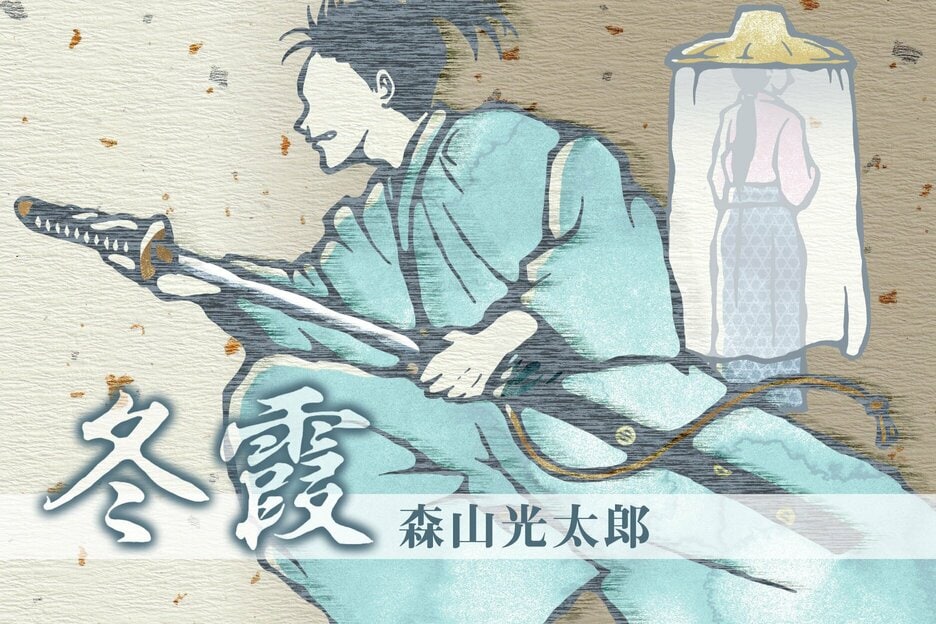第一章 麒麟
一 霞
貞和二年(西暦一三四六)五月――
京の大路を行きかう民の表情は晴れやかだ。もうじき始まる賀茂社の祭を、心待ちにしているのだろう。人の多さは、まっすぐ歩くことも難しい。青海波や七宝繋ぎの文様が染め抜かれた装束も、紅や深黄、浅緑など目が痛くなるような色鮮やかさだった。
鎌倉の幕府が滅びてから十三年。
ようやく治世の兆しを、誰もが感じ始めていた。
十三年前、鎌倉幕府を滅ぼした後醍醐帝の治世は、数年ともたず、再び全土を巻き込む戦乱へと揺り戻された。後醍醐帝を筆頭とする南朝と、足利尊氏を推戴する北朝。後の世に言う南北朝の動乱である。
武士、公家、民、身分の差を問わず、等しく包み込んだ戦乱は、多くの者を殺し尽くしたという。後醍醐帝は、自らの子を全土に遣わし、各地の武士を束ね挙げた。足利尊氏もまた、一族を全土に送り、時には自ら先陣に立ち、戦い抜いた。伯仲していた両者の実力は、だが後醍醐帝麾下の将が一人、また一人と討ち死にしていくことで、天秤が徐々に傾いていった。
忠臣楠木正成が湊川で自害し、大軍と斬り結んだ陸奥の英雄北畠顕家が討ち死にし、最後の支柱であった新田義貞は名もなき雑兵の矢に斃れた。
天皇親政による治世を目指していた後醍醐帝にとって、彼らの死は夢の終わりと思えたのだろう。延元四年(西暦一三三九)、天下一統を夢見ながら、後醍醐帝は吉野の山奥で静かに息を引き取った。
天下は、足利尊氏によって差配される。
貞和二年という年は、天下万民がそう信じ始めていた頃。吉野の南朝を継いだ後村上帝は、なおも不気味な沈黙を保っていたが、もはや南朝には形勢を覆すだけの力はない。もう、戦乱には戻さないでくれ。誰もがそう祈り、願っていた時のことである――。
綾錦のように艶やかな京の中、笠をかぶった女が一人、東に向かって歩いていた。
流れるような黒い下げ髪を、うなじのところで束ねている。薄紅の小袖と、籠目文様の灰色の裳袴は、都の鮮やかさと比べれば地味だが、人並外れて整った顔立ちは、通りの誰よりも人目を引いていた。すれ違う者は思わず振り返り、通りで話し込む老人たちも、目で追う始末だ。
彼らの視線から逃れるように、霞は笠を深くかぶり直した。
沿道の軒先には、祭りを一目見ようと集まった畿内各地の旅人が群がり、並べられた陶器や仏具を手にとっている。
「この賑わいも、大樹(征夷大将軍)のご人徳よなあ」
不意に聞こえてきたのは、旅人の感嘆の声だ。
立ち止まり、小さく舌打ちした。聞こえたのだろう。薄汚れた旅装の男が、髭面を霞の方へ向けてきた。訝しげな表情が、すぐに上気したような顔になる。睨みつけると、男が咄嗟に俯いた。
この賑わいも、今だけ。
もうじき、洛中は本来の主のものとなりましょう。
旅装の男から視線を外すと、ふたたび塩小路を東へと歩き始めた。
生まれてから十七年、吉野の深い山奥で、息を殺すように生きてきた。
父である大塔宮護良親王は、敵の多い人だった。
後醍醐帝の三皇子でありながら、後醍醐帝に疎まれ、武士の棟梁である足利尊氏とは憎しみあった。やがて足利尊氏との激しい対立の中、幽閉された鎌倉で足利家の淵辺義博という武士に斬殺された時、報せを聞いた後醍醐帝は涙ひとつ流さなかったという。
母もまた、幽閉されていた鎌倉から吉野へ逃れる際、甲斐国(現在の山梨県)の雛鶴峠で霞を生み、力尽きた。吉野の朝廷は、生まれたばかりの霞を受け入れることを拒絶し、あまつさえ大塔宮の血を恐れ、殺そうとさえした。それを防ぎ、育ててくれたのが、父と親交の深かった楠木一族の者たちだった。
女ながらも刀の技を磨き、生き延びるために忍びの技を身につけた。味方は、わずかに楠木一族の者たちだけ。父を殺した北朝も、父を見殺しにした吉野の南朝も、霞にとってみれば仇だった。
『吉野を出て、西国の海を押さえます』
足利家と戦う力を手に入れるため、吉野を出ると言った霞を、楠木一族の者たちは黙って送り出してくれた。育て親でもある楠木一族の棟梁正行は、霞の心の奥にある南朝への反骨心も、見抜いていたようだが、諦めたように笑っただけだった。
この半年、西国の武士をまわってきたのは、海に活路を見出したからだった。
足利家の勢いに押されて衰退した西国の武士には、口に糊するため海に漕ぎ出した者が多くいる。いずれも、隠し湊にごく小規模の水軍を持ち、守護に隠れて交易を生業としている者たちだ。訪れた隠し湊は、十五に及ぶ。
そのうちの一つ、肥前国(現在の佐賀県と長崎県)の南部にある杵島には、楠木一族と祖を同じくする武士がおり、そこで海を渡る船に乗せてもらった。屋敷の二階ほどの高さのある波を乗り越えてゆく船上で、冷たい水飛沫を全身に浴びた。隣を進む船が、いともたやすく木端微塵となった時、霞は鈍色の海に心を掴まれた。
決して勝てないものがこの世にはある。
だが、それは人ではない。そう思えたのだ。
杵島を根拠地として、各地に隠し湊を結ぶ。ある程度の船団となれば、海を越えて高麗や明との大規模な交易も成せる。そこで得たものは、やがて北朝と対峙する時の支えとなるはずだった。
対馬など島嶼の民は、独立心が強く、南朝北朝のしがらみとは縁が薄く、金を払えば雇うことができた。父が遺した金を、惜しみなく使った。手始めに、各地の隠し湊の水深と潮流を調べてまとめさせた。一つの湊に係留できる船の数を調べ、次の湊へはどのくらいの時がかかるのか。大型の船、小型の船での違いも測らせている。
吉野の楠木正行が、足利家を討つべく戦備えを始めた。
その報せが届いたのは、肥前国と石見国(現在の島根県)の隠し湊で、戦船の調練を始めた時だった。正行が考えていた時機と比べて、早すぎる。西国の湊を結ぶことも、始まったばかりだったのだ。京で何が起きているのかを掴むため、長門国(現在の山口県)から早船に乗ったのが四日前の夕暮れだった。
昼下がり、鴨川のほとりの草原に座り、霞は持ってきた握り飯を口に入れた。
大根の葉と一緒に炊いた飯を固めたものだ。胡麻油と塩の味付けは、吉野で親代わりだった正行から教えられたものだ。親代わりというには若すぎるほどの齢だが、背負ったものが正行の皺を深くしていた。戦を嫌っているにもかかわらず、戦場で生きることを強いられ、逃れることもできない。生まれ持った戦の才が、正行を縛っていた。
「辛いですね」
ぽつりと、こぼれた。
味方のいない京で、たった一人。寂しさが辛さを感じさせているのかとも思ったが、吉野でも味方はほとんどいなかった。宵闇で塩の分量を間違えたのだろう。貴重な塩だ。もったいないと言い聞かせた霞は、口の中に残る茎を噛み潰し、鴨川の水に手を浸した。
静かな水面に、自分の顔がうっすらと映った。
「迷ってなど、いません」
正行は、天下を賭けた勝負に出ようとしている。
南朝の英雄北畠顕家が死に、新田義貞、楠木正成までが、足利尊氏率いる北朝に討たれた。後醍醐帝も九年前に薨去し、南朝はもはや風前の灯火のようなものだ。このまま足利尊氏に呑み込まれる。誰もがそう思っているだろう。
京の通りを行く人々の笑顔も、それを物語っている。
それが、ひどく悔しかった。
天下泰平は、犠牲の上に成り立っている。恨みの輪廻を断ち切ることこそが、唯一の道だ。そんなことは、偉そうな坊主に講釈を受けずとも分かっている。だが、諦めきった言葉で納得できるほど、人はたやすくはない。父を、母を、友を殺された恨みは、決して消えないのだ。北朝の者たちにむざむざと頭を垂れるなど、できるものか。それがゆえに、正行も望まぬ戦に身を投じようとしている。どちらかが、滅びるまで戦はやまぬことを知っているからこそ、正行は立ちあがり、霞もまた吉野を出た。
この世の泰平を願っている。
だからこそ、どちらかが死に絶えるために、戦うことを覚悟しているのだ。
鴨川に浸した手は、冷えきっていた。
星のちらつく夜空を見上げ、霞は静かに立ち上がった。
足利家が、二つに分かれて戦を始めるかもしれない。停泊した伊予国(現在の愛媛県)の湊で、正行の手下がそう報せてきた。
足利尊氏の子を名乗る不可解な武士が一人、京に現れたという。名は新熊野。まだ二十歳にも届かない武士であり、その男を巡って征夷大将軍である足利尊氏とその弟足利直義の対立が深刻なものとなっている。
兄弟の対立こそ、吉野が戦を決断した理由だろう。ただ、正行はそれが罠ではないかと疑っていた。数年来、山間の要害である吉野に籠ってきた南朝を、平地に引きずり出すため、足利の兄弟が仕掛けてきているのではないか。その武士の正体を探ってほしい。それが、正行からの依頼だった。正行の懸念は、霞にも分かった。
戦乱を勝ち抜いた尊氏と、謀の権化のような直義の兄弟が、誰の目にも分かる隙を作るとは思えなかった。
西へと歩き、百々橋に差しかかったのは寅一つ(午前三時頃)すぎの頃だった。
天狗が現れるとされる北野社(北野天満宮)を、北壁沿いに進む時は、いつの間にか手を握りしめていた。幼い頃、天狗に攫われる童女の物語を聞いたことがある。
「もう、童ではないのです」
己に言い聞かせるように呟いた時、不意に、物音がした。咄嗟に背後を見たが、民の姿はなく、隠形に長けた者の気配もない。追われていないか、確かめただけだ。そう心の中で言訳をした。
短く息を吐くと、そのまま北へと道を折れた。
大徳寺の境内は、まだ新しい。開山の大燈国師が後醍醐帝の信を受けていたこともあり、北朝の朝廷や、足利尊氏とは睨みあいが続いているという。胸中にあるものが、期待なのか、それとも不安なのかも分からないまま、霞は境内に入った。細く長い石畳の左右には、鬱蒼とした竹林が広がっている。
夜明けを告げる鶏の声が、響き渡る。
甲高い鶏鳴の中に、人の声が混じっている気がした。気のせいか。いや、そうではない。耳をそばだてると、右手の竹林の隙間から、人の声が漏れていた。誰かを罵倒する言葉、それから打擲の音だ。呻き声のようなものも混じっている。
気配を殺し、霞は竹林に踏み入った。
笹がすれる音に気をつけながら、ゆっくりと進む。罵倒の声が、大きくなった。少し歩くと、わずかな崖の下に、開けた場所があった。枯れた茶色の笹が積みかさなり、五人の若い僧が円になって、一人の男に棒を向けている。
寺に入って間もない喝食を、小僧が修行と称して苛め抜くことは、どの寺にもあることだ。打ち据えられるのはまだ良い方で、夜伽の真似をさせられる者もいるという。醜悪なものを見ている気分になり、吐き気が込み上げてきた。
囲む僧の一人が棒を振り上げ、思いきり打ち下ろした。
「喝食風情が、そのような目で我らを見るな!」
若い僧が、顔を真っ赤にしながら棒を振り回す。肉を打つ音が、鈍く響く。ひとしきり打ち据えた後、別の僧が男の髪を掴み、小刀を首に添えた。抵抗する気力もないのか、男はなされるがままだ。
駆け出せば、二十歩ほどだろう。五人の若い僧は、見たところ力任せに棒を振るうだけで、武術の心得はなさそうだ。打ちのめすのは難しくはない。
止めるかと迷った時、霞は思わず息を呑み込んだ。
打ち据えられている男の瞳が、まっすぐ霞を見ていた。竹藪の中、気配は殺していたはずだ。なぜ気づかれたのか。男がうっすらと笑った。
「愚弄するのもいい加減にせよ」
男の薄ら笑いに僧たちが激昂し、打擲の音が立て続けに響いた。
息を荒らげた僧たちが、唾を吐き捨てて立ち去ったのは、男がぐったりと地面に伏した時だった。息はしている。か弱い喝食を気にしている暇はないと思いつつ、男の裂けた上衣からのぞく傷を見て、霞は竹藪をそっと出た。自分自身を守れない民の弱さこそ、自分が見捨ててはならないものだ。なにより、霞の気配に気づいたことも、気になった。
あと十歩の距離になったところで、男の手が、霞のほうに向けられた。それ以上、近寄るなということだろう。少し待つと、男がゆっくりと起き上がり、地面に胡座をかいた。
背を向けた男の表情は見えない。
「衣通姫を思わせる美貌の女が、夜明けの寺になんの用だ」
男の言葉は弱々しいが、妙に耳に残る声だった。
「なぜ、打ち据えられていたのです?」
「ふむ。話のできぬ人だな。聞いているのは俺の方なのだが」
男が、肩越しに振り返った。
浅く焼けた横顔は、すっと鼻筋が通り、目元は涼やかだ。身につけている黒色の小袖は裂け目だらけで、染め抜かれた菱紋は、かろうじて判別できる。襤褸のように埃にまみれているにもかかわらず、男の姿はどこか光っているように感じた。
歳の頃は、霞よりもやや上くらいか。二十歳ほどだろう。
目をこすってみたが、やはり、光は消えない。
男が、呻きながら立ち上がった。下手な打擲は受けるのに難儀すると呟き、男が膝を叩く。
「どこの誰かは知らぬが、俺がうつけゆえ。そうとでも言えばあんたは満足か?」
「逃げるには、十分な腕をお持ちのように見えます」
「ほう。打ち据えられている男の腕が、あんたには分かるというのか」
「私の気配を気取られました」
そう言いながら、霞は懐から蛤の貝殻を取り出し、男に投げ渡した。貝殻の内側には、乾燥させた大黄の根を粉末にし、蜂蜜で練った薬が塗られている。貴重なものだが、できることがあるのに何もしないのは嫌だった。
「血止めに役立ちます。お使いください」
男が黒く塗られた貝殻をじっと見つめて、少しだけ頭を下げ、諸肌脱ぎになった。服の上からでは分からなかったが、相当に鍛えている。僧の身体つきと言うには不自然なほどだった。捜している男かもしれない。そう思いながら、そんな都合のいいことがあるものかと心の中で呟いた。
「まじまじと見ないでくれ。寺では女と無縁なのだ。あんたみたいな美しい人に見られるのも悪くないが」
慌てて目を逸らした霞に、男は笑ったようだ。
どこか余裕がある。虐められている喝食にしては、卑屈さなど欠片も感じられない。この男は何者だろうかと、興味が大きくなった。薬を傷に塗り終わった男が、貝殻を閉じて投げ返してきた。
「逃げられないのだよ」
「なんのことです?」
「打ち据えられていたわけだ。聞きたかったのだろう?」
小袖を着なおす男が、肩を竦めた。
「童の頃に心に決めたことがある。逃げれば、何も掴めない。だからいかに辛い場所でも、その場から逃げることはしない」
正直、くだらない理由だと思ったが、この男にとっては大事なことなのだろう。それを否定しようとは思わなかった。
「抵抗すれば、折檻は無くなるのでは?」
そう言った霞に、男の笑みがすっと消えた。肩についた笹の葉を、男が払う。
「下手に抵抗すれば、殺されるだけであろう」
諦めたような言葉に、ふと苛立ちを覚えた。
「何もせずに諦めるなど」
「そういうつもりで言ったわけではないのだが。薬をよこしたり、心配したり、怒ったり。忙しい人だな」
「怒ってなどいません」
分かったというように、男が二度頷いた。
「だが、あんたが討ち手でないことは分かったよ」
「どういうことです?」
「御簾の奥にいそうな容姿で、闘争の場など似つかわしくない。にもかかわらず、あんたの腰の刀からは血の気配が強く漂っている。いや、怨念とでも言うべきかな」
詰問するような響きはなく、ただ不思議そうな声音だ。
「俺を殺す口実を探している奴らは多い。先ほどの僧の中にも、身分の高い子弟が交じっていた。俺が手を出したところに、あんたが刀を抜いて出てくるのかと思ったのさ。俺は、餌だからな」
不安が、足元から這い上がってきた。身体が、すっと寒くなる。この男が、新熊野という男かもしれない。それは、予想というよりも、確信に近かった。
人の気配を探るように、男が左右を見回した。
「名は?」
向けられた目に、何と答えるべきか迷い、霞は僅かに視線を逸らした。
「綴連」
男の目が、少しずつ大きくなり、突然咳き込んだ。
顎に当てた拳を、ゆっくりと動かし頭を抱えた。全ての息を吐き出すかのようなため息を吐いた。
「俺の知る限り、その名はとある男のものだったはずだが」
頭を抱えたまま、男が首を左右に振った。
「とんだ獲物が網に跳び込んで来たな。去るが良い、美しき人よ。いや、綴連王と呼ぶべきか。その名がまことならば、俺を見張っている者は、あんたを逃さないぞ」
動揺を気取られぬように、霞は首を左右に振った。
「私は西海道(現在の九州)からの旅の途次、大徳寺の玄恵様の高名をお聞きして、ここまでやってきただけです」
「ここで終わらせることができるような旅でもないだろう」
じっと見つめてくる男の気配が、竹藪を覆っているようだった。この場から離れなければ。焦燥に近いものが、胸から込み上げてきた。男の言葉に従うようで癪だったが、身体は外に向かっていこうとしている。
「また、いずれ」
呟き、背を向けた。
「助力は?」
「貴方に何ができるというのです」
背後から聞こえてきた言葉にそう吐き捨て、霞は足を速めた。
大徳寺の境内を出たあたりで、視線を一つ感じた。
間違いなく、霞を見ている。大徳寺の男と接触した者を、見張っているのだろう。早朝ということもあって人通りは少ない。人の中に紛れることはできない。咄嗟に、北へ向かった。
追ってくる視線は、まとわりついて離れない。
新熊野に接触すれば、何かが動く。そう思ったからこそ自ら大徳寺に赴いた。だが、霞の予想を超えて、周到な罠が張り巡らされていたのかもしれない。
「少々、迂闊だったかな」
西国の湊が上手くいき始めていたことで、どこか油断をしていなかったか。舌打ちを噛み殺し、首を左右に振った。時は限られているのだ。
足音が、二方向から聞こえた。東南と西南の二方向。数はそれほど多くはなさそうだが、立ち回りが巧妙だ。なかなか、小路に逃げ込むことができない。大きな雲の影のかかる鷹峯を北に見上げ、霞は腰の刀に左手を添えた。
固い砂の地面を歩くうちに、身体の中の血がふつふつと滾り始めた。
わずかに投じた小石が、すぐに波紋となったことは、喜ばしいことではないか。顔を見られれば、京で動きにくくなるだろうが、自分の戦場は遠い海の上だ。
吉野の南朝が飛びついた足利兄弟の対立は、やはり何か嫌な臭いがする。斬り抜け、正行に報せるべきだった。
小路を右左と折れ曲がり、追っ手を撒こうとしたが、背後の気配はむしろ増えている。相当に京の町を熟知している者たちなのだろうと思えた。
手下を配置している一ノ坂までは、一里ほど。そこまで辿り着けば、森に姿を隠すことができる。家屋が少なくなり、背後が開けはじめた。ちらりと後ろを振り返ると、霞を追う姿が三つ。身につける黒い小袖を見て、やはりかと思った。幕府の侍所に所属する雑色のものだ。塀に隠れて見えないが、聞こえる足音からして、あと四、五人はいそうだった。
急坂が見えてきた。その先には、大徳寺の住持であった高僧が隠れ住む庵が見える。一度立ち止まる。追っ手が歩を止めた。その瞬間、霞は紺の羽織を捨てて駆けだした。追っ手が一歩遅れた。胸が破れるような坂を駆け上がる。すぐに息が苦しくなった。足は鉛のようだ。
坂道を登りきった時、肩越しに後ろを見やると、六人の武士が追いすがるように駆けていた。忍びの技として、瞬時に人や物の数、対象との距離を把握できるよう鍛えられた。だが、敵の多さを分かってしまうのが、今はただ鬱陶しかった。
雑色たちは、身体を鍛え抜いているのだろう。息を荒らげてはいるが、一人として脱落していない。視線がぶつかった。男が、笑った。
咄嗟に身をかがめた。傍らに積まれていた結樽が、派手な音を立てて崩れる。そのまま前に転がり、柄に手を添えて飛び起きた。尋常の弓勢ではなかった。地面に突き立ってなお震えている矢を一瞥し、庵とその奥に広がる木立を見つめた。
骸が二つ、高い杉の根元にもたれかかっていた。
唇を噛んだ。霞が手配していた二人だ。胸には矢が突き立ち、灰色の小袖には血が滲んでいる。亡骸の横、老年の男が一人いた。皺ひとつない紺の直垂と、目を引く真っ白の長髪。背は、糸で吊るされているかのように真っ直ぐ伸びている。重藤の弓を左手に持ち、右手には新たな矢を携えていた。その両脇から、人の気配が滲み出した。右の木立の中から三人、左からは四人。
「女、刀を捨てよ」
矢をつがえた老将の左目が、鋭く光った。
正面の八人と背後の六人が、目に見える包囲の全てだ。斬り抜けるのは、なかなか骨が折れる。それが強がりであることも自覚していたが、強がれるぐらいの余裕があることが、嬉しかった。
足をわずかに右にずらした瞬間、傍らの地面に矢が突き立った。
「下手にあがくな。お主の両手両足を射つことなどたやすい」
あくまで生かしたまま捕らえたいということだろう。骸となった二人は、何もしゃべらなかったのだ。ならば、投降などありえない。
「かりそめの天を戴く者に、私が敗れるなどありえぬことです」
「ほう。やはり南朝に連なる者か」
老人の顔が険しくなった。
「しばらく、大人しくしておったと思ったが、またぞろ動き始めておることは分かっておる。実に良いことじゃ。戦が途絶え、退屈しておったゆえのう」
「戦を好む者に、天下を治めることは叶いませぬ」
「戦場にしか生きられぬ者もおるということよ」
「戦狂い、ですか」
新たに矢をつがえた老人が、笑った。
鞘から刀を抜いた。低く構える。老将の左右にいる七人の武士も、刀を抜き払った。間合いを詰めるしか、勝機はない。だが、その動きを七人が止めようとするだろう。
背に感じる朝焼けの熱が、強くなった。
矢をつがえる老人の顔が、強張った。こちらを見ていない。刹那、竹が爆ぜたような音が、背後から響いた。矢は、放たれている。狙われたのは霞ではない。
男の目が、見開かれていた。
「敵か味方かも分からぬ者に、いきなり矢を射かけるとは、ずいぶんな挨拶だな」
のんびりとした声が、背後から響く。
振り返った先、朝日の中に滲む黒い影が、ゆっくりと刀を納めた。影の足元には、真っ二つに断たれた矢が落ちている。その周囲には、霞を追っていた六人の武士が、地面に打ち倒され、這っていた。いずれも刀傷はない。当て身を食らわされたようだ。
「俺は返事を聞きに来ただけなのだが」
聞き覚えのある声だった。打ち据えられ、裂け目のある黒の小袖のまま。襤褸をまとった男が、刀を携えているのだ。いきなり射かけられてもおかしくない風体だとは思ったが、口にはしなかった。
目の前に立つ男は、先ほどとは別人のようだった。陽炎のような殺気が、そう感じさせるのだろう。小刻みに震える右手の甲を、霞は袖の中に隠した。
「お主、大徳寺の坊主か」
老人の興味が、新たに現れた男に移った。
「その弓、仁科盛宗だな。知っているぞ。信濃(現在の長野県)の鬼。戦にしか興を見いだせず、後醍醐帝に疎まれ、泰平を望む幕府も扱いきれなくなっている戦人」
「ほう。坊主の癖に、儂を知っておるか。武士とは、戦の用よ。泰平には棲めぬ」
霞を挟むようにして、二人の男が笑った。仁科盛宗が弓を捨て、刀の柄に手をかけた。
「その女を助けに来たならば、儂を殺さねばなせぬぞ」
「助けに来たわけではない。助けてほしいかという問いの答えを聞きに来ただけだ」
飄々と呟き、男がすらりと刀を抜いた。
「鬼の力には興味がある」
「小童が言いよる」
男が霞に目配せをした。道を開けろということなのだろう。背後の包囲は、男の手によって崩れている。逃げ出そうと思えば逃げ出せる。息を短く吐き、霞は道を譲った。
男が頷き、前に出た。足音が、しなかった。
「坊主、名を名乗れ」
「新熊野」
やはり、という思いと驚きが、霞の足を立ち止まらせた。