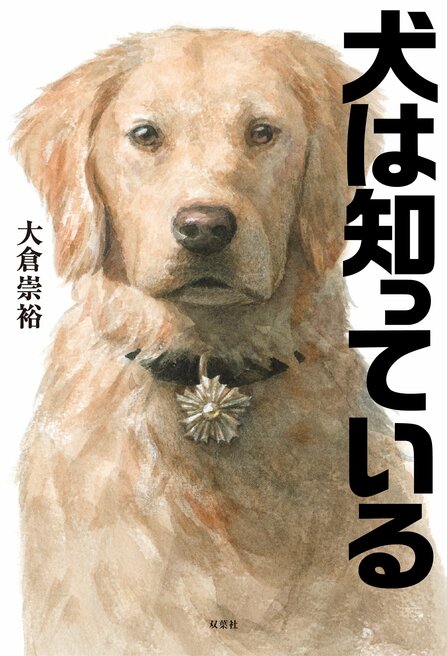九
駅からかなり離れたところにある喫茶店の窓際の席に、男は一人座っていた。心ここにあらずといった風で、運ばれてきたコーヒーにも手をつけていない。
人通りもまばらな通りに面した店は、やはり客が少なく、男のほかには、携帯ゲームに夢中の中年男性とそれをうらやましげに眺めている女性店員がいるだけだ。
笠門が入っていくと、店員が慌てて止めに来た。
「動物は、困ります」
ピーボは開いたままの自動ドアを通らず、軒下できちんと座っている。
「悪いな、仕事なんだ」
笠門は身分証を突きつける。店員は「は?」とつぶやきながら、眼前の身分証とドアの前に座る犬を見比べていた。
彼女の考えがまとまらぬうちに、笠門はピーボに視線を送る。彼はすっと控えめな様子で店内に足を踏み入れた。
リードを持ち、窓際へと向かう。
笠門が入ってきた時から、男の視線はこちらに固定されていた。
笠門はピーボと並び、テーブルの前に立つ。
「今日は休みを取ったと聞いてね、伊吹巡査部長」
「まだ、ボクに聞きたい事でも?」
向かいに座った笠門を、伊吹は油断なく見据えている。脇に座るピーボは、敢えて無視するつもりのようだ。
店員は奥に引っこみ、中年男性は不穏な空気を察したのか、そそくさと出て行った。
空には厚い雲がたれこめ、午後の早い時間だというのに、辺りは薄暗い。予報では、まもなく雨になるらしい。
「俺が今、ピーボと何をしているのか、ある程度、察しはついているんだろう? けっこう、ウワサになっているみたいだから」
伊吹はうなずいた。
「警察病院にいる患者から、その犬を使って情報を引きだすんだろう?」
「そうだ。先日、ピーボと面会したのは……」
「堀隆太郎」
「そこまで判っているのか」
「あんたらが来た時から、薄々、判ってはいたよ」
「では、俺たちがここに来た用件も?」
伊吹は何も答えない。伏せた目には力がなく、焦点を結んでいない。
「堀は安田殺しだけは自分ではないと、ピーボに語った」
「どうしてそれが、本当の事だと? 相手は常識の通用しない連続殺人鬼だ。あんたらの企みを見抜いて、デタラメを言ったのかもしれない」
「その可能性はある。しかし、あらためて安田の件を見直してみると、疑問点がいくつか出てくる。例えば、強奪した金額の少なさだ。堀はなぜ、近隣トラブルを起こしている、裕福でもない安田を襲ったんだ?」
「堀にそこまでの打算はなかったのでは? 一夜の宿にしようとしたのかもしれない。たまたま、目についただけかもしれない」
「犯行間隔にも疑問がある。六件目の殺しが起きてから、安田の遺体発見まで十三日、そして次の犯行が起きるまで十四日。安田のとき以外は、一ヶ月以上、間があいている。どうして安田の時だけ、二週間なんだ?」
「堀に聞いたらいいじゃないか。そういう事が得意な相棒もいるんだし」
冷たい視線がピーボに向けられ、笠門は思わず両手を握りしめた。ピーボがほんの微かに身を震わせる。笠門は慌てて全身の力を抜く。
「疑問はまだある。堀はどうやって、安田宅に入ったのか」
「相手は一人暮らしだ。手はいくらでもあるだろう」
「疑心暗鬼になって、監視カメラなどを取り付けている男だぞ。いきなりドアを開けろといって素直に開けたとは思えない。昼間だと人目につくし、夜間であれば、余計に警戒される」
「つまり……何だ?」
「相手が危害を加える恐れがなく、しかも見知った顔だったら?」
伊吹はふて腐れたように口を真一文字に結ぶ。
睨み合いながら、笠門は待った。
「扉くらい……開けるかもな」
伊吹がつぶやいた。
「顔見知りの制服警官は、その条件に当てはまるか?」
伊吹は足を忙しげに揺らしながら、ふんと鼻を鳴らす。
「さあね」
「安田殺しが堀の仕業ではないとすると、もう一点、決定的な問題がある。現場の偽装だ。それができた人間は、限られている」
「堀の『癖』か」
「当時、人差し指と歯の件は、公表されていなかったからな。それを知っていたのは、警察関係者のごく一部、連続殺人の捜査本部に参加した者だけだ。あんたほど、条件に合う者はいない」
「ちょっと待ってくれ」
「あんたは当時制服警官で、被害者とは顔見知り。さらに堀の『癖』についても知っていた」
「証拠もなしにいきなり犯人扱いされてもな。『癖』の件を知っていた人間は、オレ以外にもいっぱいいた」
「だが動機のある者はいない」
「オレに安田を殺す動機があると? 彼は確かに問題のある人物だったが、警察に対し何かするような事はなかった。お互い顔は知っていたけど、それだけだ。どうして、命まで……」
「きっかけになったのは、安田自身じゃない。彼の被害者だった近隣の住民だ。彼らは事あるごとに、あんたのところにやって来た。違うか。資料編纂室を通じて、当時の警察署の書類をあたらせて貰った。苦情の類いがかなり来ていたよ。それがそのまま、あんたへのプレッシャーになっていったんじゃないのか?」
「そんなのは、あんたの想像だ」
「あんたは異動してきたばかりの新参者だった。管轄区域最大の厄介者を押しつけられていたんだろう? 洗いざらい正直に話した方がいいぞ。総務課長の須脇警視正の指示で、当時の同僚、上司への聴取も始める予定だ」
伊吹が唾を飲み、唖然とした顔で笠門を見た。
「そこまでやるって言うのか? それじゃあ、まるで監察だ」
「総務課ってのは何でも屋でね。トイレットペーパーの交換から、監察の真似事までやる」
伊吹は肩を落とし、冷え切ったコーヒーに口をつけた。
「あんたの言う通りだ。あの時は本当に酷かった。安田を何とかしてくれって、住人たちが入れ替わり立ち替わりやって来る。中には、かなり高圧的なヤツもいた。町内会長だったかな。署長と懇意らしくてさ、直に電話までして訴えたらしい。副署長経由でこっぴどく怒られたよ。さっさと処理しろって。新参者だから、同僚も上司も助けてはくれなかった。どうかなりそうだった」
「それが動機か」
「いや、当時の状況を認めただけだ。殺しまでは認めていない」
笠門はいったん追及を止め、固い椅子にゆったりと座り直した。
横に控えるピーボを意識する。とたんに、伊吹は落ち着かなげな素振りを見せる。
「初めて署で会ったとき、ずいぶんとピーボを意識していたよな」
「犬があまり好きじゃないんだ」
「本当にそれだけ?」
笠門はピーボの頭をなでながら、伊吹に対して笑いかけた。
「どうした? 怖いのか? 心配には及ばない。ピーボはちゃんと、訓練を受けている」
「そ、そういう問題じゃないんだ……」
「あんた、まだ持っているんじゃないのか?」
伊吹の目はピーボに注がれたまま動かない。
「犬の嗅覚は人間の数千倍。子供でも知っている事だ」
笠門はテーブルの上で、伊吹に顔を近づけた。
「ピーボと一緒に、身体検査をやってもいいんだぞ? それとも、あんたの家を徹底的に洗ってやろうか?」
こんな会話、ピーボには聞かせたくないんだ。そんな思いが、笠門の顔を自然と険しくさせた。
伊吹は震える手を上着のポケットに入れると、縫い目がほつれた小さな巾着袋をだす。それをテーブルに置くと、糸が切れたようにがっくりと椅子に崩れ落ちた。
笠門は携帯をだし、須脇に連絡を入れた。
「すぐに捜査員を。ええ。所持していました。この場にいるのは、伊吹と私、二人だけです」
通話を終えると、笠門はうなだれる伊吹に言った。
「どうして捨てなかった?」
「偽装が上手くいかなかったとき、何かに使えるんじゃないかって。堀が捕まって、安田の件も認めたって聞いて、捨てようと思ったんだけど、なぜか……どうしても……」
「悪かったな」
「え?」
「ピーボはファシリティドッグだ。警察犬や麻薬犬みたいに、臭いの追跡なんて彼の任務には入っていないんだ」
「オレが勝手に勘違いしてたって事?」
笠門はそっと巾着を手に載せると、中を開き覗いた。折れた前歯が一本、綿に包んで入っている。現場から持ち去られた、安田の歯で間違いないだろう。
再び、笠門の携帯が鳴った。今度も、須脇からだった。彼は低い声で笠門に告げた。
「堀が死んだよ」
この続きは、書籍にてお楽しみください