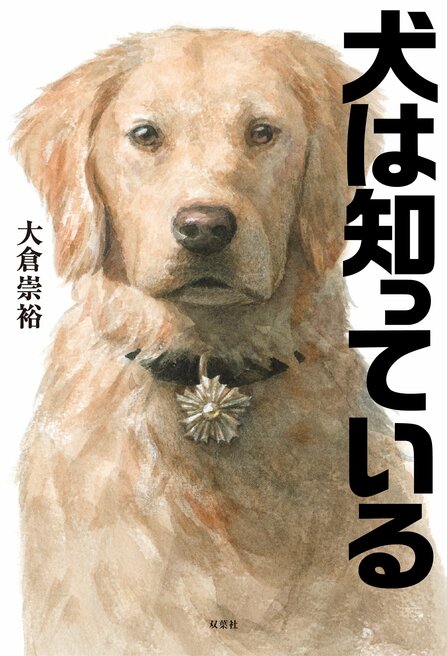七
「安田さんには、随分と酷い目に遭わされましたよ」
庭先に固定した車椅子の上で、平嶋弘子は顔を顰めた。死んだ人の事は悪く言いたくないと苦い表情で語った彩名とは、対照的だった。
神奈川県川崎市にあるケアホームに、笠門はいた。当初は応接室でと言われたが、施設内にピーボを入れる事が許可されず、結局、庭先での対面となった。入居者たちが日々、丹念に世話をするのだろう。色とりどりの花が咲いているが、笠門にはそれが何であるのか、まったく判らない。ケアホームは中心部から離れた高台にあり、入居者も五十人近いという。来る前はもっとうら寂しい雰囲気を想像していたのだが、実際は心安らぐ緑と、明るく自由な雰囲気で暮らす入居者たちの、居心地よさそうな場所だった。
笠門たちのいる場所の対面には、ピーボを囲んで人だかりができている。
「あらぁ、かわいい」
「この尻尾。ふさふさだぞ」
などと声が聞こえる。庭に姿を見せるや否や、ピーボは入居者たちの心を鷲掴みにしていた。
そんな人だかりを穏やかな笑顔で見つめていた弘子であったが、安田の名前が出るや、表情が一変した。
笠門は用意していた質問を投げる。
「実は当時の捜査資料に不備が見つかりまして。お恥ずかしい話ではあるのですが、そんなこんなで当時を知る方にお話を聞き直している次第です」
完全なでまかせだったが、弘子は何を疑う様子もなく、「あらそう」とそっけなく答えただけだった。
「あなたは二〇一五年当時、板橋の蓮根六丁目、安田氏の自宅の斜め向かいに居住されていましたね」
「ええ。二十年、そこに住んでいたわ。とてもいい所でね。引っ越すだなんて、考えもしなかった」
「自宅を手放されたきっかけは、安田氏が原因ですか?」
「主人が病気をしたり、理由はいろいろあるけれど、あの件が大きく影響したのは、確かね」
「やはり、人殺しのあった近くには住みたくないと?」
「違う、違う。問題はそのずっと前からあったのよ。ホント、安田さんには近所中、迷惑してたわ。うちは斜め向かいだったから、家の中を覗き見してるんじゃないのかって、怒鳴り込まれたりしてね。それも一度や二度じゃなかった。自分の家の前には監視カメラとか防犯用のライトとかゴテゴテ置いちゃって、本当に嫌な感じだった」
喋りだすと、止まらなくなった。安田に対する鬱積は相当なものだったのだろう。
「強く言い返してやりたかったけど、あの頃はもう主人がほとんど寝たきりの状態だったし、息子も娘も家を離れていて、心配かけたくもなかったし、じっと我慢したのよ」
「お話はよく判りました。平嶋さん以外に、酷い被害に遭われていた方というと?」
「安田さんの両隣、うちのお隣も同じように、盗撮しただなんだで怒鳴りこまれていたわ。町内会長さんも酷くやられていたわね。ゴミの出し方から通学の子どもの声がうるさいだとか」
そうした住人同士の諍いも、安田の殺害という衝撃的な結末によって終わりを迎える。しかし、凄惨な殺人事件の現場という事もあり、安田の自宅は今も買い手はつかず空き家のままだ。両隣もすぐに引っ越し、今は真新しい一戸建てがある。当時を知る者はいないかと散々調べた末、ようやく見つけたのが、斜め向かいに住んでいた平嶋弘子というわけだ。
「一番被害が酷かったと思われるのは、どなたですか?」
弘子は首を傾げる。
「さあ。誰かれのみさかいなく噛みついていたから……。さっき言った町内会長さんは、かなり精神的に参ってたけど」
「その方はいまどちらに?」
「ギリシャだったかしら」
「ギリシャぁ?」
「娘さんが国際結婚されて、向こうで暮らしているの。ビザも何とかなったみたいで」
安田殺しの強い動機を持つ者として話を聞きたかったのだが、ギリシャではどうしようもない。
「ああ、でも、会長さんは事件の事、何もご存じないわよ」
こちらの内心を読み取ったのか、弘子は尋ねもしないのに言った。
「それは、どうして?」
「事件のあった日も、ギリシャに行かれてたから。電話で報せたんだけど、ものすごくびっくりしてた」
容疑者が一人減った。
弱ったな。思わずピーボを目で探してしまった。
ピーボは入居者たちだけでなく、施設職員にも囲まれていた。初対面の人間にあれだけの勢いで囲まれれば、ピーボもさぞストレスだろう。
そろそろ引き上げて、ゆっくりと休ませてやりたい。
では、と暇を告げようとしたとき、弘子が内緒話をするように声を低くして言った。
「言おうかどうしようか迷ってたんだけど……」
笠門は上げかけていた腰を、そっと元に戻す。
「安田さんで一番害を被っていた人、心当たりがあるの」
笠門は興奮を抑えつつ言った。
「よろしければ、ぜひ聞かせて下さい」
「磯村さんて言う、ボランティアの方よ」
「ボランティアですか」
「支援団体を手伝っている人でね。ホームレスとか困っているシングルマザーの相談に乗ったりする。生活保護の申請を手伝ってあげたりね」
「その方は、安田さんの所にも?」
「ええ。病院の受診を勧めたり、一生懸命だった。でも、安田さん、ああいう人だから」
「うまくいかなかったんですね」
「磯村さんが顔を見せるたびに罵倒してね。酷いものだったわよ。私、何度か忠告したの。あの人には何をしても無駄ですよって。だけど、そういう人だからこそ、見捨ててはおけないって」
「ご立派な方なんですね」
「だけど一度だけ、見た事があるの。磯村さん、歩道に立ってじっと安田さんの家を睨んでた。その目がもう恐ろしくて。どうしたものかと思案しているうちに、安田さん、殺されてしまって……」
その言葉をどう受け取れば良いのか。笠門のとまどいを見透かすように、弘子は薄く笑った。
「ダメね、つい喋りすぎちゃった。ちょっと疲れたわ。もういいかしら」
「もちろんです。お時間いただき、ありがとうございます」
「あらあら、あなたの連れてきた犬、すっかり人気者ね」
ピーボの周りは、相変わらず、賑やかだった。
「よろしければ、ここに連れてきましょうか」
弘子は首を左右に振った。
「けっこうよ。私はネコ派なの」
八
高田馬場駅前から通り沿いに少し坂を登ったところに、土川訪問介護サービスの事務所があった。午前九時という時間であったが、一階事務所内に人気はなく、カウンターの前で笠門はピーボ共々、五分ほど佇むハメとなった。
ようやく裏のドアが開き、中年の女性が顔を見せた。
「あら、えっと……新規のご依頼ですか?」
笠門は身分証を示し、土川真子さんと会う約束をしていると告げた。
「あらあら」
女性は素っ頓狂な声を上げ、アタフタと携帯を取りだすと、通話を始めた。
「あの、真子さんにお客さん。約束したって……え? うん、大丈夫。書類なら、私がやるから」
女性はアタフタと携帯をポケットに戻すと、「いま来ますからぁ」と甲高い声で言うと、入ってきたドアから外へと消えた。
また、無人のオフィスを前に五分ほど佇む事になった。ピーボは久しぶりに訪れた静かな時間を楽しむように、ちょっと首を右に傾げている。傍目には眠っているようだ。
「お約束してたんですよね、ごめんなさい」
背後から声をかけられ、笠門は飛び上がった。落ち着いた様子のピーボとは大変な違いである。
「まあ、かわいいワンちゃん。ゴールデンレトリバーね。立派ねぇ」
吸い寄せられるようにピーボの前にひざまずくと、両手で顔を優しくなで始めた。
「いくつなんですか?」
「七歳です」
「大人しいわねぇ。全然、吠えないし。セラピードッグみたい」
「ファシリティドッグです」
女性の手が止まり、ハッとした様子で笠門を見上げる。
「どこの病院?」
「警察病院です」
「って言うと、やっぱりこの子はピーボ!」
「よくご存じですね」
「すごく興味があってね。アニマルセラピーの催しがあると、利用者さんと参加したりするの。みんな、ものすごくうれしそうでね。そうか、君がピーボか。すごいねぇ」
女性はさっきとは違う、やや力をこめた荒々しい仕草で、ピーボの頭をなでた。その後も背中から尻尾までうっとりと眺めた後、ようやく気が済んだのか、表情を引き締め、立ち上がった。
「お待たせしてごめんなさい。土川真子です」
笠門は名刺を渡す。
「お母様の磯村真紀子さんの事で参りました」
「母は二年前に亡くなりましてね。癌で。私は介護事業所を立ち上げた夫と結婚して姓が変わり、今に至るってところです」
土川真子は片時もじっとしてはいない。今もカウンター向こうに回り、机に積み上げられた書類に目を通している。話し方も含め、何ともパワフルだ。
「それで? 母の何を?」
「磯村さんは、板橋区蓮根の方でボランティアをされていましたね」
「蓮根?」
真子は書類を手繰る手を止め、眉間に皺を作る。
「母はずっとボランティアでね。あちこち出かけてたから。うん……蓮根……あ、もしかして、安田さんの事?」
思いがけず言い当てられ、笠門の方が面食らった。
「ええ、その通りです」
「母がよく愚痴ってたから、覚えてるの。何とか公的支援に繋げたいけど、難しいって」
「愚痴をこぼされる事はよくあったんですか?」
真子ははっきりと首を横に振る。
「愚痴を言ったのは、後にも先にも、安田さんの時くらいよ。ご近所との関係も完全に壊れていて、どうにもならないって」
そこでふと気づいたように、真子は言った。
「今ごろ、どうしてそんな事を?」
笠門は資料に不備があったとのいつもの言い訳を繰り返す。
真子は「ふーん」とうなずいた後、笠門に伝えるべき事を、頭の中でまとめているようだった。
「安田さんのご近所さんには、もう会ってきたの?」
「ええ、まぁ」
「ボロクソ言ってたでしょう、彼の事。でも、母の残した書類とかを読むと、別の側面も見えてくるのよね」
「と言いますと?」
「安田さんに問題があったのは事実だけれど、近所にも責任はあるって事。あからさまに厄介者扱いしたり、言葉は古いけど村八分にしたりなんて事もあったようなのよ」
「それが、安田さんが心を閉ざす原因になったと?」
「母はそう言ってた。安田さんは家が覗かれてるって主張してたでしょう? それは妄想だってみんな決めつけていたけど、実際、そういう事はあったみたい。一種の監視よね。夜中に石を投げ入れられる事もあったって」
「その件はお母様から?」
「ええ。母はわずかだけど、コミュニケーションが取れるようになってたみたい。安田さんの言い分を聞いてた人は、ほかに誰もいないんじゃないかな」
「安田さんはそこまでされて、警察などに相談はしなかったのでしょうか」
「警察や役所には不信感しかなかったみたいだから、母がすすめても頑なに行かなかったって」
言い分は、当事者双方から聞いてみねば判らないものだ。
「最後の質問ですが、安田さんに対して、特に良くない感情を持っていた人に心当たりはありますか?」
「持って回った言い方するのね」
真子は苦笑する。
「母の意見を信じるなら、近所の人はみんな、負の感情を抱いていたでしょう。母が特に気にしていたのは、斜め向かいの平嶋さんって家。旦那さんが病気だって言ってたけど、多分、石を投げ入れたのはその旦那じゃないかって、母は疑ってた。それと、町内会長さん。生活保護受給をすすめたら、断られたって。入院でもなんでもさせて、町内から追いだしたかったみたいだって」
「土川さん、その観点から一つ、ききたい事があるのです。安田さんを疎ましく思っている近隣住人が向かうところと言えば、どこを思い浮かべますか?」
「ふふーん、やっぱりそうきたか」
真子は議論の向かう先を、既に察している顔付きだった。笠門が電話をかけた時から、既に大凡のところを理解していたのかもしれない。
「相変わらず、持って回った言い方ね。あなたがどんな答えを望んでいるか、判ってる。警察や医療関係者はいつもそう。自分の望む答えをこちらに言わせようとする。私は自分で納得した答えしか口にしない。それでもいい?」
「ええ、もちろん」
真子はニヤリと子供っぽい笑みを見せた。
「でも今回ばかりは、あなたの望み通りの答えよ。近隣住人が向かう先は、警察でしょう。最寄りの地域交番ね。実を言うと、母が一番心配していたのは、住人でも安田さん本人でもない。交番勤務のおまわりさんよ」