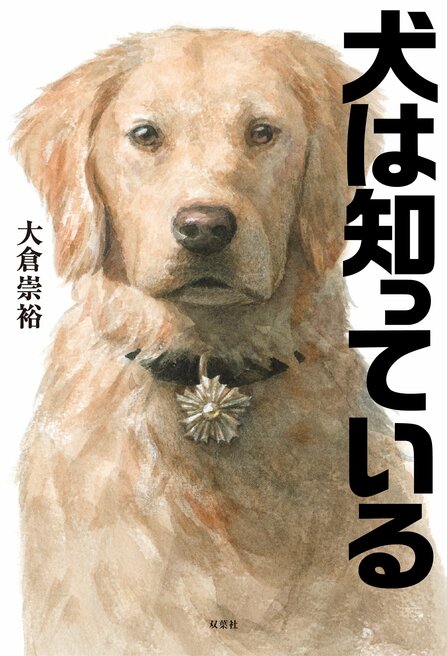三
「おまえが送ってくれた録音データを聞いたよ」
須脇文はデスクのパソコンをゆっくりと閉めた。
四十二歳になる警視正は、ズルズルと鼻をすすりながら、不快気に窓の外を見た。
「花粉だよ。年々、酷くなる。もう五月だっていうのになぁ」
桜田門にある警視庁本部の七階。そこから見える景色は実に穏やかなものだった。皇居の緑も勢いを増し、かすみを帯びた空からは、柔らかな日差しが降り注ぐ──。
須脇はしばし黙りこんだ後、部屋の隅に座るピーボを見た。
「今回もいい仕事をしてくれた」
須脇の褒め言葉を、笠門は苦々しい思いで噛みしめる。それに気づかぬ須脇ではない。
「そう思い悩む事でもないだろう。凶悪な犯罪者から情報を引きだしているんだ。始めて一年、成果もかなりだしている」
「はい……」
言いたい事は山ほどあるが、ピーボが見ている。彼の前では、なるべくネガティブな反応を見せないよう心がけていた。
「つまり、捜査を始めるという事で、よろしいですか」
「当然」
「では、捜査資料その他、必要なものを……」
「もう手配済みだ。ただし、今後は俺からではなく、捜査資料編纂室で一括して受け取ってくれ。こう見えて忙しいのでね」
「警視庁総務部総務課課長。こんな一人部屋に押しこめられて、忙しいも何もないでしょうが」
「何も知らないくせに。総務課は最近、新設部署が多くてな。いろいろ大変なんだ。今言った資料編纂室も今度、総務課の管轄になったんだよ」
「俺とピーボにも、何か部署名がいただけるんですかね」
「どうしたもんかな。考えとくよ」
須脇がパソコンを開いた。話は終わりという合図だ。
笠門はピーボに近づき、微笑みかける。こちらの意図を察し、すぐに立ち上がった。
「ピーボ、俺たちの部署名、何がいい?」
無論、ピーボは何も答えない。
資料編纂室なるものがどこにあるのか。受付も含め、誰に聞いても知る者がなく、結局、二階にある互助組合のベテラン従業員にたずね、ようよう判明した。
地下三階の一番奥。薄暗く長い廊下を進んだ先の突き当たりに、資料編纂室はあった。扉を開くと、そこは書類の墓場だった。うずたかく積まれた段ボール箱が、山脈のように連なり、かなり広い部屋を埋めている。中には天井近くまで達するものもあり、それらが蛍光灯の光を遮って、不気味な雰囲気を醸しだしていた。
「何だここは?」
ピーボを互助組合に預けてきてよかった。互助組合のおばちゃんたちは、ピーボのもてなしが上手く、彼にストレスを与える事なく過ごさせてくれる。外出時にピーボから離れる事は極力避けているが、おばちゃんたちの助けが得られる時は例外としていた。
「あのぅ」
笠門は戸口から呼びかけてみた。人の気配がまったくない。
「総務課の笠門ですが、資料を受け取りにきました」
シュィィィィィン。部屋の奥から奇妙な音がした。壊れたエアコンの上げる悲鳴、あるいは古びた冷蔵庫の断末魔。そんな感じの音だ。
「誰か……いませんか?」
笠門は部屋に足を踏み入れた。左右に箱が積み上がってはいるが、間に一本、人一人が通れるほどの隙間が空いている。これはつまり、道だ。モーゼのごとき気分で、笠門は進む。
シュィィィィィン。またあの妙な音だ。
道は入り組んでいて、迷路のようだ。一本道なので迷いようもないが、箱が崩れ道が塞がれたら、天下の警視庁本部内で行方不明となってしまう。
右に曲がり、その先を左。曲がったところに、小ぶりのデスクがあった。載っているのは、古びたパソコンだ。本体はひと抱えもあり、モニターはブラウン管である。
「シュィィィィィン」
スリープしていた画面が白く光り、パソコンが起動した。
さっきからの音ってこれ? 誰もいないのに、なぜ起動したんだ?
「こら、ポルタ!」
真後ろから突然声が聞こえ、笠門は飛び上がった。
「うわぁぁぁぁ」
「うわぁぁぁぁ」
叫び声が二人分、上手い具合にリンクする。
「いきなりびっくりするじゃないか!」
「いきなりびっくりするじゃないですか!」
立っていたのは、二十代に見える女性だった。スーツ姿で、大きくて丸いメガネをかけている。女性は段ボール箱を抱え、不審げに眉を寄せていた。
「勝手に入って来ないで下さい。ここは部外秘の資料がいっぱいあるんですから」
「扉のところで声をかけた。待っていたら、妙な音が聞こえた。だから入ってきたんだ」
「それで、ご用件は?」
「総務部総務課の笠門巡査部長だ。捜査資料を貰いに来た。須脇課長から聞いていないかな」
「ああ」
女性の表情が幾分、マイルドになった。
「それなら、いま入力中です。今朝、急に頼まれたので、最優先でやっているんですけど」
「それは……何とも、申し訳ない」
「少し待っていてもらえますか」
「もちろん」
「あ、私は資料編纂室の五十嵐いずみ巡査です」
「ほう。コマンドーだな」
「それ、よく言われるんですけど、何の事です?」
「いや、知らなくていいと思う」
「それじゃあ、かかりますね」
「一ついいか。さっき、ポルタとか何とか言ってたな。君のほかに、何かいるのか?」
いずみはニンマリと得体の知れない笑みを浮かべた。
「ポルタはこれの事です」
指さしたのは、パソコンだ。
「編纂室専用のパソコンです。見た目は古いですけど、中身は最新式なんですよ」
「ポルタってのは、パソコンのあだ名?」
「そんなものです。それ以上の事は部外秘って事で」
いずみは椅子にかけると、旧式のパソコンに向かい、なめらかな手つきでキーを叩き始める。
邪魔するのも申し訳ないので、笠門はそれ以上の質問を止めた。
埃臭い箱だらけの部屋に、キータッチの音だけが響く。腰かける椅子とてなく、立ったまま作業の終わりを待たねばならない。離れているピーボの事も心配だ。
「笠門巡査部長は、ピーボ号のハンドラーですよね」
いずみの方から話しかけてきた。
「ああ……うん」
「実は、私も元看護師なんです」
「君も?」
「犯罪の被害に遭われた方の担当になって、話とか聞くうちに……まあ、何と言うか……」
「社会正義に目覚めた?」
「そんな格好いいものじゃないんですけど、警察官なら、病院に来る前に、その人たちを救えるんじゃないかなって」
同じ経歴を持つ者が、他にいるとは。
「笠門巡査部長は、どうして?」
「すべての人を救えるわけじゃない、その現実を直視できなかった。特に患者が子供の時は……」
「判ります」
「逃げるように看護師を辞めて、まったく逆の世界に挑戦したくなったんだ。当時の俺にとって、それが警察官だった」
「それも、ちょっと判ります」
「ただ、採用されてみれば、鑑識課、それも警察犬担当。面食らったけど、まあ、性には合ってたな。だけど、その後もいろいろあって、結局また、病院に戻ってきた。何やってんだかって感じさ」
笠門は苦笑しつつ、続けた。
「でもまあ、それはそれでやり甲斐のある仕事だと思っている。君は?」
「同じです。資料入力ばかりの毎日ですが、それはそれで、やり甲斐があります」
「気が合うな」
「巡査部長のおっしゃるやり甲斐というのは、やはり特別病棟の件も含めてですか?」
その一言に緊張が走る。
「……どこまで、知ってるんだ?」
「まだほとんど何も聞かされていません。巡査部長から聞くようにと、須脇課長から指示を受けています」
「マジか」
「マジです。今後も資料の入力とまとめを続けるのなら、ある程度の情報は共有していただかないと。それで、いくつか質問があるんですけど、特別病棟で治療を受けているのは、刑務所内で病気になった囚人たちですよね」
「ああ」
「ですが、刑務所内で発病した場合、通常は東日本成人矯正医療センターに移送されるのではないのですか?」
「そうだ。だが昨年、例外的な措置として、警察病院内に特別病棟が設置されたんだ」
「例外的とは? 何か基準みたいなものがあるんですか?」
「判らん。判断は須脇課長を含む上層部がする」
「データを見ると、重症の人が多いですね」
「ちょっと待て。データを見るって、あれは部外秘のはずじゃあ……」
「資料編纂室って、色んなデータへのアクセス権があるんです」
「しかし、警察病院は警察職員の出資でできたとはいえ、あくまで民間の病院だぞ」
「そうはいっても、やはり警視庁職員が多く関わっていますから、カルテや入院患者の氏名も全部、ここに」
「それって、ほとんどハッキングの域なんじゃ……」
「私は何もしてません。ただ、アクセスできちゃうんです」
「できちゃうって……」
いずみは表示されている特別病棟入院患者のデータに目を凝らしている。キーを打つ手は完全に止まっていた。
「七〇二号に入院中の堀隆太郎の起こした事件が、今回の資料ですよね」
「ああ」
「二〇一五年から一六年にかけ、九人を殺害した罪で死刑判決……」
「ヤツは人じゃない。鬼だ。金欲しさに若者三人を殺害し一年にわたって逃走。その間に計六人を殺害した……事になっている」
「殺害時に自身の犯行であるとの証拠を残し、戦利品を持ち去る……ってあるんですけど。完全に異常快楽殺人者じゃないですか」
「まず標的の右手人差し指を折る。その後、頭部、顔面への殴打を加え、最後に折れた歯を一本持ち去る。まともじゃないよ」
「でもその件は、当時、伏せられていたんですね」
「ああ。犯人しか知り得ない秘密ってヤツでな。逮捕後公表された時は、大騒ぎになった」
「死刑判決は当然といえば当然か……。ですが、その資料をどうして今ごろ?」
「昨日、ヤツが白状した。九件の殺しのうち、一件は自分ではないって」
いずみは困惑の表情を浮かべ、笠門をふりあおぐ。
「お話の意味がよく判りません」
「堀のことを鬼だと言ったが、俺のやっている事、これを考えたヤツは、本物の悪魔だよ」
「……じゃあ、ウワサはやっぱり本当だったんですね」
「どんなウワサだい?」
「特別病棟に入院している人たちは、取調べや裁判でも証言しなかった秘密を抱えている。その秘密をファシリティドッグを使って聞きだしている──」
「有罪判決を受け服役してなお、秘密を守り通す。犯罪者として筋金入りのヤツらだ。でも、どんなに意志の強いヤツでも、激しい痛みや死が迫る瞬間に、ふと気が弱くなる事もあるだろう。そこに、張り詰めた自分の感情を癒やしてくれる天使のような生き物が現れたら、どうなると思う?」
いずみの表情には、驚きと共に、微かな嫌悪が浮かんでいた。
「つい、本当の事を漏らしてしまうかもしれません」
「俺とピーボがやっているのは、そういう事さ。特別病棟に入るとき、ピーボの首輪を替える。録音用のマイクが仕込まれたものとな。俺はイヤホンをして廊下で待機、中の様子に聞き耳を立てる。このやり方で、俺とピーボは既に三件の証言を得た。三件とも未解決の事件で、証言を元にすべて黒幕が逮捕された」
「大手柄ですね」
「証言をした服役囚三人、全員が直後に病死している。死の淵にいる者を欺して、手柄を得ている。それが本当の手柄かね」
いずみは何も答えず、入力作業に戻った。
「アクセス権があると言ったな。俺の経歴も調べたんだろう?」
口にする必要のない事まで、口にしてしまう。自分が思っている以上に、自分は参っているようだ。
いずみは作業を止める事なく答えた。
「元鑑識課警察犬係。山中に逃げこんだ容疑者捜索活動に従事中、パートナーである警察犬モリオウを……」
「もういい。君が俺の事をよく知っているのは判った。いろいろあったが、今はピーボ号のハンドラーとして、元気にやっている。そういう事にしておいてくれないか」
「判りました。そういう事にしておきます」
ターンと小気味の良い音が響き、いずみは椅子ごと体を回転させた。
「終わりました。データ、お渡しします」
手にはUSBメモリがある。
「助かるよ」
メモリを手にすると、時計を確認し段ボール箱の迷宮を出口へと向かう。
「またいつでもどうぞ」
いずみの声が追ってきた。たった一人、こんな所で資料の入力なんて──。俺なら一日ともたないだろう。何とも掴み所のない不思議な女性ではあったが、どこか惹かれる部分もあった。一線から外れたはぐれ者という共通点ゆえだろうか。
廊下に戻ると全力で駆けた。思っていた以上に時間がかかってしまった。早く、早くピーボを迎えにいかないと。