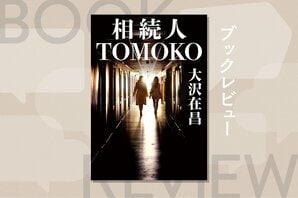「あの、他人の空似かもしれないんで……」
不安になったのか、ポーターは口ごもった。
「大丈夫だよ。あちこちで喋ったりはしない。でもその蕎麦屋さんに、もしかしたら俺が訪ねていくかもしれないと、明日にでも伝えておいてくれないか」
いって、円堂は財布からだした五千円札を押しつけた。ポーターは手を振った。
「いや、お金をいただきたくて話したわけじゃないんで──」
「わかってる。でも覚えてもらっていて、俺も嬉しかったんだ」
円堂がいうと、ポーターはようやく受けとった。
「あなたの名前を教えてくれないか」
「浜田です。蕎麦屋をやっているのは、店名通り、高取って奴で。もしいかれたら、俺の名前をだして下さってかまいませんから」
「わかった。ありがとう」
ポーターと別れ、中央通りで拾ったタクシーに乗りこんだ。
もし二見が生きているのなら、君香も生きていて不思議はない。
だが蕎麦屋にきた客はバスに乗って帰ったと浜田はいった。あのスパイダーが今も走るなら、なぜ乗ってこなかったのか。
目立ち過ぎるからだ。世界に百台しかない、フェラーリ250GTカリフォルニア・スパイダーは、その名を知らない人間にも、見るからに貴重なクラシックカーだとわかる。そんな車を始終乗り回していれば必ず噂になり、やがて二見に貸しがある人間の耳にも届く。
三十年がたち、バブル時代の債権など極道でも回収をあきらめている。だが売ればとてつもない金額になるクラシックカーを債務者が乗り回しているとなれば話は別だ。
ではなぜスパイダーを女が運転していたのか。
乗らなければエンジンが駄目になるからだ。作られてから六十年がたつ車を、極端に暑い日や寒い日、雨の日に走らせるのは故障の原因となる。壊れた部品の調達は容易ではなく、できるとしてもイタリアのフェラーリ本社とのやりとりになるだろう。
そこで年老いた犬を散歩させるように、日を選んで走らせていたのだろう。
ハンドルを二見ではなく女が握っていたのは、高齢の二見には運転の自信がなかったからではないか。
円堂は息を吐いた。考えが暴走している。
赤のスパイダーが那須を走っていたのは事実だとしても、運転していたのが君香と決まったわけではなく、会津高原の蕎麦屋を訪れたのも二見とは限らない。
二人が生きているかどうかすら定かではないのだ。
だが生きていて、今もいっしょにいるとしたら。
嫉妬が胸を焼いた。三十年間、世間から隠れ、肩を寄せ合って生きてきたとすれば、どれほど睦まじい関係なのだ。結婚すら考えていた自分より、二十五以上年上の二見と仲よく暮らしてきたというのか。
思わずため息がでた。
何もかもを失っても尚、自分より二見のほうが君香には魅力があったということだ。
男として人間として、二見にはとうてい太刀打ちできないとわかっていた。
委津子がいうように、円堂は二見を尊敬していた。同じことはできないし、同じようになりたいとも思わなかったが、円堂が生きてきた灰色の世界で、初めて筋が通っていると感じた人だった。
裏の世界の人間はすぐに「筋を通す」とか「人として」という言葉を口にするが、その大半は自分にとって都合のいい場合だ。
他人には筋を通せといっておいて、自分はその筋を平気で無視する。筋などという言葉は因縁をつけるための材料でしかない。
まっとうに生きている人間は筋を通すのがあたり前なのだ。契約を守らなければ取引相手を失くし、やがては訴えられる。
契約などない世界だからこそ、筋だの人だのという理屈が幅をきかせる。契約がないのは、筋など通していては金儲けができないからだ。
まっとうな金儲けをする能力がないからこそ、裏の世界で仕事をする。学歴がなくタネ銭ももたず、信用される所属先のない人間が大金を得たかったら、違法な手段に訴える他ない。法を犯せば、まともに勤めたのでは決して得られない金を短期間で稼ぐことができる。
だがひきかえに、刑務所にぶちこまれたり、別の奴にハメられたり、場合によっては命を落とす。
二見はそれをよくわかっていた。地上げのために、ここまではやってもこれ以上はしない、というルールを決め守っていた。二見興産が危なくなり、ケツに火がついていても、力ずくで金をむしるような商売はしなかった。
それを甘いと嗤う人間もいたが、円堂は立派だと思っていた。
君香のことさえなければ、生涯、尊敬しつづけたろう。
君香も金ではなく、人間性で二見を選んだのだ。
いや、スパイダーを残していたように、二見には隠した財産があり、君香はそれを選んだのではないか。
そう思いたい。スパイダーを残しても尚、三十年間隠遁生活を送れるほどの財産があった。だから二見についていったのだ。
中目黒のマンションに帰ると、円堂は明りもつけないまま、2LDKのリビングでアグラをかいた。
自分のほうが若く、愛情においても負けていたとは思わない。それでも君香が二見を選んだのは、二見に隠し財産があったからだ。
そう信じなければ、自分が惨めだ。
自宅で酒を飲むことは滅多にない。だがひと通りはおいてある。「いろいろ」の周年のときに客からもらったスコッチがあった。
アイラモルトで香りがきつく、一杯飲んだきりでやめていたボトルを、円堂は流しの下からとりだした。
キャップを外し、ラッパ呑みする。
こんな自問自答を何度くり返したろう。無意味だ。理由が何であれ、去っていった女は去っていった女で、まして三十年もたった今、どうすることもできない。
忘れようと決め、それに成功した、と思っていた。
中村の電話が、そうでなかったことを気づかせた。ヨード臭の強い酒が喉を焼き、胃袋を熱くする。自分を責め苛む気分にぴったりだ。このウイスキーを初めてうまい、と感じた。
翌日の午後、仕入れを終え、二日酔いが少しマシになるのを待って、円堂は中村に電話をかけた。
「はい」
執筆中だったのか、ひどく無愛想な声で中村は応えた。
「マズいならかけ直す」
「別にマズかねえよ。このクソ頭をカチ割りたいだけで。いつものことだ。何だよ」
「福島の会津高原てのは、そこから遠いか」
「会津高原? それほど遠くない。栃木との県境の近くだ。なんでだ」
「二見を見たって奴がいる」
中村は黙った。円堂は言葉をつづけた。
「そいつは昔、銀座でポーターをやってて、今はひっこんで蕎麦屋をやってるらしい。その蕎麦屋に、二見がひとりで現われ、蕎麦を食って帰ってったというんだ」
「スパイダーに乗ってたってか」
「いや、バスで帰っていった」
「バスなんて何本も走っているようなところじゃないぞ」
「だろうな」
しばらくどちらも無言だった。やがて中村がいった。
「くるのか」
「その蕎麦屋にはいってみようかと思っている」
「だったら東北新幹線で、那須塩原じゃなく新白河まできてくれ。うちからはそのほうが近い。迎えにいく」
「仕事は大丈夫なのか」
「お前がこられるとすりゃ、土曜か日曜だろ。それまでにはこの原稿のメドがついてる」
「車でいこうと思ってたんだが」
「やめておけ。帰りが渋滞する。車は俺のがある」
「わかった。土曜日にいく。泊めてもらうかもしれん」
「それはまったく問題ない」
「土曜日、乗る列車が決まったら連絡する」
「それまでにやっておくこと、あるか?」
中村は急にきびきびとした口調になった。
まるであの頃のようだ。中村が地主や借地人の情報を集め、円堂が立ち退き交渉に動く。
「スタンドだ」
円堂は答えた。
「スタンド? ガソリンスタンドか」
「ああ。スパイダーに給油する客がいなかったか、時間があれば訊きこんでくれ」
「できる範囲でやっておく」
「よろしく頼む」
「円堂──」
「何だ?」
「いや、何でもない。土曜日、連絡をくれ」
「ああ」
電話は切れた。中村のいいかけたことは想像がついた。君香だ。君香を捜す気なのか、と訊きたかったにちがいない。
君香も二見も捜す。見つけて、金をとろうなどとは思っていない。恨みごとをいう気もない。
元気でいるならそれでいい。確かめるだけでいいのだ。自分にいい聞かせた。
中村にいっても決して信じないだろう。だが、会えば、過去に決着がつく。それは確かだ。
この続きは、書籍にてお楽しみください