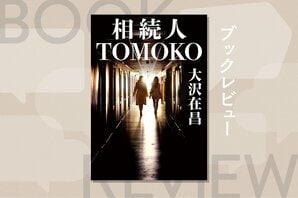大箱のナンバーワンを経て、委津子は雇われのママを十年ほどやり、やがて自分の店をもった。それはおおかたの予想を裏切りクラブではなく、こぢんまりとしたスナックだった。バーテンがひとりに手伝いの女の子が二、三人という小箱だ。料金もクラブに比べれば半分以下で、売りは料理とカラオケだった。
料理は、バーテンが洋食を、委津子が和食を作る。求められれば、味噌汁と飯をつけ定食にもする。
十二時には女の子を帰すが、クラブとちがって朝まで営業する。
委津子と知り合って三十年以上になる。知り合ったときすでに委津子はナンバーワンだった。
男女の関係にはならなかったが、太客でもない円堂を決してないがしろにすることはなかった。それが委津子が多くの客に信頼された理由のひとつだ。
バブル崩壊とともに多くの客を失っても生きのび、水商売をつづけ、今は「お母さん」と女の子たちに呼ばれている。店の名も「マザー」だ。
クラブの勘定など払える身分ではなくなった円堂が今も通う、唯一の銀座の酒場だ。
「いらっしゃい」
「マザー」の扉を押すと割烹着を着けた委津子がカウンターの中で迎えた。手伝いのユキという大学生の娘が帰り仕度をしている。
「お先です。あ、円堂さん──。円堂さんがいるのなら残業しちゃおうかな」
「タクシー代はでないぞ」
円堂はわざといった。
「だって円堂さん、中目黒でしょ。あたし恵比寿だから落っことしてもらえるもん」
店に他の客はいなかった。
「子供は帰んなさい」
「あっ、お母さんといいことするんだ」
ユキが円堂をにらむ。
「そりゃお母さんとお父さんだもの。たまにはそういうこともしないとね」
委津子がにたっと笑った。
「やだっ。親のエッチの話は聞きたくない。帰ろうっと」
ユキはいって店をでていった。
「どっちにする?」
吉四六とオールドパーのボトルをカウンターにおき、委津子は訊ねた。焼酎とウイスキーの二種を、円堂はキープしている。
わずかに息を吸い、円堂はオールドパーのボトルをさした。
「飲みかたは?」
「ハーフロック」
委津子は頷き、丸氷をいれたロックグラスに、ウイスキーと水を同量注いだ。
ホステス時代に比べればひと回りふくよかになり、そのぶんやさしげになった。現役時代の委津子は店のすみずみにまで目を配り、黒服に厳しく接していた。声を荒らげて怒ることはしなかったが、対応の悪い黒服には厳しく注意した。
委津子ママのおかげで一人前になれたという、元ボーイ、今はクラブの社長が何人も「マザー」の客にいる。
「あたしも飲んでいい?」
「もちろん」
小さなグラスに手早く水割りを作った委津子と円堂は乾杯した。
「何かあった?」
以前はシャンペンを日に三本も四本も空けた委津子だが、今は口を湿らすていどしか酒を飲まない。
「二見の車を見たって奴がいる」
わずかに間をおき、委津子が訊ねた。
「二見会長も見たの?」
委津子に初めて会った店は、二見に連れていかれたクラブだった。君香もそうだ。円堂が足を運んでいた銀座や六本木のクラブは、どこも最初は二見に連れていかれた。
二見は月曜から金曜まで、毎日飲んでいた。それも十二時までは銀座、それ以降は六本木、そして両方のクラブのホステスを連れてアフターにもいっていた。
アフターとは、店がはねたあとのホステスを連れて遊びにいくことだ。食事や歌、場合によってはそのままベッドになだれこむこともある。
湯水のように金を使い、しかしそれをひけらかすことをしなかった二見はもてた。抱いた女には、それなりに礼を払っていた。アフターが終わり近くなると、
「今日はあたし」
というホステスが、二見の隣りを奪いあうこともあった。挙句に、
「今日は二人いっぺんに面倒をみて」
といわれ、
「そんな体力あるかよ」
と苦笑していた。
当時五十の半ばを過ぎていたが、毎晩飲み、二、三日に一度はホステスを「お持ち帰り」していた。離婚し独身だったとはいえ、驚異的な体力だった。
だからこそ円堂は、二見には特定の女はいない、と思っていた。
気にいっていた女はいたろう。月に一、二度は同じ女を抱くこともあったとは思う。
が、君香が二見にとって特別な女だとは、円堂はまるで考えていなかった。君香本人も、
「二見会長とは何もないよ。だってあたし、好みのタイプじゃないもん」
といっていた。
その通りで、二見はバストの大きい、グラマラスな女が好きだった。君香は細身で、胸は決して大きくなかったのだ。
「いや、女が運転していたそうだ」
円堂は委津子に答えた。
「本当に会長の車だった?」
「百台くらいしか作られなかった、フェラーリのクラシックカーだ。たとえレプリカでもめったにない。色も同じ赤だったそうだ。見たのはクラシックカーに詳しい人間らしいんで、まちがいないだろう」
委津子は円堂を見つめた。
「会長は生きてるってこと?」
「わからない。一番気にいった車に乗って行方がわからなくなった。どこか山奥で死んだと思っていた」
「ひとりで?」
「いや。たぶん君香と」
「君香さん。円堂さんがつきあっていた、六本木の人ね」
「つきあっていた、か」
円堂はつぶやき、酒を口に含んだ。つきあっていると思っていたのは自分だけだ。
君香が本当に惚れていたのは二見で、自分は遊ばれていたに過ぎない。
「思いだすと今でも自分に腹が立つ」
委津子に目を向け、
「三十年もたっているのにな」
といった。
「つまり今も惚れているってことね。そうでなければ腹を立てたりしない」
円堂は息を吐いた。
「未練がましい男だよ。自分じゃなけりゃ、ひっぱたきたいね」
「かわりにひっぱたいてあげようか」
委津子は微笑んだ。
「やめてくれ。本気で殴られそうだ」
円堂は首をふった。
「そうよ。お母さんになったってヤキモチは焼く」
「おいおい、何もなかったろう、俺たちは」
「だから焼けるのよ」
委津子はいった。
「よしてくれ。お母さんに惚れられているなんてわかったら、何人に目の敵にされるか」
本気で委津子に結婚を申しこんだ客を三人は知っていた。ひとりは大相撲の横綱、ひとりは三代つづく大阪の大問屋の社長、もうひとりは妻に先立たれた国会議員だ。後に閣僚になった。
「皆んなにいって、とっちめてもらおうかしら。ずっと円堂さんに片想いしていたのに相手にしてもらえなかったって」
「話を作るなよ」
委津子は笑い声をたてた。
「皆んな、あたしにはすごいパパがいると思っていたのよ」
「わかるよ。でも、始めたのがこの店で、『なんだ売れない絵描きか役者でも養ってたのか』っていわれたろう」
円堂がいうと委津子はにらんだ。
「ずっと男がいなかったとはいわないけれど、面倒をみてくれた人もみた人もいない」
「崎田さんだったりして」
「お呼びですか」
キッチンからバーテンの崎田が顔をのぞかせた。じき七十三になる。委津子がママをつとめていた大箱で働いていた。退職して妻と洋食屋を田舎で始めようとした矢先に、その妻が癌になり、治療費に困っていたのを委津子が助けた。やがて妻は亡くなったが、崎田は田舎に帰らず「マザー」で働いている。
「やめて。崎田さんはマジメなんだから、そんな話をしたら切腹しかねない」
委津子がいった。すると、
「ここだけの話ですが」
と崎田が声を潜め、円堂と委津子は真顔になって見つめた。
「ママが私の娘だって噂があるんです」
「いやいや、年が合わないだろう。崎田さんがいくつのときの子供だよ」
「失礼ね。あたしはまだ五十代よ」
「だとしても年が近過ぎる」
「二人とも年をごまかしているんです。本当は私が八十で、ママが四十代なんです」
崎田がとぼけた顔でいったので、円堂と委津子は吹きだした。
「意味がわかんないよ。崎田さんが年を若くいって、ママが多くいってるってこと?」
「そうなんです。親子だというのがバレないように」
崎田は細い目を大きくみひらいて頷いた。真剣な表情だ。
「本当のところ、私もこんなに働き者の娘がいたらありがたかったんですが」
崎田には息子が二人いるらしいが、どちらも警察の厄介になりがちだと聞いていた。
「崎田さんがお父さんだったら、もっとお料理を習えた。今だって教えてくれないのよ」
委津子がいうと、崎田は鼻の穴をふくらませた。
「当然ですよ。ママが料理を覚えたら、私はお払い箱になっちまいます。こんな年寄りを雇ってくれる店はもうありませんからね」
「そんなことないわよ。一昨日も『ルアーナ』の社長が崎田さんを欲しいって口説いてたじゃない」
「えっ本当ですか。いっちゃおうかな。でもいじめられるだろうな。爺い、何しにきたって」
「崎田さんは『マザー』にいなけりゃ駄目だよ。俺もいろいろ習いたいのだから」
円堂はいった。崎田は、洋食のソースを作るコツを、いくつか円堂に教えてくれたことがあった。
「じゃあさ、円堂さんだけ別チャージね。崎田さんから料理を習ったら、指名料ってことで」
「それは私に入るんですか?」
崎田が訊ね、
「折半」
委津子は答えた。
「こんなしがない居酒屋のオヤジからぼったくるのかよ」
「若いときにとらなかったから、今、とるわ」
涼しい顔で委津子が頷いた。
「それはしかたないですね」
崎田がいい、
「何だよ。崎田さん、どっちの味方だよ」
円堂は口を尖らせ大笑いになった。
小説
晩秋行

あらすじ
居酒屋店主の円堂のもとに、バブル時代、ともに荒稼ぎをした盟友の中村から電話が入る。当時、「地上げの神様」と呼ばれ、バブル崩壊後、姿を消した二見興産の社長の愛車で、20億円の価値があるクラシックカーの目撃情報が入ったという。20億円の車をめぐってバブルの亡霊たちが蠢き出す、大沢ハードボイルドの新境地。
晩秋行(3/6)
関連記事
おすすめの試し読み