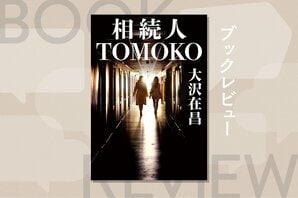1
店の電話が鳴ったのは、鳥肉、里芋と一緒に煮る大根の皮を円堂が剥いているときだった。大根の皮は千切りにしてひと塩し柚子の皮と合わせると、雑炊とともにだす漬け物のかわりになる。これを気に入った客がいて、皿いっぱいだしてくれといわれたことがある。元は大根の皮なので、一日に多くは作らない。断わると、作り方を教えてくれと食い下がられた。確か、自分も料理をするという推理小説家だった。
「親方、お電話です」
受話器を手にしたケンジがいった。
「作家の中村さんて方です」
「おい、火」
円堂はいった。ケンジはパンプキンシードの塩煎りを作っている最中だった。乾かしたカボチャの種の芯を宮古島の雪塩で煎るのだ。ワインやウイスキーに合うのだが、煎りすぎると爆ぜて食感が悪くなる。
「あっ」
ケンジはフライパンの火を止めた。
作家のことを考えていたら、別の作家から電話がかかってきた。包丁をおき手をぬぐって、円堂は受話器を耳にあてた。
「なんでいちいち作家と断わるんだ。ただの中村でいいだろうが」
「だって中村っていっぱいいるだろうが。だからって中村充悟とフルネームを名乗るのも恥ずかしい」
「作家と自ら名乗るほうが恥ずかしくないか」
「いいんだよ。お前のとこの若い衆なのだから」
三十年を超えるつきあいだ。お互い、そっけないやりとりになる。
「今、仕込み中だ」
「わかってる。携帯に電話してもでないから店にかけたんだ」
いわれて円堂は、店のカウンターにおいていた携帯に目をやった。仕込みが終わるまではいつもマナーモードにしている。
「急ぐ理由があるのか」
「あるからかけてるんだ。赤のスパイダーを見た奴がいる」
「どこで?」
「うちの近所だ」
中村は十年前、愛犬とともに栃木県に引っこした。那須の外れにある別荘地の古い一戸建てを格安で手に入れたのだ。当時は小説家としてデビューしたばかりで、東京で暮らしていくのがきつかったようだ。今は時代小説作家としてそこそこ売れているらしい。
「二見は那須に別荘をもっていたろう」
中村にいわれ、思いだした。那須の他にも熱川と軽井沢にももっていて、沖縄にも建てようとしていた。金の使い途に困っていたのだ。
「本当にスパイダーなのか」
円堂は訊ねた。
「まちがいない。四つ葉社の担当がかわってな。新しい担当が挨拶にきたんだ。そいつは前に車雑誌の編集部にいて、クラシックカーの連載を担当してたからスパイダーが日本に何台あったのかも知っていた」
「乗っている人間は見たか」
「サングラスをかけた女だったそうだ」
「ひとりか」
「ひとりだったらしい」
円堂は宙を見つめた。
二見がもっていたのは、一九六〇年に発売されたフェラーリ250GTカリフォルニア・スパイダーというオープンカーだ。二見の話ではフェラーリ250GTカリフォルニア・スパイダーは一九五七年から六三年にかけて一〇四台が作られた。話を聞いた当時でもクラシックカーで、二見はそれを十億以上の金を払って手に入れた筈だ。
二見がもっていた車は、その250GTだけではない。ふだんの移動は運転手つきのロールスロイスで、軽井沢の別荘にはランボルギーニをおいていた。ランボルギーニは音がうるさいからと、あまり乗らなかった。
だが一九九一年九月、スパイダーを運転している姿を見られたのを最後に、行方がわからなくなった。以来、消息は不明だ。
そして君香も姿を消した。
君香のことを考えると、いまだに怒りと後悔がこみあげる。三十年もたっているというのに、まだ踏んぎりがついていない自分が腹立たしい。
真剣に惚れていたからだけではない。これほどひどい裏切りをうけたこともなかった。
いや、裏切られたのは自分だけではないかもしれない。二見もまた、裏切られたのではなかったか。
「例の女じゃないのか」
中村の声が円堂を現実にひき戻した。君香という源氏名を中村も知っている筈だ。君香が働く六本木のクラブにさんざんつきあわせた。だが中村は、「例の女」としかいわない。
当時から君香のことを嫌っていた。
「ああ。だが本人の筈はない。生きていたらもう六十近い」
「そんなのわからないだろう」
「いや、俺にはわかる。あいつは生きてない。二見も、生きていない」
「じゃあスパイダーをどう説明する。あんな珍しい車が何台もある筈ない」
円堂は黙った。確かにスパイダーが、そう何台も残っているとは思えない。しかも色は赤だ。
二見は日本にはこれ一台だけだと自慢していた。
「俺たちは貸しがある」
中村がいった。
「貸し──」
「もし二見が生きていて、スパイダーをもっているなら、その貸しを返してもらってもバチは当たらない」
「二見に貸しがある奴なら、いくらでもいるぞ」
会長の二見が失踪したとき「二見興産」が抱える負債は千億を超えていた筈だ。債権者は金融機関だけではなかった。裏の筋の金も相当額、「二見興産」には流れこんでいた。
暴力団や政治団体も二見には稼がせてもらっていた。「地上げの神様」と、二見を呼んだ銀行マンもいた。
「だが俺たちのは労働債権だ」
「そんなものはとっくに時効さ。何年たったと思ってる」
円堂と中村は「二見興産 調査部」の名刺を与えられていたが、正社員ではなかった。
中村はルポライター、円堂は示談交渉人が本業だった。本業といっても職業として名乗れるようなものではなく、法ぎりぎりのところで稼ぐ灰色稼業だ。
それは二見に雇われていたときもかわらない。地主の情報を探り、弱みをつかんで「二見興産」に土地を売らせるよう仕向けるのが、二人の仕事だった。
地上げにはやくざも多く使われていた。バブルの最中だ。地主や借地人を立ち退かせるために家族を威したり放火するような奴もいた。
二見はそういう連中を「外道」と呼んで蔑んだ。
「札ビラで動かないなら、気持に訴えろ」
とよくいわれたものだ。高齢の両親、留学したがっている子供、不始末を起こした道楽息子、さらには入手が難しいコレクターズアイテム、地主や借地人がいうことを聞かざるを得なくなる“理由”を探し、説得するのが中村と円堂の仕事だった。
そうして立ち退きに合意させ、転売して得た利益の二パーセントが二人の報酬になった。
一億なら二百万、十億なら二千万だ。
二人が二見から得た報酬はいくらだったろう。合わせて一億は下らなかった筈だ。入るそばから、円堂は使っていった。「地上げの神様」についている限り、永遠に稼げると信じていた。
バブルが弾け、「二見興産」に債権者が押し寄せたとき、二人に支払われるべき報酬は八千万ほど滞っていた。
「二見興産」だけではない。地上げ、土地転がしが限界にきていることは少し前から匂っていた。が、誰もが自分だけは売り抜けられると、根拠なく信じていた。
土地転がしに携わる誰もが、導火線に火がついた爆弾でキャッチボールをしていたのだ。
が、あるとき、それらの爆弾が一斉に爆発した。まだ導火線は残っていた筈なのに、次の奴に渡す前に全員の手の中で爆発した。
「飛ぶ」と、あの頃はいった。
奴は飛んだ、あの社も飛んだ。そんな言葉をうんざりするほど聞いた。弾け飛んだ、という意味だ。何もかもが消え、身ぐるみ一切を奪われる。債権者から守るため家族と別れ、土地も家も車も絵もゴルフ会員権も、すべてを失くす。
「二見興産」も飛び、中村と円堂も飛んだ。
中村には贅沢好きの女房がいた。ブランド品が大好きで、車はメルセデス一辺倒だった。
中村が職を失ったことを聞くと、その日のうちに、買わせた洗いざらいをメルセデスに積んで、でていった。
円堂は独身で、金の使い途は女と食いものだった。六本木や銀座のクラブの女とうまいものを食べ歩き、体を重ねた。
中村よりははるかにいい思いをした、といえるだろう。金を自分の楽しみに使ったのだ。
「じき三十年。確かに時効だ。お前はいいよな。好きなことに使って、挙句に居酒屋の親父におさまった。食べ歩きも無駄じゃなかったのだからな。だが俺はどうだ? 映子がでていって何も残っちゃいない」
映子というのが中村を捨てた女房の名だ。確か元はさほど売れていないモデルだった。
「だが今は立派な作家先生だ」
「あのな、作家なんてのは浮き草稼業だ。働いたぶんしか金にならない肉体労働者なんだよ。売れなくなれば注文はこない。注文がきても書けなくなったらそこで終わりだ」
「才能があるから作家になったのじゃないのか」
「才能だと。才能は壺の中にあって、掻きだしているうちに、いつ底をつくかわからないんだよ。今日か、明日か、と怯えてる」
「だからどうしたいっていうんだ」
「探そうぜ、スパイダーの持ち主を。もしそれが例の女で、二見も生きているとなれば、俺らには、いくらか貰う権利がある」
「仮りに二人とも生きていたとしよう。お前と同じように小さな家でひっそりと暮らしてるとする。金なんかとれないぞ」
「スパイダーがあるじゃないか。走れるくらいの状態なんだ。売れば十億や二十億にはなる」
確かにそうかもしれない。だが円堂は気がすすまない。二見を探すのは君香を探すのと同じだ。
いまだに痛みが残る。三十年前の古傷をつつきたくない。
「親方」
ケンジに呼ばれ、我にかえった。
「その話はまたにしよう。仕込みに戻らなけりゃならない」
円堂はいって電話を切った。