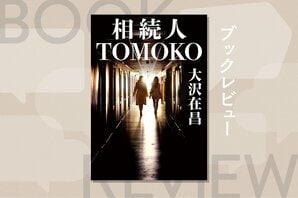笑いやむと、委津子がいった。
「乗ってたのは君香さんかしら」
「わからない。生きているとしても君香だっていい年だ。それにどうやって生きのびたのか。心中したのだとばかり思ってた」
円堂は首をふった。崎田は無言でキッチンにひっこんだ。
「無理心中?」
「二見はそういうタイプじゃなかった。死ぬなら自分ひとりで死ぬ。心中したのなら、君香のほうからもちかけたのだろう」
「なぜ?」
円堂は酒を呷った。自分と二見との三角関係に倦んでいたからではなかったか。
円堂は本気で惚れていた。結婚すら考えていた。それをいついいだそうか迷っているうちにバブルが弾けた。
君香は君香で、本当は二見の愛人だったのに、遊びでつきあった円堂に真剣になられ疲れていたのではないか。
二見との関係を露ほども円堂に気づかせないために苦労し、何もかもが嫌になったのかもしれない。
「疲れてたのだろう」
ぽつりといった。委津子は首を傾げた。
「あのとき、たいていのホステスは疲れていたし、焦ってもいた。とんでもない売りかけをしょわされて自殺した子もいっぱいいた。結局、店ごと潰れちゃうから関係なかったのにね」
売りかけが回収できれば店は安泰だが、とてもそんなわけにはいかないと、クラブのオーナーたちもすぐ知ることになった。
電話一本で土地を転がし、
「おい、また一億儲かっちゃったよ」
笑って、アイスバケットにドンペリを空けさせ、ホステスと回し飲みした客が一夜明けると文無し以下、一生かかっても返せない借金に溺れていた。
「今考えると信じられないよね。うちに帰って着物脱ぐでしょ。ぽたぽた折った万札が落ちてくるの。チップでつっこまれたお金。日給よりそっちのほうが多かったもの。若い子に話すと、嘘でしょっていわれる」
「皆が欲ボケしていたんだ。土地は永久に値上がりする。日本列島の土地の値段で、アメリカがいくつも買えるなんて馬鹿なことをいってた」
円堂はつぶやいた。
「でも君香さんが死んだとは思えないな。もし死ぬのだったら、二見会長とじゃなくあなたと死んだわよ」
「俺は自殺しない。自殺を考えなきゃならないほど大物じゃなかった」
「だったら二見会長だけ死なせて、あなたと生きる道もあった」
「それはひどすぎないか」
「そう? 女は皆んなしたたかよ」
そうしてくれたら自分はつらい日々を送らずにすんだ。だがあくまでも真実を知らなければの話だ。
二見とのふたまたを知ったら、君香を許すことはできなかったろう。心中ではなく、殺す道を選んだかもしれない。
「あいつが二見といっしょに消えて、初めて俺は二人がつきあってたことを知ったんだ。二見との関係をこれっぽっちも疑ったことはなかった」
「二見会長に恨みはないの?」
「まったくないわけじゃない。だがそれは君香のことを俺に黙っていた点だけだ。あれだけの人だ。君香が惚れたのも当然だ」
「今でも尊敬しているの?」
「尊敬か……。かっこいい人だったとは思う。理由は、わかるだろう」
委津子は頷いた。
「わかるわよ。稼ぎかたも使いかたも、下品なところが少なかった。お金って、なくてもありすぎても、人の本性をむきだしにする。いくらでもお金があると、世の中のことはたいてい思い通りになる。その結果、信じられないくらい卑しいことをするの」
「俺よりお前さんのほうが詳しいだろうな」
「ホステスは金で思い通りになる。ホステスは人間じゃない。本気でそう考えている人がたくさんいた。いい学校をでていい企業に入って、たっぷり稼いでいる人に限って、そうだった」
「そういう奴らも、今はちがう。破産して消えてなくなったのは別だが、生きのびた連中は皆、反省してるさ」
「反省なんかしてないわよ。自分は悪くない、時代が悪かったんだっていうばかりで」
「そういう客はくるか」
「くるわよ、たまに。クラブ時代、さんざん使ってやったのだから、ただで一杯飲ませろっていうの」
「飲ませるのか」
「本当に一杯だけね。二杯めは正規のお値段をいただく」
円堂は首をふった。たいしたものだ。もし委津子とつきあっていたら自分はどうだったろう。
もう少しまともな生活を送っていたかもしれない。だが長くはつづかなかった。自分が捨てられて終わり、こうして向かいあって飲む関係にはなれなかった。
「何を笑ってるの」
委津子が訊ねた。
「笑った? 俺が?」
「そうよ。今黙って笑った。何かおもしろいことを考えていたでしょう」
委津子が円堂の目をのぞきこんだ。円堂は笑いだした。
「いえないね」
「何よ、嫌な人ね。わかった。君香さんのことを思いだしていたんでしょ」
「まったくちがう」
「嘘よ」
「本当だ」
「じゃ、いいなさいよ」
円堂は首をふった。いうわけにはいかない。この場がぎくしゃくしてしまう。「マザー」で軽口を叩きながら飲む時間を失いたくなかった。
「感じ悪い」
いって、委津子は円堂のグラスに新しい酒を注いだ。そしていった。
「捜しにいけばいいじゃない」
「何を?」
「決まってる。二見会長の車。君香さんに会えるかもしれないわよ」
円堂は委津子を見つめた。
「会いたいのでしょ」
委津子はいった。
「別に今さら──」
いいかけたのを委津子はさえぎった。
「よりを戻したいとか、そういうのじゃないことはわかってる。でも会って、いいたいこととか訊きたいことがあるのじゃない?」
さしだされたグラスを円堂は口に運んだ。
「ほら、吸いこみがいい。図星だ」
「中村に誘われた。いっしょに捜そうって」
「中村さんて、中村先生?」
中村が小説家になっていることを教えると、いつからか先生と委津子は呼ぶようになった。本を読むのが好きで、物書きを無条件で尊敬しているのだ。
「そうだ。二見に貸しが残っている、というんだ。それを回収しよう、と。生きている筈ないし、たとえ生きていてもできるわけないのに」
「お金じゃないわよ。中村先生の本、売れているもの」
委津子が断言した。
「じゃあ何だ?」
「決着をつけたいのよ」
小説
晩秋行

あらすじ
居酒屋店主の円堂のもとに、バブル時代、ともに荒稼ぎをした盟友の中村から電話が入る。当時、「地上げの神様」と呼ばれ、バブル崩壊後、姿を消した二見興産の社長の愛車で、20億円の価値があるクラシックカーの目撃情報が入ったという。20億円の車をめぐってバブルの亡霊たちが蠢き出す、大沢ハードボイルドの新境地。
晩秋行(4/6)
関連記事
おすすめの試し読み