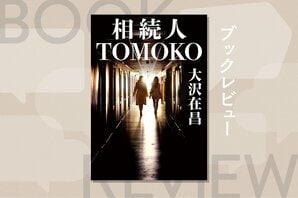「決着?」
「あなたとは理由がちがうだろうけれど、中村先生も自分の昔に決着をつけていない。奥さんに捨てられたのでしょう?」
「金の切れ目でな。別に未練はない、と思うぞ」
「じゃあ、あなたは未練があるの? 君香さんに」
「それは、ない」
「だけど思いだしては楽しんでいる」
「楽しんでる? 俺がか」
「そうよ。男って本当に馬鹿だなって思うのが、昔の女の思い出にひたるところ。とっくにあんたのことなんか忘れて楽しくやってるっていうのに、あいつは今でも俺に惚れてるなんて、感傷的になる。そういうのでお酒を飲むのが大好きなのよ」
「ひどいことをいうな」
「女は昔の男のことなんてこれっぽっちも思いださない。年をとったら、男よりいいものがたくさんある。おいしいものを食べたり旅行にいったり、年なりのお洒落をしたり。男はさ、いつまでも甘い思い出にひたってる。ま、安あがりといえば安あがりよね」
「そんなことはないだろう。思い出酒を飲ませて金をとるのだから」
円堂がいうと、委津子は舌をだした。
「だってちょろいんだもの。『今でもあの人のこと好きなんでしょ』って水を向けるだけで、勝手に喋り始めてボトルが空いちゃう。あんなことやこんなことをしてくれた、いい女だったって。ひとりで気持よく語りだすからね。こっちはハイハイって頷くだけで儲かっちゃう。あげくの果てに『あいつも俺にまだ惚れてるよ』って。そんなわけないじゃない。あんなことやこんなことは、次の男にも今の男にもしてるし、あんたのことなんてこれっぽっちも覚えていませんからって」
「そういえよ」
「駄目よ、お店が潰れちゃう。潰れたら『いろいろ』の女将さんにしてくれる?」
「そんな給料払えるわけないだろう」
委津子はにらんだ。
「意味がちがう。あたしはね、円堂さんの思い出酒にだけは、つきあうのが嫌なの。だから決着をつけてほしい」
「どう決着がつくんだ?」
「そんなのわからない。二見会長も君香さんも、生きているかも死んでいるかもわからない。でもその車を捜せば、どうなったのかはわかるのじゃない? それだけでもひとつ、決着をつけられる」
「君香が生きていて、よりを戻すって俺がいいだすかもしれないぞ」
「そのときはそのときよ。円堂さんがそうしたいならすればいい」
「強いな、お母さんは」
円堂は首をふった。
「あなたがずっと引きずっているのを見たくないだけ。二見会長が消え、君香さんがいなくなって、本当は何があったのか知りたくてしかたないくせに、痩せ我慢しているのが丸わかりなの」
円堂は首を傾げた。
「俺、そんなに思い出話したかな」
「してないわよ。思い出になんかなってないのだから」
思わず委津子を見つめた。
「今の円堂さんは不幸じゃない。それは確か。お店がうまくいって、あたしもよかったって思っている。でも、明日もし死んじゃうとしたら、気にならない? 思い残すことはないといえる?」
「思い残すことがない奴なんていないだろう」
「理屈をいわないで。あたしはあなたの話をしているの。君香さんに何があったのか、知りたいのでしょう」
「わかった、わかった。勘弁してくれよ」
「ここにきたのは、自分の気持を確かめたいから。昔話の相手ができる人はあたししかいない」
委津子の声は厳しかった。
「参ったな」
円堂は息を吐いた。
「煙草、あるか」
「駄目。何年も前に止めたでしょう」
「一本だけだ。気持の整理をつけたい」
委津子はかがみ、カウンターの下から封の切られたメンソール煙草の袋をとりだした。
「はい。お客さんの忘れもの。一本だけよ」
委津子は煙草を吸わない。あの時代、煙草を吸わないホステスはほとんどいなかった。
円堂は一本つまみだした。カチリ、とライターの火を点し、委津子がいった。
「吸い終わるまでに決めてよね」
円堂は頷き、煙を吸いこんだ。喉が苦しく、むせた。ニコチンの苦みを感じ、すぐ口から離す。
「マズい」
「やめたあとは、おいしかった記憶しかないけれど、実際吸ったらおいしくない」
「何だよ。思い出といっしょっていいたいのか」
「よくおわかりで」
委津子はにたっと笑った。
「考えるよ。店のこともあるしな」
円堂はいって、灰皿にひと口吸っただけの煙草を押しつけた。
「ケンジさんに任せられるでしょ、何日間かなら」
ケンジを一度連れてきたことがあった。あの子はいい、と委津子はいった。口が重くて腰が軽い、理想の板前になる、というのだ。
下戸だ、という点も気に入ったらしい。酒で舌が鈍らないから料理の味がかわらない。
飲みながら作ってしくじった料理人はいっぱいいるというのだ。酔って、上客とそうでない客をあからさまに差別する。そういう店は必ず駄目になる、というのが委津子の持論だった。
「相談してみる」
円堂は答えた。
3
「マザー」をでたのは午前二時過ぎだった。銀座の飲み屋街では午後十時から午前一時までのあいだ決められた乗り場以外ではタクシーが拾えないが、この時間だと通りのあらゆるところに空車がいて、客を捜している。
下手な路地で拾うと、表通りにでるまで空車の渋滞に巻きこまれる。中央通りまででることにして、円堂は花椿通りを歩いていた。
「円堂さん! 円堂さんでしょう!」
不意に声をかけられ、足を止めた。明るいベージュのジャケットを着た白髪頭の男が通りの反対側からこちらを見ている。
赤い派手な眼鏡に見覚えがあった。名前は知らないがクラブ「モンターニュ」のポーターをやっていた男だ。ポーターとは、白タクの手配をしたり、客やホステスの車を自分が“縄張り”としている路上に止めて手数料を稼いでいる連中だ。バブルの頃、銀座の街には無数のポーターがいた。客の車を預かり、駐禁を切られないように見張るだけで、毎日チップこみで何万という稼ぎを得ていた。
中にはクスリや女の手配をする者もいて、そういう人間はどこかの組に片足をつっこんでいた。
バブル崩壊とともにポーターにチップを弾む客も消え、その大半がいなくなった。
「ああ。久しぶり」
「モンターニュ」は委津子がずっとナンバーワンだった大箱のクラブだ。今も並木通りの八丁目にある。
「ごぶさたしています。お元気そうで」
ポーターは頭を下げた。二見が乗るロールスロイスが止まるとすっとんできて外から扉を開け、
「二見会長、こんばんは!」
と大声で挨拶をしたものだ。そして入る店を聞くと、ビルのエレベータのボタンを押し、
「いってらっしゃいませ!」
と叫ぶ。
「大声だすなよ」
といいながらも満更でもない表情で、二見はチップを渡していた。毎晩のことだったので覚えている。
「何とかね。もう銀座なんてこられる身分じゃないけどな」
「またまた。もっといらして下さいよ。寂しいじゃないですか」
円堂は苦笑し、
「あなた、いくつになった?」
ポーターに訊ねた。自分と同じくらいの年だろう。
「え、年ですか。恥ずかしいな。六十八です。先日、孫が生まれました」
「俺より六つ上か。それは失礼しました」
「何をおっしゃっているんです。懐かしいですね、あの頃が。二見会長とよくおみえになっていて──」
いいかけ、
「そういえば、先日、会長と会ったって者がいました」
円堂の顔を見つめた。
「二見さんに? 嘘だろう」
「あたしと同じポーターだった人間なんですが、今は田舎に帰って蕎麦屋をやってるんです。そいつの店に二見会長がきたって」
「まさか」
ポーターはあたりを気にするように声をひそめた。
「会社が飛んで、会長も行方不明になったじゃないですか。正直、生きてはいらっしゃらないだろうなって。何人もいましたから。毎晩銀座でお会いしていて首を吊った方が」
「本当に二見さんだったのか」
「そいつも訊こうと思ったけどやめたそうです。もしそうだとしても認めたくないだろうって。あれだけ羽振りのよかった人ですから」
「その人はひとりできたのか」
ポーターは頷いた。
「おひとりだったそうです。そいつの店はバス停の前にあって、盛りを食ったあと、二見さんはきたバスに乗っていったって」
「どこなんだ?」
「福島の南会津です。山の中ですよ」
「南会津」
「会津高原の『高取』って店です。円堂さん、二見会長とはその後──」
円堂は首をふった。
「いなくなってからは、それきりだ。亡くなったと思っていた」
「え、じゃマズいこといっちゃいましたかね」
ポーターは首をすくめた。
「いや、俺は二見さんに恨みはないよ。あったとしても今さらどうしようもない。二見さん、ていうか、その似た人ってのは、どんな感じだったんだ?」
「そこまではわからないですけど、何なら訊いてみますか──」
携帯をとりだしかけ、舌打ちした。
「あ、もう寝てるな。田舎暮らしなんで」
「会津高原の『高取』さんだね」
「ええ、ですけど──」
「大丈夫、迷惑はかけないよ」
「いや、そんな迷惑なんて……」
ポーターは口ごもった。
これも縁か。円堂は思った。中村が二見の車を見た者がいると知らせてきた日に、昔馴染みのポーターから二見が生きているらしいという噂を聞く。
自分の昔に決着をつけろ、という委津子の声がよみがえった。
小説
晩秋行

あらすじ
居酒屋店主の円堂のもとに、バブル時代、ともに荒稼ぎをした盟友の中村から電話が入る。当時、「地上げの神様」と呼ばれ、バブル崩壊後、姿を消した二見興産の社長の愛車で、20億円の価値があるクラシックカーの目撃情報が入ったという。20億円の車をめぐってバブルの亡霊たちが蠢き出す、大沢ハードボイルドの新境地。
晩秋行(5/6)
関連記事
おすすめの試し読み