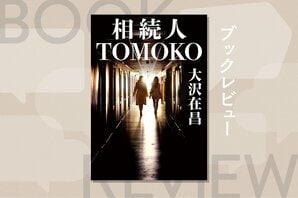2
居酒屋「いろいろ」は、中目黒の駅に近い雑居ビルの地下にある。六時開店、十時半ラストオーダー、十一時半閉店だが、十一時過ぎまで客が残ることはめったにない。
店を始めた九年前に比べても、大酒を飲んだり長っ尻の客は減っている。
一部の人間を除けば、夜遊びに関して皆おとなしくなっている、というのが円堂の印象だ。
この二年は手伝いのケンジの成長もあって商売は順調だった。お運びのユウミも客に人気がある。下積みの舞台女優だが、すれたところがなく、黒髪でピアスも入れていない。
ケンジは三十二、ユウミが二十二だ。円堂の目には、互いを憎からず思っているように映る。が、男女のことだ。もつれてどちらかが辞める、というような流れにはなってほしくない。といって、つきあうなというのも、いくら店主とはいえ横暴だろう。
ケンジは前に勤めていた鮨店でのいじめに耐えかねて「いろいろ」の求人に応じてきた。
チェーンの大型鮨店で、話を聞くと、板場は厨房というより工場のようだった。先輩料理人によるいじめが横行していて、口の重いケンジは標的にされたらしい。
暖簾をおろしたあと板場の片づけは円堂の、カウンターと小あがりの掃除はケンジとユウミの仕事だ。
解放感からじゃれあうケンジとユウミに、微笑ましいものを感じながら、
「お先に」
といって円堂は店をでた。店の鍵はケンジにも、もたせてある。最近はちょくちょくひとりで仕入れにもいかせていた。食材への目を養わせるためだ。駄目なものを買ってきたら、なぜ駄目なのかを教える。
昔の料理屋では、若い板前が悪い品を仕入れると、花板と呼ばれる板長が理由もいわずゴミ箱に叩きこんだという。
自分は本職の料理人ではない。ただの好きが昂じて包丁を握るようになった素人だ。そんな人間が、目下の者につらく当たるのは論外だと思っている。
厳しい修業を経て、技術や目を身につけたわけではないのだ。所詮、真似ごとにすぎない。本来なら、年を食っていても板場で一から修業すべきだったのを飛ばして、店を始めた。
初めの何年かはほぞをかむことも多かった。
なりがよくいかにも食通然とした客がくると緊張し、ひと口だけで箸をおかれて愕然としたこともある。
不味いなら不味い、といってもらえるほうがよかった。何がどう不味いかを訊ね、今度に役立てられる。
「お口に合わないようでしたら、お勘定はけっこうです」
と頭を下げると、
「私からはとらないが、他の客からはとるのかね」
蔑んだように返されたこともあった。
万人が旨い、と感じるものなどない。塩加減、脂ののりかた、火の入り具合、肉、魚、野菜すべてに人の好みがある。名店といわれる店は、味のパターンを守り、変えない。それを好まない客であっても、不味いとは決して思わせない。
そこに到達するのは不可能だと円堂は思っている。修業を積んだ料理人でも、ごくひと握りしか、たどりつくことはできない。
プロの料理とは再現性なのだ。
人間なのだから、日々の体調は変化する。
暑い、寒い、乾いている、湿気がある、どんなときでもプロの料理人は同じ味をだす。だが実はそれは同じ味ではない。
汗をかく夏は塩気を少し強くし、外が冷える冬は熱いものを熱いうちにだすことを心がける。
その境地に達する料理人には母性が必要だ。
上手に作るのではなく、おいしく作ろうという気持は、子供に対する母親の気持に近い。
女房も子供もいない円堂が、客に対し母親のような気持で料理を作っているといったら、常連客ですら不気味に感じるにちがいなかった。
足りない技術は気持でカバーする他ないのだ。
店をでた円堂は、徒歩で十五分ほどの自宅マンションに向け歩きだした。
が、中目黒駅の高架を見て気持がかわった。地下鉄日比谷線の北千住行き電車に乗りこむ。銀座で降り、七丁目の雑居ビルにある、委津子の店に向かった。
委津子とはバブルまっ盛りの一九八八年に銀座のクラブで知り合った。ずば抜けた美人ではないが頭が切れ、腹がすわっていた。有名な大箱のナンバーワンだった。
当時の銀座でナンバーワンになるホステスは、抜群に美しいか頭が切れるかのどちらかだった。
近くで見ているだけで男を幸せな気持にする美人がこの世にいることを、円堂はそのとき知った。
頭の中身など空っぽでもいい。ただ隣りにすわり笑いかけられるだけで、いくら使っても惜しくないと思わせられるような美女だ。
さもなければ談論風発、どんな話題にもついてきて、出過ぎた発言は決してせず、客が店に求めるものをいわれる前に提供する。接待をするなら、この店のあの女に任せるに限ると客に信頼される。
委津子はまさにそういうホステスだった。大手銀行、ノンバンクを問わず金融機関の客から全幅の信頼を寄せられていた。
バブルが弾けたとき、相当の売りかけをくらった筈だが、それでも生きのびた。
銀座のホステスは、売れっ子になると「売り上げ」といって、客の払いに責任を負うようになる。ひと晩に何十万と使う客はその場で支払いなどしない。売りかけというツケにして、月末などに精算する。
もしその客がパンクすれば、店への支払い義務はホステスに生じる。「売り上げ」になれば給料は客の使う金に連動して上がる。稼ぐホステスは月に一千万を超える。その一方で客へのつけ届け、若い「ヘルプ」のホステスへの気配りで、でていく金も多い。さらに立場に応じて、着物やドレスも安物は着られない。稼いでも、でていく金は多く、太客が飛んだとたん、何千万という売りかけを背負わされ、クラブからソープランドへと職場をかわらざるをえなくなることがある。
もちろん消える女もいる。店への借金を払わず、ほとぼりがおさまった頃、他の街でホステスを始める。
が、水商売の世界は狭い。銀座をばっくれた女が、薄野や錦、新地、中洲などで働きだせば、必ず見つかり古巣へ知らせがいく。
一方でソープランドで稼いで売りかけを完済した女が銀座に戻ってくることもある。ソープにいたとは決して口にしない。
銀座でいくら口説いてもものにできなかった女がソープにいるとわかれば、大喜びでいく客もいるだろうが、ソープで働いていることは決して教えない。
なぜなら、ソープランドで払う金額を、銀座のクラブではすわっただけでとるのだ。抱いた女に、手も握らないでそんな金を払う男はいない。だからソープで見たことがあるという客がいても、他人の空似で押し通す。ソープランドと銀座の高級クラブでは客種が異なるので、思いのほかばれない。