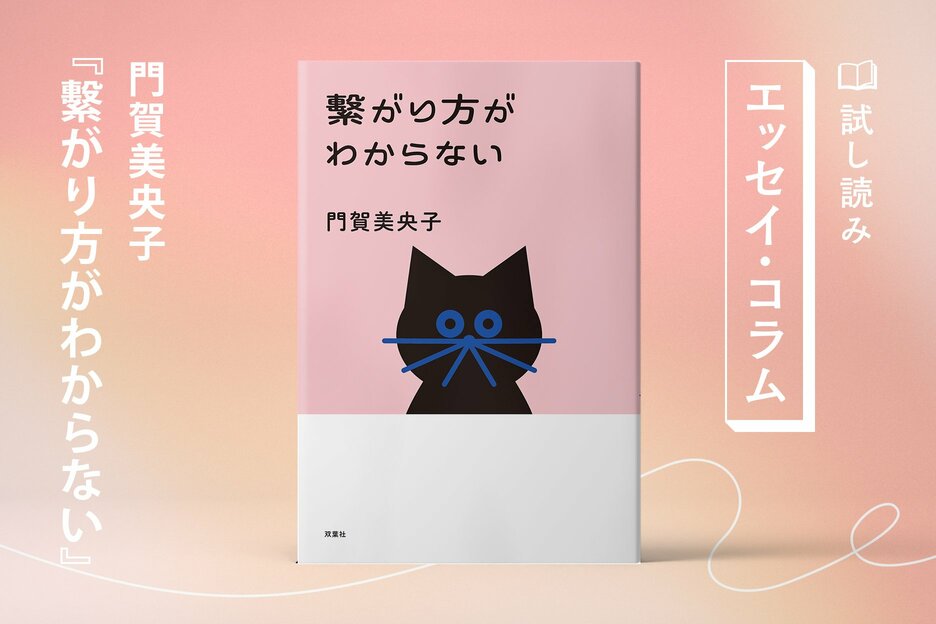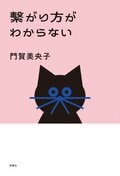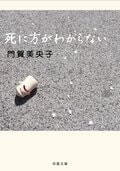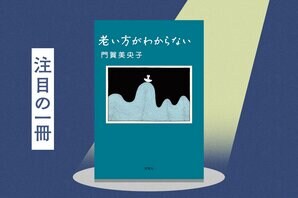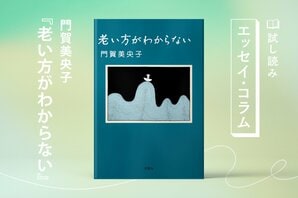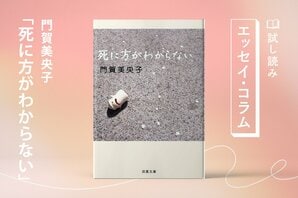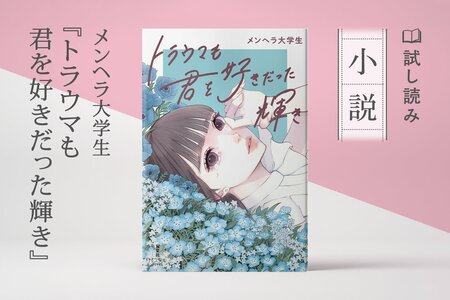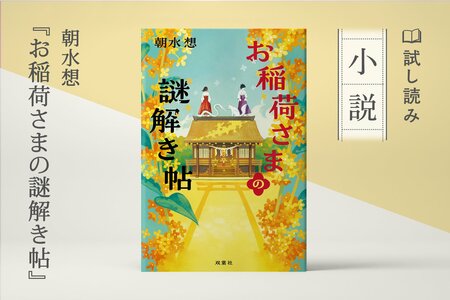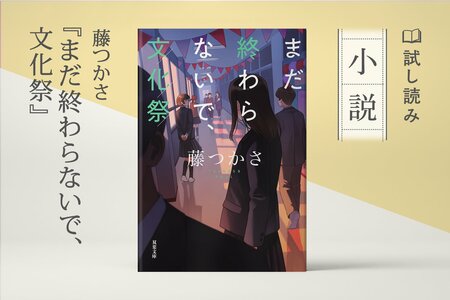言葉を整理しておこう
こうしてまた新たな探索の旅を始める運びになったわけだが、一歩踏み出す前にまず「ひとり」を巡る言葉や「孤独」と「孤立」の違いなど、前提となる情報を確認しておきたい。整理しておかないと、私の頭が混線するからだ。なにぶん作りが雑なので。
さて、この点について、様々な孤独関連書籍などに書かれていることをまとめると、だいたいこんな感じになりそうだ。
ひとり
一人──シンプルに数を示すために使われる表記。
独り──配偶者や友人などの親しい他者が身の回りにいない状態。
孤独
仲間や身寄りがない状態。さびしさやわびしさを伴ってイメージされることが多いが、あえて独りを選ぶ、あるいは他を寄せ付けない境地にある者も含まれ、後者は孤高とも表現される。
この点について、現代英語ではロンリネス(loneliness)とソリチュード(solitude)が同じく独りを指しながらも異なる概念と理解されている。いわく、ロンリネスもソリチュードも主観的な「独り」ではあるが前者は苦しみの元となる不本意な悪い独り、後者は自ら選んで楽しむ独り、であるそうな。
孤立
社会的な繋がりを完全に喪失した状態。語尾に「無援」を足すとさらに絶望的なイメージが増す。一方、「孤立」を英訳するとisolationと出てくるが、こちらは客観的/物理的なひとり(ひとつ)を指すのみで、ロンリネスのような感情的意味合いは持たないと説明されることが多い。
ぼっち
ひとりぼっちの語尾を抜き出した新しい俗語。独りの状態をより強調したい場合に多用される。蔑視あるいは自嘲的ニュアンスを含む。
おひとりさま
もとは飲食店などで一人客を指す言葉だったが、近年はあえて一人行動をする人や、何らかの理由によって一人で生活している人などを指す。比較的ポジティブな文脈で使われることが多いものの、揶揄用語になる場合もある。
ざっとこんなところだろうか。
このように、「集団から外れたひとりの状態」を示す言葉はとても数が少ない。
「独身」は婚姻関係の有無を示す言葉だし、「単身」や「単独」は数的に一人を意味するだけだ。「はぐれ者」や「一匹狼」は最近あまり使われていないし、「はみ出し者」や「異端児」になるとニュアンスがズレてしまう。
さらに言えば、日本語でこの問題を語る際に面倒なのがlonelinessもsolitudeもisolationも全部「孤独」に含まれてしまう点である。望む孤独も望まない孤独も社会的孤立もすべてがごっちゃになっているので、時として会話が成り立たなくなってしまうのである。
たとえば、私にとって孤独とはsolitudeではあるが、社会的にisolationではない状態だ。しかし、世間はlonelinessもしくはisolationと理解するのだろう。
そりゃ話が盛大にすれ違うはずである。
しかしながら、おそらく独りをsolitudeにできるのは生まれ持っての性質によるのだろうし、積極的に楽しむ領域に到るにはある種の才能が必要なのだ。
ま、言ってみれば「選ばれし者」って感じ? と、無駄な優越感が湧いてきたりもするのだが、社会的にはまったく意味のない選民意識である。しかも、一旦isolationに陥ってしまうと、容易にlonelinessに化けてしまいかねない。
しつこいが、私は独りが好きだ。
けれどもそれは、なにかあった時に少しぐらいなら頼らせてくれそうな人たちが周囲にいるからだ。また、前著二冊を書いたおかげで、利用できそうな社会制度も知ることができた。つまり、なにかあったとしても即デッド・エンドにはならない安心感があるがゆえである。
これはつまり「つながり」がある状態といえる。
だが、将来的に繋がりが失われ、社会的孤立に陥ったらどうなるだろう。
たぶん、のんきに「独りが好き」とか言っていられなくなるだろう。だって、想像するだに怖いではないか。「助けて!」と叫んでも誰も振り向いてくれない状況なんて。
死ぬまでsolitude「独りが好き」でいたいのであれば、isolation「社会的孤立」だけは避けなければならない。
そのためにできることはなんだろう。
そのために何を考えておくべきなのだろう。
そこを明らかにするのが旅のスタートとしては妥当だろう。
そこで私自身の頭の中を整理すべく、脳内に散在する人格を一同に集め、モンガーズ大会議を開くことにしたのである。
この続きは、書籍にてお楽しみください