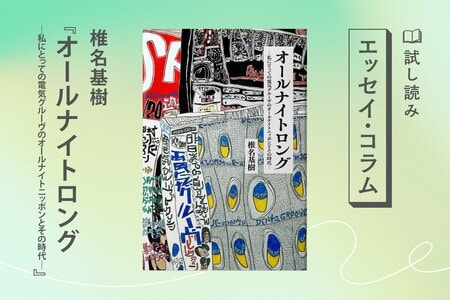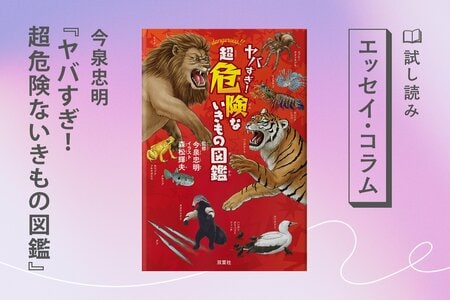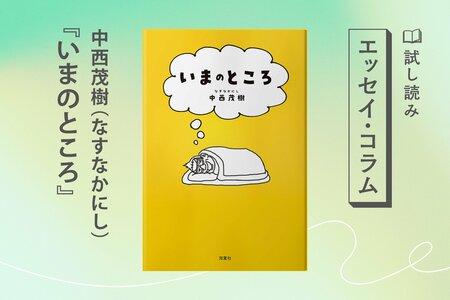「売れる」
ナイツとすゑひろがりずのシステムの共通点
過去のM‒1を振り返ると、南海キャンディーズやオードリーといった優勝はしていなくとも「売れた」芸人が何組もいます。
19年でいえば、かまいたち、ぺこぱ、すゑひろがりずは「売れた」芸人でしょう。
かまいたちはずっと面白かったんです。18年と19年で何が変わったかと言えば、18年の「ポイントカード」は山内くんの漫談に近いネタで、濱家くんのツッコミが輝きにくかったけど、19年の「UFJ」は山内くんの主張の強さがありつつ濱家くんがいないと成立しないネタでした。加えて、濱家くんが面白くて器用な芸人ということが全国的に浸透しはじめていたこともあったので、「UFJ」はハマったんだと思います。
そもそも「UFJ」は昔からやっているネタで、「絶対にウケる」とわかっているから、「どこでどうウケるか」をイメージしながら進めることができたはず。僕らもそうですから。普段やっていないネタだとハマらないことも多くて、いつものネタのほうがやっぱり強い。「絶対にウケる」ネタに2人の成長が乗っかったので爆発したんでしょうね。
すゑひろがりずのネタは「正解をズラしていく」という意味でナイツとシステム的には近い。僕らが「ヤホー漫才」で宮﨑駿作品を言い間違えていくように、すゑひろがりずも宮﨑駿作品を古い言葉に変えていくことができると思うんです。
すゑひろがりずのようなネタをやっていたコンビは過去にいたかもしれませんが、彼らは服装や小道具まで含めて「振り切った」。普通の芸人はそこまで振り切れませんから。商品としてわかりやすくパッケージされているので、バラエティ番組に起用されやすいんです。ぺこぱもパッケージの強さがありますよね。
ぺこぱは松陰寺くんの「受け入れるツッコミ」が時代に合っていたんじゃないでしょうか。ただ、知らないで観たほうが面白いスタイルなので、ずっと続けていくのは大変じゃないかな、とも思います。
オードリーが賢かったのは、08年のM‒1で準優勝すると、翌年は出場しなかったこと。そうすることでネタの鮮度を保つことができたんです。だからといってネタをやめるんじゃなくて、テレビやライブで定期的に漫才を披露しているので、世間から漫才師という印象が消えないんだと思います。
ぺこぱもオードリーと同じタイプだと思ってました。あれだけバラエティ番組に出演していれば、「売れる」という本来の目的は達成したはず。それでも20年のM‒1に参加したということは、本人たちにどうしても挑戦したいという気持ちがあったのでしょう。
M‒1に関しては「売れる」ことだけが目的じゃない部分もあって。僕自身もM‒1は優勝したいから芸歴制限いっぱいまで参加したんです。でも、『THE MANZAI』は11年に準優勝したことで目的を果たしたと思ったので、翌年は出場しませんでした。世間的に面白いと認められたことで満足できたんです。
M‒1の決勝は「スベってもいいから立ちたい」と思わせるくらい特別なステージなんです。味わったことのない緊張感の中、豪華なセットでネタをするという、唯一無二の世界ですから。番組のクオリティだって、どの賞レースより高い。
審査コメントも番組を面白くする要素だと思ってます。ありきたりなことを言っても面白くない。だから、上沼恵美子さんだってあそこまで言うんです。そもそも審査員のコメントの時間が以前よりも長くなってます。
視聴者が審査員としての僕に求めているコメントを考えると、笑いではぐらかすのも違うのかなって。紹介される時にボケることはあっても審査でボケることは基本的にありません。万が一、出場している芸人とボケが被ったら大変ですから。
ただ、自分の中で審査の基準は少しずつ変わってきているのかもしれません。巨人師匠(オール阪神・巨人)は稽古量の話をよくされていますが、僕はそこまで重視していなかったんです。だけど審査をしてみると、4分の間に高い熱量を保っていないと点数は上がらないことがわかりました。
19年に優勝したミルクボーイには熱量を生み出す稽古量を感じたんです。
毎年、覚悟を持って審査してます。「あの審査は違う」といった声を気にしていたらできませんから。漫才をやりにくい部分はあるけど、誰かが審査員をやらなきゃいけない以上、M‒1にお世話になった僕があの席に座ることは「務め」だと思ってます。
話を戻すと、「M‒1で売れる」には「ベタ」の強さも関係していると思います。かまいたちの「UFJ」もすゑひろがりずのネタも伏線回収するような難しいネタとは違って、わかりやすいネタじゃないですか。芸人って年数を重ねると、関係性で笑わせようとしてしまうんです。僕らも独演会で内藤剛志さんのモノマネをやって笑わせますけど、それって僕が『警視庁・捜査一課長』(テレビ朝日系)に出ていることが前提になっているので、初見の人は意味がわからない。それは「ベタ」じゃないですよね。
技術を身に付けた状態で「ベタ」をやることが一番ウケるのかもしれません。特に吉本興業は劇場があって営業も多いから、「ベタ」をブラッシュアップできる。それが吉本の芸人がM‒1に強い理由のひとつだと思います。
「笑辞苑」は全3回で連日公開予定