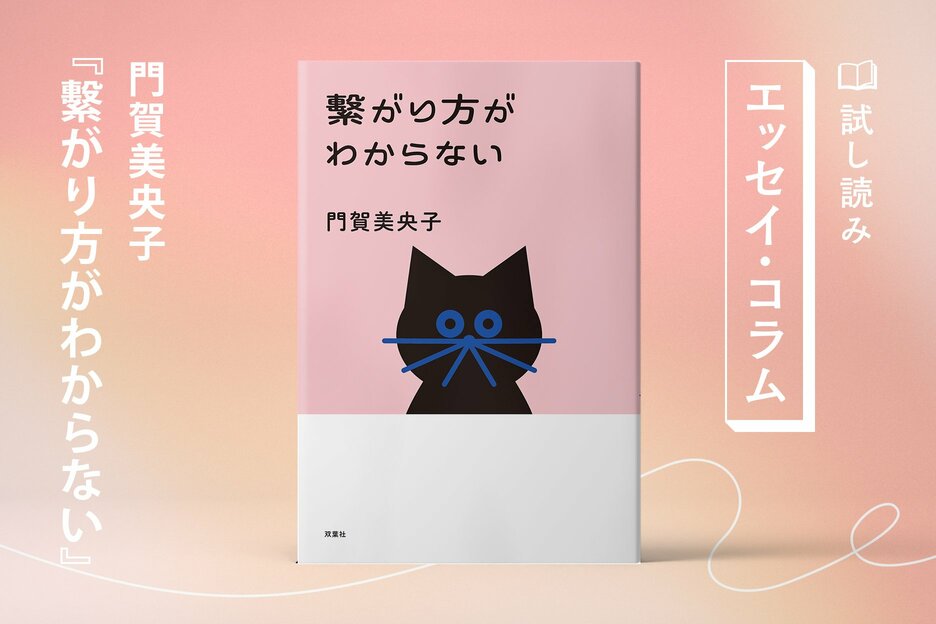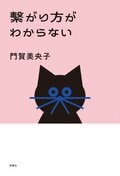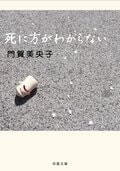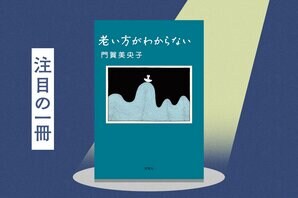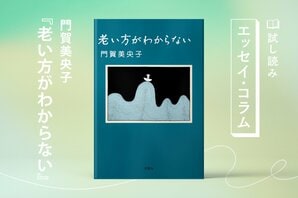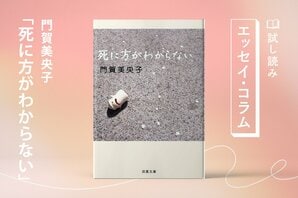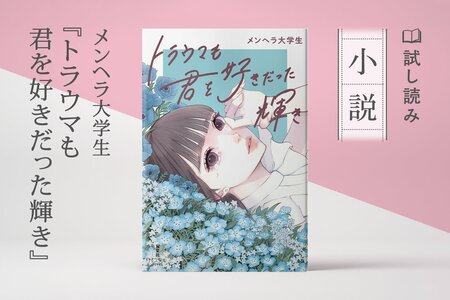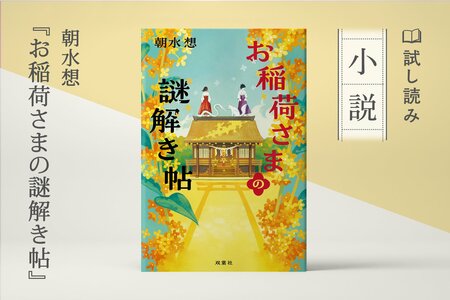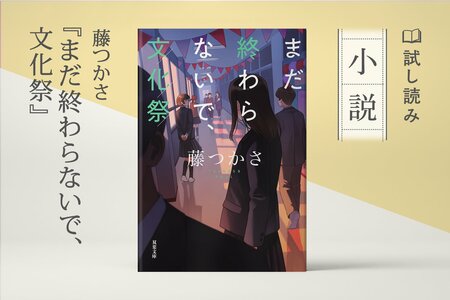社会が独り者を許してくれない?
こうした風潮を後押ししたのは政府の少子化対策だろうと推察する。二〇〇七年に生まれた「婚活」なる言葉が徐々に広がり、二〇一三年には「婚活・街コン推進議員連盟」ができた。さらに、ネット上での出会いサイトの利用が一般化し、二〇一二年にはマッチングアプリがリリースされ、スマートフォンが一人一台の時代になった二〇二〇年代からはネットde婚活は珍しくもなくなっている。恋愛市場なる気持ち悪い言葉が盛んに使われ始めたのもこの頃からだったろうか。電車に乗れば婚活広告を見ないことはなく、スマホのマッチングアプリは花盛り。テレビでは相も変わらず恋愛ドラマがのべつ幕なしにオンエアされ続けている。親から結婚への圧力があって云々みたいな導入パターン、もうそろそろ飽きないのかしら? と私なんぞは思うのだが、これこそが結婚適齢期のリアリティーとする共通認識は確固たるものなのだろう。
さらに、コロナ禍で人々が隔離を余儀なくされるようになると、ますます家族の良さが強調されるようになった。この間、実は家族間のDVや児童虐待の相談数が増えているにもかかわらず、だ。まるで、その事実を消し去りたいがごとくの勢いで「家族っていいね!」が蔓延した。
しかも、それだけでは終わらなかった。
ポリティカル・コレクトネスを前提とする現代的な“優しさ”が発動した結果、血縁や婚姻による家族が作れないなら疑似家族的なパートナーを作ればいいよ! とのありがたいアドバイスが社会に広がりつつあるのである。
なんだかもううんざり。
いや、私とて家族やパートナーの大切さはよくわかっている。「自分以外の誰か」が人生に豊かさをもたらし、彩りを添えることは否定しない。それに、独りでできることには限界がある。人間は集団で生きることを選んだ社会的動物だ。生物学的にも「ぼっち」が最適解ではないのは明らかである。
けれども、勢い余って「独りでいる人はかわいそうな孤立者です! 社会悪です! 弱者です!」みたいな言い方をされてしまうと「いやあ、それはちょっと勘弁してよ」となるのだ。
わかってくれとは言わないがそんなに俺が悪いのか、ってやつである。
社会的繋がりは拒否しないけれども、別に家人や子供や疑似家族は求めない。
そんな人間がいたらおかしいか?
しかし、繰り返しになるが、日本社会では社会的繋がりの第一を婚姻もしくは血縁関係に置いている上、それらがない場合も保証人なる謎の第三者が求められる。よって、それを所持していない/できない人間はなにかと不便が生じるようシステムが成り立っている。独り者には近頃流行りの“合理的配慮”とやらさえ用意されていない。その不便さが社会に対する居心地の悪さの源になり、あげくこの社会には居場所がないような気にさせられているのだ。
とはいえ、私自身は比較的最近まで、社会に対してそれほど居心地の悪さを感じてはいなかった。なにぶん人にどう見られているかに関しては鈍感であり、かつどう見られていたところで気にしない質だからだろう。
けれども、前々著、前著で、社会制度が徹底して独り者を無視している現状を知ると、さすがにのんびり気分も消えてきた。一度気がついてしまうと、まるっきり無視もしづらい。知らないうちにできていた背中のデキモノに一度でも触ってしまうとその後はなんだか気になってしょうがなくなるあの現象と同じだ。
よしんば、心情面では無視できたとしても、現代を生きる一市民である以上、制度面ではなんらかの形で対応せざるを得ない部分もある。本来なら、社会制度を独り者に適応させることが肝要だ。独りが独りのまま社会に居場所を確保し、独りの人生を楽しく全うできる社会にしたい。それが私の望みだ。だが、皮肉なことに、それを独力で実現するのはほぼ不可能である。
さて、どうしたものか。
また考えなければならないことができてしまった。困ったことである。
「繫がり方がわからない」は全4回で連日公開予定