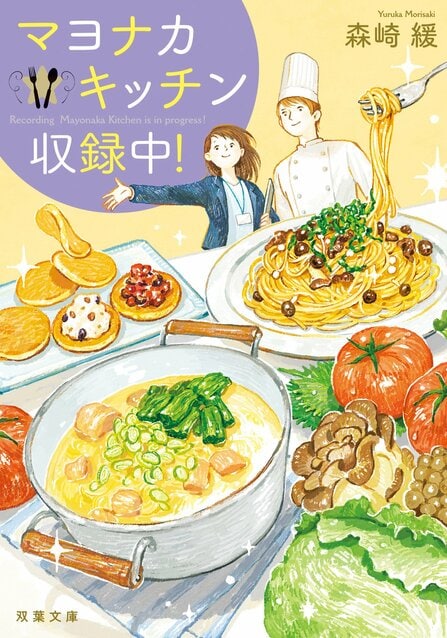母は、私がキッチンバサミで料理することをよく思っていなかったようだ。
『みっともない、ちゃんと包丁を使いなさい。私が元気になったら料理を教えるからね』
でもその約束は叶っていない。病気に倒れた母は、入退院を繰り返した後に四十代半ばで亡くなった。私が二十歳頃の話だ。
私は三十五になった今でも、キッチンバサミで料理を作り続けている。母の言う通り、みっともないのだろうと思うから、妹と父以外の前では料理をしたことがない。もっともあのケーク・サレもパプリカやズッキーニはハサミで切ったものなのに誰にもバレなかった。
母を亡くした私は、二十二の時に就職の為、上京した。
妹の華絵も、こちらで進学したいと言って高校入学前に東京へやって来た。地元に残った父から仕送りがあったとはいえ、新入社員の安月給で賄えるだけの家賃の部屋を探すしかなかった。幸い、妹の通学先は高校も大学も多摩地区で、彼女にとって通いやすい環境を整えることができたことだけはよかったと思う。
でも今となっては、ここに住み続ける理由もない。
引っ越そうかな。このアパートに素敵な思い出はたくさんあるけど、もっと会社に近い方が通勤も楽になる。仕事が立て込んでいる時も家が近ければ着替えを取りに戻るとか、シャワーを浴びに帰るとかできるし──お部屋探しの条件が仕事に関係することばかりなんて、私も他人のことが言えないくらいには仕事中毒になっているのかもしれない。
溜息をついた時、不意に手元のスマホが鳴った。
私はスマホを二台持っていた。会社で支給されている社用スマホと、自分で契約した私用のものだ。音もなく震えたので鳴ったのは私用の方だとわかり、安堵しながらディスプレイに表示されている名前を確かめる。
『華絵』
妹の名前を見て、ためらわず電話に出た。
「──もしもし?」
『あ、お姉ちゃん! もうお仕事終わってた?』
朗らかなその声を耳にしたのも何ヶ月ぶりだろう。華絵はこの部屋を出てからもマメに連絡をくれていたけど、大抵はメッセージのみのやり取りでこうして電話で話すことはなかった。完全土日休みで九時五時勤務の華絵と、撮影やロケなどの都合で休みがずれがち、残業も頻繁な私ではなかなか時間が合わないからだ。
「今日は割と早く帰れたんだ。ちょうど晩ご飯食べ終わったとこ」
『そうなんだ! いつもこのくらいに帰れたらいいのにね』
華絵はいくつになっても屈託なく笑う。その笑い声を聞くと、私の心もほんのりと温かくなった。彼女は今も幸せなんだろうと実感できるからだ。
「ところで、何か用だった?」
『あー……うん。お姉ちゃんに話したいことがあって』
彼女は電話越しにもわかるくらいはにかみ、改まった口調で続ける。
『実は私たち、結婚することにしたんだ』
結婚。
聞き慣れない単語が耳から入り込み、すとんと胃の底まで落ちてきた。
「結婚!?」
『そうだよ』
「えっ、と、い、飯島くんと!?」
『そう、智也と。やだな、他にいないよぉ』
同棲しているはずの彼氏の名前を口にすると、華絵は当たり前のように肯定してみせた。それもそうか。華絵は彼をとても大切に想っていたし、飯島くんも妹を大切にしてくれていた。
そう思うと、さざ波のように幸福感が満ちてくる。
そっか、結婚。ついに、華絵が。
「おめでとう! えーもうすっごく嬉しいよ! おめでたいじゃない! お祝い何がいい? 何がいい? お姉ちゃん奮発しちゃうよ!」
『え、そんな。気持ちだけでいいってば』
照れ笑いの後、でも、と彼女が続ける。
『一回会いたいとは思ってるんだ。ご飯でも食べながらさ。智也もお姉さんに改めてご挨拶がしたいですって。都合を合わせてもらえたら嬉しいんだけど……難しい?』
難しいものか。可愛い妹の為なら使わなさすぎて発酵しかけている有休だって使ってみせよう。あの千賀さんが駄目なんて言うとは思えないけど。
「全然大丈夫! 近いうちに社長と交渉するから、日取り改めて相談しようね。華絵は飯島くんとお店選んどいてよ。私が出すから、ちょっといいとこ食べに行こう!」
『本当? ありがとう……!』
約束をして電話を切った後、スマホをテーブルに置いた私は床に横たわる。
見慣れた照明器具の光が顔に降り注いできて少し眩しい。でもちっとも悪い気がしなかった。同じくらい、全身で幸福感を浴びている気分だ。
「華絵も結婚かあ……」
ずっと、あの子の幸せを願ってきた。母を亡くしてからはずっと、あの子を幸せにすることこそが私の役目だと思っていた。振り返ってみれば私自身は大したこともしていないけど、あの子はちゃんと自分の手で幸せをつかみ取っている。よかった。本当によかった。
でも、思ったより早かったかな。
そうでもないか、今年で二十七歳だ。結婚するのに早すぎる歳でもない。飯島くんも同い年だったし、きっとライフプランとか話し合った上で今と決めたんだろう。
そこまで考えて、はたと気づく。
「……私、もう三十五だ」
思わず飛び起きた拍子、膝をローテーブルにぶつけた。鈍い痛みに呻きつつ、それよりも現実的な自らの年齢に思いを馳せる。
妹が結婚を決めている一方、私には現在彼氏もおらず、結婚の予定もない。ライフプランなんて考える暇もないまま仕事だけに奔走している。正直結婚には憧れるし、したくないわけではないものの、そもそも今の状況では相手探しもままならなかった。過去に運よくできた歴代彼氏たちは、多忙にかまけて放置しているうちに音信不通になっているのが常だった。彼らは全然悪くない。
周りを見てみれば、うちの社内でもおめでたい結婚報告というものを滅多に聞かない。最新の結婚事例は社長の千賀さん夫妻で──なんと十年前の話だ。激務に次ぐ激務の業界とはいえ、さすがにご縁がなさすぎないか。
「もしかして、ぼちぼち焦った方がいい……?」
膝を抱えて呟いてみても、答えてくれる人はもちろんいない。
果たしてこのままでいいのだろうか。仕事に追われる毎日の先に待っているのが独り言ばかりの寂しい日々、なんてあまりにも空っぽすぎやしないだろうか。逆に言えば独り暮らしを謳歌している今こそ、彼氏の探し時と言えるのではないだろうか。
不意にそんな考えが浮かんだ、三十五の秋だった。
この続きは、書籍にてお楽しみください