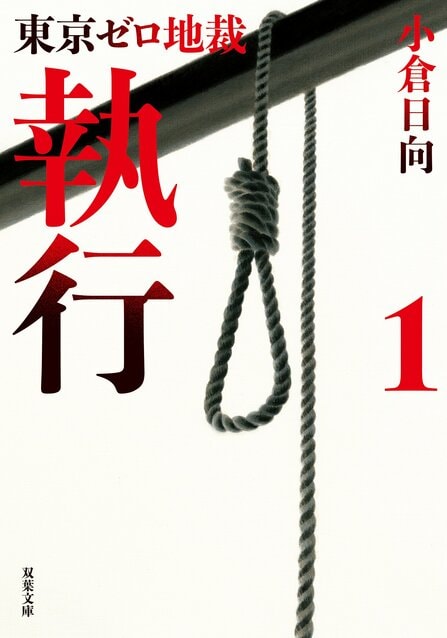被告たちが己の罪と向き合わなければ、娘はただの犬死にだ。けれど、彼らが心を入れ替え、真っ当に生きてゆく決心をしてくれれば、彼らの良心として我が子が生き続けてくれる気がする。
ふたりは忠雄にそう語り、被告たちの謝罪も受け入れた。悔恨の涙を浮かべた元少女もいたから、思いは通じたのではなかろうか。
しかし、ただひとり、倫華だけは和解に応じなかった。
民事裁判だと、弁護士など代理人が出席する場合が多い。ところが、訴えられたことが余っ程腹立たしかったのか、彼女は法廷に現れた。人証調べのとき以外にも、毎回。
倫華は美人だった。美貌を鼻にかけているところがあったと、他の被告の証言を聞かされていたが、なるほど、これならそうなるだろうと納得できた。
但し、見た目と内面はまるっきり逆である。むしろ表面的な美しさが際立っているぶん、性格の歪みっぷりは吐き気を催すほどであった。
自分はあの場にいただけで何もしていない、ただの傍観者だと彼女は主張した。他の被告の証言も、賠償金を減らすための嘘八百だと述べた。偽証はひとつとしてなく、すべて裏付けが取れていると告げても、頑として認めなかった。
そうなれば、被害者の少女や両親への謝罪など望めない。それどころか、佳帆が自殺したのは自分の醜さに耐えきれなかったからだと、冷笑を浮かべさえしたのである。
『あいつ、あたしの美貌に嫉妬して、遺書に名前を残したのよ。ブスの逆恨みね。とんだ濡れ衣だし、むしろあたしのほうが被害者なんだから』
人間の皮を被った悪魔がいるとすれば、きっとこんな姿をしているに違いない。そう思ったのは忠雄だけではなかったろう。佳帆の両親も、怒りに総身を震わせていた。
忠雄は倫華に、原告が求めた賠償金を満額認める判決を下した。ひとの命が奪われたのである。それでも安すぎるぐらいであった。
『バカじゃないの!? なんだってあたしが、あんなブスのためにお金を払わなくちゃいけないのよ!』
逆上した倫華がそう言い放ったのを、忠雄は今でもはっきりと覚えている。そんな彼女が、主張をすべて退けられた判決など、どうして受け入れられようか。
倫華は控訴したが、事実認定は覆らなかった。さらに最高裁への上告も画策したが叶わなかった。民事裁判では手続きに重大な瑕疵があるか、判決に憲法違反でもない限り、上告は認められないのである。
だからと言って、素直に賠償金を払うわけがない。遺族の元には、未だにびた一文届いていなかった。
「全然反省していないってことですよね。あんな酷いことをしたのに」
冷静で、感情をあらわにすることなど滅多にない沙貴が、目を潤ませている。書記官として、法廷や調停の場で被告たちの証言を聞いていたから、被害者の少女が何をされたのか、すべて知っているのだ。もちろん、倫華の暴言も。
忠雄とて、思いは沙貴と同じである。だが、胸の内を表に出すわけにはいかない。判事としての矜持というより、もうひとつの立場を悟られないために。
「まあ、ある程度は予想していたがね」
「やっぱり、被告に親を加えたほうがよかったんじゃないでしょうか」
「いや、被害者の両親の目的は、加害者たちに心から反省してもらうことにあったんだ。親の責任にして賠償金まで払ってもらったら、彼らは自分の過ちと向き合わずにいただろうね」
「でも……」
「それに、あんな子供に育てたんだ。北野倫華の両親も、仮に命じられたところでびた一文払わないさ」
そういう類いの親であることは、別のルートで調査済みだった。
放任主義どころではない。事件発覚後は完全に我が子を見限り、自分たちには関係ないという態度を見せていた。さらに、倫華が高校を卒業すると、さっさと独立させたのである。着火前に火の粉を振り払うがごとくに。
「この親にしてこの子ありってことですか。確かにそうかもしれないですね」
沙貴はなるほどという顔を見せつつも、当然ながら納得はできないようだ。
倫華が反省する態度を示さずとも、賠償金が支払われれば、多少なりとも慰めになる。加害者に償いをさせる証となるからだ。たとえそれが、親の金であったとしても。
おまけに、このまま逃げられるようなことになれば、遺族はさらに苦しむことになる。
「ところで、原告は強制執行の申し立てを考えているのかな?」
忠雄の問いかけに、沙貴は眉間に深いシワを刻んだ。
「どうでしょうか。被告のあの態度からして、何をしても無駄だという心境になっているかもしれません」
「そうか……」
「申し立てるには、相手の財産を調査する必要がありますよね。だけど、あの方たちには難しいと思います。ひとを頼む手はありますけど、そこまでの気力があるかどうか」
佳帆の両親が失意の日々を送っているのは、忠雄のところにも情報が入っていた。北野倫華が、現在何をしているのかも含めて。
親元から離れた倫華は、六本木のクラブで働いている。一般的な会社勤めであれば、勤務先に給与の差押えを求められるが、水商売となると難しい。
そもそも水商売は、税務調査で毎年ワーストの上位にあげられている。ただでさえいい加減なところが多いのに加え、従業員との雇用契約も、あって無きがごとしだ。報酬も給与所得なのか事業所得なのかすら曖昧である。
そんなところが調査なり差押えなりに、まともに応じるわけがない。
倫華は美人なだけあって、店ではナンバーワンらしい。お客からの贈り物も多いはず。ブランド品など売りさばけば、かなりの額になるであろうが、ああいう性格からして贈与税など関係ないと思っているのは確実だ。
現に、一等地のマンションで、かなり優雅な生活をしているそうだ。ホステスとして稼いだ金を、すべて自分のものにして。賠償金のことは、頭の片隅にも残ってはいまい。
(やっぱり両親も被告に加えるべきだったのか……)
忠雄は後悔しかけた。立場上、直接アドバイスはできないが、周囲の人間を使って働きかけるのは不可能ではなかったのに。
何より、倫華の親は資産がある。弁護士や裁判の費用は出していたようだし、預金や不動産の差押えができたはず。
だが、原告はそんなことを望んではいなかった。誰よりも倫華から、謝罪なり後悔なりを口にしてほしかったのだ。
(やっぱり、本人に払わせるしかないな)
たとえ、どんな手を使ってでも。
沙貴が出ていくと、忠雄はスーツの内ポケットから鍵を出し、デスク右上の引き出しを開けた。
中に入っていたのは携帯電話。それも、スマートフォン全盛の時代にもかかわらず、かなり古いタイプのガラケーである。液晶画面には番号しか表示されないタイプの。
忠雄はそれで、登録されていた番号にかけた。
「……ああ、私だ。今日は集まれるかい?……うん。では定刻に」
短いやりとりで通話を終え、もうひとりにかける。そちらとも、交わした言葉は一緒だった。
やるべきことを終え、携帯電話をしまう。引き出しに鍵をかけた忠雄の面相は、先刻までと一変していた。娘の言動に悩む父親のそれとも、沙貴と話したときの判事の顔とも異なる。
鬼も裸足で逃げ出すであろう、その形相を知っているのは、ごく限られた人間のみであった。
この続きは、書籍にてお楽しみください