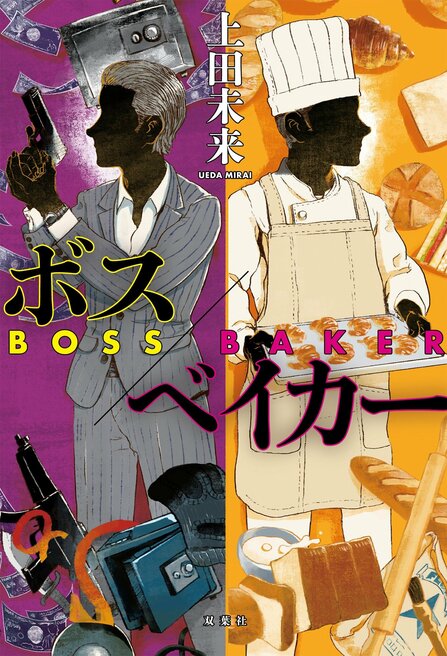どうして逃げたのだろう?
生存本能だろうか。
銃声が聞こえ、それが外れたとわかったとき、ぼくは駆けだしていた。
銃弾は、ぼくの耳を掠めていた。太陽が動揺して外したのではなかった。この家が揺れたのだ。地震だった。太陽が発射する寸前、この家が揺れて、銃弾がわずかに逸れたのだった。震度がどのくらいだったかはわからない。揺れていた時間は、おそらく二、三秒だっただろう。
この偶然について考える時間はなかった。このことについて考えるのはずいぶんあとになってからのことだ。もしもこうなっていたら、とあとから振り返ることはできるが、その渦中にいるあいだは考えることはできない。
部屋を出ると、廊下を走った。なかほどまで来たとき、太陽が廊下に出てきたのがわかった。ぼくはそばにあった階段を駆けのぼった。
二階に行ったところで逃げ場はないとわかっていたが、あのまま廊下を玄関まで走っていたら、間違いなく背中を撃たれていただろう。
階段は真ん中で踊り場があり、向きが変わる構造になっていた。必死に階段を駆けのぼる。
太陽の前で目を瞑ったときには、死ぬ覚悟でいたのに、いまは生きようとしている。生きたところで、もはや誰にも必要とされていないことはわかっているのに……。
階段をのぼった先にドアが見えた。ドアを開けてなかに入る。その部屋も一階と同じく殺風景だった。家具はない。引っ越ししてきた直後の部屋のようだ。カーテンも掛けられてなく、窓から工場街の寂しい光景が見えるばかりだった。
階段から、太陽が駆けのぼってくる音が聞こえた。
ぼくはカーテンレールを掴むと、それを壁から剥ぎとった。
直後だった。
太陽が部屋に飛びこんできた。ぼくは背中に太陽の気配を感じ、振り向きざまに、カーテンレールを横なぎに振った。カーテンレールが太陽の手にあたったのと、太陽が発砲したのは、ほぼ同時だった。
部屋に銃声が響いたが、弾はぼくにはあたらなかった。弾がどこにあたったのかはわからない。部屋の隅に拳銃が転がっているのが見えて、硝煙の匂いがした。
ぼくと太陽は対峙した。太陽がぼくを見つめている。ちらとその目が壁際の拳銃に向けられるのがわかった。太陽はそれをとるタイミングを計っているのだ。
あれをとられたら、ぼくの世界は終わる。
カーテンレールで太陽を殴りつけて逃げだそうかと思ったとき、ぼくは自分が拳銃を持っていることを思いだした。普段は持たないものだっただけに、その存在をすっかり忘れてしまっていたのだった。あの時計屋からもらったトカレフのコピーだ。
カーテンレールを横に落とし、素早く背中に手を伸ばすと、ベルトに挟んでいた、オートマティックの拳銃の銃把を掴んだ。それを太陽に向ける。
太陽が驚いた顔をした。
「そんなものを持っていたのか?」
「君を殺すために持っていたわけじゃない」
太陽がぼくをじっと見つめる。
ここから脱するためには太陽を撃つ以外に道はないことはわかっていた。しかし、太陽は、ぼくにとっては特別な存在だった。ぼくに道を示し、導いてくれた人だ。それだけじゃない。太陽は、いまのぼくの人生で一番大切な人間だったのだ。
撃ちたくはなかった。
だが、こうするしかなかった。ぼくが撃たなければ、太陽が銃を拾ってぼくを撃つことは間違いない。実際に太陽は、さっきは引き金を引いたのだ。あの地震の揺れがなければ、ぼくは確実に死んでいた。
太陽は、ぼくが持つ拳銃を見て、覚悟を決めたようだった。全身の力を抜き、ぼくに身体をまっすぐに向けた。
こういう判断の早い男だった。自分ができる範囲のことは異常なくらい力を尽くすくせに、いったん自分の力が及ばないとわかると、それを即座に潔く受け入れる。
太陽は壁際に落ちた拳銃をとって撃たれるよりも、ここでこのまま撃たれる道を選んだのだ。ぼくを正面から見据える。
彼の茶色がかった瞳に、ぼくは一瞬立ちすくんだ。
――もう引き返せない。
ふたりの関係は完全に変わってしまっていた。太陽はチームを選んだのだ。ぼくは裏切られたのだ……。
銃口を太陽の額に向けた。
「最後にこれだけはいっておく」ぼくはいった。
死にゆく者にいまさら弁解しても意味はないと思ったが、これだけはいわずにいられなかった。真実をわかってほしかった。
「ぼくは、ほんとうに仲間の金は盗っていない。君に信じられなかったのが残念だ」
ぼくはこれまでのふたりの関係を握りつぶすようにして引き金を引いた。
刹那、右手に強い反動を覚え、弾が飛んでいくのが、まるでスローモーションの映像のように見えた。全集中がぼくの指先に宿り、極度に張り詰めた知覚が、銃砲から放たれた弾丸をぼくに見せていた。
これは幻覚なのだろうか? ぼくにはわからなかった。
スローモーションの映像は続き、ボトルネック型のトカレフの弾丸が、吸いこまれるように太陽の額に入っていくのが見えた。太陽の額の皮膚がまるで液体であるかのように、皺の波紋をつくるのさえ見えた。そこから血が噴きだし、太陽がうしろに倒れるのも見た――。