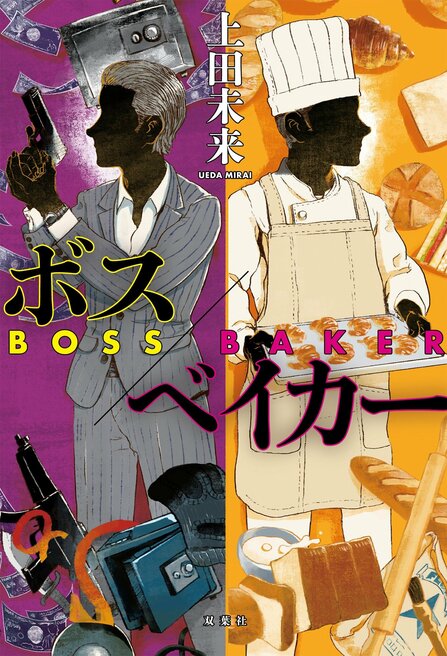――午前二時。
その日の仕事はスムーズに終わった。何も問題がなかった。ないどころか予想以上の成果をあげてもいた。当初はそれほど大きな成果に繋がらないだろうと思っていた案件が、かなりの大仕事に変わったのだ。
それに気づいたのは、ぼくが金庫を開けたときだった。数百万ぐらいはあるだろうと思っていたが、そこには数千万ほどの現金が入っていたのだ。ボストンバッグをふたつ使うことになった。
「あいつはよっぽどあくどいことをしてるな」ぼくがいうと、太陽は、「かもな」と素っ気なく返した。
五人で等分すると、ひとりあたり一千万以上になりそうだった。もっとも、この半分は慈善団体に寄付をし、残りの一割はチームのプール金として貯金するというのがこのチームのルールだ。ぼくたちは、これを“税金”と呼んでいた。それでもかなりの額になることは間違いない。
ぼくと太陽は、ビルを出て、鬼山の運転するホンダのSUVに乗った。バックアップ役の島袋とトマリは、別の車で移動している。
あのふたりは、ビルの近くから、ビル内の警備システムをハッキングし、何も起こっていないように偽装する役目だった。今回も警備システムに異常は出なかった。
逃走時間はじゅうぶんにある。
ビルから二ブロック離れたときだった。
「鬼山、いまから指示する場所へ行ってくれ」太陽がいった。
「……わかりました」鬼山が答えた。
ぼくと太陽は後部座席にいた。ふたりのあいだには、金の詰まったボストンバッグが置かれている。
ぼくは考えていた。太陽は、ぼくとどこへ行こうというのか?
これまでにはなかったことだ。いつもなら、仕事が済めば、隠れ家に行って金をわける。
いったい、何をするつもりなのか?
太陽が鬼山に指示して向かった先は、工場の並んでいるとおりにある一軒家だった。あたりに住宅はなさそうだった。薄暗い街灯が寂しくとおりに並んでいるだけだ。
「俺と錠二は、ここで少し話をする。お前は先に隠れ家に行っておいてくれ」
「金はどうしますか?」車を停車させ、運転席に座っている鬼山が振り返った。
「先にお前らで、わけてくれ。俺の分と錠二の分は、隠れ家に置いておけばいい」太陽がいった。
鬼山が頷いた。
ぼくと太陽はSUVをおりた。鬼山の乗った車が暗がりのなかを走り去っていく。
「あいつを信用するのか?」ぼくは太陽に訊いた。
太陽は、振り返り、ぼくを暗い瞳で見つめた。
「ああ、信用する。仲間だからな」
“仲間”という言葉を妙に強調して太陽はいった。
さあ、行くぞ、と太陽は声をかけ、玄関に向かって歩いた。ドアの前まで来ると、太陽はポケットに手を突っこんで鍵をとりだした。それをドアに差しこむ。慣れた様子で玄関に入ると、壁のスイッチを入れた。
いったい、この家は何なのだろうか、と思った。太陽の家ではないはずだ。だが、来慣れた様子がある。彼は住まいを転々とする男だが、たいていはマンションに住んでいる。
建売住宅のような、素っ気なく、誰にでも好かれるがけっして愛着を持たれないような家だった。細長く奥に続いている。ぼくは太陽のあとを歩いた。途中で左手に二階に繋がる階段があった。太陽はそこをとおり過ぎた。突きあたりはキッチンだった。殺風景なキッチンで、使われている様子はない。建物自体は古かったが、綺麗に片づけられている。というよりも、ものがほとんどなかった。
太陽の様子がいつもと違っていることが気になった。いままで見たことのない雰囲気を纏っている。
キッチンの横の暗い部屋に入り、太陽が灯りをつけると、そこはダイニングルームのようだった。合板のテーブルが真ん中に置かれ、それにはマッチしていない不揃いの木の椅子が二脚、間に合わせのように向かい合わせに置いてある。太陽が用意したものかもしれなかった。
「そこに座ってくれ」
ぼくが座ると、太陽がぼくの正面に腰をおろした。太陽のうしろには紺色の遮光カーテンが掛けられている。カーテンには流れ星の絵が描かれてあった。
「ここで何をするんだ?」
太陽はぼくをじっと見つめて答えなかった。
ぼくは太陽の雰囲気に戸惑っていた。
彼が何をいいだすのかわからなかったからだ。
ここに来てからの太陽の口調は、一言一言に重みがあり、ぼくは圧迫感を感じていた。
ひょっとして、このチームを解散しようというのだろうか? またふたりだけでやっていこうというなら大賛成だったが、それは期待しないようにした。期待すれば裏切られる。期待しなければ裏切られることもない。
「きょうはいい日だったな。結局、“ジャッカル”も出なかったし」
ぼくは話題を振ってみた。しかし、太陽は眉ひとつ動かさず、ぼくを見ているだけだった。彼の足先だけが小刻みに揺れているのを感じた。テーブルが微かに揺れていたからだ。
“ジャッカル”というのは、最近出没するようになった男のことだ。ぼくたちのような窃盗グループが仕事をしたあとに獲物を横取りする男だった。どうやって情報を掴んでいるのかわからなかったが、そいつは武装していて、狙われた者たちは従うしかなかった。このあいだも知り合いのグループがやられた。次はお前たちが狙われるかもしれない、と忠告され、ぼくは拳銃を準備していたのだった。
「お前は、俺たちのチームのことをどう思う」太陽が静かに尋ねた。
「どう思うかって? いいチームだと思うけど」
太陽は軽く頷いた。
「そうだな。確かに、いいチームだ。仕事はいつも完璧だ。俺は自分でつくりあげた、このチームに誇りを持っている」
話の行方がわからなかった。ぼくは黙って話の続きを待った。
「だが、この完璧なものに罅が入ったかもしれない」ぼくを見ながら、太陽はいった。
「罅?」
太陽はジャケットのポケットに手を入れると、そこから何かをとりだしてテーブルに置いた。テーブルに置かれるときに、かちり、と固い音がした。手を離すと、そこには拳銃があった。スミス&ウェッソンのリボルバーだ。銃身は短く、掌に収まるほどの大きさのものだ。
これまで太陽が銃を持っていたことはなかったから、ぼくは動揺した。太陽もジャッカルに対抗しようとして銃を用意したのだろうか? それにしても、この雰囲気は妙だった。どうして銃をとりだしたのか?
太陽が指で、滑らせるようにして拳銃を回転させはじめた。神経質な動作だ。リラックスした様子と緊張した挙動が混在するのがこの男の常だったから、ぼくはただ黙ってそれを眺めていた。
ぴたりと、指が止まって、銃口がぼくを向いた。
「チームの罅はお前だ」
一瞬、間があいたあとで、ぼくは聞き返した。
「ぼくが罅……。それは、どういう意味だ?」
太陽は素早く拳銃を掴むと、ぼくに向けた。
彼の目は恐ろしいほどに冷たかった。
「文字どおりの意味だ。お前が俺の組織をばらばらにしかねない存在だということだ」
ぼくは、太陽の目をまっすぐに見返した。
彼の目は、まるでヘビやトカゲのような爬虫類のそれを思わせた。ぼくは一心にその瞳のなかに光を探した。ぼくを照らしてくれる光だ。ぼくをこの世界から探しだし、照らしてくれた、あの暖かい光だ。しかし、茶色がかった瞳のなかに、その光は見いだせなかった。極寒の地に降り注ぐ月光のように冷たいままだった。
――あり得ない。
このときのぼくの気持ちは誰にも想像できないだろう。自分が一番信頼し、また尊敬している人間から、いきなり銃を向けられているのだ。
太陽がぼくに銃を向けるなんて、あってはならないことだった。ぼくはここ数年間、太陽の信頼を勝ち得るために生きてきたようなものだ。太陽のためだったら、なんだってできる。
そう。死ぬことだってできると思っていたのだ。
そんなぼくに銃を向けるなんて――。
「ぼくを殺すつもりなのか?」
太陽は答えなかった。
だが、緊張した身体から漂う雰囲気が、肯定の意をはっきりと伝えていた。
「どうしてなんだ? 理由を聞かせてくれ」ぼくは尋ねた。
太陽はぼくを見据えた。
「これはチームのためだ。お前はチームのルールを破った。金庫を開けるとき、お前は、俺たちに渡す前に金を盗っている」
一瞬、太陽が何をいっているのか意味がわからなかった。ぼくが金を盗っているって?
ぼくは声を出して笑った。
「何いってるんだ。ぼくがそんなことするはずないだろ。きょう、君も近くで見ていたじゃないか」
「きょうは盗ってないな。だが普段はお前ひとりで金庫を開ける。そのときに盗っていただろ」
それで、きょう太陽は、ぼくが金庫を開けるときにそばにいたのか。これまでそんなことはなかったので不思議に思っていた。太陽は、ぼくが金を横取りするか確認していたのだ。
「盗ってないっていってるだろ。いつもいってるじゃないか、ぼくは金が目的でこんなことをしてるんじゃないって」
静かな部屋に、ぼくの声が響いたが、太陽の表情が揺らぐことはなかった。その顔を受けて、ぼくの表情も次第に硬くなっていった。
ぼくは落ちついた口調に切り替えて尋ねた。
「君は、ほんとうに、ぼくがそんなことをしていると思ってるのか?」
「俺がどう思ってるかは問題じゃない。仲間がそういっていることが問題なんだ」
そうじゃない、とぼくは思った。太陽がどう思っているかが問題なんだ。ほかの誰にどう思われようともぼくは構わない。世界中の人々から非難されたっていい。たったひとり、太陽だけが信じてくれればよかった。
燃え盛るような激情がぼくの胸に湧きあがったが、ぼくは冷静に尋ねた。
「仲間って誰だ?」
「残りの三人、全員だ」
鬼山だ、と思った。あいつがほかのメンバーを唆して、あるいは脅して従わせたのだ。それしか考えられない。いかにもあいつのやりそうなことだった。あいつはぼくを嫌っている。ぼくを排除してチームのナンバー2の座を狙っているのかもしれなかった。
「何か証拠でもあるのか?」
「三人とも見たことがある、といっている」
「動画にでも収めてあるのか?」
「いや、それはない。だが、この場合、証言だけでじゅうぶんだ」
「じゅうぶん? ぼくのいい分は聞かないのか?」
太陽は首を振った。
「俺は、このチームを存続したい。この仕事がどれだけ危険なものか、わかっているだろう。些細なことが命取りになる。五人のチームのうち三人がお前を疑っている。こんな状態では仕事はできない」
「それで、ぼくを殺すっていうのか? 極端な話だな」
ぼくはいったが、太陽が極端な男であることはよく知っていた。白か黒か。有か無か。生か死か。太陽が完璧さを求めるあまり極端な行動に出る場面をこれまでに何度も見てきた。
それよりも、ぼくは、太陽がぼくよりも三人をとったことが許せなかった。
――どうして、ぼくじゃないんだ。
ぼくは努めて冷静な声を出した。
「君のチームに金庫破りは必要じゃないのか?」
「また誰かを探す。チームを裏切らない人間を、な」
「それじゃあ、どうして、さっさと撃たないんだ。この部屋に入るまでに撃つ機会はいくらでもあっただろう」
太陽は銃口をぼくに向けたまま、いった。
「俺はフェアにしたいだけだ。理由もわからずに死ぬのはいやだろう」
「……わかった。じゃあ、撃てよ」
ぼくはきつく目を瞑った。この世界を閉じるように。
もうどうでもいい、と思った。家族を失い、愛する人間からも見捨てられようとしている。もはや生きている意味はないと思った。