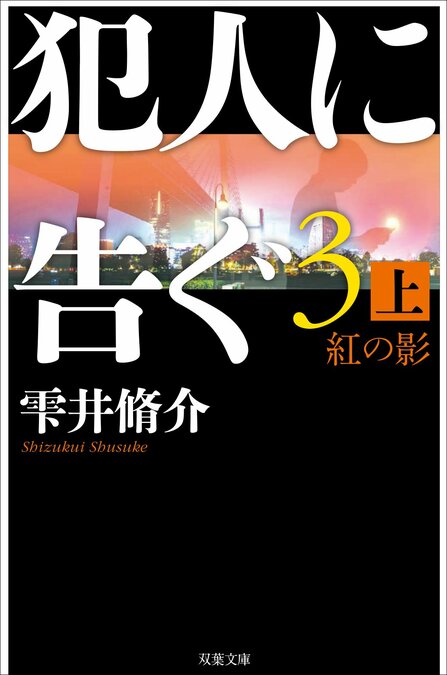コンピュータによる顔認証技術は、今や非常に精度が高くなっていて、例えば、空港のゲート前のカメラで乗客を撮影し、旅券の顔データとリアルタイムで照合させると、髪形や体重の変化、表情の変化があったとしても、九十九パーセント以上の確率で同一人物かどうかの判定ができるという。
顔認証の仕組みは、従来からある指紋認証と同様、画像上から特徴点を探し出し、それが対象とどれだけ一致するかを計算するのが基本だが、顔認証は目、鼻、口、耳などの位置や形状だけでなく、額、頬、あごの形状など、つまり顔のありとあらゆる部位から特徴点が探し出され、その豊富な手がかりから同一の顔かどうかが判定されることになる。
先日も真帆を通してそんな説明を聞かされ、巻島は最先端技術のレベルの高さに感心させられたのだが、今回のケースにそれが通用するかどうかは分からないような気がした。こちらの手もとにあるのは、決して鮮明とは言えない横顔の画像だけである。単純に考えても、ここから多くの特徴点を抽出するのは難しいと感じる。
しかし、最先端技術がそれほど高度であるなら、粗い画像を鮮明化処理したり、あるいは横顔から3D的に解析して正面からの顔を導き出すことも可能ではないか、それができればこの横顔の画像も捜査に大きく役立つだろうという思いで、真帆に問い合わせを託しておいたのだった。
しかし、残念ながらそこまでは難しいようだった。
「私たち人間が人の横顔を見て、正面はこんな感じだろうって想像したとしても、意外と実物は違ってたりするじゃないですか。コンピュータを使ったとしても、それくらいの誤差は出るみたいで、それで無理に正面の顔を作ったとしても、本物とはどこか違うような顔にしかならない可能性が高いっていう話です」
「なるほど」
コンピュータがいかに賢いといっても、そのあたりはまだまだ、人間の能力と大して変わらないということらしい。
「それから鮮明化の画像処理も同様で、膨大な人間の顔のデータからパターンを認識して、このシルエットなら、こんな顔だろうっていうのを導くだけであって、答えとして出た顔が誰の目で見てもその人だというように定まるかというと、実際はなかなか難しいっていう話です」
「そういうもんか」
人の顔など目鼻立ちのわずかな違いで成り立っているものであり、その領域すべてを神のように支配するのは、最先端の技術でも及ばないことが多いようだ。
「ただですね」真帆の話には続きがあった。「顔認証で使う特徴点っていうのは、粗い画像であってもいっぱい抽出できるそうで、精度的には確かに落ちるみたいですけど、それでも本人が映っていれば、ヒットする確率は高いだろうってことなんです。要するに、街中の防犯カメラの映像を集めて、そこから〔リップマン〕を探したいのであれば、粗い横顔の画像のまま照合にかけちゃえばいいんですよ。他人が何人か、あるいは何十人か知らないですけど、間違ってヒットしたとしても、本物もその中にちゃんと入ってるとしたら、捜査としては大きな前進ですからね」
「なるほど……指紋みたいに、ニアヒットでもいいからと、照合にかけてみる手はあるわけか」巻島はそう応じながら、思案を進める。「しかし、それで引っかかった人間をどこの誰だと特定したり、〔リップマン〕か〔リップマン〕じゃないか判定したりするのは簡単じゃないな」
「毛髪も採れてますから、最後はそれで特定することは可能ですけどね」一緒に話を聞いていた秋本が言う。「ただ、防犯カメラの映像なんてものは、すべて過去のものですからね。一週間前の何時に〔リップマン〕がそこを通ったからといって、今からそこに駆けつけたところで捕まえられるわけじゃないですし、その人物の所在をつかまなきゃいけないとすると、どれだけの成果が挙がるかは分かりませんね」
「ただまあ、この横顔を何とか活かすとすれば、その方法以外ないってことだ」
「引っかかった映像から所在についてのヒントが何か出てくるかもしれませんしな」
本田の同意の言葉には、致し方ないという意味合いがこもっていた。横浜の街の主要な各所から防犯カメラのデータを集めてきて、さらにヒットした人間を一人一人つぶしていくとなると、今余っている捜査員の手では到底足りないということも容易に想像できる。しかも、成果という面でも計算は立たないのだ。
それでもやるしかないかと巻島が考えていると、真帆がさらに話を続けてきた。
「顔認証だけだとそうなるでしょうけど、さらにちょっと面白い話を仕入れてきまして」
巻島たち捜査幹部は、停滞感から来る重苦しさがついつい表情に出てしまっているのだが、彼女の顔はあくまで明るい。
「科捜研のほうで、AIの犯罪予測システムを大学の研究室と一緒に作って、試験運用を始めたらしいんですよ」
「AIですか……こういう話は本当、弱いんだよな」本田が早くも白旗を上げるように独りごちた。「うちの息子なら苦もなく理解できるんでしょうが」
「私も全部を理解してるわけじゃないですけど」真帆はIT時代から脱落気味の中年の弱音を微苦笑で受け流し、話を続けた。「でもすごいんですよ、AIって。例えば、管内で起きた引ったくり事件をデータとして全部打ちこむわけです。検挙・未検挙の別、発生場所に被害金額、被害者の性別・年齢、あるいは日にちや時間や天候なんかもです。それに加えて、地図情報も入れておくと、そこが駅や幹線道路からどれだけ離れているかとか、付近の交通量とかも分かるわけです。で、そういうデータが多ければ多いほど、AIは賢くなって、次は何月何日の何時頃、どこどこあたりで引ったくりが起きる可能性が高いなんてことを教えてくれるようになるっていうんですよ」
「へえ……それはまあ、当たる確率はともかく、どこをパトロールすれば効果的かっていう目安にはなりますわな」
本田の言い方には、どこか眉唾に受け取っているような思いが見え隠れしていた。
「いや、それが馬鹿にできないくらい当たるらしくて、実際、パトロールに活用するようになると犯人側も警察の姿見てやめちゃうから、当たったのかどうか分からなくなるんですけど、単に予測をウォッチしてる段階では、AIが予測した場所付近で、時間も一、二時間の誤差で引ったくりが発生したこともあったらしいんですよ。そこは別に、以前、引ったくりがあった場所じゃなくて、ほかの事件から考えて、今度はこのあたりでって弾き出された場所なんです。すごくないですか?」
「ほう」本田も思い直したように驚いてみせた。「日にちも当たったんですか?」
「三月の各木曜日にその予測が付いて、発生も木曜日だったそうなんで、当たりですよね」
「なるほど、確かに」もはや降参するしかないというように、本田は肩をすくめてみせた。「それを今回のに、どう使おうと?」
「顔認証で引っかかった防犯カメラの場所や引っかかった時間を、データとしてその予測システムに入れるんですよ。それが本物の〔リップマン〕かどうかは考えなくていいんです。ただとにかく、街のあちこちから防犯カメラの映像を取ってきて、顔認証にかけて、ヒットしたものをデータ化する。そうすると、〔リップマン〕じゃない人は、たまたまあるところでは照合に引っかかったけど、ほかでは引っかからないかもしれない。逆に本物の〔リップマン〕はどこでも引っかかる可能性が高いから、データを集めれば集めるほど、そこに本物が混じる確率が高くなってくるわけですよ。どの人物が本物か、捜査員の目で画像を見極める必要もなくて、そのデータのまま、今度は予測システムのAIに任せちゃうんです。そしたらAIが、〔リップマン〕は何月何日何時頃、どこどこ近くに出没する可能性が高いって教えてくれるんですよ」
「なるほど」巻島はうならされた。「データに本物が混じる確率が高くなっていれば、それだけその予測は、本物の〔リップマン〕の行動予測に近くなるって寸法か」
「そうです、そうです」
「いやあ、すごい時代になったな」本田は呆れたように笑っている。
「しかし、データからそれが弾き出されるとすれば、我々が重視する鑑と同じようなことだ。使ってみるのも面白いかもしれない」巻島はすでにその気になっている。
「どれだけの映像を集めてこられるかに、成否はかかってますね」秋本が言う。「人員には余裕がある気がしてましたけど、また一気に手が足りなくなりそうだ」
「課長、横浜や川崎の各所轄に、映像集めを手伝ってくれるよう要請してもらえますか」
巻島の言葉に、真帆は「分かりました」と気負ったように応じた。
「よし、そうと決まったら、うちの遊んでる連中も尻をたたいて働かせなきゃな」本田も気持ちを切り替えるように言った。
結果が出る保証はどこにもないが、曲がりなりにも捜査方針が定まったところで、指令席にもにわかに活気が出てきた。
この続きは、書籍にてお楽しみください