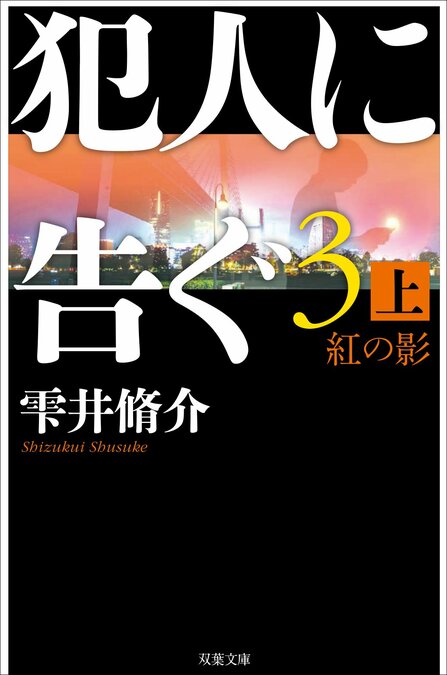刑事特別捜査隊の巡査長・小川かつおは、昼食に行こうと山手署の玄関を出たところで、刑事総務課長の山口真帆と特捜隊同僚の小石亜由美が連れ立って歩いてくるところに出くわした。
「お疲れ様でーす」
美人二人が並んでいる光景に眼福を感じながら、小川は声をかけた。
「あ、いねむりくん、お疲れ様」
「ちょ、ちょ、ちょっ」
山口真帆が朗らかに返してきた言葉に小川は焦り、誰か聞き耳を立てていないかと周りを見回した。
「やだなあ、何ですか、その、聞いたこともない変なニックネームは?」
「でも、いねむりくんなんでしょ」真帆はくすくす笑いながら言う。
「な、何を言ってるんですかぁ……そんな、おかわりくんみたいな、ほのぼのしたニックネームは、この殺伐とした刑事の世界にはいらないんですよ。いったい誰が考えたんですかぁ?」
もしやと思い小石亜由美を見ると、彼女は視線をすっと外した。
先の誘拐事件では、張りこんでいた小川が睡魔に負けて居眠りしていた最中に、犯人グループが身代金の金塊を奪いに来るという、我ながら頭を抱えたくなるような失態があった。一緒に張りこんでいた亜由美の活躍で大事には至らずに済んだが、小川は今でも事の次第が周囲に広まるのを恐れ、火消しに余念がない。
亜由美にも、あれは居眠りしていたわけではないと言い訳しているのだが、どうやら聞き入れられてはいないようだった。
亜由美一人が胸の内に収めている話ならまだいい。真帆は特捜隊の上に立つ管理職という意味ではまったくよろしくないのだが、規律に厳しいタイプではないし、キャリア組なのでいずれまたどこかへ行ってしまうと思えば、ひとまずごまかしておくことで何とかなる人間ではある。
しかし彼女には、今のように、人の失敗を罪なくからかったり、面白がったりするところがある。放っておけば、本田や巻島といった、ごまかしの利かない強面のおじさんたちにまで話が広がりかねない。これが困る。
「小石さんは何か誤解してるんですよ」小川は作り笑いを顔に張りつけて、強弁に回った。「僕はあのとき決して、居眠りしてたわけじゃないですからぁ」
「じゃあ、何してたの?」真帆がニヤニヤしながら意地悪く訊く。
「考え事をしてたんですよ、考え事を」
「普通に呼びかけても、全然反応なかったんですけど」
当然だとも言えるが、この言い訳に納得していないらしい亜由美がそう言った。
「それはだって」小川は言った。「ゾーンに入ってたから」
「ゾーン?」真帆と亜由美の声が重なる。
「一流のスポーツ選手たちが、よく言ってるでしょう。集中力が極限に来ると、周りの動きが遅く見えたり歓声が聞こえなくなったりするゾーンの状態に入るって……あのときの僕がそれだったんですよ。犯人たちはどうやって金塊を奪おうと考えてるのか、それを頭の中で懸命にシミュレーションしててゾーンに入ってたんですよ。その結果、僕は行き着いたんです。犯人たちは社長が帰宅した隙をつき、バイク便を装って金塊を取りに来るに違いないってことに。しかし、それに気づいて顔を上げたのは、小石さんがちょうど犯人を追って出ていくときでした。ほんのわずか間に合わなかったんですよ」
渾身の熱弁を振るってみたのだが、いまいち伝わり切らなかったらしく、二人とも冷めた顔をしている。亜由美に至っては「ふーん」と、小馬鹿にしたような相槌を打った。
「何かなぁ、その疑わしげな目は」小川は負けじと言う。「何か僕がチョンボを必死で隠してるような目で見てるけど、忘れないでほしいのは、この小川かつおこそ、〔バッドマン〕事件で本部長賞をもらった男だということだよ」
「私も今日、もらってきましたよ」亜由美がさらりと言った。
「え?」
「小石さんに本部長賞が決まったの、知らなかったの?」真帆が言う。「午前中に表彰があって、私も付き添ってきたのよ。まあ、あれだけの活躍をしたんだから、もらうのも当然よね」
「そ、そうなんだぁ……それはおめでとう」
まずい。自分の栄光が色あせてしまう……小川は焦りを募らせた。
「小川さんも、そのゾーンとやらに入ってなかったら、一緒にもらってたかもしれないのに残念だったわね」真帆が笑いを含みながら言う。
「いやあ、僕はすでに一度もらってますし、これが若手の小石さんの自信につながると思えば、結果的にはよかったんじゃないですかねえ」小川は先輩刑事としての威厳をにじませて言った。「僕はただ、ゾーンのことを理解してもらえれば十分ですよ」
「了解。ゾーンね、ゾーン」
何とか真帆には納得してもらえたようだった。それで二人とは別れた。ただ、亜由美は別れ際まで、小川に冷ややかな視線を向けていた。
以前はことあるごとに「どうしよう」「どうしましょう」と戸惑いの言葉ばかり吐いている頼りなげな女の子だったのだが、事件での活躍を境に、すっかり自信を持ってしまったようである。
それとともに、中堅刑事らしく遇されていない小川の隊内での地位が、さらに下がっているような気がしている。今までは、どう軽んじられても、亜由美が自分の下にいると思っていられたのが、そうも言っていられなくなった。
しかし、今は何より、居眠りの失態が表沙汰になることを防ぐのが最優先である。
そのためには屈辱も我慢して、しばらくおとなしくしていることも大切だと、小川は自分に言い聞かせた。
「おかげさまで本部長賞、いただいてきました~」
捜査本部で打ち合わせを重ねていた巻島たちのもとに、小石亜由美が山口真帆とともに現れ、表彰状を広げながら県警本部で表彰を受けた様子を嬉しそうに報告してきた。
「おめでとう。今回の件では、我々も大いに助けられた。本部長賞は当然だな」
巻島がそうねぎらうと、亜由美はさらに嬉しそうに相好を崩した。
「小石のファインプレーは、小川の指示を聞かずに自分で判断して機転を利かせたところだ。そこを誤ってたらと思うと、今でも冷や汗が出るよ」
本田もそんな言い方で彼女を褒めた。
「いねむりさん……小川さんの意見の逆を行けっていう、隊長の教えのおかげです」
「ちょっと顔つきが変わったな。自信が表情に出てる」
巻島の言葉に本田も、「そうそう、私もそう思いましたよ」と同意した。
「あのときはいねむりさん……小川さんしかいなくて、自分がやるしかない状況だったんですけど、何とかがんばれて、それが自信につながりました」
亜由美は「いねむりさん」と言い間違えるたびにあっと口に手をやりながら、しかし、言葉通り自信にあふれている口調で言った。
捜査は〔リップマン〕に迫る手立てが見つからず、停滞感を強めているが、そうした空気をも少し軽くしてくれるような、明るい報告だった。
「本部長もさすがに機嫌がよさそうでしたよ」山口真帆が付け足すように言った。「ただ、〔リップマン〕も早く捕まえろとの言葉も頂戴してきましたけど」
「機嫌がいいなら、もう少しは猶予がありそうですが」本田がそう解釈してみせる。
「いや、そんなのはいつまで持つか分からん」巻島は苦笑気味に応じる。「地元の大物代議士からも催促があったらしいからな。そのうちまた爆発するだろ」
「まあ、そうでしょうな」本田も肩をすくめてうなずく。
「そうだ」真帆が何かを思い出したように口を開き、亜由美に「もういいわよ」と言って退がらせてから話を続けた。「例の〔リップマン〕の横顔の写真ですけど、捜査支援室の米村さんが〔新日本電算〕の画像解析の技術担当の方に問い合わせて、あれこれ訊いてみたそうです。そしたらやっぱり、横顔から正面の顔を解析するのは、なかなか難しいだろうってことだそうです」
捜査支援室は刑事特別捜査隊と同様、刑事総務課の下に置かれている部署で、文字通り、捜査の支援部隊なのだが、主に捜査で集まってくる防犯カメラなどの映像データから事件関係者の行動を割り出す作業などを任されている。誘拐事件の捜査過程でも、犯人グループの車の足取りを追う解析作業などで、彼らの力を借りた。米村数正はそこの室長を務めている男だ。
画像の解析は探し出したい人物や車などの特徴をつかみ、解析担当者の目でもって、映像データを丹念に追っていく手法が今も根強いが、場所や時間などの絞りこみができない場合は、対象となる映像が膨大なものとなり、解析がなかなか追いつかないことになる。
街に防犯カメラが増え、刑事捜査に画像解析の重要度が増すにつれ、その作業の効率化が課題となっていた。捜査支援室の設置はそうした流れの中でのものだが、近年はコンピュータによる画像解析の技術も発達し、捜査支援室でも最先端の顔認証ソフトなどを導入するようになった。その世界トップの技術を誇ると言われている大手ハイテク企業〔新日本電算〕製のものである。