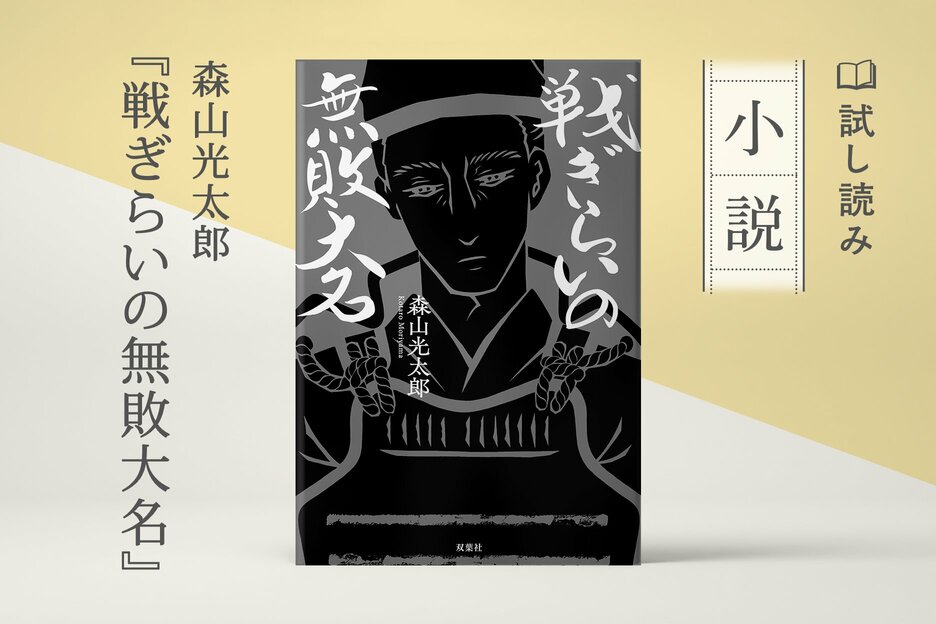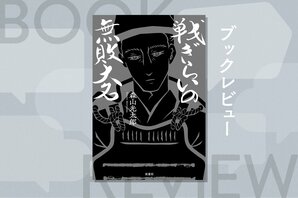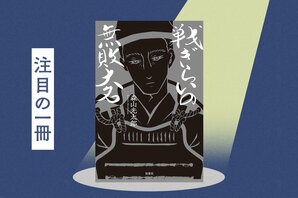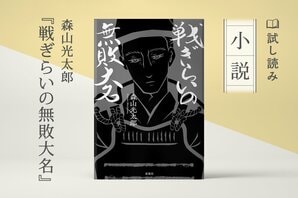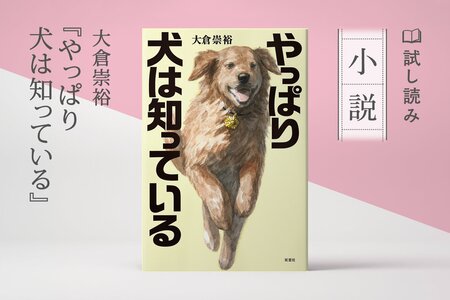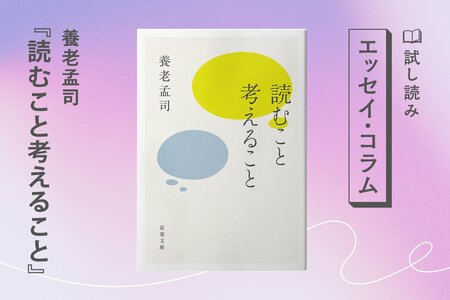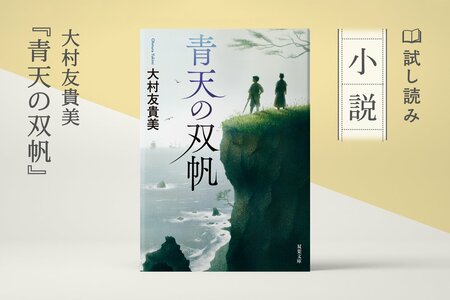大内家という言葉に、空気が張り詰めた。
豊前(現在の福岡県北東部)を巡り、長年にわたって大友家と敵対してきた西国最大の大名家だ。蒲池家も大友軍の与力として干戈を交えてきた。
「当主大内義隆卿が、筆頭家老である陶隆房に滅ぼされた」
大書院が騒めき、たちまち鎮堯の言葉が聞こえないほどになった。目の前では、兄が呆然と口を広げ、天地が逆さになったと肩を震わす者もいる。
「龍造寺は、いかに動きますか」
収まらぬ喧騒を遮ったのは、傍らの統光だった。
肥前龍造寺。少弐家宿老から、肥前の盟主となった名族だ。だが、数年来、家中は村中城と水ヶ江城の二つに割れ、お家騒動が続いている。柳川の北に接する龍造寺家の動きは、柳川の乱れに直結する。我が子の冷静な言葉に、鎮堯が小さく首肯した。
「大内の騒動によって、龍造寺は大きく動くであろうな」
「村中の龍造寺本家が、水ヶ江の分家を討ちますか」
「うむ。水ヶ江の分家には、滅ぼされた義隆卿の庇護があればこそ、本家も手出しはできなかった。義隆卿亡きいま、村中の本家は戦備えを始めておる」
「戦となれば、我らはいかに」
家中の者に理解させるため、大木父子は問答しているようだ。この親子には、独特の呼吸がある。だが、話を断ち切って膝を乗り出したのは、それまで黙っていた兄鎮久だった。
「よい機ではないか」
手を叩いた鎮久に、大書院の視線が集まった。
「両者が争えば、我らは村中の本家に加勢して、水ヶ江を攻め取るのも一興。肥前の水ヶ江を取れば、筑後において我らを脅かす者はいなくなるであろう」
興奮する鎮久に、鎮堯が困ったような表情をした。
「若、不用意なことを申されるな。大殿は軍兵を引き連れて肥後へ出征している最中。我らのみで攻め落とせるほど水ヶ江は容易くありませぬ」
「何を悠長なことを。戦は迅雷が第一。敵が備える前に一揉みにしてやればよいではないか。鎮堯。父に諮ることが留守役の務めではないぞ」
鎮久の嘲りに、鎮堯の顔が怒りで歪んだ。
俄かに家中の空気が滾り始めるのを感じた。背を押すような空気を感じ取ってか、鎮久の頬がさらに赤く染まった。
「義隆卿の死を見てみよ。殺すべき機を逸したがゆえ、義隆卿は家臣に討たれて滅んだのだ。今、我らの目の前には手を伸ばせば取れる水ヶ江がある」
兄の初陣は半年前、勝利の決まった戦での掃討戦だった。兄は三つの首級を挙げており、以来その言葉も勇気に満ちたものになっている。それを無謀と止める者もいなかった。
騒めく一座を見回し、鎮堯がちらりと鎮漣の方を見た。
「十郎様、さきほどから黙されておりますが」
大書院の視線が自分に集中するのを感じた。一気に頬が熱くなる。そこに鎮漣の言葉を吟味しようという気配はなく、世継ぎにも発言させておくか程度のものだ。
いつの間にか、手が小刻みに震えていた。
「さすれば」
取り繕うように白扇を広げ、口元を隠す。緊張から扇の親骨が震えていた。
「水ヶ江の龍造寺隆信殿を攻めることは、やめた方がよいのではないでしょうか。柳川の兵は、先年来戦続き。戦となれば死人も出ます。民が憐れです」
呆気にとられたような空気が満ちた。何を腰の抜けたことをというような視線の中で、統光だけは安堵したような表情をしていた。
不意に畳が激しく打たれる音がし、一座が肩を震わせて驚いた。
「それでもそなたは武門の子か」
正面を見上げると、刀のこじりを畳に打ち付け、立ち上がった兄がいた。思わず知らず、目尻に涙がたまる。
「あの忌々しい隆信めを討ち取る好機なのだぞ。討てば、水ヶ江どころか、勝ちに乗じて村中までもがそっくり手に入るやもしれぬ」
「隆信殿は猛き武士にございます」
鎮漣の脳裏にあるのは、伝え聞く龍造寺主従の姿だった。
六年前のことだ。主君少弐家の騙し討ちに遭い、龍造寺一門のほとんどが殺戮され、わずかに生き延びた者が柳川に落ちてきた。当主の首は、少弐家臣によって蹴鞠のように扱われたという。
当時の龍造寺家は、大友家の敵。だが、父宗雪は、年来の仇敵であった龍造寺家兼を捕らえることなく、柳川の一木村に手厚く迎え入れた。
さて、落ち延びて、襤褸のような直垂を着た一団の中に、その青年はいた。漆黒の僧衣。名は、円月。家兼の曾孫である若い僧の風貌は、齢十七にして見る者を傅かせる威容に満ちていた。
宝琳院で修行していた円月は、書を取れば一を知って十を解する名僧だったという。武芸の腕前も、際立っていた。一木村に来た円月と立ち合った鎮久はついに一太刀も入れられず、居候の身に遠慮した円月が、自ら木刀を取り落として場を収めたと言われている。
その一年後、当時肥前一の名将と謳われた龍造寺家兼は円月に還俗を命じる遺言を残し、水ヶ江龍造寺を継がせた。異例の抜擢だったが、九十歳を超えて戦乱を生き延びた家兼の目は、正しかったのだろう。
家督を継いだ円月は、わずかな兵力で少弐家の本城である勢福寺城を陥落させ、拠っていた少弐冬尚を追放してしまったのだ。父祖の仇である馬場頼周をも、一戦で討ち取り、晒し首にしている。あまりにも鮮やかな戦ぶりに、筑後中が円月という鬼才の登場に恐れ慄いた。
その円月こそ、龍造寺隆信という若武者だった。
「私は、隆信殿に勝てるとは思いませぬ」
「うつけめ。誰がお主に勝てるなどと言った」
兄の舌打ちが響き、鎮堯がとりなすように手を広げた。
「大内家の変事を受け、近く大殿が帰還される。それまでおのおのがた、かたく領内の守りを固めていただくよう」
鎮堯によって評定の終了が告げられると、統光と鎮漣を残して大書院から家臣たちがいなくなった。
いまだ鎮漣の膝の上で震える白扇を見て、統光が口を開いた。
「十郎様のお考えは間違ってはおりませぬ。戦続き。柳川では、米の収穫も減っております。今は領内をしかと固めるべき時でございましょう」
「家中の者からは、懦夫と思われたであろうな」
「今に始まったことではありますまい。それに、あの場にあって柳川の民のことを考えていたのは、十郎様だけでございました。よくぞ言葉にされたと存じます。そろそろ、震えをお収めください。敵が来れば、この統光が守りますゆえ」
そう言うと、統光が微笑んだ。
この続きは、書籍にてお楽しみください