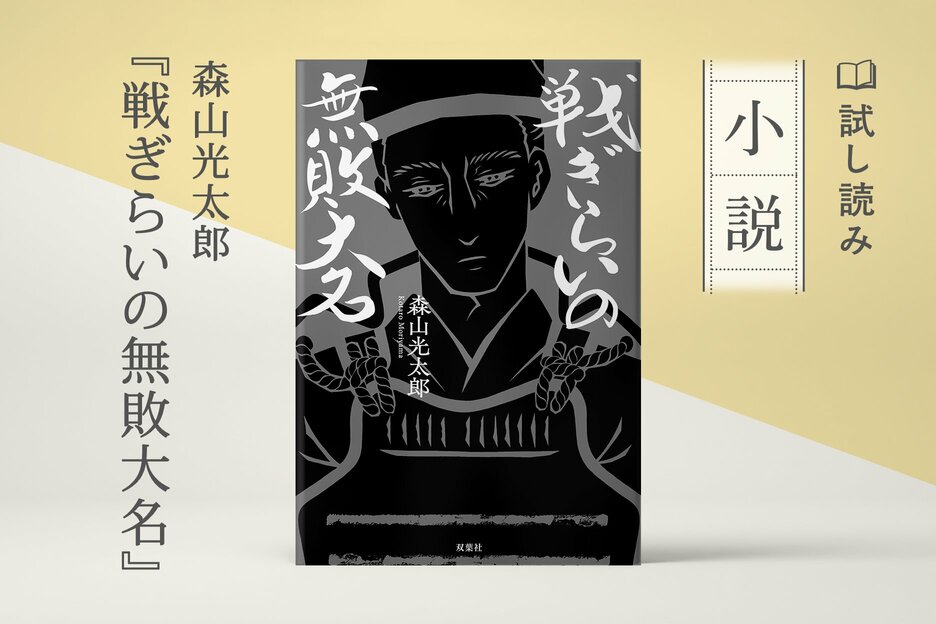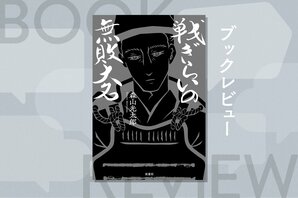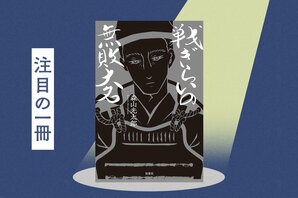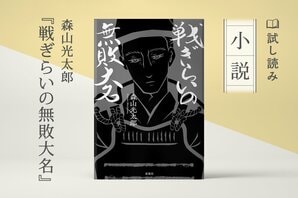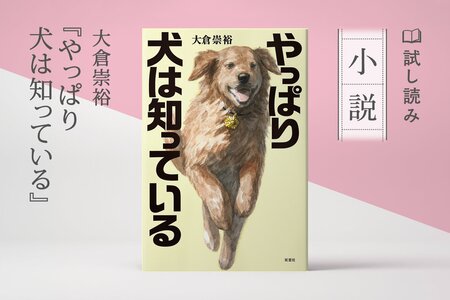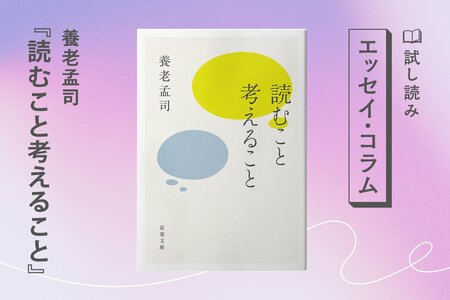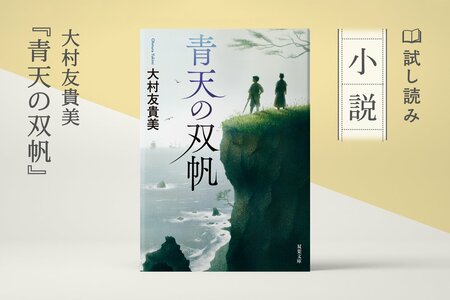破
一 鎮漣
天文二十年(西暦一五五一)──
灰色の空から、強い風が吹いた。
龍神の息吹だ――。
筑後国柳川の町を行きかう者が誰ともなく呟き、水路を行く船頭は櫂を強く握りなおした。城下には、無数の水路が縦横に通り、舞鶴とも称される見事な柳川城を十重二十重に囲んでいる。溢れんばかりの水路の逆巻きは、天の荒々しさに呼応しているようだった。
立つこともままならないほどの風は、やがて城下から筑紫平野へと広がり、黄金色の稲穂を横殴りに倒していく。
──応仁の乱より始まる戦国という時代が、いつをもって終わるのかには諸説ある。しかし、誰が終わらせたのかといえば、戦国三英傑の一人、豊臣秀吉であることは周知の事実だろう。
天文二十年という年は、織田信長が、織田弾正忠家を継ぐ前年。のちに江戸幕府を開き、二百六十年余の天下泰平をもたらす徳川家康が、数えて九歳の頃であり、いまだ戦乱を終わらせる者の気配を、誰も感じ取ることはできなかった時である。
天下泰平の兆しは分厚い曇天に遮られ、遠く西海道に目を向ければ、のちの九州三国時代を彩る大友宗麟、島津義久、龍造寺隆信らも、二十歳前後の青年時代。西海道の覇を胸に抱き、届かぬ曇天を遠く睨みつけていた頃である。
筑後柳川は、西海道を縦横に往来する時、必ず通らねばならぬ要衝。大友、龍造寺、島津の若獅子たちが、大望を成すためには、避けては通れぬ地であった。
城主は、義心、鉄の如しと謳われる名将蒲池宗雪。彼のいる間は、何者の手出しもできぬことを、若獅子たちも分かっている。それでも彼らがほくそ笑むのは、宗雪の子が、姫若と名高いうつけ者であったからだろう──。
蝉の声はいつしか消え、八月も半ばを過ぎていた。
陽は中天に昇った頃であろうか。曇天の下、吹き荒れる風の中で、蒲池十郎鎮漣はしたたかに転び、膝を擦りむいた。薬師小路を越えて、坂本小路まで来たところだった。
小ぎれいな黒の肩衣の背には左三巴紋があり、整った顔には歳相応の幼さがある。かぞえて十二歳。戦乱の時代の世継ぎとしては、その人相はいささか迫力に欠ける。今年元服を迎えたが、いまだ当人にその自覚はなく、すぐに目を真っ赤にはらすのは、童の頃から変わっていなかった。
涙を隠そうと俯いた鎮漣の前に、影が一つ伸びた。
「十郎様、お手を」
そう言って右手を差し出したのは、大木統光だ。几帳面を絵に描いたような男で、総髪を椿油で綺麗に撫で固めている。春風を思わせる顔立ちは、町娘からの評判も高いが、本人は気にすることもなく、浮いた話一つない。かぞえて二十歳。柳川城主である蒲池宗雪から鎮漣の傅役を任された器量は、同輩の中でも抜きんでていた。
「もう歩けぬ」
またかというように、統光が短く息を吐きだした。
「民が見ております」
「この痛みを抱えて歩けというなど、統光は鬼じゃ」
「案山子でも鬼でも天魔でも構いませぬが、立っていただかねば。強い風でした。まだ身体の細い十郎様が転ぶのも無理はありませぬ。恥ずかしがらず、お立ちください」
苦し紛れの慰めだった。同い年で、風ごときに転ばされる者などいない。頬が熱くなるのを感じながら、鎮漣は地面を叩いた。
「この道が悪いのじゃ。でこぼこで歩きづらい」
「足腰のよい鍛錬になりましょう」
「戦ばかりにかまけて領内を整えぬから、こうして怪我する者が生まれる。見よ。血が出ておるではないか」
顔を上げると、そこには困った表情をする統光がいた。この顔をする時の統光は、話が長い。地面に胡坐して、鎮漣は唇を噛んだ。
「十郎様が大きくなれば、領内の備えにも力を入れましょう。それに、かような擦り傷で涙を目に浮かべていては、戦場で困りますぞ」
「う、浮かべておらぬ。戦場にも出ぬ。困りはせぬ」
「などと、無茶を言うものではありませぬ。今もまさに大殿は肥後(現在の熊本県)の菊池征伐の真っ最中にございましょう」
「戦場ならば、兄上が行くといつも言っておるではないか。よいか、統光。何事にも人には向き不向きがある。戦場で輝くのは、兄上でよい」
「鎮久様は兄君なれど、正嫡は十郎様。いずれ、蒲池の老臣たちを率いて戦場に出るのは十郎様なのです」
「あ奴らは、嫌いだ。口を開けば戦のことばかり。それに知らぬのか。斬られれば、人は死ぬのだぞ」
呟くと、統光が首を左右に振り、羽交い絞めにするようにして鎮漣を立ち上がらせた。
「それも幾度となく聞きました。老臣たちを嫌うのは構いませんが、せめて民に不安を抱かせぬようにしていただきませぬと」
通りをゆく民は、鎮漣と統光を見て、いつものことだと薄く笑いを浮かべている。
姫若殿、はようお城へ戻りなされ。
聞こえてきた野太い声に、統光が丁寧に頭を下げた。心配しているというよりも、揶揄の響きが強い。黒い手拭いを頭に巻いた男児に背を向け、鎮漣は歩き出した。
城を北に出て、崇久寺へ向かうと、そこには山のように書が積み上げられていた。六韜三略など唐国伝来のものから、貞永式目や万葉集など日本古来のものもある。刀の修錬よりは好きだが、だからと言って真面目に取り組むほどでもない。
早朝に来ることを命じられていたが、父が戦で不在の今、毎日のように刻限を破っていた。師を務める僧も呆れ果て、いまや言葉を交わすこともほとんどない。
広庇に足を投げ出して三略を捲ると、黴臭い匂いが鼻を衝いた。
顔をしかめて書を閉じた時、門をくぐる艶やかな姿の女性が目に入った。橙色の小袖姿。母、貞心院だ。鎮漣に気づいたのだろう。束の間、ばつの悪そうな表情をした母が、取り繕うように怒りを貼りつけて近づいてきた。
「十郎殿。師の言いつけを守っておらぬと聞きました」
「いえ、今朝は腹の具合が悪く」
「黙りなさい。言い訳など見苦しい」
甲高い声で吐き捨てた母が、眉間を指でつまんだ。その目尻にはうっすらと皺が伸び始めている。
「刀や弓では、鎮久殿に及ばぬのです。せめて文の道で人並みとなれば、蒲池の家に頼らずとも生きていく術もありましょう」
「戦ぎらいの無敗大名」は全4回で連日公開予定