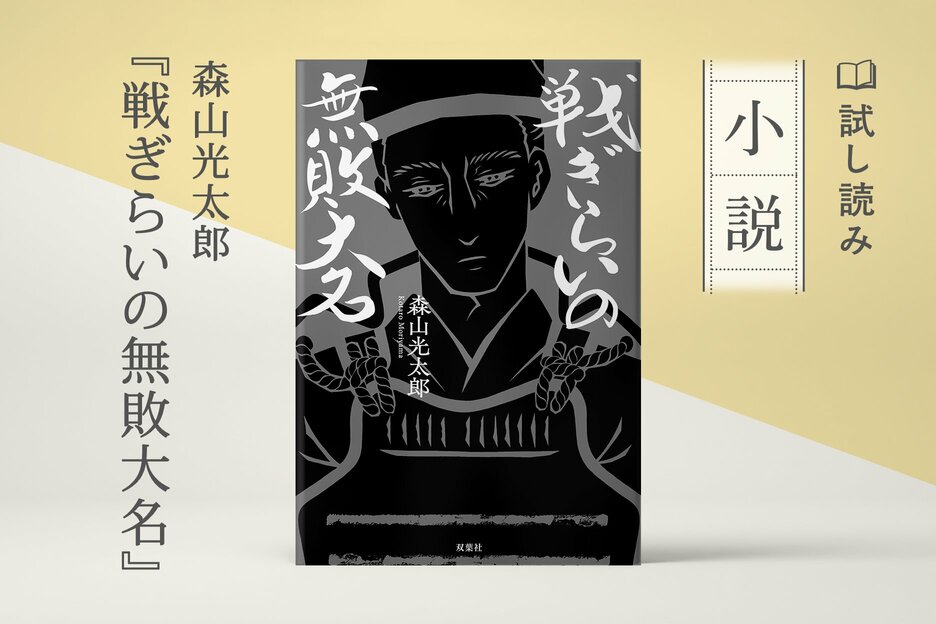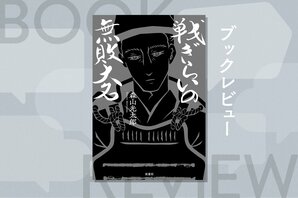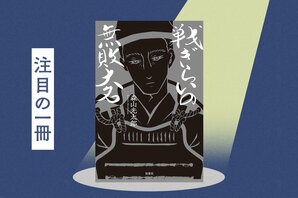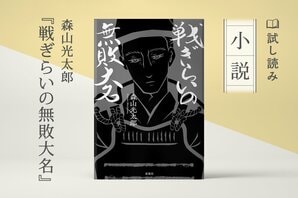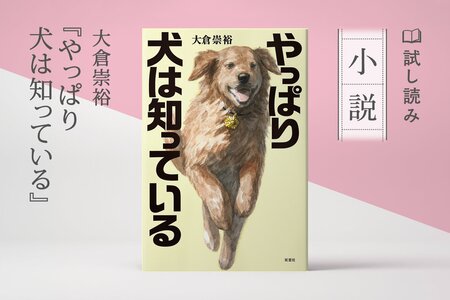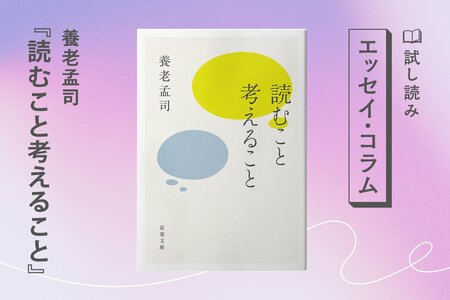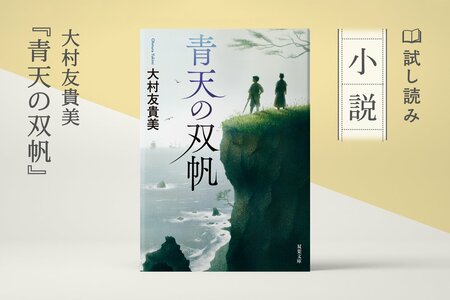鎮漣が家督を継げば、家中は割れ、蒲池の家は滅びることになる。
老臣たちは、もっぱらそう触れ回っている。名門田尻家の姫として誇り高い母には、自らの子が軟弱と蔑まれることが許せぬらしかった。鎮漣を廃嫡させ、同腹の弟に跡目を継がせるため、崇久寺の住持と密談を重ねていることは誰もが知ることだ。
父宗雪が廃嫡を認めないことに業を煮やし、近頃では腕の立つ者を密かに雇い入れているという風聞もある。それが何のためかは、考えるだけで恐ろしかった。
「十郎殿は、蒲池と田尻、由緒正しき武門の血を引いているのです」
切れるように細い母の瞳から、思わず目を逸らした。
この目だ。母にこの目を向けられると、目尻が熱くなる。鎮漣に目を向けながら、鎮漣を見ていない。母の目は、自らの子としてふさわしい武士だけを求めている。
「なぜ、そなたのような子が生まれてしまったのか」
情けないと舌打ちし、母は首を振った。
「統光。しかと見張っておきなさい」
そう言い残した母は、本堂へと姿を消した。母の笑顔を最後に見たのはいつのことか。それも分からなかった。
義心、鉄の如し――。
父は、敵味方からそう称賛される武士だった。
百七十余の城が散在する筑後は、多くの領主が主君を変えながら離合集散する戦乱の地だ。その中で、蒲池家は豊後(現在の大分県)を本貫とする大友家に仕え、その筑後支配の一端を担ってきた。当代の蒲池宗雪は、流血を顧みずに働き続け、知勇兼備の将として厚く信頼されている。
父への称賛は、味方からばかりではない。敵からも畏敬される所以は、大友家に滅ぼされ流浪となった者すら手厚く庇護してきたことによるものだ。民に至るまでの誰もが、父のことを理想の武士だと言い、筑後十五城の旗頭と呼ぶ。
だが、その称賛は悍ましい犠牲の上に成り立っているものだ。
「流した血の量が、忠義の厚さと言うならば、民にとって迷惑この上ないことではないか」
曇天にそう呟くと、統光が静かに書を閉じた。
「滅多なことを口にされませぬよう。心なき者が聞けば、謀反の疑いありとして、私も磔にされましょう」
身体を杭に縛り付けられ、槍で突き殺される。想像して、怖気がこみ上げてきた。統光が声を落とした。
「確かに、蒲池の御家は、大友の御屋形様の命で筑前(現在の福岡県)から肥後まで駆けまわっております。しかしそれも、柳川の民を守るためであることは、十郎様もご存じでしょう」
「大友の庇護を捨てれば、柳川は四方を敵に囲まれるな」
「左様です。北の大内、肥前(現在の佐賀県と長崎県)の少弐、肥後の菊池。大友の庇護下にあるからこそ、彼らは容易に柳川への手出しはできませぬ」
「だが、その大友の命によって、どれほどの柳川の民が死んだ」
統光が口をつぐんだ。
「見知らぬ肥後の地まで出向き、亡きがらだけが柳川に戻ってくる。戦のたび、城下には念仏の声が溢れているではないか」
城内から崇久寺まで歩く途中も、肥後の菊池征伐において南関(現在の熊本県北西部)で戦死した兵の骸が、列をなしていた。境内の僧たちは慌ただしく動いているが、それも千に上るという戦死者の供養塔を用意するためだった。
父への称賛が大きくなるほど、崇久寺の墓所はどこまでも広がっていく。
ため息を吐き、鎮漣は右手で左腕を掴んだ。
「統光、私は殺されて死にたくはない」
幾千の骸を見てきた。顔中に刀傷をつけ、糞尿と腐った臓物の臭いを漂わせ、蛆がたかっていた。青白い顔と白く濁った瞳を初めて見た時、鎮漣は夜寝ることもできなくなった。亡きがらを抱きしめ、その功績を褒めたたえる父も恐ろしかった。
蒲池の後継ぎとなれば、いずれ鎮漣も戦場で殺されるかもしれない。自分の骸は、敵の将によって、無惨に晒されるのだろう。
「書も好かぬ。刀はもっと好かぬ。戦など最悪だ。私が当主となれば、蒲池の家はすぐに滅ぶぞ」
統光が身じろぎせず、口を開いた。
「十郎様の優れたるところは、かようなところではありませぬ」
慰めの言葉に、鎮漣は顔を背けた。自分の優れたところなど、何があろうか。劣っているところを挙げればきりがなかった。戦に怯え、刀を見れば手足が震える。帰城した兵の流す血を前に、気を失ったこともある。戦ぎらいと呼ばれ、父からは鬼のような形相で折檻されてきた。
それでも、恐ろしいものは恐ろしいのだ。
「……戦ぎらいの、何が悪い」
鎮漣の呟きに、統光が目を細めた時だった。
遠く、太鼓の音が響いた。三つ連なり、それが十回に及ぶ。
言いかけた言葉を飲み込み、統光の顔が強張った。
その音律は、変事の報せだった。
慌ただしく城内へ戻った鎮漣たちは、その足で大書院へと向かった。すでに留守役を命じられた者のほとんどが集まり、三十畳ほどもある大書院は人の熱気でむせかえるようだった。
用意された褥へ座ると、兄の鎮久が虎髭を震わせてこちらを睨んでいた。正面に端座し、額には青筋が浮かんでいる。
「遅い」
「崇久寺におりましたゆえ」
「言い訳をするな!」
大書院が静まり返った。
「非常の鼓の音だった。何をおいても真っ先に駆けつけねばならぬ。十郎、お主は端武者などではなく、筑後十五城の旗頭、蒲池家の正嫡なのだぞ」
兄の厳しい言葉もいつも通りだった。
妾の子ゆえ、当主になることは叶わない。自らのさだめを聞かされた頃から、兄の鎮漣に対する態度は堅くなった。鎮久を後継ぎに望む家中の声も、兄の尊大さを助長させてきた。
頭を下げれば、兄は満足するだろうか。
腰を折った時、背後から失笑が聞こえた。一人や二人ではない。頭上で、兄は嗤っているだろう。
鎮漣への失望が大書院に広がった頃、咳が一つ響いた。
大木鎮堯。統光の父だ。一文字に結ばれた口は、融通の利かない性格を見事に表している。蒲池家の宿老として宗雪がいない間の取りまとめを命じられていた。大書院の空気が落ち着くと鎮堯が一座を見回した。
「長門国(現在の山口県)、大内家に変事があった」
「戦ぎらいの無敗大名」は全4回で連日公開予定