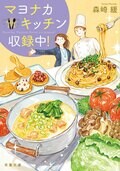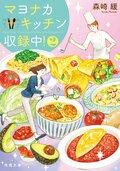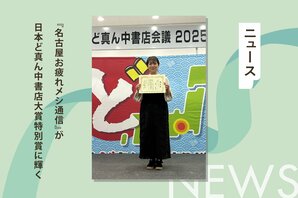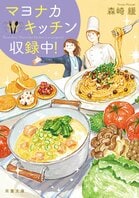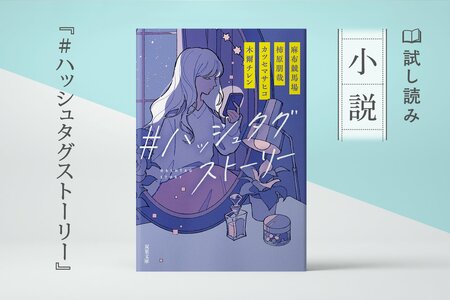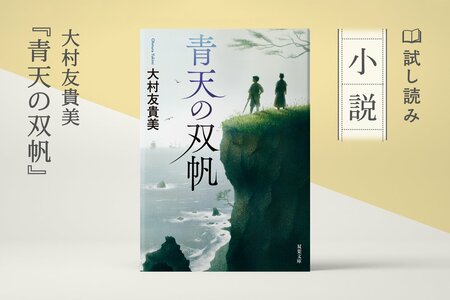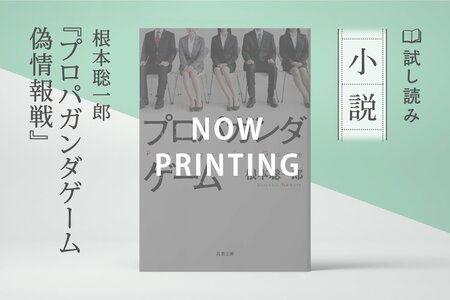「納得できる形になったら読ませてよ。楽しみにしてるから」
「はい」
僕が頷くと、依田さんは笑顔で僕の二の腕を叩いた。
「期待してるよ、仁木くん。君のパッションを見せてくれ」
「わかりました」
僕は依田さんが好きだ。この人は僕みたいな実績もまだない新米にも心を砕き、真剣に向き合ってくれる。今時の若者と言われる僕なりに、この人の期待には応えたいという気持ちがあった。
「じゃ、よろしくな」
話を終えようとした依田さんが、壁掛け時計を見た。
編集局内にはそのまま時計店が開けそうなほどたくさんの壁掛け、あるいは吊り下げ時計が設置されている。日本時間を表示しているものもあれば、海外都市の時刻を示しているものもあった。依田さんが見たのは日本時間の方で、今は午前十時を過ぎたところだ。
「そういえば今日は、青木クリニックに取材の日だった?」
「あ、そうです。これから星ヶ丘まで行ってきます」
僕の仕事は名古屋メシのコラムだけではない。生活部には僕と依田さんを含めて七人の記者がいるが、その中で僕は子育て記事を担当しており、例えば出産や育児についての自治体の補助やボランティアの支援などを調べたり、子供の発達や病気について取材した上で特集を組んだり、子育てに関する行政の施策に動きがあれば新旧照らし合わせて記事にしたり、時には子供たちの間の遊びの流行なども調査したりする。今日は来たる夏休みに備えて子供の感染症について取材に行く予定だった。医療担当だった依田さんは青木クリニックの院長ともパイプがあり、今回取材を申し込むに当たって仲介までしてくれた経緯がある。
「先生によろしく言っておいて。また娘を連れていくからって」
依田さんからの伝言を携え、僕は席を立った。
立ち上がると編集局内の様子がある程度は見渡せるが、八階建てビルのワンフロアまるまるの広さがあるので端の方までは見えない。雑誌から専門書まで取り揃えている大きな書店くらいの広さはあるし、いつもほのかに紙とインクの匂いがするところもちょっと似ている。初めて編集局に足を踏み入れた時は途方もない面積と働く人の多さに戸惑いすらしたものだ。勤務を始めて三ヶ月が過ぎたが、他部署の人の顔を覚えられないどころか、まだ会ったことのない人すらいる。
中京新聞は愛知県名古屋市に本社を置く新聞社であり、愛知県はもちろん岐阜県、三重県でもシェア一位を誇る国内最大級のブロック紙だ。発行部数は在京新聞社の全国紙と肩を並べる数字だそうで、それだけの購読者が僕の書いた記事も読んでいるかもしれないと思うと、緊張感がある。
そんな新聞紙面を制作している編集局には社会部、政治部、経済部、生活部、文化部、スポーツ部などが地続きで並んでおり、各部署ごとに机を寄せ集めた『島』を形成していた。資料の詰まった書棚やスチール棚がパーテーション代わりにはなっているものの、壁はなく、物理的には風通しのいい職場だ。
いつも忙しそうな姿が目につくのは社会部の人たちだった。それでなくとも大都市名古屋、そして一大経済圏である中京圏では日々事件や事故がつきものだし、看過できない社会問題だって常に存在している。ニュース速報が入ろうものなら慌ただしく駆け出していく記者もいるし、警察署に詰めていて滅多に戻ってこない記者もいるそうだ。
「先日の中区で起きた窃盗、やはり連続ひったくり事件との関連性があるようです」
「警察発表によれば、犯人のバイクが監視カメラに写っていたとのことで──」
今も出口へ向かう僕の脇を、社会部の人たちが慌ただしく追い抜いていった。時間に余裕があるからとのんびり歩いていた僕も、自然と背筋が伸びてしまう。
出口近くに島があるスポーツ部は空席が目立っていた。七月は夏季スポーツが盛んな時期で、特に高校野球は熱心に報じられている印象がある。愛知県大会は十ヶ所の球場で行われていると聞いたので、現地取材にもそれなりの人数を割いているのかもしれない。また愛知には野球、サッカー、バスケットボールなどメジャースポーツのプロチームが揃っている上、ウインタースポーツの強豪校まである。スポーツ部はスポーツ部でいつも忙しそうだ。
僕のいる生活部は、社会部やスポーツ部と比べたらそれほど慌ただしくはない。緊急性のあるニュースを扱うことがあまりないので締め切りには余裕があるし、取材先は専門家や病院、公的機関などのことが多かった。生活部の島は常にざわざわしている編集局の中でも静かな方で、穏やかな空気が漂っていて過ごしやすい。
もっとも名前の通り『生活』に関わる部署だけあって、記事の内容は読者に寄り添うものが求められる。僕は子育て担当だが子供はいない。それどころかまだ独身で、経験から語れることは皆無だが、依田さんはこんな言い回しで太鼓判を押してくれた。
「仁木くんだって昔は子供だったんだから、その時の親御さんの気持ちになって記事を書けばいいんだよ」
僕が憧れた新聞記者像もどちらかといえば生活部の仕事に近い。ニュースを追う記者ではなくて、人々の暮らしに密着した、誰かのためになる記事を書く方が面白そうだ──そう思ってこの仕事を志したのだ。
丸の内駅から地下鉄桜通線に乗り込み、今池駅で東山線に乗り換える。
名古屋市内の移動は地下鉄が特に便利だ。住み始める前は車社会という印象があり、マイカーがないと買い物やレジャーに不便ではないかと案じてもいたのだが、住んでみれば移動は地下鉄だけで事足りる。たまに取材で名鉄やJR東海道線を利用することはあったが、名古屋市内なら地下鉄で十分だった。
ラッシュを過ぎた正午前だが、東山線は乗客が多く混雑している。僕はカバンを胸に抱き、ぎゅっと身を縮めて乗り込んだ。地下鉄の車内は走行音が大きく、ノイキャンのないイヤフォンだと何も聞こえなくなるほどだった。僕は通勤でも地下鉄を利用しているが、乗車時はイヤフォンの使用を諦め、資料を見たり記事の続きを考えたりしながら時を過ごしている。
今は、スマホに保存している記事を読み返しているところだ。
〈洋食店のハンバーグはデミグラスソースが主流だが、東京都豊島区池袋にはすき焼き風ソースのハンバーグを提供する老舗店がある。「創業当時からの味を守りたいと続けてきました」と「洋食タイラ」を営む平高雄さん。常連客に愛されている伝統の味は、店主の心意気によって守られてきた。〉
これは僕が書いた記事ではない。昨年夏、とある全国紙の増頁──本紙とは別に折り込まれている特集紙面に掲載された記事だ。洋食タイラ店主の笑顔の写真、そして照り焼きハンバーグの写真も共に載っている。
〈つなぎを使用しない粗びきハンバーグは牛肉のうま味が詰まっており、割り下から作るすき焼き風ソースとの相性も抜群だ。流行に左右されない味付けの極意は、創業者から受け継いできた八十年物のレシピにある。時代が流れても伝統は変えない、壊さない。老舗のプライドが光るこの味が多くの客をつかんで離さないのだろう。〉
グルメリポートとしてはありふれた筆致だ。だが店で働いていた僕からすると、これほど心揺さぶられる称賛の言葉は他になかった。伝統の味が認められた喜びもあったし、その評価が新聞というメディアに掲載されたことで、口コミやネットレビュー以上に『公のもの』になった実感もあったのだ。この記事が掲載された半年後に洋食タイラは店を閉めてしまったが、記事そのものが僕の中に憧れの形で残った。『老舗のプライドが光る味』、その言葉は今でも思い出したくなるほど的確にあの店の味を表している。こんなふうに誰かを喜ばせる記事を、いつか僕も書いてみたい。
「名古屋お疲れメシ通信」は全3回で連日公開予定