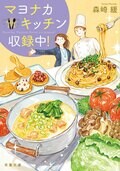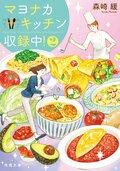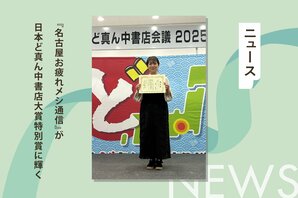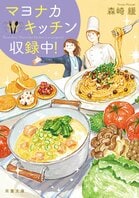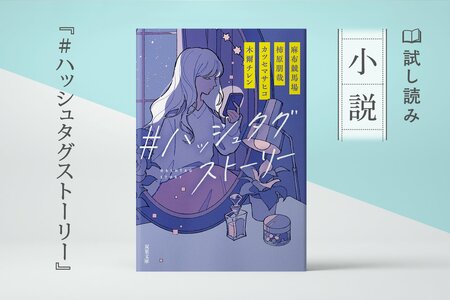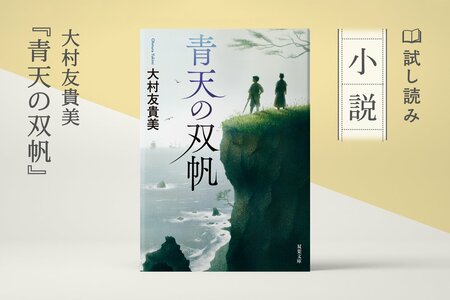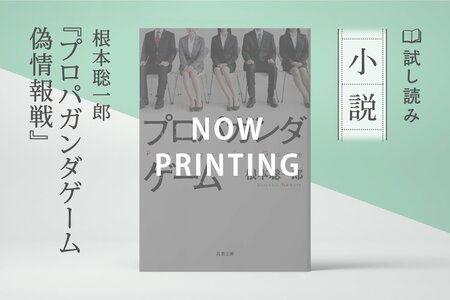名古屋市中区三の丸、これが僕の現在の職場、中京新聞社の所在地だ。
三の丸というだけあって名古屋城の三之丸の内側にある。職場の近くには二十一世紀の今でも三之丸の土塁と空堀の跡が残っていて、そこから名古屋城本丸までは更に一キロくらいの距離があることから、本来は相当大きな城だったんだと想像すると、途方もない気持ちになった。
去年までの僕にとって、名古屋は東海道新幹線の駅の一つという程度の印象しかなかった。東京生まれ東京育ちの僕には、家族旅行で大阪まで行った時も、あるいは修学旅行で広島へ向かった時も、名古屋駅は新幹線で通り過ぎるだけの駅だった。ホームに立ち食い蕎麦ならぬ立ち食いきしめんがあるのを車窓から見て、どんな味がするのかなと思った程度だ。
だからまさか、自分が名古屋で働くことになるなんて想像もしていなかった。
「名古屋の丸の内駅で働くの? そこって名古屋城のお膝元だろ?」
中京新聞社に就職が決まったことを報告した時、僕の祖父が目を輝かせていたのを覚えている。
「千春、落ち着いたらそっちに呼んでくれ。お父さんお母さんと一緒に行くから」
東京を離れる日、新幹線のホームまで両親と共に見送りに来た祖父が、最後にそう言っていた。僕としてもいつかは家族みんなに遊びに来てもらい、名古屋城を見せたいと思っている。
僕が今いる中京新聞社の本社ビル五階の窓からは、名古屋城の緑青色の屋根と金の鯱の輝きが見えていた。近代的な街並みの中に城がどっしり構えている風景は、まだ新鮮で仕方がない。
「名古屋の人は、お城のある生活をどういうふうに捉えているんでしょうね」
ふと疑問を口にすると、直属の上司である依田さんはびしっと指を差してきた。
「仁木くん、そのクエスチョン大事だよ! そういう気づきがいい記事の第一歩になるんだ」
「はあ……」
「気の抜けた返事をしない。そういう疑問を抱いたら、自分の足で調べに行く。それが新聞記者の仕事ってもんだよ」
依田勇人さんは記者歴二十年を超える大ベテランだ。ちょんまげみたいに結んだ髪に立派なあごひげと、時代劇で悪の人斬りを演っていそうな顔立ちをしている。物腰はとても柔らかな人だが、かつては医療担当記者として、感染症がもたらした日本の混乱や終末期医療の在り方、現代の医療制度における課題などを筆鋒鋭く追及してきたらしい。現在はここ中京新聞社の編集局で生活部のデスクを務めている。
僕はそんな依田さんの下に配属され、今年の四月から三ヶ月、記事の書き方や取材のやり方などをみっちり学んできた。お蔭でこの頃は新聞記者らしく仕事ができるようになってきたと自負しているのだが、依田さんに言わせるとまだ不足しているらしい。
「仁木くんはパッションが足りないんじゃないか」
と、依田さんは自らのあごひげを撫でる。これは抱えた不満をやんわり伝えようとしてくる時の、依田さんの癖だった。
そして僕には、話している相手の顔を密かに観察してしまう癖がある。
「なかなか熱くならないというか、失敗を恐れず踏み出す蛮勇さに欠けるというかね。いいんだよ、若いうちなんて失敗してナンボだ。常にアンテナを張って歩き、どんなネタでも貪欲に拾って生かすんだ」
「なるほどですね」
僕は頷いた。
本音を言うと失敗を恐れているわけではなく、文化部ならともかく生活部記者の僕が名古屋城に対する意識調査をしても記事にはしにくいだろうし、世間話をしただけのことだ。とはいえ依田さんの言葉は熱くて格好いいので同意しておく。
生活部はその名の通り、人々の暮らしに関するテーマを取り上げており、例えば今日の朝刊の生活面トップ記事は『食中毒予防に昔の知恵 抗菌の知恵あれこれ』だし、その他には増加する強盗、ひったくり事件に備えた防犯グッズの紹介、市内の小学校で地場産オーガニック食材を使った給食が出されたというニュース、端切れで作るエコバッグの型紙などが載っている。
閑話休題、僕の同意は依田さんに響かなかったようだ。たちまちしょんぼりして自分の机に向き直ってしまう。
「今時の若者って難しい……」
お互いに響かないと感じているのだから、なんだか申し訳ない限りだ。
今時と言っても僕は既に二十六歳、新米記者を名乗るには少々年嵩だ。中京新聞社には第二新卒で入社して、ここ生活部に配属された。
ちなみに依田さん以外の同僚たちから、僕はこんなふうに呼ばれている。
「あっ、ほら。あの子だよ。元料理人の新人くん」
生活部のデスクが並ぶ『島』を、背伸びして眺めてくる他部署の記者さんの声だ。僕が振り返って会釈をすると、笑顔で手を振られた。
毎年三十、四十人は採用される新人の中でも元料理人の肩書は珍しいようで、七月に入った今でも噂になっているらしい。そもそも前職のある新人自体が希少なのだから仕方ない。
僕は昨年まで東京の池袋にある洋食店で料理人をしていた。洋食と言っても高級店ではなく、昔ながらの庶民派洋食店だ。だが店が諸般の事情で閉まることになり、僕は次の職探しを余儀なくされた。新卒カードが使えないこともあり職探しは楽ではなかったが、開き直り、どうせならやりたいことをやろうと新聞社の求人を探しまくった。あいにく在京の新聞社は経歴で門前払いがほとんどだったが、名古屋に本社を置く中京新聞社では第二新卒の採用を行っていた。どうにか試験にもパスできた僕はこの春、意気揚々と名古屋に乗り込んできた。
名古屋に住むのも初めてなら、いわゆる会社勤めも初めてだった。前の職場は家族経営の小さなお店だったから、上司らしい上司がいるのも、部署なるものに配属されることも全てが新鮮で堪らない。
「まあ、仁木くんも得意分野ならやる気になれるかもな」
短い間に自力で立ち直った依田さんが、僕に向き直って微笑んだ。
「例のコラムは進捗どう? 筆は進んでる?」
「一応、書き始めてはいるんですが」
僕は正直に現状を報告する。
「まだ掴みかねているところがあるんです。名古屋メシというものを」
コラムの大きなテーマは『県外の人から見た名古屋メシ』だ。グルメとして既に全国的な知名度のある名古屋メシではあるが、他所からやってきた人は唯一無二のその個性に戸惑うことも多いという。
実際、僕も名古屋に来て早々、ふらっと入った食堂で赤だしが出てきた時は戸惑った。定食についてきた味噌汁の色が濃いなとは思ったが、飲んでみたら自分で普段作るものとは風味が全く違うのだ。豆から造られたという八丁味噌には独特の深いコクや酸味、ほのかな苦味もあり、いつもの味噌汁感覚で飲むとびっくりさせられる。
コラムは月一掲載、全五回の連載を予定しており、掲載日は第四週の水曜日と決まっていた。なぜこの日かというと、普段水曜日にレシピ記事を載せている料理家さんが月末は本業で忙しいからだそうだ。連載開始はこの七月と言われていたが、僕はまだ一回目の記事も書き終えていない。今は出会う名古屋メシの意外性にいちいち驚かされているばかりで、味にしっかり向き合えていないという状況だった。
「その『驚き』を素直に書けばいいんじゃないの」
報告を聞いた依田さんはそう言うのだが、僕は自分で納得できていない。
「依田さんは僕が元料理人だからこそ、このコラムを任せてくださったんですよね。僕としても経験を踏まえて書くなら、ただ驚いたというだけで終わらせたくないんです。もっと名古屋メシを掴んでおきたいと言いますか……」
料理の記事を書くなら、その美味しさを前面に押し出して書きたい。驚いた、だけなら書き手は僕でなくてもいいはずだ。だから一回食べただけでは済ませたくないし、できれば自分で作ってみてから記事にしたかった。
「いいね! やっぱり料理に関してはパッションがあるんだな。仁木くんに任せて正解だった」
進捗としてはよくない状況にもかかわらず、依田さんは嬉しそうな顔になる。
「もちろん仁木くんの前歴も任せた理由ではあるけど、そもそも地元の味を地元民が誉めても『そりゃそうだ』としかならないからな。県外から来た人が地元グルメの魅力を教えてくれたらみんな嬉しいし、再発見にもなる。そういう記事を期待してるんだよ」
僕の生まれ育った東京で、地元グルメと言えばもんじゃくらいしか思い浮かばない。
だが勤めていた洋食店には創業当時からの味と言われる看板メニュー、すき焼き風ハンバーグがあった。割り下から作るソースはザラメを加えているので照りがよく、粗挽きのハンバーグに絡めて食べると肉の旨味と相まってとても美味しい。どのメニューだってお客様から誉められると嬉しかったものだが、照り焼きハンバーグへの誉め言葉が一番嬉しく、誇らしかった。
同じようなことを、人々は地元グルメに思うのだろう。風土が生み出した名産品をより美味しい料理に仕上げた歴史を知っているからこそ、他所から来た人に誉められたら嬉しくなる。
「名古屋お疲れメシ通信」は全3回で連日公開予定