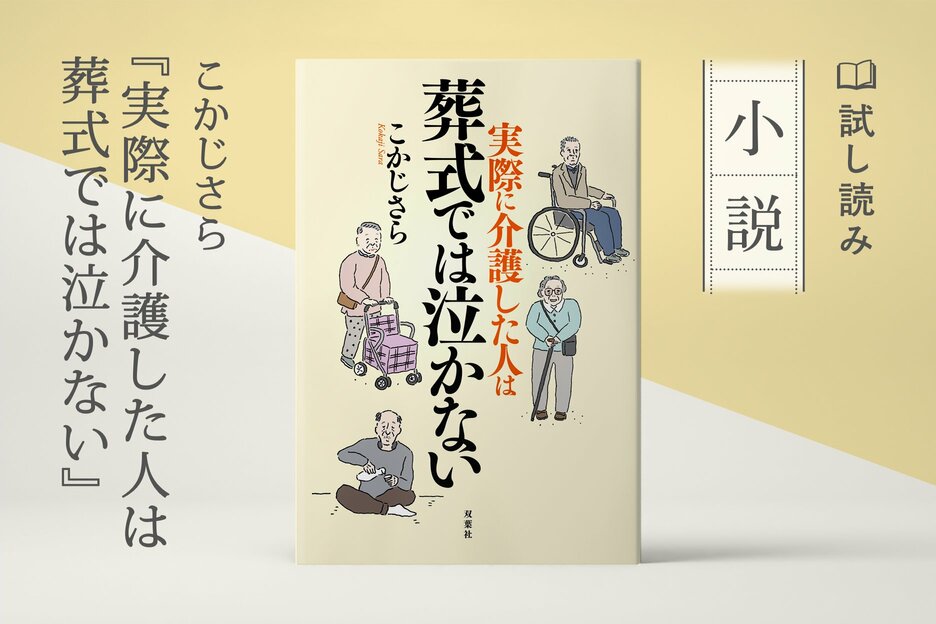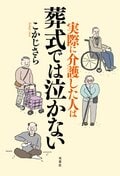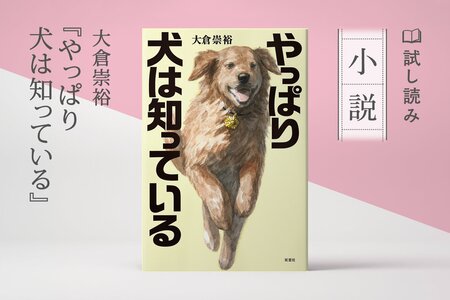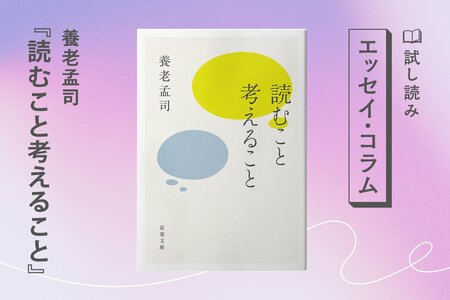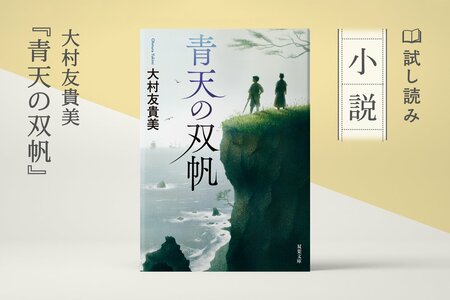はじめに
「困っているのはお年寄り本人ではなく、ご家族や周りの人なんですよね」
介護付き有料老人ホームの施設長がつぶやいたそのひと言に、
「そうなんですよ」
私は大きく頷かずにはいられなかった。
足腰が衰え、認知機能もかなり低下しているにもかかわらず、口だけは驚くほど達者。ウチの母もまさしくその一人なのだが、日頃から高齢者と接している方ならそれがどれほどやっかいかはおわかりいただけるだろう。
二階の自室で仕事をしていると、むむむ……? 階下の台所から立ち上ってくる焦げた臭いが鼻を突く。
まただよ。
ため息をつきながら階段を駆け下りると、真っ黒焦げになった片手鍋からもくもくと黒煙が上がっている。
急いで火を止め、鍋をシンクに放り込み、蛇口を捻る。
一体、いくつ鍋を焦がせば気が済むのだろうか……。
耳が遠くなった九十代の老父母が大音量でテレビを観ている茶の間をのぞくと、火を付けっぱなしにした張本人は、口を半開きにして午睡を貪っている。
「おかあさん! 火を付けたら、その場を離れないようにって前にも言ったよね」
「えっ……?」
すぐには状況を把握できないのだろう。空虚な眼差しで私を見る。
「鍋が火を噴いてたの!」
ここまで言われてやっと、何が起こったのかを理解できたのか。
「そうだ! 枝豆を茹でてたらトイレに行きたくなって」
言い訳がましいことを言いながら、どっこらしょ! と、ソファーから立ち上がった。
忘れっぽくなっているのは仕方ないが、火の元に関することは洒落にならない。
「トイレに行きたくなったら、必ず火を止めてから行くようにしないと」
やんわりと釘を刺すが、
「いつもはちゃんと消すんだけど、今日はたまたま」
いやいや、たまたまじゃないでしょ。
この期に及んで自分の非を認めようとしない。
「ほかのことをやると、前にやってたことを忘れちゃうんだから、特に火の傍を離れるときは気をつけないと、火事になってからじゃ遅いんだよ」
ガミガミ言いたくはないが、こう何度も火を付けっぱなしにされたら黙って見過ごすわけにもいかない。だが、負けん気の強い母は、
「お前は、何度もしつこいんだよ」
非難の矛先を私に向けてくる。
年を取るとなぜ、こんなにも頑固になるのだろうか。
老親との同居は、こうした、ため息をつきたくなるようなやり取りの繰り返し。端っから聞く耳を持たない相手には、言うだけ無駄、言っても無駄なのはわかってはいる。
がしかし、すべてを飲み込み、ただ黙って見守るなんてことは私のような凡人にはできるわけがない。
兎にも角にも、高齢者介護にきれいごとは通用しない。
そう身を以て思い知ったのは二〇一九年の春、千葉県の片隅にある故郷にUターン移住し、当時八十九歳だった父と八十七歳の母と同居してからのことだ。それまでは、介護をどこか他人事のように捉えていたのだから、
「介護のたいへんさは実際にやった人にしかわからないんだよ!」
老父母との同居以前の自分に言ってやりたくなる。
感情のコントロールが利かなくなり、ときに狂犬と化す老父母への対応だけでもてんてこ舞いだというのに、ある事件をきっかけに実家近くに住む子どものいない叔父と叔母(共に老父母同様九十代目前)の面倒まで見ざるを得なくなったのだから……。そのストレスたるや、想像を遙かに超えている。
*
「昔々、あるところにお爺さんとお婆さんが住んでいました」ではじまる昔話は、まさにいまは昔。二〇二五年の我が国ニッポンは、
「日本中いたるところにお爺さんとお婆さんが住んでいます」
こんな冗談が冗談と言えないほど、我が家のご近所も、杖を突く、老人用カートを押すなど、危なっかしい足取りの高齢者で溢れかえっている。
「本日の午前十時頃出掛けたまま行方不明になっている八十代の男性がいます。身長百六十センチくらい。瘦せ型で短髪の白髪頭。グレーのジャンパーに黒のズボン、腰が少し曲がっています。見掛けた方は、お近くの交番まで連絡をお願いします」
行政無線も頻繁に流れてくる。
それもそのはず、二〇二三年九月の総務省発表によると、八十歳以上の人口は約一千三百万人。
人口の九・九パーセント(十人に一人)が八十歳以上なのだから、それも当然と言えば当然だろう。そして視点を変えると、高齢者を介護、サポートしている人も日本中いたるところにいる、ということになる。
それを実感するのが、同年代の友人との会話だ。
「ウチの母親、とにかく気が強くてさ。こう毎日憎まれ口を叩かれたら堪らないわ」
思わず愚痴をこぼすと、
「ウチもよ。貯金はない、不便な所にある実家は売りたくても売れない。これからどうしようって頭を抱えてる私の気持ちなんてお構いなしに我が儘を通そうとするんだもの。腹立つなんてものじゃないわよ」
「ウチは舅。言った、言わないの果てに怒鳴りはじめるなんてことも日常茶飯事。年を取ると、私たちもあんな風になるのかしら」
気づくと、老いた親のあるある話で盛り上がっている。
まあ、一度言い出したら聞かない、何が何でも意地を張り通す、そんな自分本位な高齢者の何と手強いことか。
まともに対応していたら、こちらが壊れかねない。実際、かなり追い詰められている同輩があちらこちらにいる。
自身の経験からも、終わりの見えない高齢者介護で心掛けるべきは、頑張り過ぎないこと、一人で抱え込まないこと、情に流されず、ある程度突き放してクールに対応すること。さらには、親に優しくできない、苛々してしまう自分を責めないこと。
老親の介護に汲々としているご同輩のみなさんに、千葉県の片隅で繰り広げられる老父母と叔父と叔母とのてんやわんやな日々が参考になれば(ならないか……)と思い、ペンを取った次第である。
「実際に介護した人は葬式では泣かない」は全4回で連日公開予定