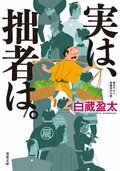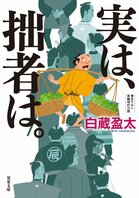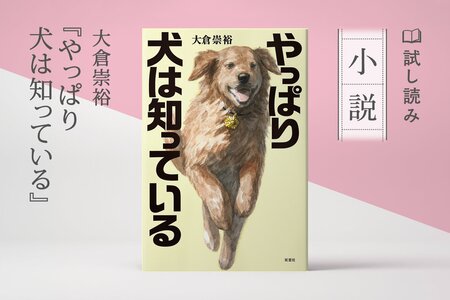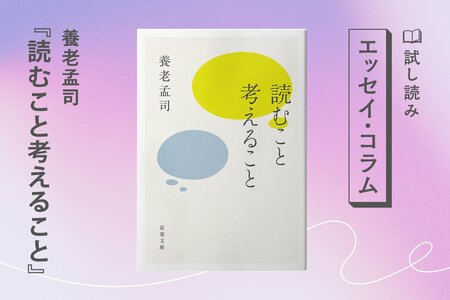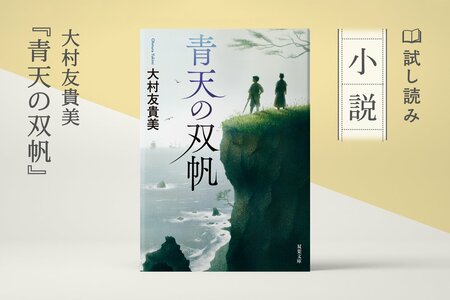秘剣、隠密、裏稼業。
影と忍びは江戸の華。
やけに気さくなその人は、
実は高貴なあのお方。
江戸の町は、決して人に知られてはならぬ裏の顔であふれている。
第一章 実は、それがしは。
一
「ああ、案外遅くなっちまったなぁ。早く帰らねえと木戸が閉まっちまう」
棒手振りの八五郎は、そんな独り言をブツブツ言いつつ、別に急ぐでもなく提灯片手に夜道を歩いていた。桜も散り、そろそろ木々に若葉が芽吹きはじめる季節だが、宵五つ(午後八時頃)ともなると外はまだ若干肌寒い。
亀戸の知り合いを訪ね、ちょいと一杯ひっかけて深川の長屋に帰るところだった。八五郎は齢二十二、まだ直ちに身を固めねばと焦る歳でもなく、妻子を持たぬ気楽な身の上である。
天秤棒を担いで青菜を売り歩く、棒手振り稼業の実入りは少ないが、自分一人が食っていくだけなら多少の酒手も手元に残る。大店に奉公に出て、毎日番頭の顔色を窺ってびくびく暮らすような人生よりはよっぽどましだと、いまの気ままな貧乏暮らしを八五郎はそれなりに気に入っていた。
そんな八五郎が、半刻(約一時間)ほどの道のりをほろ酔い気分で鼻唄交じりに歩いていたら、人通りの少ない辻の先から、男どもが何やら大声で騒ぐ音が聞こえてきた。
「なんでえ。こんな夜中に喧嘩か?」
声の人数は五、六人くらいだろうか。厳めしい言葉遣いからいって、この先で揉めているのはおそらく町人ではない。おおかた浪人同士の諍いといったところか。だとしたら触らぬ神に祟りなしで、見なかったふりをして素通りするに越したことはない。
だが、酔っぱらって気持ちが大きくなっていた八五郎は、むくむくと湧いてくる野次馬根性をどうしても抑えきれなくなった。それで、思わず塀の陰に身を隠し、ひょいと頭だけを出して声のするほうをのぞき込んだ。
わずかな月明かりを頼りに八五郎が目を凝らすと、その先で六人の侍と一人の浪人風の男が対峙していた。
侍たちは全員が仕立てのよさげな羽織を着ている。その身なりからいって、どこぞの大身の武家の一行であろうことは一目でわかった。中央にいるのがおそらく主人で、その主人を守るように五人の供回りが抜刀して扇の形に並んでいる。
それに相対するは、月代の伸びきっただらしない浪人髷を結った、着流し姿の痩躯の男。刀を下段に構えたその姿はまるで古柳のようで、いかにも不気味だ。そして、その不気味さをさらに際立たせているのは、男が顔に着けている黒漆塗りの面頬だった。
恐ろしげな面頬に隠されて、浪人の目から下の表情は見えない。ギラリと鋭く光る目玉だけが、暗闇の中で静かに侍たちを睨みつけている。浪人は幽霊のようなおどろおどろしい声で、侍の集団に声をかけた。
「抜け……刀を抜け……」
主人と思しき中央の侍だけが、まだ刀を抜いていない。供回りの一人が鋭い声で不気味な浪人を怒鳴りつけた。
「面妖な奴め! こちらのお方を、市橋伊勢守様と知っての狼藉か!」
「抜け……刀を抜け……」
「問いに答えよ無礼者! さもなくば斬るぞ!」
「抜け……刀を抜け……」
浪人はさっきから同じことしか言わない。
なにやら魂のこもっておらぬ木偶のようで、実に気味が悪い。とうとう主人らしき侍が、辛抱できなくなって周囲に号令をかけた。
「ええい、不気味な奴じゃ! 皆の者、構わぬ。斬って捨てよ!」
その声と同時に、五人の供侍たちが叫び声を上げて一斉に浪人に飛びかかる。侍たちの踏み込みは鋭く、剣術の心得のない八五郎が素人目に見ても、とても避けられそうにない練達の一撃のように見えた。
だがそのとき、摩訶不思議なことが起きた。
浪人が、まるで五人の侍たちがどう動くのかを先に知らされているかのように、わずかに体をひねるだけで強烈な踏み込みを易々と躱したのだ。
そして、下段に構えた刀を摺り上げて侍の一人を斬りつけたが、その斬撃はまるで撫でるかのように、ゆったりと滑らかなものだった。次の刹那、その奇妙な斬撃を食らった侍は、腕から鮮血を飛び散らしてその場にうずくまる。
浪人は返す刀でもう一人の侍の脛を、これまた優しく、書の達人が静かに筆を振るうかのごとく悠々と薙ぎ払った。これだけゆっくりした斬撃ならば簡単に躱せそうにも見えるが、相手はなぜか一歩も動けず、あっさりと斬られてその場に崩れ落ちる。
あっという間に二人の仲間が倒されたことで、侍たちは思わず怯んで少し距離を置いた。
「抜け……刀を抜け……」
相変わらず、浪人はそれしか言葉を発しない。黒い面頬で隠されたその下の表情がどんなものかがわからないので、まるで幽霊のように不気味だ。
その闘いを物陰から見ていた八五郎は、思わずごくりと唾を呑み込んだ。
「間違いねえ、ありゃあ噂の『鳴かせの一柳斎』だ」
いま、江戸中の話題をさらっている謎の幽霊剣士、それが「鳴かせの一柳斎」である。
一柳斎は夜中、裕福そうな侍を見つけては行く手を阻み、刀を抜けと迫る。その剣は捉えどころがなく、刀を下段に構えてゆらゆらと切っ先を動かす様子がまるで柳の枝のようであることから、誰が呼ぶともなく「一柳斎」の名がついたのだった。
その太刀筋は一見するとゆっくりで、撫でるように柔らかであることから、傍目で見ていると簡単に受けたり避けたりできそうに見える。だが、実際に一柳斎と闘った者は口を揃えて、
「気がつけば斬られていた」
と言った。
金持ちの侍は当然ながら、腕の立つ供回りを身の回りの警護のためにぞろぞろと引き連れて歩いている。それなのに、そんな屈強な供回り複数人を一度に相手にしながら、一柳斎はこれまでただの一度も敗れたことがなかった。それどころか傷のひとつも負ったことがない。
「ゆるゆるとした足さばきで、決して動きも速くないのに、なぜか何度斬りつけても刀が当たらない」
これも、一柳斎と闘った者たちがしばしば証言することだ。
そして一柳斎は、警護の者たちを死なぬ程度に傷を負わせたり、峰打ちで気絶させたりして闘えぬようにしてから、狙いをつけた侍に改めてこう尋ねるのだ。
「抜け……刀を抜け……」
──不気味な黒漆の面頬に、古柳のごときめっぽう強い剣。どう見てもあの男は「鳴かせの一柳斎」だ。ということは、次は……。
八五郎は無責任な野次馬根性で、事の成り行きを物陰でわくわくしながら眺めていた。そうこうするうちに、一柳斎はあっという間に警護の者たちを片付け、市橋伊勢守と呼ばれていた裕福そうな侍に改めて抜刀を迫っている。
「さあ、鳴くか? 鳴かぬか?」
八五郎は固唾を呑んで、期待のこもる目で見つめながら一柳斎の次の言葉を待った。一柳斎が「鳴かせの一柳斎」の異名を取るのは、この後に見せる奇妙な行動にあるからだ。
「ええい! 不届き者め! 斬り捨ててくれる!」
市橋伊勢守が激昂して刀の柄に手をかけ、鯉口を切った。だが、五人の供回りをあっという間に倒した一柳斎のとんでもない腕前を目にして、市橋伊勢守の顔には、八五郎でもはっきりとわかるほどに焦りの色が浮かんでいた。
すらり、という鞘走りの音と共に市橋伊勢守の刀が抜かれる。白刃が月光を受けて妖しく煌めいた。これほどの身なりの侍であるからには、この刀もどこぞの名工が鍛えた、ひとかどの業物に違いない。
だが、その様子を見た一柳斎はがっくりと肩を落とし、ぼそりとつぶやく。
「鳴かなんだか」
八五郎はその様子を見て「おお!」と思わず感嘆の声を漏らした。読売や噂話で面白おかしく語られていた、まさにそのとおりの台詞だ。
「鳴かせの一柳斎」は、理由はまったくわからないが、とにかく相手の刀が「鳴く」かどうかを試すのである。刀が鳴くというのがいったい何を意味しているのかも謎だが、鳴かなかったとすると、次に飛び出すのは例のあの台詞に違いない。
「去ぬか? 死ぬか?」
期待どおりの名文句に、すげえ、と八五郎は思わず手に汗を握った。
一柳斎は狙いをつけた相手に刀を抜くことを迫り、抜くと「鳴かなんだか」と残念そうにつぶやき、その後は黙って去るか、踏みとどまって闘うかを相手に選ばせる。黙って去れば、一柳斎は決して危害を加えない。
とはいえ、郎党をことごとく倒され、一人残された主人が闘わずに去ったとあれば武門の恥である。
それゆえ、逃げ去った者は一柳斎と出会ったこと自体をひた隠しにするのが常であった。それでも秘密は必ずどこからか漏れるもので、どこそこの家の何某という侍は一柳斎と闘わずに逃げたらしい、といった噂が、いくつかの大名家の重臣や旗本らに対して、まことしやかに囁かれていた。
今日の獲物である市橋伊勢守は、己が身よりも名を惜しんだらしい。
「おのれ曲者、許すまじ!」
そう叫んで怒気を発すると、刀を青眼に構え、全身に気迫をみなぎらせてじりじりと間合いを詰めていく。
八五郎は剣術のことはさっぱりだが、それでもこの市橋という侍が放つ剣気は尋常ではなく、かなり腕が立つと一目でわかった。最近では一柳斎のとんでもない強さがすっかり噂になったことで、勝負を避ける者が増えている。市橋伊勢守が逃げずに闘おうとしたのは、それだけ己の腕前に自信があるということなのだろう。
それに相対する一柳斎は、柳の古木を思わせる細身の体に一切の力みはなく、下段に構えた切っ先は相変わらずゆらゆらと左右に揺れている。
「はあっ!」
先に仕掛けたのは市橋のほうだ。
鋭い踏み込みは、さながら兎に飛びかかる虎のごとく、八五郎の目ではその動き出しを捉えることすらできなかった。だが一柳斎はひとつも慌てることなく、すっと体を開いてその一撃をいなした。
必殺の踏み込みを躱された市橋が、すかさず向きなおって再び刀を青眼に構えようとした、そのときだった。
八五郎は己が目を疑った。
市橋の右腕が音もなくだらりと下がり、構えていた刀を取り落としたのである。市橋は苦痛に顔を歪めながら左手で右腕を押さえ、がくりと地面に膝をついた。
「な……何をしたんだ一柳斎は?」
市橋は苦悶の表情を浮かべたまま一歩も動けない。いつの間にか、一柳斎に右腕を斬られていたのだ。
だが八五郎が見る限り、一柳斎は左足を引いて、市橋が繰り出した鋭い突きを避けただけである。そのときに一柳斎の刀が何となく動いたような気もするが、一瞬のことでよく見えなかった。
一柳斎は、市橋伊勢守がもはや戦意を失ったことを見届けると、懐紙を取り出して刀の血を拭い、鞘に納めると何ごともなかったようにその場を後にした。
一柳斎が自分のほうに向かって歩いてきたので、八五郎は慌てて物陰に隠れ、息をひそめて気配を殺した。すると一柳斎は隠れている八五郎に気づくことなく、そのすぐ横を通り過ぎて夜の闇に消えていった。
一柳斎が去った後も、八五郎は驚愕のあまり動悸が止まらず、しばらくその場を動くことができなかった。
八五郎の驚きは、もちろん噂の一柳斎の闘いを直にこの目で見たということもあるが、それよりもまったく別のところにあった。
「面頬で顔を隠していたけど、あれ、どう見ても隣の部屋の雲井の旦那だよな。なんで旦那が、鳴かせの一柳斎なんてやってんだ?」
小説
実は、拙者は。
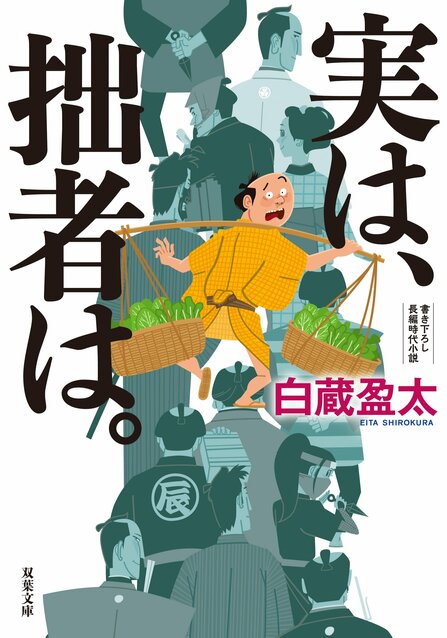
あらすじ
深川佐賀町の裏店に住まう棒手振りの八五郎は、平凡かつ地味な男。人並み外れた影の薄さが悩みの種だが、独り身ゆえの気楽な貧乏暮らしを謳歌している。そんな八五郎は、ある夜、巷で噂の幽霊剣士「鳴かせの一柳斎」が旗本を襲う場に出くわす。物陰から固唾を呑んで闘いを見守る八五郎だが、一柳斎の正体が、隣の部屋に住まう浪人の雲井源次郎だと気づき──。影と秘密は江戸の華!? 期待の新鋭が贈る、書き下ろし傑作時代小説。
実は、拙者は。(1/4)
関連記事
おすすめの試し読み