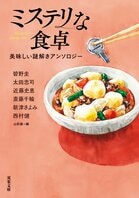カフェ・ルーズは毎月一日から八日が休みだという。営業は九日から月末まで。休みすぎのような気もするが、週休二日と考えるとべつにおかしくはない。そして、円はその間旅に出るという。そして買ってきたものや見つけたおいしいものをカフェで出す。
「もちろん毎月海外というのは無理だし、国内のときもあります。どこにも行かずにメニューを試作してるときもあります」
円は小首を傾げながら、そう言った。
ゆるいなあ、と思う。そんなことで大丈夫なのだろうか。もちろん、大丈夫でなくても瑛子が口を出すべきことではないのだが。
円と再会できたこと、彼女が自分の店を持っていたことで、心が軽くなった気がした。だが、帰ってから気づく。円に謝ればよかった、と。
次にルーズに行ったときには謝ろう。居心地のいいカフェだったし、夜も十一時まで開いているから、平日だって行ける。
「夜はお酒も出してますよ。ぜひ、またいつでもきてください」
思いの外長居してしまって帰るとき、円は前歯の見える笑顔でそう言った。六年の月日があっという間に縮まった気がした。
月曜日、職場であずさに円の話をした。
「あっ、覚えてます。ちょっと変わった子ですよね。飲み会にもあんまりこなかった……」
「そうだっけ」
瑛子は何度か同席した記憶がある。だが、六年前のことだ。その間に、何度飲み会があって、何度、円と一緒になったかははっきりと思い出せない。瑛子だって毎回出席するわけではない。二回に一回は顔を出すようにしているが、つまり二回に一回は休んでもいいことにしている。
この部署でいちばん年上の亜沙実は、何事にも頑張るタイプだから残業もするし、飲み会でみんなとコミュニケーションをとる努力もする。二番目の瑛子までが、そういう場に常に顔を出していると、年下の子たちが欠席すると言いにくいのでは、というのが毎回出ない言い訳なのだが、まあ、要するにめんどくさいのだ。
自宅のソファでひとりでハイボールを飲んでいる方がいい。
瑛子の家の近所だと聞くと、あずさの目が輝いた。
「あっ、彼が今度店を出すのも、その近くなんですよ」
くわしく話を聞くと、駅の反対側にある雑居ビルらしい。少し古いが賑やかな場所で飲食店も多い。カフェ・ルーズは住宅街の中にあるから環境はまったく違う。
「あそこなら、お客さんもたくさんきそうね」
「そうなんです! あそこを借りられることになって、話がトントンと進んで……」
気持ちが盛り上がっているのかあずさの声が高くなる。なぜかそれを見ると、喉になにかが詰まるような気がした。
嫉妬だろうか。自分は幸せになりそうな彼女に嫉妬しているのだろうか。
「でも、わたしも行ってみたいです。夜は何時まで開いてますか?」
「十一時までだって」
今日、仕事が終わってから一緒に行くことにする。幸い、今日は急ぎの仕事もない。
五時半に仕事を終え、帰り支度をしていると、あずさがやってきた。
「すみません。話をしたら彼も一緒に行きたいって言ってるんですけど、いいですか?」
大人としては嫌とは言えない。
まあ、経験上、彼女の知人と会おうとしない男性よりも、会社の同僚や友達とも親しくなる男性の方が結婚がうまく行く確率は高い気がする。データではなく、瑛子の印象だが。
瑛子は少し気詰まりだが、店に行くのだ。知らない人がいたって円は気にしないだろう。店の距離も少し離れているから、ライバルというわけでもない。
最寄り駅に到着すると、背の高い男性が改札口で待っていた。
「どうもこんにちは。蘇我正彦です」
ぺこりと身体を半分に折ってお辞儀をする。
「あずさがいつもお世話になっています」
礼儀正しい男性でほっとする。この人ならば気を遣わずに済みそうだ。
駅からは少し離れているのでタクシーに乗り、カフェ・ルーズに向かう。タクシーを降りると、ちょうど円は店の前にあるプランターに水をやっているところだった。瑛子たちを見て、少し驚いた顔になる。
「葛井さん、こんばんは!」
あずさが手を振ると円は少し微妙な顔で、頭を下げた。誰か思い出しているような顔だった。無理もない。一緒に働いていたのは、六年前だ。
「えーと……」
「中村です、中村あずさ」
名前を聞いて、やっと思い出したようだった。
「わあ、ご無沙汰しています!」
正彦は円が水をやっているプランターをのぞき込んだ。
「ハーブですか? これはローズマリーですね。これは?」
「これは大葉月橘ですが……」
円は不思議そうに正彦を見上げた。
「ええと……氷野照明の方でしたっけ」
あわててあずさが、二人の間に入る。
「わたしの彼氏です。蘇我くん。彼も今度、このあたりで飲食店やるから、ちょっと勉強させてもらおうと思って」
「どんなお店を?」
円の表情からは不快に思ったかどうかはわからない。だが大歓迎という様子でもないようだ。瑛子は助け船のつもりで正彦に尋ねた。
「カレー屋さんだったっけ?」
「ええそうです。駅前だから、ここからちょっと離れてるんですけど」
店内には誰も客がいなかった。昼の客が帰り、夕方からの客が訪れる前なのだろう。
円がドアを開けて、店の中に瑛子たちを招き入れる。慣れた様子で、ふたりがけの席を移動させて、四人掛けの席を作ってくれる。
「どうぞ」
彼女が運んできた水のグラスには、ライムが浮いている。
正彦はメニューをちらりと見ただけで、「じゃあビールを」と言った。瑛子もメニューを見る。夜のメニューらしくアルコール類も揃っている。
チーズだとかグリルソーセージなど、お酒に合う小皿もいくつかあるので、バーのように利用することもできるだろう。
お酒も飲みたいが、このあいだのアルムドゥドラーもまた飲みたい。メニューを見ていると、白ワインのハーブレモネード割りというのがあったので、それを頼んだ。
「わあ、なに、それおいしそう」
あずさが瑛子の注文を聞いて、メニューを探す。彼女も同じものを頼んだ。
円は飲み物だけでなく、オリーブの塩漬けやプレッツェルののった小皿も持ってきた。
「どうぞ。サービスです」
白ワインをアルムドゥドラーで割ったものは、爽やかで、夏に向きそうな飲み物になっていた。少し甘いが、ハーブの香りが爽やかだ。
円はテーブルの横に立った。正彦に話しかける。
「お店、駅前のどのあたりなんですか?」
「来月から内装工事をはじめるんですけど、ほら一階にコンビニの入った雑居ビルで紀谷ビルという……」
「ああ、いい場所ですね」
円は小さく頷いた。
「でも、あのあたり、チェーンのカレー屋ありますよね」
「ああ、うちはエスニックカレーだから大丈夫。タイとかスリランカとか」
正彦がそう答えると、円は微笑んだ。
「それはおいしそうですね」
仕事をするためか、円はテーブルから離れた。
あずさと正彦は椅子を近づけて、見つめ合っている。なんだか居心地が悪く感じる。この前のようにくつろげない。
一杯だけ飲むと、瑛子は退散することにした。またひとりでくることにする。
「じゃ、今日はわたし失礼するわ」
「えー、そうなんですか? 残念」
少しも残念そうでない口調で、あずさが言う。まあ、明日にはまた仕事で会うのだから、本当に残念がられても困るが。
先輩の意地があるので、少し多めだが千円札を置いて席を立つ。カウンターの中の円に声をかけた。
「じゃあ、わたしは今日はこれで」
「あ、ありがとうございました」
円は店の外まで送ってくれた。階段を降りようとしたとき、ふいに、袖をきゅっとつかまれた。
「あの……、またいらしてくれますよね。遠くないうちに」
「あ、うん。またくるよ」
どぎまぎしてしまったのは、円がひどく真剣な顔をしているせいだ。円は続けてこう言った。
「少し、気になることがあるんです」