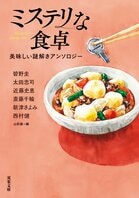この世でいちばん好きな場所は自宅のソファだ。
超高級品ではないけれど、瑛子にしては頑張った。たしか三十万円ほど。二人掛け、オットマンもつけて、セミオーダーで。
そこにクッションを四つも置いた。片方にクッションを重ねて、身体を預けてテレビを観る。足がむくんでいるときは、ソファに横たわって、クッションの上に足を置く。残業でくたくたに疲れ切って帰ったら、クッションを全部床に落として、ソファにばったりと倒れ込む。
会社で仕事をしているときも、早く帰ってソファに寝転がりたいと思う。そして、土曜日と日曜日、ソファの上でゆっくりと本を読んだり、借りてきたDVDを観るときは、この上ない幸福を感じる。
客観的に見れば、あまり人にうらやましがられたり、優越感を持てるような状況ではない。
三十七歳、独身、一人住まい、子供もいないし、恋人もいない。取り立てて美人というわけではない。趣味らしい趣味もない。読書や映画を見るのは好きだけど、マニアと言えるほどではない。
貯金はそんなにない。三年前にこの中古の1LDKを買うのに使ってしまった。そこから少しは貯めることはできたが、充分な貯蓄額とは言えないし、マンションのローンもある。
部署の独身女性の中では、いちばん上の年齢になってしまった。他の部署にはもっと年上の独身女性もいるけれど。
二十代の若い女の子たちとも仲良くしているし、煙たい先輩にはなってないと思いたいが、そうも言い切れない。職場の男性たちからは冗談のように「お局」と言われることもあるし、若い子たちとあからさまに差をつけられる。
自分が不幸だとも思いたくないが、それでも三日に一度くらいは不安になる。昨日と変わらない明日。いや、変わらなければラッキーで、この先いきなりリストラされたり、大病をして働けなくなることも考えられる。
毎日会社に行き、代わり映えのしない仕事をして残業し、夜遅く家に帰る。休日はくたくたで、出かける気にもならない。
ただひとつ、たしかなのは、この先自分に映画のような特別な恋が降りてくることも、隠された素晴らしい才能が目覚めて、ミュージカル女優になることも、莫大な遺産を相続して大富豪になることもないということだ。
1LDKのリビング、110cm幅のソファ、瑛子の幸せはその上に収まってしまっている。もちろんなにもないよりはずっといいのだけれど。
ソファの上にいるときは幸せな気持ちでいられる。だが、その幸福感には、いつも憂鬱のベールがかかっている。
その日もいつもの朝と同じだった。
ぎりぎりの時間に起きて、高速でメイクをし、電車に飛び乗った。満員電車の女性専用車両でぎゅうぎゅうにプレスされながら通勤時間を耐え抜いた。
ここだけ早送りしてくれればいいのに。毎日、通勤時間はそう思う。薬かなにかで意識を飛ばして、なにも感じないようにできればいいのに。
会社で、話の通じない上司に嫌味を言われたり、取引先でぞんざいな扱いをされたりするときも同じだ。少しの間だけ、なにも感じないようにしてほしい。
もちろん、そんなのは無理な願いで、ダメージはしっかり蓄積されるのだけれど。
家で入れてきた保温マグのお茶を飲んでいると、中村あずさに声をかけられた。
「奈良さん、今日ランチどうしますか?」
あずさは、今年三十三歳になる後輩で、よく一緒に昼ご飯を食べに行く。だが、こんなふうに朝からランチの予定を聞かれたのははじめてだ。
「今日は外出予定はないから、なんか食べに行く?」
あずさはぱっと笑顔になった。
「わ、よかった。じゃあ、一緒に行きましょ」
「うん、じゃあ昼にね」
にこやかに返事をしたが、頭の中に黄信号が点る。
普段、あずさとランチに行くときは、昼休みになってから誘い合う。あずさはよく弁当を持ってきているし、瑛子だってたまには残り物を詰めただけの弁当を作る。
もしくは近所に新しい店ができたときに、「木曜日あそこに行ってみる?」などと相談することもある。
だが、今日のあずさは行きたい店があるようでもない。単純に、瑛子の昼の予定を押さえておきたかったような感じだ。
好かれているのね、と喜ぶわけにはいかない。これまでに何度もこんなことがあって、それはあまり喜ばしいことではなかったからだ。
仕事を辞めるという報告だったり、ひどい扱いを受けたという相談だったり。少なくとも、にこにこと聞いていられるようなことばかりではない。
もしかすると、結婚するとかそういう話かもしれない。彼女には一緒に暮らしている彼氏がいる。
それならばまだいい。微妙な寂しさや、置いてきぼりにされたような切なさは残るが、結婚したからといって、すぐに仕事を辞めるようなことはないだろう。
仕事を辞められるのがいちばん、困る。瑛子が今働いている部署は女性ばかりだが、ひとり辞めたばかりで、もうひとり育休をとっている。何度も人事に掛け合っているが欠員補充はまだない。
もし、あずさに辞められたら、六人分の仕事を三人でまわさなくてはならなくなる。さすがにそれは困る。育休をとっている櫻井が帰ってくるまでに、まだ四ヶ月もある。
憂鬱な予感を振り払って、瑛子はパソコンの電源を入れた。
パスタ専門店にふたりで入って席に着くと、あずさは前置きもなく言った。
「今、わたしが辞めたら迷惑ですよね」
どきり、とする。やはり悪い予感は当たった。あまり動揺を見せないように、瑛子はメニューを開いた。
「そりゃあ、困るけど……でもなにかあったの?」
職場で見ている限り、あずさが他の社員と折り合いが悪いようにも思えないし、ひどいストレスを抱えているようにも見えない。
あずさは比較的ドライなタイプで、他の社員が残業してようが自分の仕事が終わると、さっさと帰ってしまう。そういうところで、一番年上の久保田亜沙実とはあまり仲がよくないが、亜沙実があずさを苛めているというわけではなさそうだ。
もしかすると、体調でも悪いのかもしれない。
ウエイトレスが注文を取りに来る。あずさはメニューも見ずにカルボナーラを頼んだ。瑛子もあわててペペロンチーノを頼む。ウエイトレスが行ってしまってから、平日はにんにくのきいたものを食べないようにしていたことを思い出した。
あずさは一瞬視線を下に落としてから、顔を上げた。少し迷ってから口を開く。
「もうすぐ結婚するんです」
「そうなんだ、おめでとう」
あまり、祝福しているような口調にならなかったのは、あずさがあまりにも、言いにくそうにしているからだ。独身の自分が気遣われているようで居心地が悪い。もっと、うれしげに報告してくれれば、おめでとうも言いやすいのに。
「仕事、辞めるの?」
あずさは小さく頷いた。
「できれば辞めたいと思っています」
妊娠を機に仕事を辞めた人はこれまでもいたが、結婚をきっかけに辞めるというのもなにか事情がありそうだ。
「彼氏が遠くに転勤するとか?」
「そういうわけではないんですけど……彼がお店を始めるんです。いろいろ大変だし、最初から従業員を雇うのは難しいから、わたしが一緒に手伝おうと思って……」
瑛子は一瞬ことばに詰まった。コップを引き寄せて水を飲む。
「お店ってなんの?」
「カレー専門店だそうです。彼、調理師なんです」
「そうなんだ……」
飲食店を始めることはけっして簡単なことではないし、失敗する可能性も高い。冒険であることは間違いない。
だが、失敗するとは限らない。あずさの彼が作ったカレーを食べたこともないし、どんな人かも知らないのに、瑛子が口を出すことではない。
なのに、口の中が粘ついて渇いた。「よかったね」とか「頑張ってね」と言うのが難しい気がした。それを悟られたくない。できるだけ笑顔を作って、言った。
「大変だろうけど、頑張ってね。で、辞めるとしたらいつ頃になる?」
「一応、櫻井さんが戻ってきたらと思ってるんですけど……」
それを聞いて少しほっとする。今日明日にという話ではないようだ。
「式とかはしないの?」
そう言うと、あずさはやっとはにかんだような笑顔になった。
「お店を始めるのにお金がいるだろうからやめときます。籍は七月のわたしの誕生日に入れようかと」
二ヶ月後だ。毎年、同僚たちとあずさの誕生日会をしていた。
胸がきゅっと痛む。彼女とは会社では仲良くしているが、あずさが会社を辞めてしまえば、きっとプライベートで会うことはないだろう。これまでもそんな同僚は何人もいた。
自分だけが川の中洲に取り残されているみたいだ、と思う。
みんな流れていく。思い思いの場所に。
パスタが運ばれてくる。瑛子は半ばやけっぱちな気持ちで、ペペロンチーノを口に運んだ。