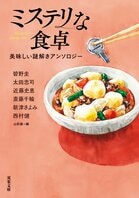ふいに六年前のことを思い出した。
当時、一緒に働いていた後輩に、同じような相談をされたことがあった。
短い髪と小さな顔、ちょっと前歯が目立つリスみたいな顔をしていた。
会社にいたのは、半年くらいだろうか。職場の女性たちは、みんな柔らかい茶色に髪を染めていたのに、彼女の髪だけが真っ黒だった。化粧もほとんどしていなかった。
それほど仲良くしていたわけではないのに、ある日、いきなり昼食に誘われた。
コーヒー専門店で、サンドイッチを食べながら向かい合った。皿に残された緑のパセリをぼんやりと眺めていたのを覚えている。
サンドイッチを食べ終わると、やっと彼女は口を開いた。
「会社を辞めようと思うんです。奈良さんにはお世話になったのに、申し訳ないんですけど」
きっぱりとした口調だった。そんなにお世話はしただろうか、と考えて、単なる社交辞令だろうと判断する。
「辞めてどうするの?」
そう言うと、彼女は少し口元をほころばせた。前歯がのぞく。
「自分のお店がやりたいんです。カフェとか」
思わず言っていた。
「やめた方がいいんじゃないの?」
彼女の笑顔が凍り付いた。自分の口から出たことばに、重みを与えるために、瑛子は話し続けた。
「そんな簡単なものじゃないよ。飲食店って新規開業した七割以上が二年以内につぶれるって、このあいだ雑誌で見たよ。考え直した方がいいよ」
実際に、その記事を見たのは嘘ではない。彼女の先行きを心配したのも事実だ。決して意地悪な気持ちなどではなかった。
だが、彼女が会社を辞めてしまった後も、そのことを何度も思い出す。あんなことを言わなければよかった、と思うのだ。
うまく行くか行かないかなんて、あの時点ではなにもわからなかった。七割のお店はつぶれるとしても、三割は残るのだ。自分だって、週のうち半分くらいは飲食店で食事をしているのに、なぜあんなふうに決めつけてしまったのだろう。
もう彼女の名前も思い出せない。半年の間、職場にいただけだから、誰も彼女のことを思い出さないし、話題にも出さない。
ただ、そのときの彼女の悲しげな顔だけが頭から離れない。
土曜日は晴天だった。空はアクリル絵の具で塗りつぶしたように青い。
こんないい天気の日は散歩にどこか遠出したいと思ったが、掃除や洗濯をしているうちに午後になってしまった。
せめて買い物ついでに、近所を散歩でもしたい。でないと運動不足になってしまう。
今のところ服のサイズは変わっていないが、体重もじわじわと増加気味だ。
しばらく最愛のソファでだらだらしていたが、えいやっと立ち上がる。
足を延ばして、十五分ほどかかる大きなスーパーまで行こう。あそこなら野菜もきれいだし、フランス産のチーズや塩漬けオリーブなど、素敵な食材がたくさん揃っている。
いちばん近所のスーパーは、あまり品揃えがよくないし、野菜も少し萎れている。
いい天気だからひさしぶりに自転車に乗ることにした。ポタリングは数少ない趣味だが、気候のいい春や秋しか乗らない。夏と冬は自転車はしまい込まれている。
おっくうなのは、自転車を引っ張り出すまでで、乗ってしまえば遠くまで行きたくなる。似たようなことはたくさんある。
分厚い翻訳ミステリに手を伸ばしたときとか、寒い日にお風呂に入るときとか。最初のおっくうささえ乗り越えてしまえば、そのあとは素敵な体験が待っている。
いつもと違う道を通り、あえて坂を上る。住宅街をふらふら走っていると、ふと一軒の店が目にとまった。
パン屋かカフェか。白い一軒家で、木の看板が出ている。カフェ・ルーズという名前が目についた。店の前にはハーブらしきプランターが並んでいる。
時間はいくらでもあるから、ここで休憩してもいいかもしれない。もし、居心地のいい店ならば、ときどきここでくつろぐこともできる。
短い階段を上がって、店に入る。小さなカフェだった。ふたりがけのテーブルが四つ。カウンターに椅子が五つ。すでに、二組の女性客がいた。
きょろきょろしながら、中に入る。
「いらっしゃいませ。お好きなお席にどうぞ」
明るい声がキッチンから聞こえる。カウンターに座った方がいいかと思ったが、好きな席でいいと言われたので、窓際のテーブル席に座って、メニューを広げた。
メニューはそう多くない。食べるものはサンドイッチとカレーやパスタ。お腹は空いていないから、飲み物のページを見る。
コーヒー、紅茶、カフェオレ、オレンジジュース。普通なのはそこまでだった。
ミント水、ざくろ水、クワス、ハーブレモネード、杏ネクター。見たことのない飲み物の名前が並んでいる。ウィンナコーヒーやベトナムコーヒーは知っている。カフェ・マリアテレジアというのはいったいなんなのだろう。どれにも説明が書いてあるけれど、とりあえず名前だけを見ていく。
お菓子のコーナーを見ると、もっとよくわからない。ストロープワッフル、シナモンプッラ、パイナップルケーキ。
どれもなんだかおいしそうな響きだけど、なにがなんだかわからない。説明を読み込もうとメニューに顔を近づけたとき、頭の上から声がした。
「奈良さん? 奈良さんですよね」
顔を上げると、そこには前歯の大きい、リスみたいな顔があった。
話ができるようにカウンターに移動した。
葛井という姓は顔を見たら思い出した。葛井、葛井円。それが彼女の名前だ。
「何年ぶりですか。えーと……」
円が指を折るから、先回りして言った。
「六年ぶりだよ」
この前思い出したときに数えたから間違いない。
「わあ、そんなになるんですね。まだ氷野照明にいらっしゃるんですか?」
「うん、そう」
瑛子の勤めているのは、主にオフィスや店舗に照明器具を販売している会社だ。新卒から勤めているから、もう十五年になる。
「葛井さんは、いつからこのお店やってるの?」
「ええと、二年前ですね」
そのことばを聞いて、きゅっと胸が痛んだ。二年以内に七割以上が潰れると言ったのは、瑛子だ。
「長く続いてるんだ。お客さんもきてるし、感じのいい店だね」
それは決してお世辞ではない。凝った内装ではないが、光がたっぷり入って居心地のいい店だ。
そういえば、まだなにも注文していなかった。あわててメニューを見ると、円がグラスを前に置いた。
「よかったらこれ、飲んでみませんか? サービスです。あんまり注文が出なくて……」
氷とレモンが浮かべられたグラスの中には、褐色の炭酸水が入っている。ジンジャーエールのように見える。
おそるおそるストローをくわえた。ジンジャーエールに似ているが、生姜の香りはしない。薬草のような不思議な匂い。だが、癖はなくて飲みやすい。
「これ、なあに?」
「アルムドゥドラーって言うんです」
「アルム……」
一回では覚えられない。舌を噛んでしまいそうだ。円はくすりと笑って、メニューを指さした。
「お客さんもだいたい一度では言えないから、メニューにはハーブレモネードって書いてます」
なるほど、たしかに香りはハーブのものだ。甘さはあるが控えめで、少し大人っぽい味がする。
「いかがですか?」
「うん、おいしいよ。はじめて飲んだ」
「よかった。奈良さん、炭酸水お好きだったな、と思って」
それを聞いて驚く。たしかに瑛子は炭酸飲料が好きだ。夏はガス入りミネラルウォーターばかり飲んでるし、お酒もスパークリングワインや、ソーダ割りが好きだ。だが、一緒に仕事をしたり、飲み会に行ったのは六年前なのに、そんなことまで覚えているなんてすごい記憶力だ。
円は少し困ったように笑った。
「なんとなく覚えてたんです。間違ってなくてよかった」
もう一口アルムドゥドラーを飲んでみる。たしかにおいしい。好みの味だ。
「これ、どんなところで買えるの?」
「普通には買えないと思います。オーストリアの炭酸飲料なんです。取り寄せてもらってるんです」
いきなり出てきた国の名に、瑛子は思わずまばたきをした。
「えーと、カンガルーがいる方? いない方?」
「いない方です。いる方はオーストラリア」
それでちょっとイメージできた。ヨーロッパの音楽の都だ。行ったことないけれど。
そんな遠い、一生行くことがないかもしれない国の飲み物がここにある。
ちょうど、別の客が入ってくる。今度は、若い男性と女性の二人連れだ。円は水のグラスを持っていった。
アルムドゥドラーを飲みながらオーストリアのことを考える。『サウンド・オブ・ミュージック』とか、ハプスブルク帝国とかそういう断片的な知識だけしか浮かばない。だが、椅子だけがふわりと浮かび上がったような気持ちになる。空飛ぶ絨毯のように椅子だけが飛んで旅に出る。
帰ってきた円に言う。
「なんか旅に出てるみたい」
名前も存在も知らなかった、外国の飲み物と出会える。
円はくすりと笑った。
「うち、そういうコンセプトのカフェなんです。旅に出られるカフェ。わたしもしょっちゅう旅に出て休みにするし、その代わりお客さんもここで旅を感じる」