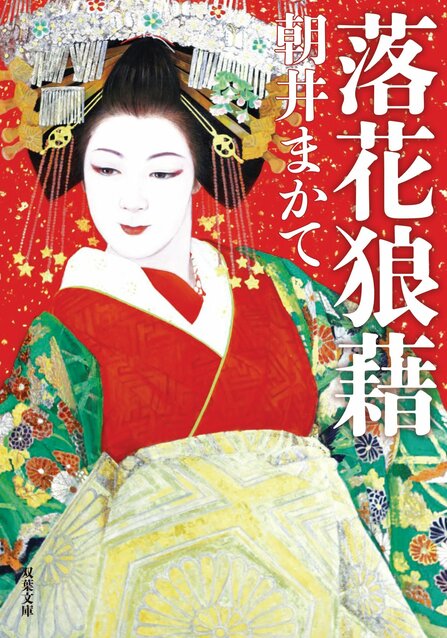堤道はいつしか、大変な人だかりになっていた。七人と四人で相対し、五挺の駕籠も下ろしたままであるので、道を堰き止めた恰好になっている。
まごまごしている暇はない。結着をつけよう。
「そうは申しておりませぬ。ただ……」
突かれた胸の前を、ゆるりと掌で払った。
「天下の形勢に色目を遣うて江戸に下ってきた連中に、こちとら、大きな顔をされる謂れはないんだよ」
言い放つや、踊子の胸を突き返した。尻からどっと土の上に落ち、裾が無様に開く。太腿の奥の繁りまで露わになった。
「何をするのや」
金切り声でわめいている。笛を手にした男が、「しっかりせえ」と腕を持って助け起こした。その脇から、若衆髷の男が前に出てきた。随分と若く、やけに妖艶な目をしている。
「西田屋とやら。気取りくさって、手ひどい真似を働くもんやな」
「己から難癖つけといて、身構えもしない方が悪い。踊子なら、ひらりと飛び退いてみせなよ。五条の橋の、牛若のごとく」
見物人の間から「そうだ、飛べ飛べ」と、声が上がった。
「吉原と歌舞妓の喧嘩ってか」
「こいつあ、久しぶりに面白ぇ見世物だ」
人波は堤下まで押し寄せ、川を行く舟までが留まってこちらを見上げている。
若衆髷の若者は横笛を手にしながら奇妙に躰をくねらせ、間合いを詰めてきた。近勝りのする、怖いほどの美形だ。歌舞妓といえば男装の女と決まっているので、若者は鳴物を受け持っているのだろう。そして幕の陰では、男でも女でも相手にする遊郎だ。
笛を持つ左手の手首を回している。ひゅい、ひゅいと、風を切る音がする。
身構えると、「姐さん、これ」と背後から声がした。顔だけで見返れば、人垣の間から若菜が顔を出している。
「駕籠の中でお待ちと言っただろう」
「違いいすよ。これ」
棒のような物を突き出してよこしたので、とっさにそれを掴んだ。若菜は瞬く間に頭を引っ込めて姿を消した。瀬川らの声がするので、皆で駕籠に逃げ帰ったのだろう。
なら安心だ。腕っぷしの強い陸尺らがそばにいる。
花仍は棒を右手に持ち替えて、それが杖だと察した。若菜が陸尺から借りたか、奪ってきたか。
肩と肘の力を抜き、杖を両の掌で握って構えた。遊郎が片頬で嗤う。
「生意気な。剣術の真似をしくさるか」
遊郎は蟷螂のごとく、ゆらりと両の腕を振り上げた。
おあいにく。脇が甘い。
花仍は見て取り、右足だけで踏み込んで杖の先を咽喉許に突き当てた。皮一枚分は残してあるが、遊郎の咽喉がぐうと音を立てた。寸分も動けないようだ。
仲間の者らが血相を変え、いきり立った。
「おい、遠慮は要らん。やってまえ」
「そうや、撲ちのめせ」
五月の蠅みたいに、うるさい連中だ。腰の物を抜き、鞘を払って土の上に叩き落している。しかし身を飾るためだけの、薄く軽い鈍刀だ。饂飩だって切れやしないだろう。
花仍は頭を澄ませて思い描く。いちどきに叩きのめすには、まず腰を低め、連中の膝を打つ。三人、いや、五人はやれる。こちらは右腕が伸びて躰が開く前に腰骨を回して、残りの連中の肩を打ち、背中を突く。
どれ、さっさと片づけてしまいましょう。
腰を落とした。左手を杖から放し、右肘を微かに上げる。視線の端にある膝を目がけて、杖を突き出した。遊郎が蒼褪めて、わめき立てる。
また桜の風が吹き寄せてきた。
その刹那、なぜか動けなくなった。肘を掴まれている。背後からだ。
何たる不覚。いつのまに回り込まれた。
こうなれば、どう動く。このまま腕を捩じ上げられたら、かなり厄介なことは察しがつく。ありとあらゆる顛末を覚悟して、息を整えた。
そろそろと相手を見上げて絶句した。
「随分と楽しそうだが、そろそろ幕を引いてもらおうか」
肘を掴んでいるのは、亭主の甚右衛門だ。
その背後には、供として出ていた番頭の清五郎の顔も見える。清五郎は「まったく」と片頬をしかめて、仰向いた。
この続きは、書籍にてお楽しみください