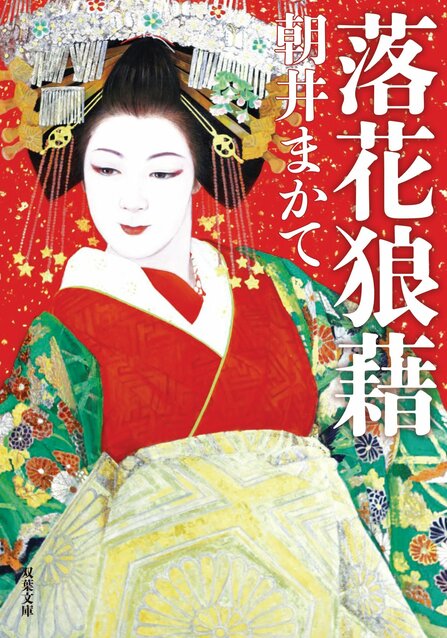だが今日、夕霧と辻花は朝から御公儀の評定所に出張っている。御奉行の集まりに吉原の家々から太夫を差し向け、茶菓を給仕する勤めを賜っているのだ。これは開府以来の慣いで、そちらには甚右衛門と番頭の清五郎が付き添っている。
それで花仍の誘いに乗ってきたのが、瀬川と若菜ら四人だった。
前を行く若菜はとうに身を戻していて、朱赤の袂の先だけが駕籠から零れている。見れば四挺とも袖が少し出ていて、色とりどりに揺れている。
「兄さん、ゆっくり行っとくれな」
花仍は駕籠を舁く陸尺に声をかけた。
酒代を弾んだので、返事も「へいッ」と威勢がいい。花仍が今朝、若い衆に大門通りまで呼びに行かせたところ、いつものごとく賽で暇を弄んでいた陸尺らは「五挺」と聞いても顔を上げなかったが、注文の主が「西田屋の女将」と耳にするや、我勝ちに立ち上がったらしい。
「前にもそう伝えとくれ。さほど急ぐこともないって」
こんなふうにしみじみと春野を行くのは久方ぶりなのだ。見世に帰れば、また夜の喧騒が始まる。若菜をねぎらったつもりの「ゆっくり気をお伸ばし」は己に投げた言葉だったかと、花仍は少しばかり苦笑して肩をすくめた。
その時、急に駕籠が斜めに動いた。いきなり躰がのけぞる。咄嗟に、両手で綱をひっ掴んだ。
何ごと。
小太鼓の音が聞こえる。女の声もある。やけに通る怒声だ。はっとして、顔を外に出した。と同時に、陸尺に命じていた。
「降ろしとくれ」
すぐさま駕籠が揺れ、土の上へと床が下がる。
「先で、揉めてるみたいですぜ」
陸尺の二人が肩を盛り上げ、少し昂ぶるように言った。花仍は黙って草履に足を入れ、前に向かう。
前の四挺が思い思いの向きになって止まっており、陸尺らの腕越しに瀬川の後ろ姿がある。そのかたわらには端女郎の二人も見える。道を塞ぐように対面しているのは、七人ほどか。身形から察するに、歌舞妓の連中だ。
厄介な連中に引っ掛かった。不穏な予感がして、小走りになる。前の若菜がちょうど草履を手にして駕籠から降りようとしていて、「姐さん、喧嘩」と訊いてくる。
「駄目、降りるんじゃない」
走りざまに言い捨て、さらに足を速めた。
「何様のつもりや」
懐手をした女が、瀬川に噛みついている。
「乙に澄ましたとて、しょせんは女郎やないか」
「前を開けておくれとお願いしたのが、何ゆえそうもお気に召さぬ。ここは天下人馬の往来道、お前らだけの道ではありいせん」
花仍は舌打ちをしたい思いで、足を運ぶ。
瀬川さん、相手になっちゃいけない。口を返したら、必ず揚足を取られる。
「ありいせんとは、どこぞのお訛りやろう。わっちらには皆目、見当がつきいせん」
あんのじょう、廓の里言葉を真似てあげつらってきた。